- 対象: 全社向け
- テーマ: マネジメント
- 更新日:
モチベーションマネジメントとは?意欲を効果的に引き出す9つの施策
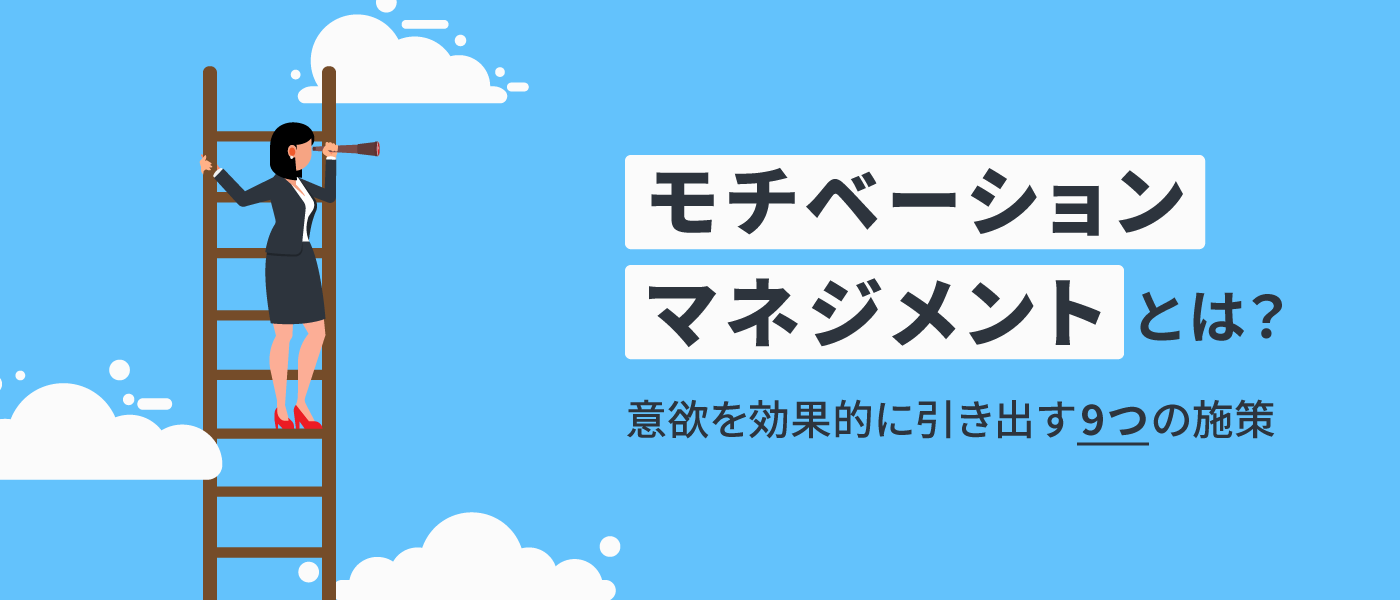
企業の生産性向上に役立つ戦略として注目されているのが、「モチベーションマネジメント」です。
従業員のモチベーションを引き出し、活気ある組織を維持することは、優秀な人材の確保や人材不足の解消にも欠かせません。
今回は、モチベーションマネジメントの効果やモチベーションが低下する原因、有効な施策について紹介します。
関連資料

関連資料
エンゲージメントや満足度はどのように変化しているのか経年で比較調査
パフォーマンスにつなげるエンゲージメント調査
モチベーションマネジメントとは
まず、モチベーションマネジメントの概要と基本的な考え方を整理しておきましょう。
モチベーションマネジメントの概要
モチベーションマネジメントとは、モチベーション(動機、やる気)の源泉に働きかけて従業員の意欲を高め、自発的に仕事へ取り組めるようにサポートする管理手法です。成長促進や生産性向上を目的として行われます。
モチベーションは日本語で「動機づけ」を意味しており、目標や目的を達成するための積極的な行動を喚起して、持続させるプロセスを指します。
モチベーションマネジメントにおける重要な考え方
モチベーションを引き出す「動機づけ」は、内発的動機づけと外発的動機づけの2種類に大別されます。それぞれ解説します。
① 内発的動機づけ
内発的動機づけとは、好奇心や挑戦心、楽しさ、熱意など、内的な欲求に基づくモチベーションを引き出すことです。内発的動機づけが成功すると、内なる欲求から行動できるようになるため、行動自体が報酬となります。
例えば、従業員が自分のスキルや知識を高めたいと感じることが、内発的な動機づけにつながります。新しいプロジェクトに挑戦することで自分の専門知識を深めたり、資格取得のために勉強したりするケースなどです。
このように、自らの意志による自発的な行動を促すことから、創造性の発揮や継続的な成長なども期待できます。ただし、長期的に形成される傾向があるため、即効性はあまり期待できません。
② 外発的動機づけ
外発的動機づけとは、賞罰、報酬、評価や称賛など、外部からの働きかけで目的意識や意欲を引き出すことです。
例えば、成果に応じた給与アップやボーナスの支給は、典型的な外発的動機づけの例です。売上目標を達成したときにインセンティブが支給される場合は、報酬を目的として行動が促されます。
また、外発的動機づけは、短期的な成果を上げる際に効果が期待できます。一方で、目標を達成した時点で満足感が得られるので、長期的にみるとモチベーションをキープしづらい側面もあります。
内発的動機づけと外発的動機づけは、互いに影響し合っています。特に、内発的動機づけで仕事へのやりがいを感じつつ、外発的動機づけによる報酬や評価があることで、従業員はより高いパフォーマンスを発揮するといわれています。
ただし従業員によっては、内発的動機づけに強く反応する人もいれば、外発的動機づけに刺激を受ける人もいます。また、仕事の性質や状況によっても適切な動機づけの方法は変わります。そのため、両方を適切に組み合わせることがモチベーションマネジメントの重要なポイントです。
モチベーションマネジメントが企業にもたらす効果・メリット
モチベーションマネジメントの取り組みがうまく機能すれば、次のような効果やメリットを企業にもたらすことができます。
生産性の向上
モチベーションマネジメントのメリットは、一人ひとりの従業員のやる気と能力を引き出し、企業全体の生産性や競争力の向上につなげられる点です。
仕事への意欲が高まった従業員は、組織や個人的な目標の達成に向けて、自律的に業務へ取り組むようになります。自発的なスキルアップや創意工夫を進んで行うようになれば、高いパフォーマンスの発揮や業務品質の向上などが期待できます。
このようなモチベーションの高い従業員が増えると、社内コミュニケーションが活発化し、企業全体の士気や業務効率にも良い影響を与えるでしょう。限られたリソースで最大限の成果を出せるようになるため、企業の継続性や競争力にもプラスに働きます。
従業員の自己成長を促進
従業員が自己成長を目指すようになると、目的実現に向けた積極的なチャレンジや自己研鑽も進んで行うようになります。そのため、自律的で生産性の高い人材の育成にも効果的です。
アウトプットの質が高まることで業務効率化やビジネスチャンスの獲得などにもつながり、企業の成長を後押しします。自己成長の実感は自己肯定感が育まれる好機となり、より高い目標へ挑戦するための原動力にもなるでしょう。
離職リスクの低減
モチベーションマネジメントによって、従業員が自身の役割に満足感を得られるようになり、会社への愛社精神や貢献意欲が高まります。そのため、優秀な人材の定着や離職防止に効果的です。採用コストや教育コストの削減も期待できるでしょう。
従業員のモチベーションが低下する原因
効果的な施策を考えるためには、従業員のモチベーションを低下させる原因を押さえておくことも重要です。次に、従業員のモチベーションが低下する主な原因を5つ紹介します。
原因1|希望する仕事内容が実際と異なるため
入社前に期待していた仕事内容と現状のギャップに直面し、従業員のモチベーションが低下するケースは多くみられます。こうした状況では、内発的動機づけとなる好奇心や挑戦心などが刺激されないばかりか、仕事の価値も感じにくくなります。
「仕事がつまらない」「自分には向いていない」というネガティブな感情は、意欲低下やストレスの原因です。その結果、仕事をうまくこなせていないと感じる機会が増え、自信を喪失してしまうこともあります。
このような状態を放置すると、生産性の低下に加えて離職を招く原因にもなるため、注意が必要です。
原因2|目の前の仕事をこなすだけになっているため
常に目の前の仕事に追われるような忙しい状況も、モチベーション低下の原因です。厳しい納期やノルマ、オンオフの切り替えがない働き方などは、従業員から時間と心の余裕を奪うことがあります。
ワークライフバランスが崩れた働き方は、心身の疲労をもたらし、従業員の向上心や創造性、仕事を楽しむ気持ちなどを低下させることにつながります。過度なストレスで心身に不調をきたすリスクもあるため、注意が必要です。
また、中長期的なキャリアにつながらない仕事が続く状況も、モチベーションの低下を招く一因といわれています。
原因3|正当な評価を受けていないと感じるため
給与アップや昇給・昇格などのリターンは、外発的動機づけとなる要素のひとつです。一方で、不当な人事評価や不合理な同僚との待遇差などがあると、モチベーションの低下を引き起こす要因になり得ます。
評価が不公平な状態では、従業員が企業に対して不信感をいだいたり、自信を失ったりしてしまいます。企業は内発的動機づけだけでなく、外発的動機づけもバランス良く生み出されるような職場環境を整備することが大切です。
原因4|職場の人間関係が良くないため
人間関係に問題がある職場環境は、従業員のストレスを増幅させて仕事へのモチベーション低下を招くおそれがあります。
例えば、下記のような状況には注意が必要です。
- 部下の失敗を強く叱責する上司がいる
- ハラスメントがある
- 困ったときに協力し合う文化がない
- 必要な情報が共有されない
コミュニケーションが円滑でなく、互いに信頼関係を築けない職場で、仕事へのモチベーションを維持することは容易ではありません。
特に上司との関係は、仕事のパフォーマンスや組織へのエンゲージメントにも大きく影響する要素です。そのため、日頃の上司の指示や命令、評価などへの不信感が、部下のモチベーションを低下させる要因となり得ます。
なお、ハラスメントについては、下記のコラムでも詳しく解説しています。
原因5|心理的安全性が低いため
職場の心理的安全性も、従業員のモチベーションを大きく左右する要素です。心理的安全性が高い職場は、個人の気持ちや意見などを自由に表現できる状態にあります。
組織全体の成長意欲が強く、自分の考えや疑問を安心して率直に表現できるのが、心理的安全性の高い職場の特徴です。
また、 Googleは2012年から約4年間をかけて「プロジェクト・アリストテレス」を実施し、成功し続けるチームに必要な条件を探りました。その結果から、パフォーマンスや生産性の向上のほか、定着率などにも良い影響を与えることが判明しました。
一方で、従業員の考えを尊重しない職場は、心理的安全性が低くなります。意見を否定されたり、評価が下がったりすることへの懸念から、上司や先輩への意見や間違いの指摘を躊躇するケースが増えてしまうのです。
従業員のモチベーションや定着率の向上に加え、多様なアイデアからイノベーションが生まれる職場づくりを目指す上でも、心理的安全性は重要なポイントといえます。
心理的安全性については、下記のコラムでも詳しく解説しています。
代表的なモチベーション理論
モチベーションマネジメントを実践するのに役立つモチベーション理論の概要を解説します。
理論1|マズローの欲求段階説
アメリカの心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5つの次元で捉える「欲求5段階説」を1943年に提唱しました。欲求段階はピラミッド型に階層化されており、下位の欲求が充足されることで、より上位の欲求が高まるという理論です。
| 次元 | 欲求段階 | 内容 |
|---|---|---|
| 下位 | 生理的欲求 | 食事や睡眠など、生きていくための本能的欲求 【例】生活を維持できる給与の保障 |
| 安全欲求 | 心身ともに健康で、安心・安全に暮らしたいと願う欲求 【例】安定した雇用、働きやすい労働条件や職場環境 |
|
| 社会的欲求 | 集団に属したい、受け入れられたいと求める欲求 【例】良好な職場の人間関係、組織へのエンゲージメント |
|
| 尊厳欲求 | 他者から承認を得たい、尊敬されたいという欲求 【例】昇進・昇格、組織からの信頼、評価 |
|
| 上位 | 自己実現欲求 | 能力を最大限に発揮して、理想の自分を実現したいという欲求 【例】自分の能力を発揮できる創造的な仕事、夢の実現 |
この理論のポイントは、欲求の種類や強さは一様でなく、置かれた環境によって変化すると主張したところにあります。例えば同じ企業で働いていても職位や家庭環境、経歴などはさまざまで、充足させたいと感じる欲求も異なります。
モチベーションマネジメントでは、こうした各従業員の欲求を理解した上で、その欲求に適した働きかけをすることが重要です。
理論2|ハーズバーグの二要因理論
アメリカの心理学者フレデリック・ハーズバーグが、19世紀に提唱したモチベーション理論です。ハーズバーグはこの理論で、仕事の動機づけを「衛生要因」と「動機づけ要因」に分けて考える必要があると主張しました。
✔衛生要因
職場への不満感を左右する要素で、「不満足要因」とも呼ばれます。満たされていないと職場への不満足感の要因になるものの、改善されても満足感は得られないという特徴があります。具体例は下記の通りです。
- 経営方針
- 給与、福利厚生
- 上司との関係
- 職場の人間関係
- 労働環境
✔動機づけ要因
「促進要因」とも呼ばれ、仕事の満足度に関わる要素を意味します。これらは改善されなくても即時的な不満にはつながりませんが、増加・拡大すれば仕事のモチベーションを高められる可能性があります。
- 周囲からの承認や評価
- 仕事での達成感
- 責任や権限の拡大
- 昇進・昇格
- 自己成長や仕事での挑戦の機会
この理論のポイントは、仕事で満足感がもたらされる要因と不満足につながる要因は、対極の関係にないと指摘した点です。つまり衛生要因の改善に努めても、従業員の満足感が増すわけではないということを意味します。
モチベーションの向上という意味では、特に動機づけ要因が重視されているものの、動機づけ要因と衛生要因は互いに補完し合う関係にあります。
例えば、やりがいはあまりないけれども高収入である仕事は、衛生要因を満たしてはいますが、仕事での達成感や自己成長にはつながりづらいかもしれません。こうした状況にある従業員の離職を防止するには、周囲の評価や成長の機会などの動機づけ要因が必要です。
反対に、創造性を発揮できる希望の仕事ではあるものの、給与や職場環境に不満足なケースでは、衛生要因である待遇面の改善が必要となるでしょう。
モチベーションマネジメントにおいても、このように一人ひとりの欲求や状況を見極めながら、衛生要因と動機づけ要因の両方へアプローチすることが求められます。
理論3|マクレランドの欲求理論
欲求理論は、行動の原動力となる人間の欲求を4種類に分類したモチベーション理論で、アメリカの心理学者マクレランドが1976年に提唱しました。
モチベーションマネジメントでは、従業員の行動がどのような欲求や動機に基づくのか理解する際に用いられ、それぞれの特徴に合わせた管理に役立てられます。4種類の欲求の特徴を下記でみていきましょう。
① 達成欲求
自分自身の力で成し遂げることを望む欲求です。達成欲求が強い従業員は、業績向上への意識が高く、自己実現や自己成長に関心をもつ傾向があります。目標達成に役立つようなフィードバックを好む点が特徴的で、営業職への適性があるといわれています。
② 親和欲求
人から好かれたいという欲求です。親和欲求の強い従業員は、他者との関係を重視しており、競争よりも良好な人間関係や相互理解を望みます。社交的で人の役に立てることに喜びを感じる傾向があるため、対人業務に向いているといわれています。
③ 権力欲求
影響力を発揮して、他者を動かしたいという欲求です。権力欲求の強い従業員は、責任ある立場や他者との競争を好み、地位や名誉を望む傾向にあります。管理職やマネジャーに適しているといわれています。
④ 回避欲求
失敗や批判を回避し、安心・安全な環境にいたいという欲求です。回避欲求の強い従業員は、難しいことには挑戦せず、人と違う意見を述べないといった傾向が見られます。トラブルを回避する能力があることから、事務職や検証業務などで力を発揮するといわれています。
モチベーションマネジメントの重要なポイント
従業員のモチベーションを高めるための重要なポイントは、エンゲージメントの向上です。エンゲージメントとは、従業員が会社や自身の仕事に対してどれだけ熱意を持ち、積極的に取り組んでいるかを示すものです。
エンゲージメントが高まると、ビジョン・理念に対する共感や企業への信頼感も強くなるため、自分の役割に対する責任感が増し、モチベーションが高まります。
また、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑になり、フィードバックやサポートを受けやすくなるため、自分の成長や達成感を感じやすい職場環境も構築されます。これらの要素が相互に作用し、従業員のモチベーション向上につながるのです。
管理職ができるモチベーションマネジメントの具体的な施策
続いて、管理職が実践できる、部下のモチベーションを引き出すための施策を紹介します。
対話型マネジメント
管理職が部下の自律性を高める方法として、「対話型マネジメント」があります。双方向のコミュニケーションを通じて、管理職が経営層の考えや会社の方向性などをわかりやすく伝えることにより、従業員の自発性や成長、納得感を引き出す手法です。
一人ひとりの感情や価値観も尊重しながら、従業員のエンゲージメントやモチベーションの向上を促します。
社会の変化が加速するなか、トップダウン型や細かい進捗管理で動くのではなく、自律的に問題解決へ取り組める人材が求められていることから注目が高まっています。対話型マネジメントの代表的な方法が1on1ミーティングです。詳しくは下記のコラムをご覧ください。
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックは、従業員の強みや努力、姿勢などの良い点に着目し、肯定的な言葉がけや評価で自信を高め、成長を促す手法です。
上司からの期待や応援が伝われば、従業員のそれに応えようとする気持ちも高まりやすくなります。管理職との信頼関係が強化されるほか、自己効力感や主体性を引き出す効果も期待できます。
効果的なポジティブフィードバックの方法は、こちらの記事をご覧ください。
心理的安全性の醸成
心理的安全性の高い職場づくりも、管理職のモチベーションマネジメントにとって重要な施策です。
職場の心理的安全性を高めるために、下記のような施策を行いましょう。
- 発言の機会を平等に設ける
- ポジティブな考え方と言動を意識する
- 1on1ミーティングの効果を高める
- 新人のサポート体制を強化する など
具体的な方法は、下記のコラムでも詳しく解説しています。
企業全体のモチベーションを高める具体的な施策
企業全体では、従業員のモチベーションを高めるために何ができるのでしょうか。具体的な施策を6つ紹介します。
適切な人材配置
適材適所の人材配置は、従業員のモチベーション向上に効果的な施策です。スキルや経験、希望に合った仕事は、業務の効率化やストレス軽減、モチベーションの上昇につながり、自律的な働き方も促進します。
人材配置を適正化するには、各業務に求められる能力と従業員のスキル・経験とのマッチングが重要です。企業側は従業員の現状のみで判断せず、中長期的な成長やキャリア展望も加味した配置を考える必要があります。
定期的なヒアリングで従業員の希望を把握しつつ、適性検査や360度評価なども活用しながら、総合的な視点で判断しましょう。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、人材の有効活用に役立つアセスメントツールを目的別・階層別にご用意しています。詳細は下記からご覧ください。
人事評価制度や待遇の見直し
会社からの評価や待遇は、外的動機づけとして従業員のモチベーションを大きく左右する要素です。評価基準の曖昧さ、努力や成果が反映されない待遇などがみられる場合、人事評価制度の見直しを検討すべきでしょう。
制度見直しのポイントは次の通りです。
- 経営方針や経営課題を反映できているか
- 成果のみならず、意欲や勤務態度も考慮した評価基準になっているか
- 明確な評価基準や評価方法を構築できているか
- 人事評価制度に透明性があるか
- 評価者向けの研修を実施しているか
適切な評価と正しい処遇が受けられる人事評価制度を整えて、社内に広く周知しましょう。また、人事評価制度の形骸化を防止するため、評価基準や評価方法の定期的な見直しも欠かせません。
JMAMでは、管理職の評価バイアスを判定するWebテストを提供しています。人事評価制度を見直す際にご検討ください。
ワークライフバランスの実現
ワークライフバランスを実現する施策は、従業員と企業の双方に利益をもたらします。育児・介護と仕事を両立する従業員のモチベーション維持や離職の防止にも効果的です。
下記は、企業によるワークライフバランス施策の具体例です。
- 育児休暇や有給休暇の取得促進
- 短時間勤務の導入や残業時間の削減
- 家事代行や介護費用の助成といった家事・育児の支援
- テレワークやフレックスタイム制を導入
社内におけるコミュニケーションの活性化
社内コミュニケーションは、良好な人間関係の土台です。職場のコミュニケーションが活発になれば、業務効率や情報共有のみならず、従業員のモチベーションにも良い影響を与えるでしょう。
社内コミュニケーションを見直す際は、課題の発見や改善などを行う前に、現状を客観的に把握するプロセスが必要です。コミュニケーションの質や活性度、満足度などを測るための測定方法として、下記があげられます。
- ストレスチェック
- 従業員満足度調査
- 職場の強みチェックリスト
- 360度評価
現状を把握できたら、下記の例を参考に、自社の状況に合った具体的な施策を検討してみましょう。
- 社内SNSや社内コミュニケーションツールの活用
- 1on1ミーティング
- フリーアドレス制の導入
- リフレッシュルームの設置
- 社内サークルやイベント
従業員の健康増進への投資
従業員の健康維持・増進を図る「健康経営」の取り組みは、生産性向上を目的に、今や広く普及しています。その理由として、従業員のストレスや心身の疲労・不調は、個人の問題にとどまらず、離職率や企業の生産性、株価にまで波及する課題と捉えられているからです。
人的資源でもある従業員の健康増進への投資として、具体的には定期検診の実施やメンタルヘルスケアの支援、健康的な食事や運動機会の提供などが行われています。中でもモチベーションに大きく関与するのがメンタルヘルスケアです。
具体的には、次のような施策があげられます。
- 相談窓口の設置
- メンタルヘルス不調の早期予防・早期発見のための体制整備
- セルフケア研修・セミナーの実施
- メンタルヘルスケアに関する管理職の研修
従業員のメンタルヘルスケアには、JMAMの研修もご検討ください。
ビジョン・理念の浸透
ビジョンや理念の浸透は、社内の価値観の統一、従業員にとっての仕事の意義や価値の理解などに役立ち、企業全体のエンゲージメントやモチベーションの強化につながります。
多くの場合、ビジョン・理念を知っているだけでは、エンゲージメントの獲得をはじめ、仕事への姿勢や行動の変化にまでは至りません。社内へビジョン・理念の浸透を図り、理解が深まってこそ従業員のエンゲージメントが高まるでしょう。
下記は企業全体へビジョン・理念を浸透させる施策の例です。
- 社内報におけるメッセージの発信
- クレドカードの作成
- ビジョン・理念への理解を深める研修・セミナー
- ビジョン・理念を反映させた人事評価制度
まとめ
モチベーションマネジメントは、従業員の成長や企業の生産性向上、離職率低下にも有効な手法です。従業員のやる気を引き出すためにも、まずは職場環境を見直し、モチベーションが低下する要因を取り除きましょう。
また、適切な人材配置や人事評価制度、対話型マネジメントなどにより、多角的な視点から働きやすい環境を整えることが重要です。
パフォーマンスにつなげるエンゲージメント調査
「自社のモチベーションマネジメントの問題点を知りたい」「離職率を低下させたい」といった課題の解決を図る上で、エンゲージメント調査は有効な手段のひとつです。今やHR領域では欠かせない指標として活用されています。
JMAMの「パフォーマンスにつなげるエンゲージメント調査」は、仕事や報酬・評価などが従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントに与える影響を可視化したレポートです。この機会にぜひご覧ください。
調査資料|パフォーマンスにつなげるエンゲージメント調査
エンゲージメントや満足度はどのように変化しているのか経年で比較調査
エンゲージメントを「従業員エンゲージメント」と「ワークエンゲージメント」に分けて、それぞれに影響を与える要素を「仕事」「職場」「報酬・評価」といったカテゴリー別に紹介しています。
- 経年比較から見るエンゲージメント
- 経年比較から見るカテゴリー別満足度調査
- GAPで見るエンゲージメント
- 調査結果から見るエンゲージメントを高めるポイント

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















