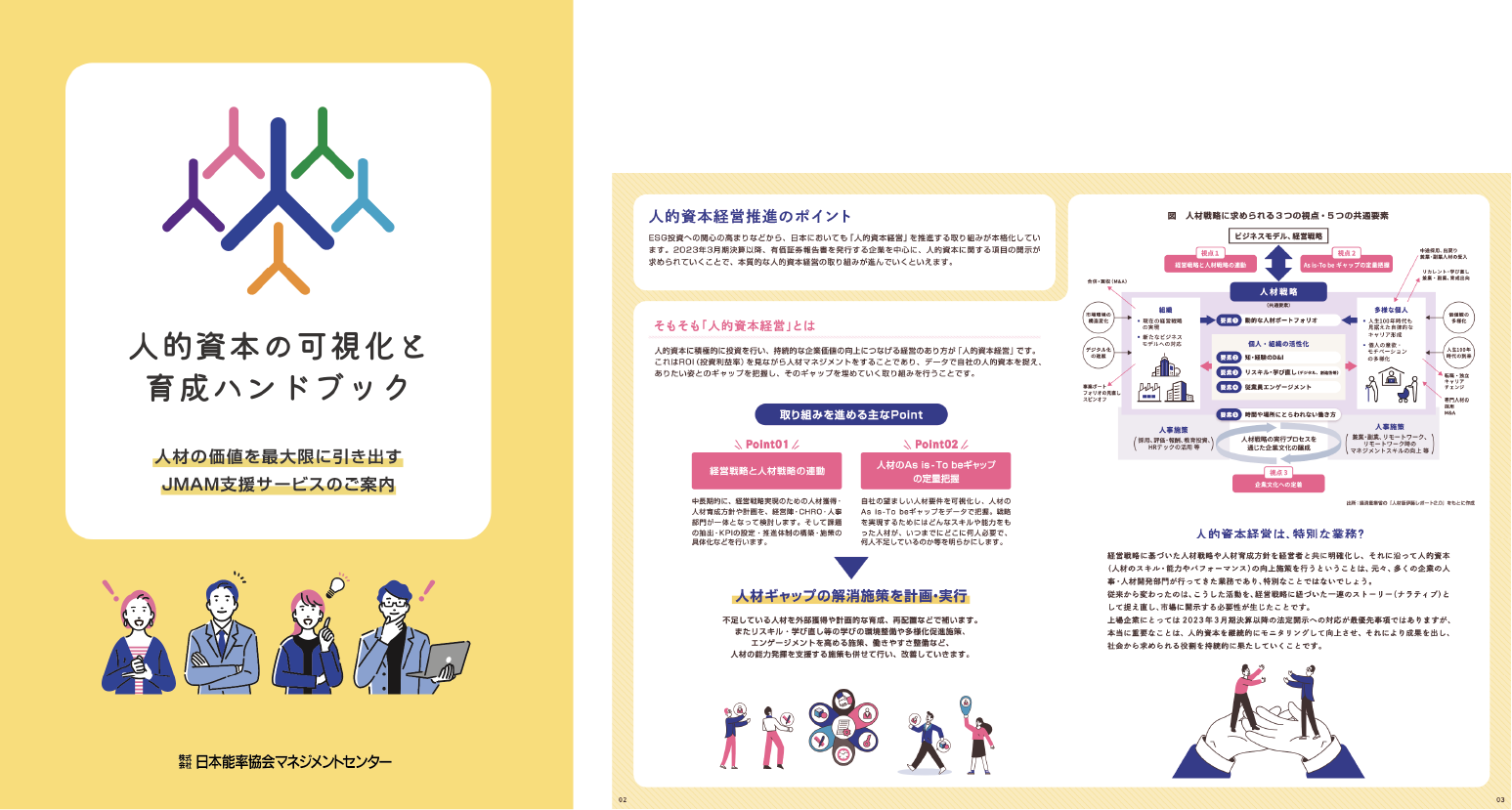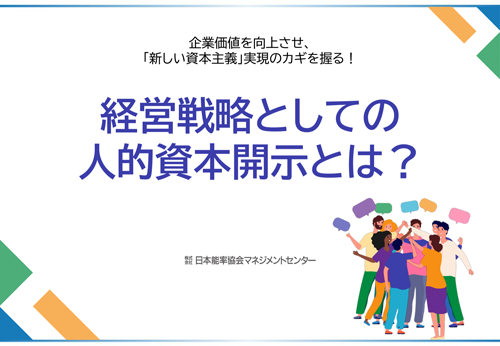ビジョン実現を支える
人材戦略・マネジメント
朝山 玉枝氏
イケア・ジャパン カントリー・ピープル&カルチャー マネジャー
人への投資を積極的に行い、企業の持続的価値の向上につなげる人的資本経営。それをまさに体現する企業といえるのが、スウェーデン発のホームファニッシング(家具・家庭用品)ブランドを展開するイケア・ジャパンです。「一人ひとりが成長することでより良い企業になる」と信じ、従業員のエンゲージメントも高い同社では、従業員の自由意志を尊重しつつ意欲を高めながらビジョン実現・バリュー徹底をめざす働き方改革やマネジメントが行われています。実務家のエキスパートとして、同社の人事部門を統括する朝山玉枝氏に聞きました。
取材・文=増田忠英 写真=イケア・ジャパン提供/PIXTA
- ビジョン「より快適な毎日を、より多くの方々に」を実現するための人材戦略
- 進むべきキャリアを自分で決める「ジャングルジムキャリア」
- ビジネスの変化に対応するためのアップスキル、リスキル
- マネジャーの役割は「ビジネス」と「ピープル」が半々
ビジョン「より快適な毎日を、より多くの方々に」を実現するための人材戦略
Q人的資本経営では、経営戦略と人材戦略の連動が重要とされています。まず、貴社の経営戦略についてお聞かせください。
朝山 玉枝氏(以下敬称略)
イケアのビジョンは「より快適な毎日を、より多くの方々に」お届けすることです。そのために私たちが大切にしているのが、8つの価値観からなるイケアバリュー※1です。イケアバリューは全ての基本であり、日々の業務の道しるべとなるものです。
ビジョン実現のために、経営戦略として3つの大きな柱を持っています。1つめは「アフォーダビリティ(お手ごろ感)」。デモクラティックデザイン※2の理念に基づいたイケアの製品を、お客さまにお手ごろな値段でお届けすることです。2つめは「アクセシビリティ」。店舗だけでなく、様々な場所で利用しやすくすることに取り組んでいます。そして3つめが「サステナビリティ」。人、社会、地球にポジティブな影響を与えることです。
この3つの戦略のもと、イケアがいま目指しているのが「オムニチャネルリテイラー」になること。イケアは従来、郊外の大型店舗を中心に事業を展開してきましたが、近年はオンラインストアや都心型店舗、期間限定のポップアップストアを開設し、従来アフターサービスを中心に行ってきたカスタマーサポートセンターでもセールスを行うように変わってきています。また物流の面でも、店舗のないエリアに商品受取りセンターを設けるなど、様々な形でお客さまとのタッチポイントを増やし、総合的にアプローチするオムニチャネル化を加速させています。
※イケアバリュー:「連帯感」「環境と社会への配慮」「コスト意識」「簡潔さ」「刷新して改善する」「意味のある違うやり方」「責任を与える、引き受ける」「手本となる行動でリードする」の8つからなる。
※デモクラティックデザイン:デザイン、機能性、品質、サステナビリティ、低価格の5つの要素を考慮した製品づくりを行うイケアのデザイン哲学。

Qその経営戦略を実現するために、どのような人材戦略を取っているのでしょうか。
朝山
これらの経営戦略を推進するには、「生産性の向上」が人材戦略上の大きなポイントになります。コワーカー(従業員)一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるようになるために、働き方の変革と、オムニチャネルに合ったコワーカーの価値向上のための教育機会の提供(アップスキル・リスキル等。後述)の2つに取り組んでいます。
デジタル化の進展などによってもたらされる新しい働き方の方向性は、働く私たちにとってもチャンスだと捉えています。たとえば、店舗でお客さまから最もよく聞かれるのは「この商品はどこにありますか?」という質問です。こうしたベーシックな質問は、今後はおそらくデジタルが対応してくれるでしょう。そしてその代わりに、私たちが本当にやりたいことがもっとできるようになるのではないかと考えています。
私たちがお客さまに最もお伝えしたいのは、商品の魅力であり、家での暮らしをより良くする「ライフ・アット・ホーム」の考え方です。日本におけるライフ・アット・ホームの浸透はまだまだ道半ばです。家の中がもっと快適になるようなアプローチができることを、私たちは楽しみにしています。
進むべきキャリアを自分で決める「ジャングルジムキャリア」
Qイケアにおける人材と、キャリアについてのお考えをお聞かせください。
朝山
イケアは、一人ひとりが成長することによってビジネスも会社も成長すると考えています。そのため、人の力を信じるアプローチをとっているところがポイントと言えます。私たちは「イクオリティ(平等性)」「インクルージョン(多様性の受入れ)」「セーフティ」の3つを重視して働く環境を整備しています。
「イクオリティ」の面では、平等な機会を徹底的に追求しています。平等な機会がなければ、自分の可能性を拓こうと思わなくなり、諦めてしまうかもしれないからです。「インクルージョン」では、多様な考え方の人が認められ、リスペクトされる環境を用意しています。「セーフティ」については、「自分の意見を正直に言っても大丈夫」という、安心して働ける環境を整えています。
こうした環境をベースに、自分の成長に責任を持ち、どのように成長していきたいかを自分自身で決めてもらいます。会社から辞令が出ることはありません。社内公募制度(オープン・イケア)を通して挑戦したい役割に応募したり、職務を異動することができます。上のポジションを目指す人もいれば、現在のポジションを突き詰めたいという人もいます。また、ライフステージに合わせて勤務時間を減らした働き方を選ぶこともできます。誰もが自由に自分の目指したいところへ進んでもらえばいい──それが、当社の「ジャングルジムキャリア」という考え方です。
Q人材ポートフォリオのAs is - to beギャップを埋めるという観点や、サクセッションプランについては、どのように取り組まれていますか。
朝山
会社が求めるポジションに人が足りないということもあります。そのため、会社としてサクセッションプランは用意しており、各ポジションに就ける人のリストはあります。しかし会社から強制することはなく、あくまでも本人の意志でポジションに就いてもらうようにしています。
たとえば、新店舗のフードマネジャーのポジションが必要で、なり手がいない場合。コワーカーに素質があっても、その仕事をする自信がないケースが考えられるので、そのポジションに必要なトレーニングやアクティビティを企画して、コワーカーのアウェアネスを促す施策を行うことはあります。もちろん、トレーニングへの参加は本人の意思に委ねられます。また、そのポジションに対するコワーカーの意欲を促すために、毎月行われているマネジャーとの面談の場でコーチングを行いながら、必要な支援を行う体制をとっています。
サクセッションプランで強化していかなければいけないと考えているのは、「常にバリューが中心」という考え方です。「連帯感」「環境と社会への配慮」「コスト意識」「簡潔さ」「刷新して改善する」「意味のある違うやり方」「責任を与える、引き受ける」「手本となる行動でリードする」、の8つが少しでもずれると、どこかにひずみが生じます。そのため、これらのバリューをもとにリーダーシップがとれる人を重視しています。
また、様々な考え方を受け入れてビジネスにうまく反映させていくために、インクルーシブなアプローチをとれる能力を、さらに伸ばしていくことが課題です。
ビジネスの変化に対応するためのアップスキル、リスキル
Qワーカーの価値向上のための教育機会の提供についてお聞かせください。貴社の「Data and Progress FY21」には、カスタマーサービス、設備、ストア(customer service, facilities and store)のコワーカーに対し、アップスキル、リスキルの機会を提供していることが記載されていました。人的資本経営において、リスキルや学び直しも重要な要素の1つとされています。
朝山
私たちがアップスキル、リスキルに注力するようになって5〜6年が経ちます。理由は、お客さまのニーズやビジネススタイルの変化に対応するためです。たとえば、現在、店舗にて写真のようなセルフレジが増えていくことに伴い、そこで働いてきたコワーカーは同じ部署内で違う業務についたり、新しい業務にチャレンジします。そのために必要なスキルを習得する機会を提供しています。

カスタマーサポートセンターの役割も、従来のアフターサービスにセールスが加わり、キッチンの担当であれば、キッチンの売り場で研修を受けるといった、オムニチャネル化に対応するために必要なプログラムも用意されています。
なお、こうした職場に起こる変化は、早い段階から社内でシェアされています。いまビジネスで行っていること、これから起こり得ることについては、コワーカーとオープンにコミュニケートしているため、新たな学びの必要性をコワーカーもあらかじめ意識しやすいと思います。
また、コワーカーが社内公募でやりたい仕事に就けるようになるための学びの機会も、柔軟に提供しています。将来フードの仕事がしたい場合には、マネジャーと相談して、1週間フードの現場を体験するといったこともできます。もちろん、現在の業務が軽減されるわけではありませんので、トレーニングの時間を捻出するために忙しくはなってしまいますが。
コワーカーの成長に関しては、毎年の目標設定と学びは一体で、「仕事を通じて成長する」ことに重点を置いています。各自の目標はマネジャーと話し合って設定しますが、必ずストレッチがかかるように設定されるので、目標到達のために必要な個人のデベロップメントポイントも一緒に設定します。eラーニングを中心に、様々な学習コンテンツを用意していますが、学ぶ機会の中心はやはり現場です。
なお目標設定は、以前は年に一度でしたが、変化のスピードが速くなっているため、途中でフレキシブルに修正できるようにしました。また、チーム内での各自の目標の決め方はマネジャーにお任せしています。私の場合は、まずチームのゴールを全員で確認したうえで、そのゴールに対してどのような貢献ができるかを、各自の業務遂行責任に基づいて個別に提案してもらい、最後に皆でシェアするようにしています。なかには、チーム全員で話し合って決めているマネジャーもいます。
マネジャーの役割は「ビジネス」と「ピープル」が半々
Qコワーカーのキャリアを支えるマネジャーの存在が重要だと感じました。改めてイケアにおけるマネジャーの役割と、マネジャーに対する会社としてのサポートについて教えてください。
朝山
マネジャーの役割については、「ビジネス」と「ピープル」に半々の比重を置くことを大事にしています。会社のサポートとしては、マネジャーのためのリーダーシップトレーニングを用意しています。
マネジャーの役割で最も重要なことは、どういうタレントを見つけ出すかということです。イケアの成長のためには、その仕事に適した人を見つけるのではなく、イケアのバリューに適した人や、イケアの将来に必要なポテンシャルを備えている人を見つけて、その人たちに投資していくことが大事になるからです。
採用では、どうしても仕事に適した人を候補にしがちですが、イケアでは何よりもバリューに合った人を採用し、スキルに関しては後から育てていくようにしています。そのため100%を求めず、80%でいいから失敗を恐れずにやってみる、ということを大事にしています。
恐れずにやってもらうためにはある程度の裁量が必要で、イケアはコワーカーに裁量を与える重要性を信じています。イケアバリューにもある「責任を与え、責任を引き受ける」ことは、個人として成長し能力を伸ばすための有効な方法です。互いを信頼し合い、ポジティブで前向きな考え方をすることが、発展に貢献したいという意欲を全員に与えます。
Q人材の育成面における課題や、今後の展望をお聞かせください。
朝山
今後の育成面でのポイントは「リーダーシップ・バイ・オール」です。イケアバリューにも「手本となる行動でリードする」という項目がありますが、リーダーシップはマネジャーだけでなく全てのコワーカーに求められるものです。リーダーシップがなければ何も変わっていかないため、リーダーシップの育成にとても力を入れています。
学びというと、未だに教室などで学ぶイメージが強いですが、本来、学ぶことは日常的なことであり、自ら学ぶ姿勢を持つことが大切です。学びを待つ姿勢がどうしても強いので、そのマインドを変える必要があり、ラーニングカルチャーをつくっていくことも課題と考えています。コワーカーのライフステージは様々で、学びたい時間や場所も異なりますから、1つのやり方では対応しきれません。スマホで手軽に学びたいという人もたくさんいます。そのため、多様な学び方ができる環境を充実させることが必要だと考えています。
また、これは私個人の考えですが、これから特に意識を変えていかなければいけないのは、皆さんが自分の生活と仕事を、自らデザインして働けるようになることです。会社の中で働く時代は終わり、これからは個人が会社と契約して働く時代になっていくのではないかと思います。そうすることで自分の成長に責任を持つことを大事にした方が、個人も会社もより成長できるのではないでしょうか。

朝山 玉枝氏
あさやま たまえ
イケア・ジャパン カントリー・ピープル&カルチャー マネジャー
他のエキスパート解説を読む