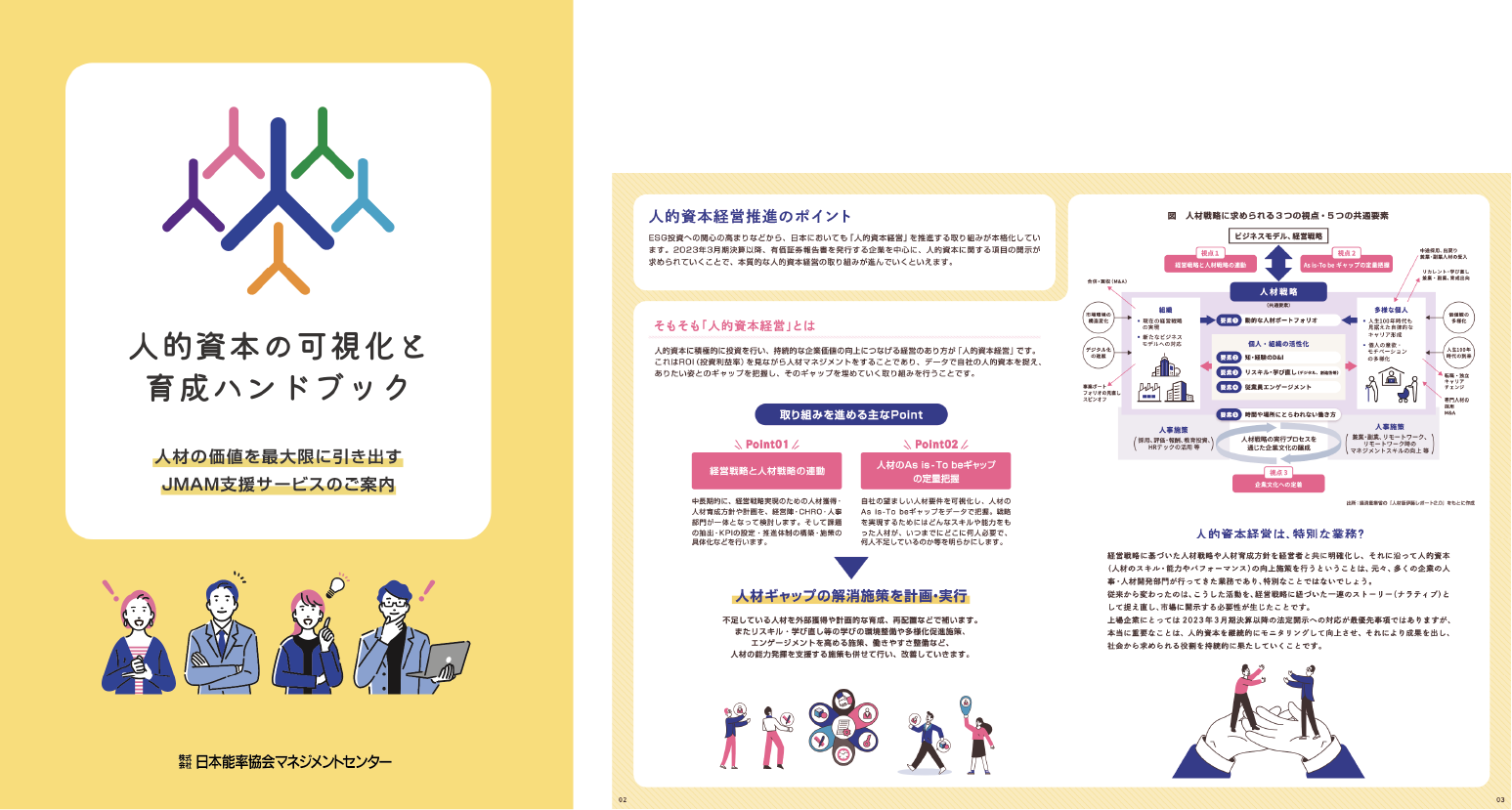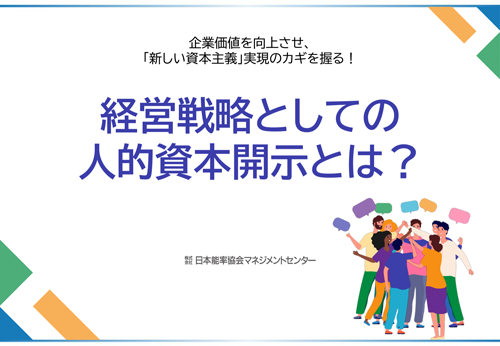人への投資と労働生産性の相関を
どう開示するか
滝澤 美帆氏
学習院大学 経済学部 教授
人的資本の開示で悩ましいのは、人への投資が企業の業績にどう貢献しているかを示すことではないでしょうか。そのために重要となる、人的資本と労働生産性の計測方法や両者の関係などについて、マクロ経済学や生産性分析などを専門とする学習院大学経済学部教授の滝澤美帆氏にお聞きしました。
取材・文=増田忠英 写真=滝澤美帆氏提供
- 人的資本は国を成長させるための重要な要素
- 人的資本はどのように計測すればよいか
- 人的資本投資は労働生産性にプラスに作用する
- 労働市場の流動化と人的資本投資の両立が重要
- ジョブ型人事によって、人的資本投資は行いやすくなる
- 産業・業種別に見て強化すべき人的資本
- 自社の目的に合致した人への投資を「等身大」で伝えるべき
人的資本は国を成長させるための重要な要素
Q「人的資本経営」という言葉がややブームになっています。この言葉自体やブームになっていることについて、どう受け止めていらっしゃいますか。
滝澤 美帆氏(以下敬称略)
私の専門はマクロ経済で、特に「生産性はどうすれば上がるのか」について長らく研究しています。日本では生産性がなかなか上がらない状況がありますが、どうすればよいかを考える際に、経済学では人的資本の重要性が長年にわたり指摘されてきました。したがって、人的資本に注目が集まること自体は、とても良いことだと思います。
ただ、経済学では、人的資本(ヒューマンキャピタル)という言葉はかなり以前から使われています。1960年代には、既に経済学の著名な先生方が論文や著書などで取り上げていました。私の専門のマクロ経済学には、経済成長論や経済発展論など、国がどのように発展していくのかを研究する分野があるのですが、その教科書の中で人的資本という言葉が使われないことはほとんどありません。経済学では昔から慣れ親しまれている言葉です。
人的資本という言葉がこれほど注目されるようになったのは「人材版伊藤レポート」が公表されてからだと思いますが、それ以前から、日本は人口減少により人手不足が深刻になっていました。その状況を補うための手立てとして、人的資本を蓄積して国を維持していこうということで、既に人的資本は重要視されていました。それだけに、今になって非常に注目されている状況については、やや驚いています。
人的資本はどのように計測すればよいか
Q人的資本経営や人的資本開示が数年前から企業に迫られる中、投資家は人への投資が企業の生産性や業績にプラスに作用することの論拠を求めており、企業はその証明に苦しんでいるようです。経済学では、先生の研究や先行研究も含めて、その証明をどのようにされているのでしょうか。まず、人的資本の計測方法から教えてください。
滝澤
人的資本の計測には様々な方法がありますが、「測るのが難しい」というのが我々の認識です。各企業の人的資本を計測したくても、正確に計測するのは難しいというのが大前提としてあります。
人的資本への投資をどの程度従業員に対する教育を実施したのかで計測する場合、会計上は「教育訓練費」という費用として計上されています。従って、教育訓練費を増やせば、売上に占める費用が増えることになり、利益が小さくなってしまうということで、この20〜30年、企業は人的資本を増やすことに二の足を踏んでいたように思います。
経営学や会計学では個々の企業のケースに着目しますが、経済学では、企業のビッグデータを集めて、共通の手法で各社の人的資本を計測し、生産性との間にどのような関係性があるのか、比較可能性を担保した分析をしています。データが限られているため、基本的に「教育訓練費」という費用を投資額として考えます。これを「コストベースアプローチ」と呼びます。たくさんお金をかけたら、その分、投資をしたと考えるわけです。
教育訓練費を積み上げていくことで、人的資本投資のストック額を計算します。その際にいつも議論になることがあります。建物や設備などが年々古くなっていくのと同様に、従業員が教育訓練を受けたことで蓄積した知識の内容も古くなっていきますが、その減耗率(価値が減少する割合)をどう測るかということです。先行研究では25%や40%など、割と大きな減耗率が仮定されています。そのデータを当てはめて、一社ごとに人的資本ストック額を計算して労働生産性との関係を比較します。
ただし、注意点として、ここで人的資本投資の対象として見ているのは教育訓練費、つまり集合研修などのOff-JTにかかった費用になります。日本では、職場で先輩から直接教わるOJTの割合が高いといわれていますが、経済学ではその部分を測ることができていません。OJTに関しては、どのくらい時間をかけたかをアンケート調査で測ることが多いです。その結果から、総労働時間に占めるOJTにかけた時間の割合を計算できますので、それに賃金総額をかけて、その企業のOJT投資額を計算するという方法があります。
ただ、この方法はアンケートを取る必要があるため、分析対象となるサンプルは少なくなります。また、国際比較も難しくなります。ですから、経済学における人的資本投資は、Off-JTへの投資を指していると考えていただくとよいでしょう。
Q労働生産性はどのように測るのでしょうか。
滝澤
生産性の定義は「アウトプット ÷ インプット」であり、労働生産性の場合はインプットを労働で測ります。企業ごとの労働生産性を測る場合は、その企業の従業員数×平均労働時間がインプットになります。企業が1年間にどのくらい労働投入したかを示す「総実労働時間」がわかれば、なおよいでしょう。分子(アウトプット)で一番良いのは付加価値、つまり企業が新たに生み出した価値の金額です。例えば、売上から中間投入費用を引いた金額です。この割り算をすることによって、その企業の1時間あたりの労働生産性がわかります。
人的資本投資は労働生産性にプラスに作用する
Q人的資本投資と労働生産性の関係は、どのように分析するのでしょうか。
滝澤
まず、人的資本投資額と労働生産性との相関関係を見ます。人的資本投資をしてから効果が出るまで時間がかかる可能性がありますので、タイミングをずらして、1〜2期後の労働生産性を見るという形で時差の相関を見たりします。このようにして行われた先行研究の多くが、人的資本投資は労働生産性にプラスに作用していると結論づけています※。
※村田治(2019,関西学院大学)等。
人への投資は設備投資と違い、効果が現れるまでに割と時間がかかると考えられていますが、我々の研究成果ですと、一期差くらいでも正の関係が見られますので、一般に考えられているよりも早く効果が出ている感触はあります。
ただ、人的資本投資が労働生産性になぜプラスに作用するのか、そのメカニズムに関しては様々な見方があります。例えば、人へ投資すると従業員の意欲が高まり、エンゲージメントが高まる。すると、どうすれば効率的に仕事ができるかを自ら探求するようなプロアクティブな行動につながり、その結果生産性が上がる、という研究をしている人がいます。
あるいは、例えばIT研修を受けてデジタルリテラシーが上がると、業務を効率化できるので、それによって生まれた余裕をイノバティブな行動につなげることで付加価値が増えて生産性が上がるといった経路も考えられます。
 ※イメージ
※イメージ
Q企業が人的資本を開示するにあたり、ぜひアドバイスをお願いします。
滝澤
何らかのエビデンスを示すと良いでしょう。自社データで検証する方法が1つあります。こういう投資をしたら、こういう成果がありましたということを、統計的に示すのです。最初は単純な相関でも良いと思います。
もう1つは、我々のような研究者が研究結果を公表していますので、「先行研究では人的資本投資と労働生産性あるいは利益率が正の相関をしています。だから当社ではこれに力を入れていきたいと考えています」という示し方もあります。
さらに単純な方法としては、産業別の統計が公表されていますので、「業界の教育訓練費の平均よりも当社は多いです」という示し方もあります。荒削りでもいいので、データに基づいた説明を行えば、自社の経営陣も投資家も求職者も、納得しやすいのではないでしょうか。
労働市場の流動化と人的資本投資の両立が重要
Q「失われた30年」は、日本の人的資本の点で見ると、何が失われた時代で、それを取り戻すためには政府・企業はどんな役割を果たし、何を強化すべきでしょうか。
滝澤
「失われた」という言葉は、我々の中では基本的に経済成長がなかったことを指しています。バブル経済崩壊以降の30年間、日本では高い経済成長はもってのほかで、経済の停滞が続いてきました。GDP(国内総生産)成長率がそれ以前と比べると非常に低くなり、それに伴って企業ができなくなったことがいくつかあります。不幸にしてそのうちの1つが「人的資本投資」です。
バブル期は、従業員を海外に留学させてMBAを取らせるなど、人材の研修や経験付与にある程度の投資をしていたという話を聞きます。しかし、私がアメリカに留学していた2013年頃は、日本人が非常に珍しがられていました。バブル崩壊以降、経済全体に資金的な余力がなくなり、人への投資が思うようにできていなかったのが「失われた30年」だと思います。
もちろん、企業を存続させるために費用を節約して、企業を倒産させない、雇用を守らなければいけないという時期はあったでしょう。ただ、それは多分2000年代前半までで、少なくともここ10年は企業が徐々に資金を蓄積してきた時期ですので、本来であれば、人的資本を増やしていくべきでした。
一方で、この間、日本全体で雇用を調整しやすくしようという動きがあり、非正規社員が増えてきました。非正規社員への教育訓練投資は正規社員よりも少なくなるので、結果として経済全体の人的資本投資額が減ってきた側面もあります。
失われた30年を取り戻すには、まず、適材適所の人材配置で生産性を高めるために、労働市場を流動化させることが必要です。日本は、人材の再配分(リアロケーション)のメカニズムがうまくいっていなかったと言われています。例えば、非常に生産性の高い企業が規模を拡大できていない一方で、生産性の低い企業が市場から退出していません。つまり、良い企業に人が移動できていないわけです。それが、日本の再配分効果の低さとしてデータに現れています。
ただ、人が簡単に他社へ移ってしまうと、「どうせ出ていってしまうから」と企業が従業員への投資に二の足を踏む恐れがあります。それに対して補填するのが政府の役割だと思います。教育訓練費に対して減税や補助金などの形で補填することによって、中小企業でも人への投資が増え、日本全体の人的資本投資が増えることにつながります。
企業の役割は、これまで圧倒的に少なかった人的資本への投資をもっと増やすことです。たとえ人材流動性が高まっても、社会や経済全体を良くしようという気持ちで人へ投資するのです。そうすることが、結果として自社の将来にも良い影響をもたらす可能性があります。
また、人的資本投資の日米比較を実施した学習院大学の守島基博先生によれば、アメリカでは、自社に必要な人材を部署や仕事ごとに細かく明確化し、人を採用したら、その人にカスタマイズした人的資本投資をしているようです。日本でも、一律で採用して同じ研修を受けさせることも大事ですが、より一人ひとりに適した形で教育訓練をしていくことが求められます。
Q日本企業の多くの経営者が人材の重要性を説いていながら、人的資本投資が増えなかったのはなぜでしょうか。
滝澤
恐らく、多くの企業が注力してきたのはOJTではないでしょうか。OJTは「企業特殊的な人的資本」、つまり企業固有のスキルを蓄積するうえでは重要な取り組みです。しかし、OJTだけではイノベーションや付加価値の点では伸長しないことが先行研究で指摘されています。ですから、新しい知識を仕入れるためにOff-JTを増やす必要があります。
例えば、小売業のある企業では、特定の有望な従業員に、海外の芸術について学ばせるなど、業務と直結しないような教育訓練をさせているそうです。Off-JTで専門外の知識を吸収することも、付加価値を高めるためには重要でしょう。
QOff-JTに関連してご質問です。Off-JTよる教育訓練費が多い方が、対外的なイメージアップにつながりそうです。そのため、それまで社内講師に担ってもらっていた研修を社外講師に代えることで投資額を増やすこともできそうですが、そこに問題はないのでしょうか。
滝澤
とても重要なポイントだと思います。本来は社内講師の方が適している研修を、人的資本開示のために外部講師に依頼するのは本末転倒です。確かに、社外講師に依頼すればP/L上の教育訓練費の項目でカウントできますが、社内講師の場合は難しいかもしれません。
ただ、本来であれば、社内講師の費用も人的資本投資額としてカウントすべきです。社内講師の場合は、社員が講師業務に携わった時間当たりの費用を給与から割り出すことができます。講師として費やした時間で評価するなど、工夫次第で様々な開示の仕方が考えられます。
 ※イメージ
※イメージ
ジョブ型人事によって、人的資本投資は行いやすくなる
Q話は変わりますが、多くの企業で、ジョブ型人事制度の導入が進んでいます。日本的雇用慣行が大きな転換期を迎えていますが、気をつけるべき点はありますか。
滝澤
ジョブ型雇用が進むと、基本的に労働の流動性は高まっていくと思われます。労働の流動性が高まれば、適材適所で生産性の向上につながりますので、ジョブ型になっていくことは良い流れだと考えます。
ジョブ型の方が、企業は人的資本投資をしやすいと思います。階層別だけでなく仕事単位でどういう教育をすべきかが、より明確になるからです。また、人材タイプ別の教育効果も計測しやすくなりますので、トライアル&エラーで人的資本投資が進みやすくなるのではないかと考えています。
ただ、転職する際に、短い期間であっても失業状態になる可能性があります。それが嫌でリスクを取りたくないという人もいるかもしれません。そこで、失業状態になったとしても、次の職に移るまで安心できるセーフティネットの仕組みが拡充されていく必要があります。
もう1つはマッチング機能です。労働者のジョブディスクリプション(職務記述書)と企業の求める人材像がスムーズにマッチングできるような機能が必要ではないでしょうか。
産業・業種別に見て強化すべき人的資本
Q産業や業種で見た場合、今後特に、どんな分野の人的資本を、どのように強化すべきでしょうか。
滝澤
これは、現状を見て、人的資本投資が少ない分野がどこかを考えることです。現在は雇用の7割が非製造業ですが、この20〜30年、製造業よりも非製造業の方が人的資本投資の伸びが芳しくありませんでした。従って、非製造業の人的資本投資を増やしていくべきだと思います。
非製造業の人的資本投資が伸びない要因の1つは、非正規社員が多いことです。ただ、正規も非正規も同じ仕事をしている場合は、教育機会も均等化されるべきですので、同一労働同一賃金を推し進めることが対策として挙げられます。
Qデジタル人材資本やDXへの投資という点ではいかがでしょうか。日本はやはり足りていませんか。
滝澤
日本はデジタルに関する投資ではアメリカと比べても、実は負けていません。GDPに対するデジタル投資額の割合は、アメリカと遜色ない水準です。また、研究開発費も決して少なくありません。それでもDXが進んでいないのはなぜかというと、やはり人に投資できていないという事実があります。DXは人への投資と密接に関係しており、デジタル投資だけでは不十分です。今までできていなかった人への投資を同時に進めていかなければ、DXは進みません。
自社の目的に合致した人への投資を「等身大」で伝えるべき
Q最後に、人的資本の開示を目的化すると、真に意味のある人材マネジメントがおろそかになる懸念があるのではないかと考えますが、先生はいかがお考えでしょうか。
滝澤
「開示のための開示にならないように」ということは、よく言われています。私は日本経済新聞社の「スマートワーク経営研究会」のメンバーとして、評価の高い企業からよく話を聞くのですが、良い企業ほど開示については「等身大でやる」「ありのままを伝える」と言います。恐らくそういう企業は、人的資本投資の目的をはじめから理解してやっているのでそうできるのでしょう。
ただ、多くの企業は、何をどのように開示すればいいのか悩んでいらっしゃるでしょう。基本的には、自社のミッションに合致した人的資本投資を考えてアピールしていく必要があります。取り組んでいることを等身大で見せるべきです。
最もよくないのは、「言われたから開示する」という姿勢です。報告書の中に唐突に教育訓練費が一人あたりいくらと書かれていても、その意味を読み取ることはできません。そこは読み手を考えて、投資家であれば「投資したい」、求職者であれば「働きたい」と思ってもらえるような書き方をする必要があります。
人的資本投資の効果をすぐに検証するのは難しいものですが、「こういう取り組みをしたことにより、こういう成果が出ました」という形で開示することが最も望ましいと思います。

学習院大学 経済学部 教授
2008年、一橋大学にて博士号(経済学)取得。日本学術振興会特別研究員(PD)、東洋大学、ハーバード大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経て、2019年より学習院大学准教授。2020年より現職。現在は、中央省庁における複数の委員や東京大学エコノミックコンサルティング株式会社など複数の民間企業のアドバイザーを務めている。主な著書に『グラフィックマクロ経済学 第2版』(新世社、宮川努氏と共著)などがある。
他のエキスパート解説を読む