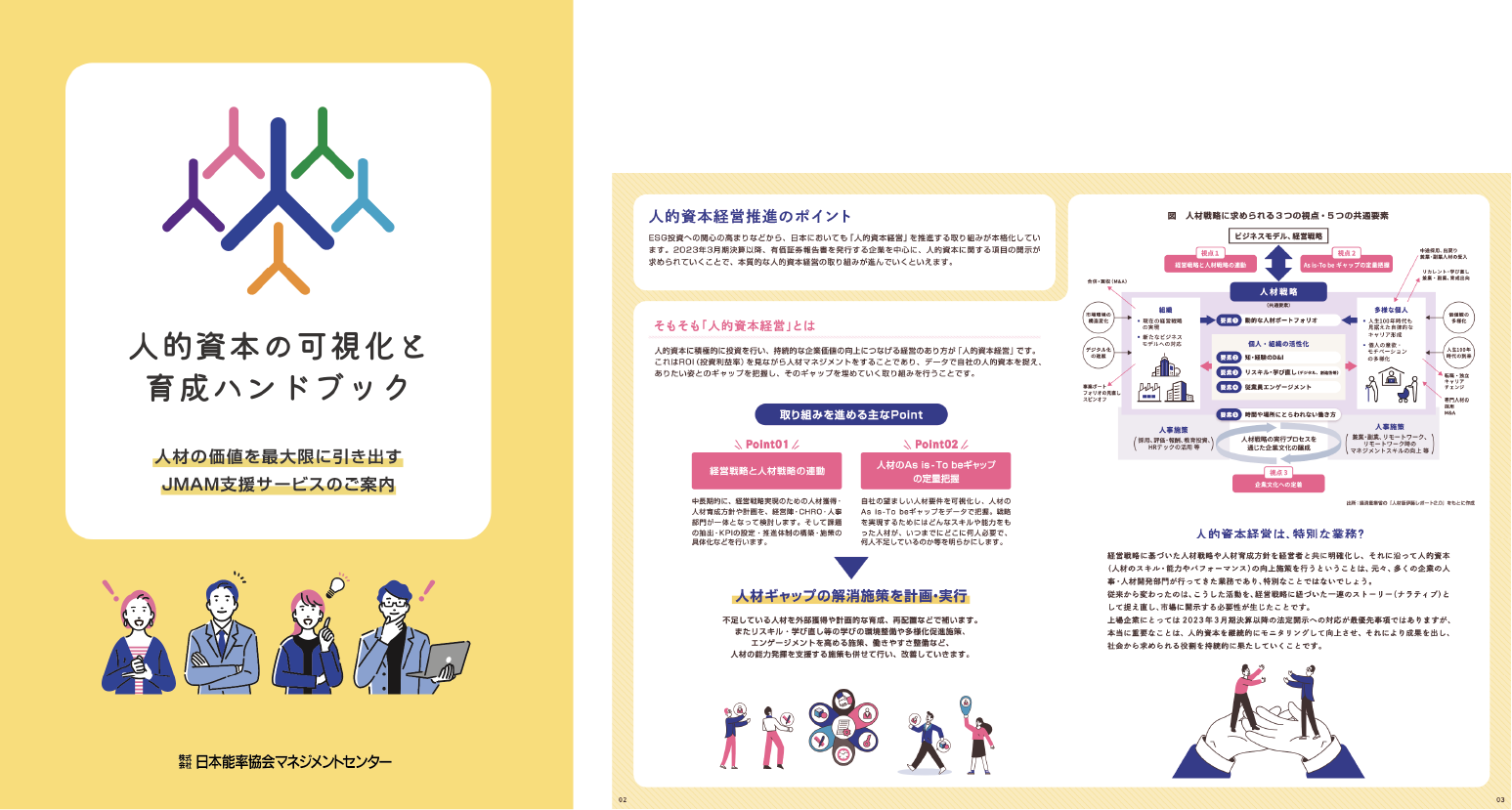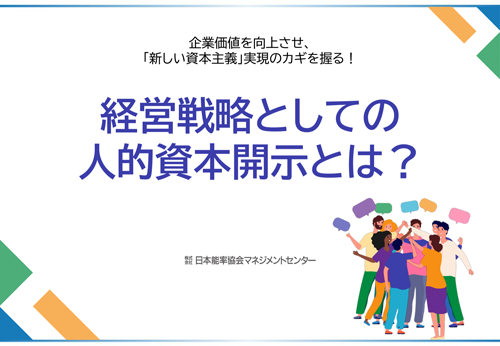「知・経験のダイバーシティ」を
結果につなげるには後編
谷口 真美氏
早稲田大学商学学術院 早稲田大学大学院商学研究科 教授
経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会」委員
人的資本経営を実現するうえで欠かせないのが、人材の「知・経験」の多様性を活かすという観点です。
そこでダイバーシティの専門家として「人的資本経営の実現に向けた検討会」に参加した谷口真美氏(早稲田大学商学学術院教授)に、「後編」として、外部人材との協働や女性社員の活躍支援、若手の意見をつぶさない方法、マネジャー支援、そして人的資本経営を形骸化させない方法について聞きました。
写真=谷口真美氏提供、PIXTA
- 外部人材と協働しても、結果を出せない企業の問題
- 女性社員が上位職にいる会社の秘密
- 若手選抜プロジェクトは、この2つがあれば失敗しない
- 国籍を取っ払えば、解決に近づく
- マネジャーには議論の仕方を教えよ
- 人的資本経営しているフリ”をしないために
外部人材と協働しても、結果を出せない企業の問題
Q外部人材との協働も「人的資本経営の実現に向けた検討会」(以下、検討会)で検討されたとのことでした。日本企業が外部人材と協働するうえで、結果につなげられない企業の問題点は、どのようなところでしょうか。
谷口 真美氏(以下敬称略)
多くの企業が「オープンイノベーション」と謳い、様々なプロジェクトを行いますが、ほとんど実装(結果)につながっていない。これはあくまで私見ですが、結果につなげられない企業というのは、役割や成果に関する約束がきちんとなされていないように見受けられます。こんなミッションのために、こんな目標があり、これをきちんと達成するとこのように評価されますよ、という約束です。結果を出さなければ容赦なく降格やクビ、という企業は少ない。
結果につなげられない企業では、このプロジェクトに入って、2年ぐらいお茶を濁してやっていたら、あの部署にまた戻れるだろう、といったようなことが往々にしてあります。プロジェクトでの結果に対する厳しさや、役割に対する使命感がない。権限と役割に対する評価が明確ではないということだと思います。これではオープンイノベーションも実装にはつながりません。
話がやや変わるようですが、性別・年齢・国籍に関しても、よく「何割いますよ」という話になりますが、割合、つまり表層のダイバーシティの話と「知・経験のダイバーシティ」が結びついていないのです。そこにもやはり取り組みとその結果との関係が曖昧という日本企業の問題が見えます。女性活躍推進でも国籍のダイバーシティでも、推進の取り組みをやっていますという話はあっても、それがどんなふうに価値創造につながっているかの説明がない傾向にあります。
女性社員が上位職にいる会社の秘密
Q検討会では、性別・年齢・国籍はあまり議題にはならなかったということですが、そんな中でも、少しでも話題になったことはないですか。
谷口
女性・年齢・国籍、どちらもそれぞれ課題は特定できていて、制約をなくす取り組みを対象者に提供することが大事だという考え方が、委員の皆さんから出されていました。これは私の解釈ですが、たとえば女性の制約は育児や介護等の家庭責任や時間の制約等なので、そのあたりのハンデをなくせば、あとは公平に処遇すればいいじゃないか、ということです。これについては後ほど、見解を述べます。
また、「知・経験のダイバーシティ」に着目し、たとえば性別を問わず公平に人材マネジメントを行っているといって、結果的に女性の比率が低いことの言い訳にするのも正しい在り方ではありません。数値目標のように望ましい割合を目指しながら、知・経験をベースとしたダイバーシティ推進を行うべきだという意見もありました。しかし検討会の大多数の方たちは、知・経験、つまり深層のダイバーシティの方に主に着目しましょうというご意見であったように認識しています。
他に、女性に関連して議論のなかで出てきたのは、日本企業は、取締役レベルの女性割合は13%程度と、ある程度増えてきていますが、執行役レベルにはまだまだ少ないという話題です。これにはおそらく2つの問題が根っこにあり、1つには、日本企業では、執行役員レベルは内部昇進が多い。むしろ取締役レベルは、社外取締役のような業務執行から距離をとったポストに女性を登用しやすいのですが、実際に事業を回す執行役レベルは、自社で育成した人が多いのです。社内の人をよく知っていて、周りをすごく動かせる人がなっている。そこに女性が少ないのは、中途社員をよく活かせないこととほぼ同じで、異質の人材が活躍できない風土や制度の運用上の問題があるのです。
2つには、先ほど申し上げた「制約」をどこまでとらえるかの問題です。男女を公平に処遇するためには、育児や介護などライフイベントに関する制度面を整えるだけでよいのか、ということです。マジョリティとマイノリティでは、実は見えないところに差がある。マイノリティには、人的ネットワーク不足やインフォーマルな支援が足りない・得にくい、などの見えない現実のハンデがあるものです。そうした理由から、昇進のテーブルに乗った際、同じ経歴でも女性の方が見劣りし、男性が選ばれてしまう。それでは公平なようで実は公平ではありません。こういうことから数値目標設定には、批判もありますが、少しは考慮されて然るべきでしょう。
これは今回の検討会とは別の、私の専門の話ですが、この問題は、ハイポテンシャル人材が異なる「知・経験」が積める、積ませるような会社であれば解消されます。今はコロナ禍なので難しいかもしれませんが、例えば男性と同じように海外MBAに行かせ、ファーストトラックで帝王学のような経験を積む、といったことです。そうすると、リーダーとしての動機付けを早い時期に持つことができ、俯瞰した目線で物事を見て事業を動かせるようになります。そういうことができる会社では、実際ちゃんと女性も上位職にまで昇進しています。
 ※イメージ
※イメージ若手選抜プロジェクトは、この2つがあれば失敗しない
Q年齢のダイバーシティに関しては、検討会でどんな議論がなされたのでしょうか。
谷口
年齢については、「若手の意見を潰さずにビジネスのなかに取り入れるにはどうしたらいいか」という話が検討会で多く出ていました。
トップは真剣に、若手の意見を採り入れたいと考えていても、現場のマネジャーが「新卒が提案だなんて10年早い」という態度をとってしまうことがある。若手を集めたプロジェクトやビジネスプラン検討会などを行う会社がありますが、単なる若手の発表会で終わることも多いようです。一方、うまくいっている会社では、そこにトップ自身が関わります。ビジネスに結びつけるために社長や経営陣が関わるようになったら、途端にすべての事業が成功するようになった事例の紹介もありました。
もう1つ、うまく活かせるポイントは、創成期や成長期にある事業領域で若手の意見を取り入れることです。ビジネスモデルが固まった成熟期以降には、もはや若手の意見を活かす余地は少なく、「いいプレゼンテーションだった」で終わってしまうことが多いからです。
国籍を取っ払えば、解決に近づく
Q国籍のダイバーシティについての検討会での議論は、どのような内容でしたか。
谷口
国籍のダイバーシティの話も、「外国人の比率」という言葉で人材版伊藤レポート2.0に記載がありますが、人的資本といったとき、国籍を取っ払って考えれば、世界中の人材プールから人を採用し活かすことになります。
この取材でも、「日本人をどうするか」という話ばかりです。日本人の給料、日本人女性、日本の若手をどうするかなど、人的資本の対象を全部「日本人」だと考えてはいないでしょうか。でも、国籍を取っ払えば、世界との人材獲得競争のなかで、ただ適切なスキルや経験をもった人材に来てもらい、適切な給料を払わないといけなくなります。すると、自ずと性別や年齢などの他の属性も関係なくなり、女性・若手等々個別の課題も、すべて検討する必要がなくなります。人事制度や運用も改革していくことになります。そして、加わってもらう人材には、本当に結果を出してもらわないといけなくなります。
ですから、検討会でも人材プールのフレームを変えるところからリスタートしたらいいのではないでしょうか、というお話をしました。検討会では、こと英語使用という点で外国人に劣後しかねない日本人人材への支援―早期からの教育投資―の必要性への言及もありました。
 ※イメージ
※イメージ
マネジャーには議論の仕方を教えよ
Q話が変わるのですが、ダイバーシティ・マネジメントにおいて、真に違いを活かせるステージを目指す際、現場でのマネジメントの未成熟さが壁になるのでは。マネジャーが対話やコンフリクトを恐れずに踏み込むコミュニケーションが必要になりますが、どのようにしたら踏み込めるでしょうか。
谷口
ご存じの通り、「人的資本経営の実践のための検討会」は、経営や人事側が企業価値向上のために組織の制度や風土をどう変えていくか、そのために何ができるか、という議論が中心でした。その中で、ミドルがなかなか変わらないとか、いやミドルに全責任を押しつけるのではなくて、トップ自身が変わってロールモデルにならないといけない、といった話もありました。
ただし、ミドルが対話やコンフリクトへの不安を乗り越える勇気を持つには、組織的な仕掛けが大事です。結果に対して厳しくあるべきという話と逆行しているところもあるのですが、経営側は、チャレンジを奨励するとともに、失敗を許さない風土を改めていくことが必要だという点も提起されました。
変革や対立に対して後ろ向きになってしまうことには、いくつか原因があると思いますが、まず言えるのは、それらを乗り越えて結果に結びつけた成功体験がないことでしょう。そういう方には経験を積ませることが大事ですし、ミッションを明確にして、それをサポートする支援体制をつくる。また、異なる意見を取りまとめてプラスに結果をつくったことが評価される評価の仕組みが大事という意見が検討会では出ていました。
Q人材版伊藤レポート2.0にも「マネジメントの改善を高く評価する」工夫が大事だと記載があります。
谷口
そうですね。個人の側の話でいえば、“議論の仕方のトレーニング”が有効です。たとえば、グローバルな会議や議論の場で意見を言わないと、話が理解できないか、怒っているか、興味がないと受け取られます。とにかく自分の意見と立場を明確にし合ったうえで「じゃあ、我々としてはどんなふうにするといいか」を議論する。そういう議論の仕方のトレーニングを行う必要があるでしょう。議論に不慣れな日本人が対立意見を言うときに、変に嫌味っぽくなってしまったりすることもあります。私も、時々失敗します(笑)
日本では、意見が出ない=合意できてよかった、という感覚がありますね。他方、多国籍なメンバーが集まる場では、意見が出なかったら、みんなの興味・関心を全然ひき付けられなかった、と捉えた方が良いでしょう。
誰も意見を言わないと、原案そのままで一面的な結論になる。多面的に意見を受けて原案をさらに磨き上げなければなりません。
対立をうまくコーディネートして、結果に結びつけるリーダーシップは「パラドキシカルリーダーシップ」と呼ばれています。日本では先ほどの議論の仕方も含めて、あまり教育されていませんが、ここには、一段高いところから見る力、構造化能力や俯瞰能力が含まれます。同じ目線で見て話をすると、詰め将棋みたいになってしまう。そうではなく、俯瞰してみて、そこから新しいものを生み出すリーダーシップや議論が必要です。
“人的資本経営しているフリ”をしないために
Q最後になりますが、人的資本の開示を目的化すると、多様な人がいる・スキルがあると可視化して見せることに注力し、真に意味のあるダイバーシティ・マネジメントがおろそかになる懸念があるのではないかと考えますが、どうお感じになりますか。
谷口
大事なポイントです。キャリア採用者や博士人材等の専門的人材などすべて、数だけを目的にしては駄目です。その人たちを採用したり、その人たちを雇用することによって、どんなイノベーションや価値創造と結びつけたか、そのために組織をどうするかが大事です。DX人材が何人いるかということより、その人たちが参画することで何を生むのかということをステークホルダーも知りたい。数を追うと形だけになり、“やっているフリ”になってしまいます。
Q“人的資本経営をしているフリ”をしないためには、どうしたらよいでしょうか。
谷口
形だけ取り組まないことですね。企業価値向上のために、執念深く、どんなことが必要で、何をするべきなのかをしっかりと見据えて実行する。とにかく結果に結びつける。あとはトップの支援や、事業のライフサイクルをきちんとみきわめて、適切な人材をアサインし支援する。人材版伊藤レポート2.0は、人的資本経営のヒントを示していますが、手段が目的化しないように注意すること―目的は企業価値を高めることに尽きると思います。

早稲田大学商学学術院 早稲田大学大学院商学研究科 教授
1996年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)取得。
広島経済大学経済学部経営学科専任講師、同助教授、広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授、早稲田大学大学院商学研究科准教授を経て、2008年4月より現職。
2013年8月より2015年3月まで、マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院研究員。
著書に『ダイバシティ・マネジメント-多様性をいかす組織』(白桃書房)など。
他のエキスパート解説を読む