- 対象: 全社向け
- テーマ: 働き方
- 更新日:
静かな退職とは?原因や兆候、企業にできる対策を紹介

近年、「静かな退職(quiet quitting)」が注目を集めています。特にZ世代を中心に広がりを見せており、その背景にはハッスルカルチャーの衰退やワークライフバランスの重視、キャリアパスの不透明化などがあります。
静かな退職が増えると、企業にとっては生産性の低下やコミュニケーションの問題、人材育成の難化などさまざまなリスクがあります。今回は、静かな退職の原因や兆候、企業が取るべき対策などについて詳しく紹介します。
関連資料
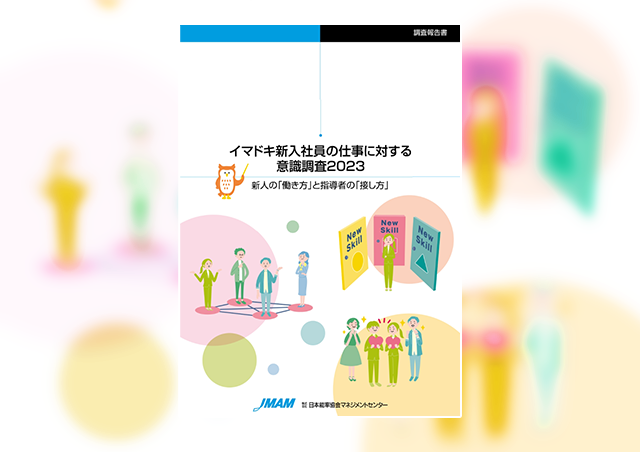
関連資料
最新版!新人の「働き方」と指導者の「接し方」の実態とは
今すぐ無料で見る|イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2023
(電子ブック版)
静かな退職とは
「静かな退職」とは、仕事に対する熱意を失い、必要最低限の業務だけを淡々とこなす働き方を指します。実際に退職はしていないものの、心理的には会社を去っている従業員のような状態です。アメリカで、キャリアコーチのブライアン・クリーリー氏がこの言葉を発信したことで、特にZ世代を中心に話題となりました。
例えば、プロジェクトに対する積極的な提案やアイディア出しをせず、指示されたことだけをこなすような態度が典型的なケースです。在籍しながら契約上義務づけられた必要最低限の業務だけを行い、仕事とプライベートの境界線を明確に引いて、仕事に自己実現ややりがいを求めない割り切った働き方です。チームの士気や生産性が低下するリスクが高まるため、企業側も対応策を考える必要があります。
静かな退職が日本で増えている原因
日本で静かな退職が増加している原因には、いくつかの背景があげられます。具体的 な要因について詳しく解説します。
ハッスルカルチャーの衰退
ハッスルカルチャーとは、仕事を人生の最重要項目と位置付け、多忙であることや生産性が高いことを美徳とする考え方です。具体的には、夜遅くまで働き続け、休日も仕事に取り組むことが当たり前とされる風潮などがあげられます。
ハッスルカルチャーは成功に対するモチベーションが高まる一方で、過度なストレスや燃え尽き症候群のリスクをともないます。こうした過剰な働き方に疑問をもつ人が増え、結果として静かな退職への共感が広がっていきました。
ワークライフバランスの重視
ワークライフバランスを重視する従業員が増えたことも、静かな退職がみられるようになった原因です。
従来の日本社会では、プライベートを犠牲にして仕事に打ち込むことが美徳とされてきました。しかし、近年はプライベートや家庭生活、育児などに時間を費やすことを重視する人が増えています。また、働き方改革の普及やウェルビーイング(幸福感)への意識の高まりも、この傾向を後押ししています。
労働時間を自主的に調整したり、家庭の時間を優先したりする動きが増えた結果、仕事への熱意が下がってしまったというケースです。
キャリアパスの不透明化
かつての日本では終身雇用制度が一般的で、大企業に入社すれば安定したキャリアを築くことができました。しかし、転職するのが当たり前の現代では終身雇用制度が崩壊しつつあり、大企業であっても安定が保証されなくなっています。
そのため、長期的なキャリアプランを描くことが難しくなり、組織に依存せずに自分のキャリアを模索する人が増えています。この結果、組織へのエンゲージメント(帰属意識)が低下し、必要最低限の業務だけをこなす静かな退職が増加しました。
静かな退職の兆候はある?
静かな退職の兆候を見極めることは、早期に対策を講じるためにも重要です。
下記のようなケースは、静かな退職の兆候であると考えられます。
- 求められている以上の仕事をしない
- 会議で発言しない
- チーム内で孤立している
- 最低限の会話しかしない
- 周囲の従業員の業務量が増えている
- 社内イベントに参加しない など
従業員が求められている以上の仕事をしなくなると、新しいプロジェクトへの参加意欲が低下し、提案や改善のアイディアが減少します。これにより、チーム全体の創造力や生産性が低下する可能性があります。
さらに、チーム内で孤立している様子や最低限の会話しかしない場合も注意が必要です。コミュニケーションが減少すると、チームの一体感が失われるリスクがあります。その結果、周囲の従業員の業務量が増えて、全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすこともあるでしょう。
静かな退職を防ぐための企業側の対策
静かな退職を防ぐためには、企業側が対策を講じることが重要です。具体的な防止策を紹介します。
職務範囲を明確にする
職務範囲を明確に定義することで、従業員は自身の役割や責任を明確に理解できます。業務への取り組み方が改善され、生産性の向上につながります。
具体的には、業務内容を具体的に記載したマニュアルを作成し、定期的に見直すことが有効です。曖昧な職務範囲による混乱を防ぎ、従業員が自信をもって業務に取り組めるようになります。また、目標設定を明確にすることで、従業員は達成感を得やすくなり、モチベーションを維持しやすくなります。
人事評価制度を見直す
公正で透明性の高い人事評価制度を導入することで、従業員のモチベーションを高めることができます。具体的には、成果だけでなくプロセスや努力を評価する仕組みを取り入れると良いでしょう。例えば、360度評価制度を導入し、同僚や部下、上司からのフィードバックを反映させることで、より多角的な評価が可能になります。
なお、JMAMでは新人・若手社員の360度評価に活用できるアセスメントツールを提供しております。ご興味のある企業様は、下記から詳細をご覧ください。
また、評価結果を基にキャリアパスのアドバイスやスキルアップのための研修を行い、従業員の成長をサポートすることも重要です。
社内コミュニケーションを活発化させる
コミュニケーションの活性化は、心理的安全性を醸成し、従業員の帰属意識を高めます。具体的には、定期的な1on1ミーティングを実施し、従業員の意見や悩みを直接聞く機会を設けることが有効です。
また、社内イベントを通じて、従業員同士の信頼関係を築くこともチームワーク力の向上につながります。
1on1の効果を高める実施方法については、こちらもご覧ください。
メンター制度を導入する
メンター制度は、経験豊富な社員が新人や後輩社員に対して指導やサポートを行う仕組みです。個々の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。
メンターは相手の自主性を尊重し、自ら考え行動する力を引き出すサポートに徹する必要があります。経験や知識だけでなく、コミュニケーション能力や指導力も求められるため、適切な人材を選定することが重要です。
従業員エンゲージメントを調査する
従業員エンゲージメントを調査することは、組織の健康度を把握するために不可欠です。エンゲージメントが高い従業員は、仕事に対するモチベーションが高く、生産性や業績に良い影響を与えます。
エンゲージメントを調査する際は、個別面談やアンケートを通じて、従業員の既存業務や職場環境への満足感、キャリアプランなどを詳しく把握することが重要です。具体的には、「現在の業務に満足していますか?」「職場の改善点はどこだと思いますか?」といった質問を行います。
このような調査を行うことで、従業員の不満や改善点を明確にし、職場環境の改善策を具体的に立案できます。また、従業員の意見を取り入れることでエンゲージメントが高まり、仕事に対するモチベーションが向上します。
ただし、時間と人員が不足しているために社内調査が難しい場合は、他社事例や調査レポートを参照し、活用することも検討しましょう。例えば、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)の「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査 2023年度版」資料では、新入社員(Z世代)の実態や指導育成方法を解説しています。
若手社員が何を考えているか、どのように育成すれば良いか悩んでいる企業様はぜひご覧ください。
まとめ
ワークライフバランスの重視やキャリアパスの不透明化により、実際に退職はしていないが必要最低限の業務だけをこなす静かな退職が増加しています。人事評価制度の見直しやメンター制度の導入は有効な対策ですが、まずは調査を通じて従業員が何を考え、どんなことに悩んでいるのかを知ることが最も重要です。
今回、解説した内容をもとに、静かな退職の対策を始めましょう。
イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2023
新人の「働き方」と指導者の「接し方」
2016年から毎年行っている「新人の働き方と指導者の接し方」に関する内容に加え、Z世代のキャリアと成長実感にも焦点を当て、さまざまな切り口からその実態を明らかにしました。
- イマドキ新入社員(Z世代)の実態
- 世代別比較からみる新入社員(Z世代)の特徴
- イマドキ新入社員(Z世代)のキャリアと成長実感
- イマドキ新入社員(Z世代)への指導・育成
以下より無料でご覧いただけますでので、ご活用ください。
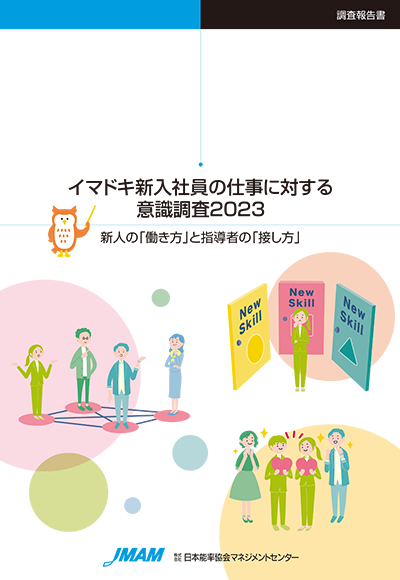
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















