- 対象: 人事・教育担当者
- テーマ: 研修/教育
- 更新日:
行動変容とは?ステージ理論を活用した社内研修の設計方法

従業員の行動変容を促す研修を設計するのは容易ではありません。研修を実施しても成果がみられず、何が問題なのかと頭を悩ませている方も多いでしょう。実際、人の行動を変えるには、ただ情報を伝えるだけでは不十分です。行動変容を実現するためには、行動の変化を促す仕組みを理解し、それに基づいた研修設計が不可欠です。
今回は、行動変容を促すためのステージモデルや、行動変容を妨げる要因、そしてそれらを克服するための具体的な研修設計のポイントについて詳しく解説します。
関連資料

関連資料
組織づくりにおける「対話」の重要性と「1on1ミーティング」のポイントについて解説
ニューノーマル時代の管理職のための1on1ミーティング
従業員育成における行動変容とは
行動変容の一般的な意味は、人の行動が変わることです。元来は、アメリカの禁煙プログラムの研究から、行動変容というモデルが生み出されました。現在は、日本でも医療やマーケティング、人材育成の分野で活用されています。
研修などの従業員育成においては、業務において課題となっている行動をより望ましい方向に変えることを意味します。具体的には、指示待ちなどの受動的・消極的な状態から、自主性をもって業務に取り組む能動的・積極的な状態に変えることです。
研修によって行動変容を促すことができれば、従業員のスキルアップやモチベーションの向上につながります。能力が高く自律的に動ける従業員が増え、組織全体の生産性向上や事業の拡大にもつながっていくでしょう。
行動変容のステージモデル
行動変容には5つのステージがあり、各段階に応じて効果的なアプローチは違ってきます。
- ステージ1|無関心期
- ステージ2|関心期
- ステージ3|準備期
- ステージ4|実行期
- ステージ5|維持期
まずは、対象者のステージに応じた効果的な働きかけを押さえていきましょう。
ステージ1|無関心期
自分が変わるための行動に関心がない状態が、無関心期です。本人が現状に課題を感じていない状態、または感じていてもさまざまな理由から行動を起こす意欲がない状態のままでは、行動変容は望めません。
無関心期では、課題を認識させた上で、行動変容の必要性を感じさせることが効果的です。解決するメリットと放置するデメリットを明確に伝え、現在の行動が将来的にどのようなリスクを伴うかを具体的にイメージしてもらいましょう。また、いきなり変化を求めるのではなく、小さなステップから始めることをすすめるのがポイントです。
ステージ2|関心期
関心期では、ざっくりと課題を把握し、解決に向けた行動をする必要性は認識しています。ただ、まだ具体的な行動を起こすには至っていません。
関心期における有効なアプローチは、実践するためのノウハウやプロセスを教えて、道筋を示すことです。ただし、行動を強制するとモチベーション低下につながり、無関心期に逆戻りするリスクがあるため注意が必要です。従業員の意思を尊重し、自主的に行動を選択できるようにサポートしましょう。
ステージ3|準備期
準備期までくると、課題を具体的に把握し、近いうちに行動を実行に移そうという気持ちが固まってきています。しかし計画段階なので、実践するまでには至っていません。
この段階では、従業員の自信を高めて実行へのモチベーションを上げることが重要です。例えば、周囲からの肯定的なフィードバックや、次にすべき行動や目標を具体的に示すなどのアプローチが有効です。
ステージ4|実行期
実行期は従業員が実際に行動を始めている時期ですが、行動がまだ習慣として定着していない段階です。また、行動を継続することに対してまだ不安や抵抗感があることが多く、挫折しやすいのが特徴です。
この段階では、成果を具体的に褒めて自信をもたせることが重要です。達成可能な目標を設定し、その成果を逐一褒めることで、従業員が小さな成功体験を積み重ねられるようにします。また、経営層や上司だけでなく、同僚からのサポートも有効です。周囲から積極的にフィードバックを与え、継続力を強化できる環境を提供しましょう。
ステージ5|維持期
維持期は、従業員が課題解決に向けた行動を始めて半年以上経過し、生活の一部として定着している状態を指します。自信をもって行動を継続しており、多少の困難があっても挫折しにくいのが特徴です。
この段階では、従業員の行動ができるよう継続的なサポートとフィードバックを与え、さらなる自信をもたせましょう。新たな目標を設定して次のステップに進む具体的な計画を立てることも、モチベーションアップにつながります。また、良好な人間関係の構築や、失敗を前向きに捉える文化の醸成など、ポジティブな職場環境をつくることも大切です。
社内教育の行動変容を妨げる要因は?
従業員育成において、行動変容を妨げる大きな要因となるのが、誰しもがもつ「現状維持バイアス」や「同調バイアス」です。
現状維持バイアス
現状維持バイアスとは、たとえ現在より状況が良くなるとわかっていても、変化をもたらす行動ができない心理傾向のことです。変化に対する不安や恐れ、未知のリスクを避けるための防衛機制によって働きます。
現状維持バイアスを克服するには、変化するメリットを明確に伝え、段階的なアプローチをすることがポイントです。
同調バイアス
同調バイアスとは、個人が自分の意見や行動を、周囲の意見や行動に合わせる心理傾向を指します。組織の一員としての承認や安心感を得たいという思いから同調バイアスは生まれ、周囲と異なる意見を発したり、行動したりするのを避けてしまうのが問題です。
従業員が安心して意見を述べられる環境を整えることで、同調バイアスの影響は軽減できます。
従業員の行動変容を促す教育施策のポイント
行動変容を起こすためには、教育施策にID(インストラクショナルデザイン)の手法を取り入れることが効果的です。
IDとは、教育や研修プログラムの設計、開発、実施、評価を体系的かつ科学的に行うプロセスを指します。IDを取り入れることで、効果的で効率的な教育内容を設計できます。
ここでは、IDのうち代表的な「ARCSモデル」「ADDIEモデル」「TOTEモデル」について紹介します。
ARCSモデル|学習意欲を高めるための工夫
ARCSモデルは、学習者の動機付けを引き出すための設計指針です。学習へのモチベーションを維持し、高めるための具体的な戦略が整理されています。
| A(Attention):注意 |
・学習者の注意や興味、関心を引く ・面白そうだという気持ちにさせる |
|---|---|
| R(Relevance):関連性 |
・学習内容が学習者の現実のニーズに関連していることを気付かせる ・「やりがいがある」と積極的な気持ちにさせる |
| C(Confidence):自信 |
・学習者に小さな成功体験をさせ、達成可能であると思わせる ・これなら自力でできそうという気持ちにさせる(自己効力) |
| S(Satisfaction):満足感 |
・学習者を評価し、成果に対する満足感を与える ・「やってよかった」という気持ちにさせ、次につなげる |
ACRSモデルの仕掛けを研修に取り入れることで、学習することに対する動機付けができ、具体的な行動につながりやすくなります。
ADDIEモデル|行動定着に結びつける考え方
ADDIEモデルは、教育や研修プログラムの設計、開発、実施、評価を体系的に行うためのフレームワークです。下記の5つの要素で構成されています。
| A(Analysis):分析 | 学習者の特性、学習環境、現状の課題や目指すべき姿を分析し、研修の目的やニーズを検討する |
|---|---|
| D(Design):設計 | 研修目的やニーズに合ったカリキュラムの設計や、教材の選定などを行う |
| D(Development):開発 | カリキュラムに応じて教材や資料を準備する |
| I(Implementation):実施 | 準備した教材や資料を用いて、実際に研修を実施する |
| E(Evaluation):評価 | 学習者のパフォーマンスや研修全体の評価から研修の効果を測定し、改善点を特定する |
ADDIEモデルを活用すると、各フェーズで詳細に計画を立てることができ、体系的なアプローチが可能です。PDCAサイクルによって、より効果的な研修が設計できるようになります。
TOTEモデル|目標達成に向かうプロセス
TOTEモデルは、問題解決や行動計画のプロセスを示すフレームワークで、研修目標を達成するのに役立ちます。下記の4つのステップで構成されています。
| T(Test):テスト | 現状で目標とどの程度差があるのかを検証し、問題点を明確にする |
|---|---|
| O(Operation):操作 | 目標達成に必要な研修を実施する |
| T(Test):テスト | 再びテストに戻り、実施した研修の効果を評価し、目標に対する進捗を確認する |
| E(Exit):出口 | 現状と目標とする状態が一致すれば終了する |
TOTEモデルを活用すると研修の効果を段階的にチェックでき、目標達成までの継続的な改善ができます。
【7ステップ】行動変容を促す社内研修の設計方法
教育施策のポイントに基づいた、効果的な従業員研修の組み立て方を解説します。
ステップ1|ヒアリングをベースとした現状調査を実施する
まずは、従業員や経営層に対するヒアリングを基本とした現状調査を実施し、現在の課題やニーズを具体的に把握しましょう。
業務に携わる従業員の意見を直接聞くことで、研修で解決すべき課題や目指すべき到達点・必要な内容が明確になります。
主に下記のようなポイントを念頭に置いてヒアリングを進めると、課題をつかみやすいでしょう。
- 組織全体、部署あるいは階層別で不足している知識やスキルは何か
- 立場や部署によって課題とする内容に差はあるのか
- どのようなスキルを身に付けさせれば組織にとって有益か
ステップ2|「SMARTの法則」を活用して研修目標を設定する
ステップ1で明らかになった情報をもとに、「SMARTの法則」を活用して研修目標を設定しましょう。「SMARTの法則」は、適切な目標設定のための重要なポイントを指します。
| S(Specific) |
具体的で、達成すべき内容や責任者が明確化されているか (例)「来期までに各営業担当が週20%増の架電を実施する。」 |
|---|---|
| M(Measurable) |
目標の達成度を定量的に測定できるか (例)「現在、各営業担当が週50回の架電を実施しているが、これを週60回に増やす。」 |
| A(Achievable) |
現実的で、達成できるような目標か (例)「4か月以内にOfficeソフトの教育プログラムを実施し、来期までにMOS資格取得者を2名創出する。」 |
| R(Relevant) |
企業の全体戦略と一致しているか (例)「企業の顧客満足度向上の戦略に応じて、カスタマーサポートの顧客対応スキルを高める。」 |
| T(Time-bound) |
達成期限が定められているか (例)「半年以内に不良率を25%削減する。」 |
ステップ3|研修の計画を策定する
研修の目的や目標をもとに、具体的な研修計画を策定していきます。
ここでポイントとなるのが、研修テーマの見せ方です。研修の参加者に「自分にメリットがある」「面白そう」と思わせ、積極的に参加する姿勢になってもらうことが大切です。そのため、ヒアリング調査などで把握した個人のニーズにマッチするテーマを設定しましょう。
例えば医療現場における患者への健康指導では、メタボ対策や生活習慣病予防をテーマとするよりも、お腹を引き締めスマートになるためにと伝えたほうが、患者のやる気は高まります。
ステップ4|研修前に事前テストや1on1を実施する
研修前に、受講者が自分の課題を認識できるようにしましょう。具体的には、下記のようなアプローチをすると効果的です。
●事前テスト
現状のスキルや知識レベルを定量的に把握するテストを実施し、受講者の不足するスキルや知識を明確化します。
●1on1
上司や研修担当者が個別に1on1を実施し、受講者が目指すべき状態と現実とのギャップを説明します。この際、行動変容のメリットや効果を明確に示しましょう。
ステップ5|受講者自身にゴール設定をしてもらう
研修のなかで、受講者自身にゴール設定をしてもらいましょう。
具体的な方法として、マンダラチャート(マンダラート)を紹介します。9×9マスの表に、テーマに含まれる要素を分解して書き出し、情報を整理する手法です。
1.中心のマスに目標を書く
中央のマスに達成したい具体的な目標を記入します。
2.周囲の8マスに要素を書く
目標達成に必要な要素を、中心の目標の周囲8マスに記入します。
3.各要素をさらに分解する
8つの要素それぞれを中心に置いた9マスの枠を新たに作成し、具体的な行動や施策を記入します。
4.行動目標を設定し、実行する
各マスに記入された行動目標をもとにディスカッションやグループワークを行い、他者の意見を取り入れつつ、マンダラチャートを完成させます。
ステップ6|実際の行動計画を策定する
目指すべきゴールを設定できたら、課題解決に向けて必要な取り組みや行動計画を策定し、実践してもらいます。
この際に重要となるポイントは、下記の2点です。
- 少し物足りないレベルの取り組みにすること
- 達成期限を定めること
少し物足りないくらいの取り組みを設定すれば、この程度なら自分でもできる、という自信につながります。
また、いつ・何をするのかまで決めておくことで、必ず実践しなければならないという意識が芽生え、具体的な行動を促すことができます。
ステップ7|振り返りを定期的に行う
行動を習慣化するためには、継続的なフォローが重要です。研修後は、実行計画に基づいた行動をサポートしましょう。
具体的には、1on1などの機会を設けて、振り返り・コーチング・フィードバックを定期的に実施することが効果的です。
この際、上司や研修担当者はポジティブフィードバックを意識しましょう。小さなことでも積極的に褒めることで、本人のモチベーションが上がり、課題解決に向けた行動の継続・定着につながります。
行動変容を促す教育施策を成功させるには?
行動変容を促す教育施策を成功させるには、心理的安全性を確保することが大切です。心理的安全性とは、組織やチームで、誰もが安心して自由に発言できる状態を指します。
従業員が恐れずにアイデアや意見を出せる職場には、失敗するリスクのある行動にも積極的に挑戦できる風土が醸成されます。
心理的安全性を確保する方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
行動変容を促す研修のカリキュラム例
行動変容を促す研修のカリキュラム例として、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)の「目標を完遂し人を育てる管理者基本コース」を紹介します。
| 事前課題 |
・日々の管理者としての行動の記録 ・「株式会社アイジム伊藤課長のケース」の読み込み ・「支援傾向フィードバック」への回答(Web受検) |
|---|---|
| 1日目 |
1.オリエンテーション ・相互交流 2.管理者の役割について ・管理者の基本 ・管理者の役割(演習1) ・管理者の役割を果たしているか(演習2) 3.目標完遂 ・(株)アイジム伊藤課長のケース(ケース演習1) ・目標完遂の基本 ・部門目標の設定 ・計画(役割分担)の策定 ・進捗管理 ・相互インタビュー(演習3) ・目標完遂に関する現状と今後の課題 |
| 2日目 |
1.部下育成 ・部下育成の基本 ・3つの支援と部下の成熟度の解説 2.支援傾向診断フィードバックと実務適用(演習4) 3. (株)アイジム伊藤課長のケース(ケース演習2) ・育成のポイントと方法 4.相互インタビュー演習(演習5) ・部下育成に関する現状と今後の課題 5.管理者としての行動変容(演習6) ・相互フィードバック 6.アクションプランの策定 |
| 事後課題 | ARノートによる職場実践 |
本研修では、受講者自身の行動の課題を認識するため、対話などを通して業務における自分のあり方を振り返る場を設けています。このプロセスによって、職場における具体的な行動の実践を動機付けることが可能です。
また、職場での実践をフォローするために、「アクション&リフレクションツール」を提供しています。「約3週間行動を継続すると、習慣化できる」という脳科学の考え方を取り入れたツールで、設定した行動目標を21日間継続する効果が期待できます。
まとめ
行動変容とは、業務における課題ある行動を、より望ましい方向に変えることです。行動変容には、無関心から維持までの5段階があり、各フェーズに合わせたアプローチが必要です。
行動変容においては、無関心から関心期に移行した際に本人への動機づけも忘れてはいけません。各教育施策でも目標の明確化や達成の道筋を作るなどで動機づけをしていくことになります。
また、現状維持バイアスや同調バイアスによって、行動変容は容易に妨げられます。ID(インタラクショナル・デザイン)モデルなどを教育施策に取り入れて、効果的で効率的な研修を設計しましょう。
JMAMでは、自ら育つ環境づくりを大切にした体系的・実践的な研修プログラムを提供しています。行動変容は短期間で実行できることではありません。自身の行動を振り返りながら実行し続けることで、管理者に期待される行動変容へとつなげる研修を行っています。管理職の行動変容を引き出すについては、「目標を完遂し人を育てる管理者基本コース」をご覧ください。
ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方
書籍「チームワーキング」ポイント解説
チームの機能不全状態を解消し、成果を創出する
本資料は立教大学の中原淳教授・田中聡助教著『チームワーキング ケースとデータで学ぶ「最強チームのつくり方」』をベースに、チームの機能不全に悩む職場の立て直しに資する内容となっています。
- 「チームの病」を克服するために必要なチームワーキング
- チームが機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」
この機会に下記より資料をご請求ください。
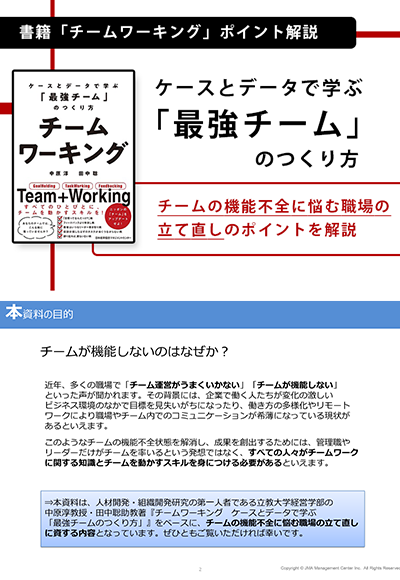
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















