
ビジネスの世界では、さまざまな場面でフィードバックが行われています。この記事では、社内でフィードバックによる人材育成を行いたいと考えている担当者に向けて、フィードバックの意味や種類、実践方法について解説します。
関連資料

関連資料
組織づくりにおける「対話」の重要性と「1on1ミーティング」のポイントについて解説
ニューノーマル時代の管理職のための1on1ミーティング
基本的なフィードバックの意味を解説
フィードバックとは、口頭や文章などで行う指摘のことです。フィードバックは、あらかじめ定めている目的を達成するために行われます。評価そのものをフィードバックと表現する場合もあります。フィードバックという言葉は、もともと制御工学で使われていました。
ビジネスにおけるフィードバックの意味とは
ビジネスにおいては、目標を達成するための行動やその結果について指摘するためにフィードバックが行われます。上司と部下や、マネージャーとメンバーなど、1対1でフィードバックを実施するのが一般的です。
なお、フィードバックでは、主観による判断で相手の人間性を否定してはいけません。根拠となる情報を提示したうえで、改善点を明確に伝える必要があります。
フィードバックが必要とされている理由とは
フィードバックは、さまざまな理由から必要とされています。
たとえば、部下とのコミュニケーションが不足している場合、フィードバックにおける適切な指導や修正を通じて、部下の仕事の進め方や考え方を知ることができます。働く人たちの価値観も多様化しているため、フィードバックを行うことが相互理解のきっかけとなるのです。様々なタイプの人材を雇用していても、フィードバックを行うと組織の一体感を高めやすくなります。
テレワークでも部下のモチベーションを上げ、生産性を高める!
「 チーム力を高めるテレワークマネジメント(通信教育)」はこちら
フィードバックと混同しやすい単語
フィードバックに似た言葉は複数あります。ここでは、フィードバックと混同しやすい単語について解説します。
コーチング
コーチングとは、質問しながら話を聞き、相手が自ら問題の解決策を導き出せるようにサポートすることです。一方、フィードバックは、行動や結果について客観的に伝え、改善策も提示します。
フィードアップ
フィードアップとは、フィードバックの目的や目標を定めることです。フィードバックを行う際には、フィードアップが前提になります。
フィードフォワード
フィードフォワードとは、目標を達成するためにどのような方法があるか話し合うことです。フィードバックでは過去の出来事に焦点をあてますが、フィードファワードでは未来での取り組みについて意見を出し合います。
マネジメント
マネジメントとは、目標を達成するための方法全般を表す言葉です。フィードバック、コーチング、フィードアップ、フィードフォワードなどは、すべてマネジメントの手法に含まれています。さまざまな方法を組み合わせ、マネジメントの効果を高めます。
レビュー
レビューとは、評価や批評のことです。レビューでは、物事に対する単純な感想がまとめられる場合がほとんどです。それに対してフィードバックは、単なる感想ではなく問題の解決に関する助言が含まれています。
チェックバック
チェックバックとは、さかのぼって確認するという意味です。チェックバックという言葉が使われるのは主に映像業界であり、制作された映像をチェックして修正の指示を出すために行われます。一方、フィードバックはビジネス全般で使用されています。
企業でフィードバックを実施する目的を確認
企業でフィードバックを実施する目的は様々です。ここでは、フィードバックの具体的な目的について解説します。
目的1:人材育成のため
フィードバックは、人材の成長を目的として実施されるケースが多いです。社員の行動やそれによる結果を踏まえてフィードバックを行えば、課題を発見するためのスキルや課題を解決するための能力を養えます。
目的2:目標を達成するため
こまめにフィードバックを実施すると、目標を達成しやすくなります。方向性が間違っている場合でも、早い段階で軌道修正が可能です。目標に向けて最適な取り組みができるようになり、効率的に目標の達成を目指せます。
目的3:生産性を向上させるため
フィードバックを行えば、課題の解決方法も明確になります。解決方法を明確にしたうえで目標を達成するための取り組みができるため、成果に結びつきやすいでしょう。よって、フィードバックは生産性を向上させたい場合にも効果的です。
目的4:社員のモチベーションをアップさせるため
目標を達成するための取り組みについて社員がネガティブな意識をもっている場合でも、フィードバックにより、自らの行動に対して適切な評価やアドバイスを貰うことはポジティブな意識転換のきっかけになります。自己肯定感を高めるための動機付けにもなり、前向きに取り組めるようになります。
目的5:社員の自己認識力(セルフアウェアネス)を高めるため
周囲からのフィードバックは、社員にとって客観的に自分自身を知る機会になります。自分の強みや弱みといった特性を把握し、自己認識力(セルフアウェアネス)を高めることができ、状況に応じた行動がとれるようになります。将来的には、社員が自らフィードバックを求めるような能動的な姿勢(フィードバックシーキング)が身に付くことが望ましいです。
参考:【会員限定】立教大学 中原淳教授|セルフアウェアネス 鍵はフィードバックにあり。他者を通じて自己を知る/Learning Design Members
フィードバックには2種類ある
フィードバックには主に2つの種類があります。以下でそれぞれについて解説します。
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックは、相手の行動を肯定的に捉えてフィードバックする方法です。社員の承認欲求を満たし、自己肯定感を高められます。仕事に対するモチベーションアップも期待できます。
ただし、フィードバックの目的を踏まえ、次につながる助言もする必要があります。言葉選びに注意しながら、前向きな表現で改善点を伝えましょう。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックは、相手の行動の問題点を指摘することで、立て直しを支援するフィードバックの方法です。自分の行動を否定されると、社員は自ら改善点を模索するようになります。主に、成長を促す目的で実施されます。
ネガティブフィードバックは社員にストレスを与える可能性があるため、対象者の選定や伝え方には十分な注意が必要です。
フィードバックの基本的な手法は3種類
基本的なフィードバックの手法は、3種類あります。ここでは、それぞれの手法について解説します。
1.SBI型
SBI型とは、状況を説明したうえで具体的な行動をピックアップし、その行動に対する感想を述べる手法です。Sは「Situation(状況)」、Bは「Behavior(行動)」、Iは「Impact(影響)」を表しています。順序立ててフィードバックするため、内容を理解してもらいやすいことが特徴です。
2.サンドイッチ型
サンドイッチ型とは、ポジティブな内容にネガティブな内容を挟んでフィードバックする手法です。
最初に相手のいいところをほめたうえで改善点を指摘し、最後にもう一度ほめてフィードバック全体を締めくくります。最初と最後にポジティブな内容が示されるため、ネガティブな内容を伝えても社員のモチベーションを維持しやすくなります。
3.ペンドルトンルール
ペンドルトンルールとは、フィードバックを受ける社員に自分自身の改善点を考えさせる手法です。
上司に改善点を報告し、話し合いながら課題を解決するための方法を探します。時間をかけ、コミュニケーションをとりながら進めていくのが大きなポイントです。社員は自ら改善点を見つけられるようになるため、成長につながります。
フィードバックで使える例文を紹介
フィードバックはどのように伝えればいいのでしょうか。ここでは、フィードバックの例文を紹介します。
SBI型の例文
「先週のミーティングにおいて、論点がずれそうになったときに本質的な課題を提示してくれました。その結果、メンバーは論点に即した意見を出すようになったと感じます。話し合いの生産性も向上し、とても助かりました」
サンドイッチ型の例文
「プレゼンで取り上げていた事例がわかりやすく、先方もプレゼンを高く評価していました。しかし、プレゼンの声が小さく、先方の様子をあまり確認せずに話を進めていたのが少し残念です。プレゼンの内容そのものは優れていたため、今後はプレゼンの仕方も工夫しましょう」
ペンドルトン型の例文
部下から「資料の作成に時間がかかってしまうため、今後はフォーマットを用意して効率化したいと思います」という報告を受けたとしましょう。
この場合、上司からは「フォーマットがあれば、生産性も向上しそうですね。どのようなフォーマットを作成しようと考えていますか」などとフィードバックします。
うまくフィードバックするコツとは
フィードバックを成功させるにはさまざまなコツがあります。ここでは、具体的なコツについて解説します。
目標と関連性を持たせる
フィードバックを行う場合、あらかじめ目標設定を行いましょう。目標があると、達成のためにどのような行動が必要なのかわかりやすくなり、フィードバックを行う際に焦点を定めやすくなります。行動の方向性も明確になるため、スムーズに成果を出せるようになります。
実現できる可能性があるフィードバックを行う
フィードバックするときは、相手にとって実現可能かどうかについても配慮します。実現できそうにないフィードバックをしても、行動を起こせません。相手が意欲的にフィードバックの内容を実践し、課題を改善できるようにしましょう。
できるだけ具体的に伝える
フィードバックは具体性が重要です。フィードバックが抽象的であると、指摘を受けても課題を解決できない可能性があります。また、相手から不信感をもたれる原因にもなるため注意が必要です。どの行動をどのように改善すべきか伝えましょう。
タイムリーに行う
フィードバックは、なるべくリアルタイムに行う必要があります。行動してから時間が経つと、フィードバックしてもあまり効果を期待できなくなるでしょう。一方、すぐにフィードバックをすれば、目標に向けた改善策を実行しやすくなります。
客観的な事実に基づく
フィードバックでは主観的な内容を伝えるのではなく、客観的な事実に基づいて伝えるべきです。主観的に判断すると、目標や目的と逸れたり、相手のパーソナリティを否定する恐れがあります。指導者としての思いを伝える場合も、事実に基づいた内容になるよう意識しましょう。
適切な環境で実施する
フィードバックを行うときは、環境も大切です。理想的なのは、相手がリラックスできる環境を確保することです。状況によってはアイスブレイクも取り入れつつ、相手がスムーズにフィードバックを受けられる状況を作りましょう。
信頼できる関係づくりを意識する
フィードバックをするうえでは、信頼関係も重要です。信頼関係がない状態でフィードバックをすると、予想していないような反応が返ってくる可能性もあります。普段からコミュニケーションをとっておくと、フィードバックもしやすくなります。
言葉選びに気を付ける
フィードバックにおいては、言葉選びに気を付ける必要があります。何気なく発した一言でも、相手にとってはネガティブな発言に聞こえる恐れもあります。基本的には否定的な言葉を使わないようするなどし、相手へ配慮しましょう。
適宜フォローアップを行う
フォローアップとは、取り組みについて改めて確認して支援する方法です。フィードバックを行ったうえで定期的なフォローアップも実施すれば、目標達成に向けた取り組みを成功させやすくなります。
フィードバックに関するQ&A
フィードバックについては、さまざまな疑問をもっている人もいるでしょう。ここでは、よくある疑問とその答えを解説します。
フィードバック面談で注意する点とは?
フィードバック面談を実施するときは、その重要性を相手に伝えておきましょう。また、フィードバックを行う上司にもあらかじめ、部下指導に関する教育を実施しておくと、適切なフィードバックを実現しやすくなります。フィードバック面談を終えたら、社員にアンケートをとって改善点を把握するのもひとつの方法です。
フィードバック面談ではどんな質問をすれば良い?
フィードバック面談では、相手が答えやすいよう「はい」や「いいえ」で答えられる簡単な質問から始めましょう。また、相手が自ら答えを出せるよう、適宜サポートしながらフィードバック面談を進める必要があります。
まとめ
フィードバックはさまざまな目的のために実施されています。フィードバックの手法も複数あるため、相手の状況に応じて実施しましょう。フィードバックの際は、今回解説したコツを意識すると効果的です。
株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、役割や立場に応じた教育プログラムを提供しています。経営環境に即したテーマに幅広く対応しているため、人材育成や組織力強化のためにぜひ活用してください。
ニューノーマル時代の管理職のための1on1ミーティング
成長する組織は、対話を重視している
組織づくりにおける「対話」の重要性と、その手段である「1on1ミーティング」のポイントについて解説します。
- 組織に対話が求められる背景
- 1on1ミーティングの効果 (対話がもたらす変化)
- 1on1ミーティングのコツ3点
この機会に下記より資料をご請求ください。
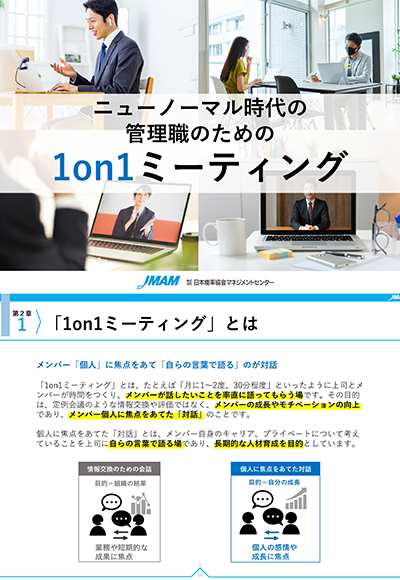
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
-
 中原淳氏|セルフアウェアネス 鍵はフィードバックにあり。他者を通じて自己を知る
中原淳氏|セルフアウェアネス 鍵はフィードバックにあり。他者を通じて自己を知る -
 柳澤 さおり氏|絶好の成長機会を活かす 人事評価のフィードバックを学習につなげるには
柳澤 さおり氏|絶好の成長機会を活かす 人事評価のフィードバックを学習につなげるには -
 田中 潤氏|キーワードは「振り返り」 経験から学ぶ習慣をつける 新入社員研修のつくり方
田中 潤氏|キーワードは「振り返り」 経験から学ぶ習慣をつける 新入社員研修のつくり方
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















