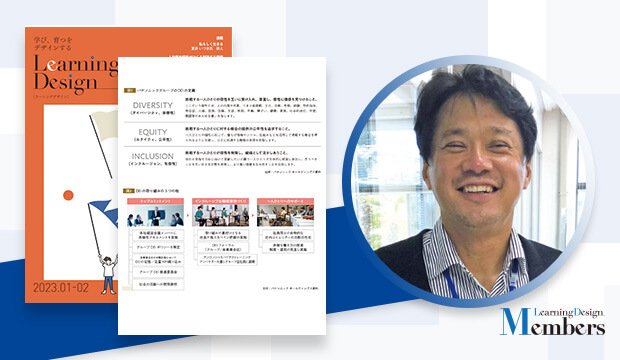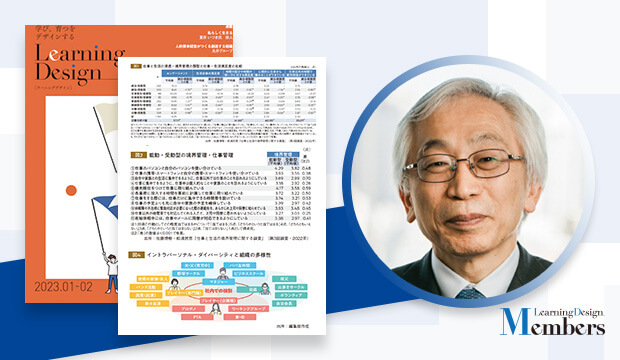- 対象: 人事・教育担当者
- テーマ: 組織風土・文化
- 更新日:
リバースメンタリングとは?導入方法や事例を徹底解説

リバースメンタリングとは、若手社員がメンターとして、メンティーである先輩社員に助言を行う教育支援制度のことを指します。近年の急激なデジタル化や、多様性推進の潮流により導入企業は増えつつあります。
この記事では、リバースメンタリングとは何か、導入方法や注意点、企業事例について解説します。企業の経営者や、人事・人材育成に関わる方は、ぜひ参考にしてください。
関連資料
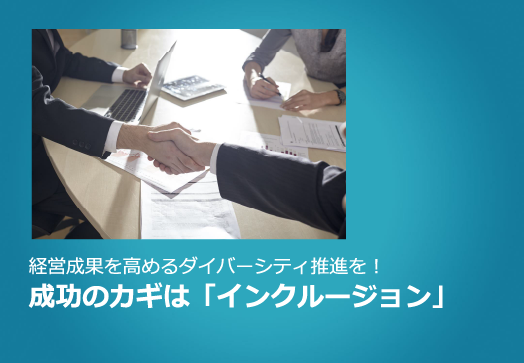
関連資料
経営成果を高めるダイバーシティ推進が分かる
成功のカギは「インクルージョン」
リバースメンタリングとは
リバースメンタリングとは、若手社員と先輩社員が立場を逆転し(=リバース)、若手社員がメンターとして、メンティーである先輩社員に助言を行う教育支援制度のことです。
若手社員が指導者となるため、先輩社員が苦手とするデジタルスキルを教える、若い世代の価値観を教える、といったことがリバースメンタリングの内容です。「先輩社員よりも若手社員が詳しいこと」が、主な指導内容となります。
リバースメンタリングの発祥
リバースメンタリングは、米国のゼネラル・エレクトリック(GE)の元CEOジャック・ウェルチ氏だといわれています。CEO時代、ウェルチ氏は若手社員をマネジャーのメンターにする制度を導入。当時普及前だったインターネットの使い方を、ウェルチ氏自身も学んだそうです。
この成功に倣い、他社でも導入が進みリバースメンタリングは定着していきました。現代でも、最新デバイスやアプリケーションの使い方から、SDGsやダイバーシティ&インクルージョンといった新しい概念理解のために、リバースメンタリングが用いられる場合があります。
そもそもメンター制度とは
従来のメンター制度は、経験が豊富な先輩社員が若手社員の指導役となり、様々なサポートを行う制度のことです。直属の上司ではなく、別の部署からメンターが選ばれる場合が多いです。そのため、業務に関することだけではなくキャリアについての相談等、幅広く対応できることが特徴です。
リバースメンタリングを導入するメリットとは
企業がリバースメンタリングを導入するメリットについて解説します。
ベテラン社員の視野が広がる
リバースメンタリングを導入することで、メンティーであるベテラン社員の視野や知見を広げることができます。デジタルリテラシーの向上や知識の獲得はもちろん、若手の価値観や感覚に触れることで、新しい視点を獲得し、事業や施策の考案につながる可能性もあるでしょう。
若い優秀人材を獲得できる魅力的な組織にするためには、ベテラン社員の視野を広げ、組織の在り方を変えていくことが求められています。
若手社員とベテラン社員のコミュニケーションが活発になる
普段はなかなか接する機会のない若手社員とベテラン社員がフラットに面談できることで、コミュニケーションが活性化します。リバースメンタリングの取り組みが広がれば、縦の交流が社内全体に広がっていくでしょう。
その結果、立場の違いを超えて意見を交わし合える、オープンでフラットな組織風土につながることが期待されます。
若手社員のリテンションにつながる
リバースメンタリングによって、上意下達ではないフラットな組織風土が広まれば、若手社員の心理的安全性も高まるでしょう。また、気軽に話せるベテラン社員がいることや、ベテラン社員が自分を信頼し自己開示してくれることは、若手社員のエンゲージメント向上にも寄与するはずです。結果、若手社員の離職を防止するリテンション効果があるといえるでしょう。
管理職層のマネジメント力向上につながる
若手社員とのコミュニケーションが増えることで、若手社員の価値観や悩みに触れることができます。結果、自身が部下をマネジメントする際に、どんな点に気を付けるべきかが理解できるようになるかもしれません。リバースメンタリングを行うことで、管理職の視野が広がり、マネジメントの質も向上するといえるでしょう。
リバースメンタリング導入が推奨される組織
リバースメンタリングの導入は、どのような組織にとって効果的でしょうか。
リバースメンタリングを行うことで、世代間を超えたコミュニケーションが発生し、互いへの理解が深まることから、組織の硬直化を緩和させることができるでしょう。
そのため、以下のような課題を持つ組織は、リバースメンタリングを導入してみると良いかもしれません。
- 年功序列型の組織
- ヒエラルキー型の組織
- 平均年齢が高い組織
- ダイバーシティを推進したい組織
上意下達でヒエラルキーが強い組織は、社員の同質化が進みやすくなります。しかし、ビジネス環境の変化が激しく答えがない現代においては、同じ考え方や発想しか生まれない企業は苦しい状況に立たされる可能性が高いでしょう。
多様な人々が能力を発揮できる組織を目指すための方法として、リバースメンタリングは有効であると考えられます。
リバースメンタリング導入の方法
実際にリバースメンタリングを導入するためには、どのような手順を踏めばいいでしょうか。人事部門担当者がすべきことについて、順に解説します。
①目的を設定する
リバースメンタリングの導入は手段であって、目的ではありません。なんのために導入をするのか、会社はどのように変わりたいと思っているのかといった目的を設定したうえで、導入するようにしましょう。
②人選
若手社員/ベテラン社員といっても幅広く、年代や役職も様々です。どの世代・役職の人にどう変わってもらいたいか、どんな効果をもたらしたいかを考えたうえで決定しましょう。
また、メンターとメンティーの組み合わせも重要です。たとえば、直属の上司・部下だと指導がしづらいといったことが考えられます。また、それぞれの持つスキルやキャリア志向、性格等も加味しながら組み合わせが決められるようにするとよいでしょう。タレントマネジメントシステムを活用すれば、社員それぞれの志向性の入力や組み合わせの設定がスムーズに行える場合があります。
③目的の共有
対象者が決定したら、目的の共有を行います。見込んだ効果を発揮し、対象者にも安心して実施してもらえるように以下の点を共有しましょう。
- メンター(若手社員)に期待すること
- メンティー(先輩社員)の心がけ
- 運用のルールやサポートについて
④オリエンテーション
実施が決まったら、まずはオリエンテーションから始めましょう。人事担当者が同席し、ファシリテーションやアドバイスを行うといった方法も考えられます。
また、必要に応じてメンターに研修を受けてもらうといったことも検討するとよいでしょう。
⑤関係部署から同意を得る
本格的に導入する前に、関係部署にも同意を得るようにしましょう。現場に協力体制を築いてもらう、理解を深めてもらうことは、社内風土の改善において重要なことです。
⑥フォローアップ
実施状況を確認し、必要なフォローアップを行うようにしましょう。メンターの負担を軽減したり、効果を高めるために、新たなルール策定や緩和等を検討し、良い実施環境を整備していくことが大切です。
リバースメンタリング導入時の注意点
リバースメンタリング導入の際に気を付けたい注意点について解説します。
目的を明確にする
繰り返しですが、リバースメンタリングの導入は手段であって、目的ではありません。
対象者にどのようなことを望むのか、それによって組織をどのように変えていきたいのかを明確にすることで、達成基準を決め、効果測定を行うこともできます。
また、対象者や現場が目的に共感してくれれば、制度が社内に浸透しやすくなるでしょう。
実施の負担に配慮する
リバースメンタリング実施に当たっては、対象者に精神的な負担が生じる可能性があります。特にメンター側の若手社員は、「自分より立場が上の先輩社員に指導する」ということに緊張や抵抗感を持つかもしれません。
人事担当者は、メンティーの指導を受ける姿勢や傾聴の姿勢についてルールを設けたり、メンター側を二名体制にするといった仕組みを設ける等、負担に配慮するようにしましょう。
メンター・メンティーが価値観を尊重しあう
リバースメンタリングは、互いの価値観の違いを学ぶことも目的の一つです。メンターとメンティーに大きな歳の差がある場合や、グローバル企業においては国籍が違う場合もあるでしょう。自分と離れた価値観であったとしても、まずは一度受け止めて尊重する姿勢が大切です。対象者にそのことを意識してもらえるよう働きかけましょう。
評価への反映を検討する
メンターのモチベーション維持のために、リバースメンタリングへの貢献を人事評価に反映させることも検討しましょう。その際は、どのような基準で評価するか、軸をあらかじめ設定しておくことが重要です。
リバースメンタリングの国内事例
日本国内における代表的なリバースメンタリングの実施事例を紹介します。
スリーエム ジャパン
化学・電気素材メーカーのスリーエム ジャパンは、2018年にリバースメンタリングを導入。属性を超えた相互理解を目的とし、DE&I推進の一環として始まりました。メンターとメンティーがエントリーシートを記入し、それを元にマッチングを行ったことで、良い関係性を築きやすい土台が整ったとのことです。
その取り組みが評価され、現在ではグローバル展開。異文化コミュニケーションの学びのために、他国のメンターを中心としたマッチングが行われています。
P&G
P&Gは日本で初めてリバースメンタリングを導入したといわれている企業です。メンターは若手社員に限らず、外国人社員や子育て中の社員等も任命されています。
メンティーのメンターに対する相談内容は、仕事に関することだけではなく、生活面の相談、仕事と子育ての両立相談といったことも対象となっています。
その結果、同社のリバースメンタリング制度は女性が働きやすい職場風土づくりに貢献しました。
参照:内閣府男女共同参画局/【組織部門優秀賞】P&G
https://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/h21torikumi/pdf/case2/b13_1.pdf
資生堂
資生堂では、若手社員がエグゼクティブオフィサーや部門長のメンターとなって意見交換するリバースメンタリングプログラムを実施しています。2017年から2021年までの間に600人以上が実施しており、デジタルスキル向上のほか、世代を超えたコミュニケーションにより、異なる価値観を尊重できるフラットな組織風土づくりを実現しています。
参照:資生堂HPより『多様なプロフェッショナル人財』
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/value_creation/process/people/strategy/
まとめ
リバースメンタリングは、ダイバーシティの推進や、フラットな組織風土づくりに貢献するなど、様々な効果が期待できる制度です。導入する企業も増えており、これからますます注目が集まるでしょう。
なお、ダイバーシティの推進方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下のホワイトペーパーが参考になります。1979年より企業向け研修を実施している「株式会社日本能率協会マネジメントセンター」が提供しているホワイトペーパーです。ぜひダウンロードしてみてください。
関連資料
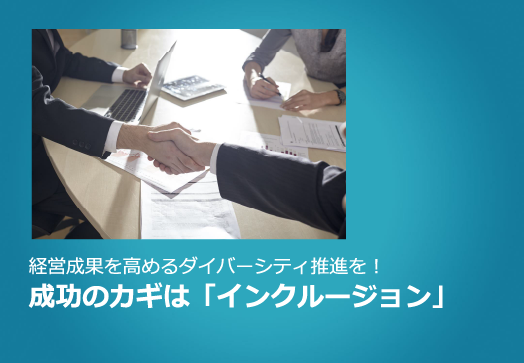
関連資料
経営成果を高めるダイバーシティ推進が分かる
成功のカギは「インクルージョン」
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
-
 リバースメンタリング|“教える-教わる”の立場逆転で深まる相互理解
リバースメンタリング|“教える-教わる”の立場逆転で深まる相互理解 -
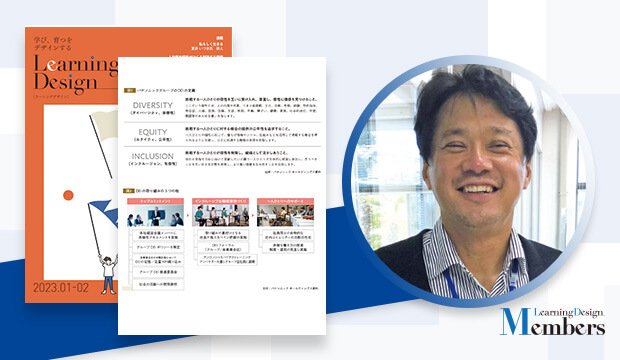 DEI|「平等」ではなく「公平性」を重視した人材戦略 DEI
DEI|「平等」ではなく「公平性」を重視した人材戦略 DEI -
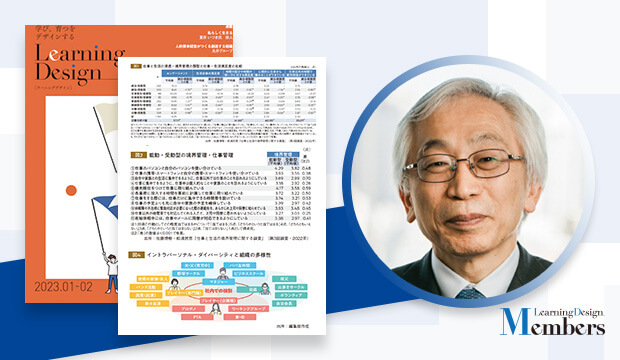 バウンダリー・マネジメント|仕事とプライベートの境界をマネジメントする
バウンダリー・マネジメント|仕事とプライベートの境界をマネジメントする
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます