- 対象: 人事・教育担当者
- テーマ: 採用
- 更新日:
構造化面接とは?メリットや導入事例、実施する際の注意点も紹介
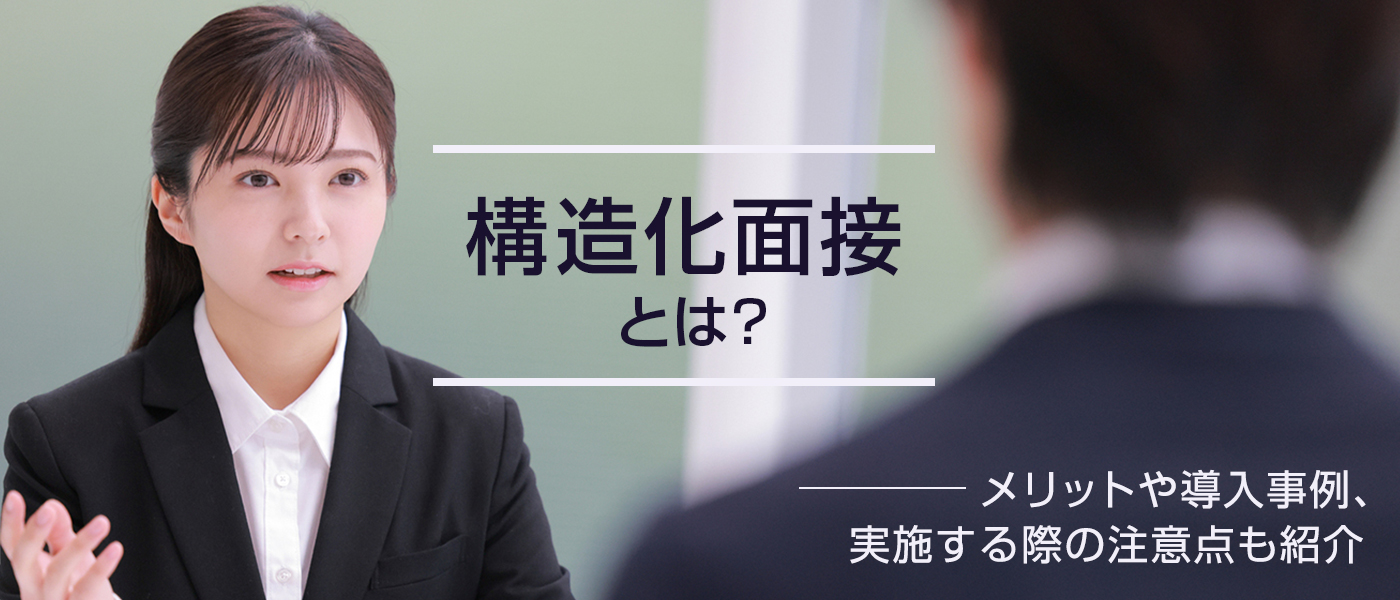
構造化面接は、採用プロセスの効率化と公平性の向上を目的とした面接手法です。面接官の主観による評価のばらつきを抑え、客観的な基準で候補者を評価できます。
今回は、構造化面接の定義や特徴、従来の面接手法との違いについて詳しく解説します。
関連資料
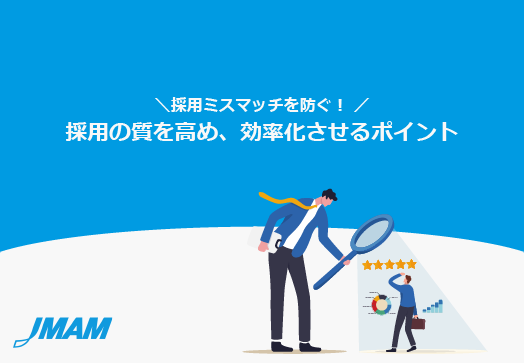
関連資料
企業が人材採用活動の質と効率を向上させるための効果的な方法を解説
採用ミスマッチを防ぐ!採用の質を高め、効率化させるポイント
構造化面接とは
構造化面接は、あらかじめ設定された評価基準や質問項目に沿って、手順通りに実施する面接手法です。
面接の内容や形式があらかじめ決められており、すべての候補者に対して同じ質問をすることが特徴です。面接のプロセスが体系的(構造化)になっていることから、「構造化面接」と呼ばれます。
まずは、その手法と従来の面接との違いについて説明します。
構造化面接の手法
構造化面接は、臨床心理学のアプローチのひとつとして、古くから行われてきました。「面接官が主導で聞きたい情報を取りに行く」「オンライン面接に向いている」などの特徴があります。
面接の質問例として、下記2つの切り口があります。
1. 経験ベースの質問
STAR面接と呼ばれる手法が利用されることが多くあります。STAR面接とは、Situation (状況)、Task (課題)、Action (行動)、Result (結果)に関する質問をする面接のことです。
【質問例】
・今まで所属した組織でのあなたの役割は何でしたか?
・どのように周りを巻き込みましたか?
2. 仮説ベースの質問
仮定した状況で、どう思考するかという思考パターンをみます。
【質問例】
・もし○○だった場合、どのように行動しますか?
・なぜその対策を講じますか?
従来の面接(非構造化面接・半構造化面接)との違い
構造化面接は、従来の面接手法と比較して、体系的かつ一貫性のある評価が可能です。
一方で、非構造化面接は質問項目や質問の順番は面接官の自由であり、評価基準の一貫性が低くなる傾向にあります。
また、半構造化面接は同じ質問を決まった順で行い、面接官が自由に質問する手法です。こちらも、評価基準の一貫性を保つことが難しい場合があります。
どちらの面接も、構造化面接と比べると候補者を客観的かつ公平に見極めることが難しい点が課題になりがちです。
構造化面接は、以前からある2つの手法と異なり、一貫した評価基準と質問項目を用いることで、より客観的で公平な評価がしやすいと考えられています。
採用プロセスの質を向上させ、適切な人材を選考することが期待されています。
構造化面接を導入するメリット
構造化面接の導入には、採用プロセスの改善や効果的な人材選考の実現が期待されるなど、多くのメリットがあります。
なかでも重要な3つのメリットについて詳しく説明します。
面接官の評価のばらつきを防ぐ
構造化面接のメリットは、面接官による評価のばらつきを抑えやすい点にあります。
質問項目の内容と順番が事前に決められており、各評価項目に対して1から5のような段階評価が設定されています。
構造化面接のアプローチ方法により、面接官の主観や個人的な好みによる偏りを防止できます。
結果として、候補者のスキルや能力をより客観的かつ高い精度で見極めることが可能です。
また、評価基準が明確に定められており、面接官による解釈の違いも最小限に抑えられます。
採用後のミスマッチを抑えられる
構造化面接の2つ目のメリットは、採用後のミスマッチを効果的に減らせる点です。
求める人材に必要なスキルや能力を評価基準として明確に設定し、それに沿った質問を行うため、採用要件に適合する人材を正確に見極めやすくなります。
採用後に期待していた能力と実際の能力のギャップが生じるリスクを低減できることから、長期的な人材定着率の向上にもつながります。
採用の効率化につながる
構造化面接の3つ目のメリットは、採用プロセス全体の効率化です。
質問項目と順番が事前に定められているため、より短時間で効率的に質疑応答ができます。
面接官が質問内容をその場で考える必要がなくなり、話が脱線するリスクも減少します。限られた面接時間を最大限に活用し、必要な情報を漏れなく収集できるでしょう。
さらに、面接の準備や評価にかかる時間も短縮されます。
事前に質問リストと評価基準が用意されているため、面接官は面接に集中でき、面接後の評価もスムーズに行えます。
構造化面接の導入事例
構造化面接の効果を実感するため、実際に導入している3つの企業の事例をみてみましょう。
構造化面接をどのように活用し、どのような成果を得ているかを確認してみてください。
事例1|株式会社Another works
株式会社Another worksは、採用を経営の最重要事項と位置づけ、採用基準の明確化に注力しています。
同社の採用基準の特徴は、つくりたい組織から逆算して必要な価値観を基準としている点です。
スタートアップ企業である同社は、スキルマッチよりもカルチャーマッチを重視しています。役員面接では、管掌役員が業務スキルを見極める一方で、管掌外の役員があらかじめ定めた評価基準に従って質問する構造化面接の形式を採用しています。
結果的に、候補者の適性を多角的に評価し、同社の文化に適合する人材を選ぶことが可能になりました。
事例2|株式会社アトラス
株式会社アトラスは、候補者をより正確に見極めるため、非構造化面接から半構造化面接に移行しました。
同社の面接では、必須質問と面接官による臨機応変な質問を組み合わせて実施しています。
また、採用マッチング率を向上させるため、求める人物像と評価基準の見直しも行ったそうです。評価基準は「志向性や考え方」と「経験や過去の行動」に分け、特に後者を重視するよう変更しています。
非構造化面接から半構造化面接に移行したことで、アトラスは候補者の適性をより正確に把握し、採用後のミスマッチを減少させることに成功しています。
事例3|株式会社ヌーラボ
株式会社ヌーラボは、公正かつ適正な判断を行うため、構造化面接を導入しています。事前に面接の質問リストを作成し、候補者ごとにGoogleドキュメントをコピーして活用しています。
さらに特徴的なのは、面接30分前に候補者のレジュメをみながら質問リストに肉付けする事前ミーティングを実施していることです。
各面接官が候補者に質問したいことを挙げ、面接中に深掘りすべきポイントをすり合わせることで、効率的な面接を実現しています。
結果的に、候補者同士の比較を容易にし、質問の漏れ防止に成功しました。また、面接の質を向上させ、より適切な人材の選考を可能にしています。
構造化面接を実施する際の注意点・ポイント
構造化面接は多くのメリットがある一方で、実施する際にはいくつかの注意点があります。構造化面接を効果的に行うためのポイントと、起こりうる課題への対策を解説します。
機械的な印象を抱かれる可能性がある
構造化面接では、あらかじめ決められた質問を順番に行うため、候補者に機械的な印象を与えてしまう可能性があります。
機械的な印象は、面接官と候補者の自然なコミュニケーションを阻害し、候補者の本質を見逃す原因になりかねません。
構造化面接を導入する際は、候補者との良好な関係性を構築しつつ、必要な情報収集をするための対策が必要です。
例えば、下記のような対策が有効です。
- 面接の冒頭でアイスブレイクの時間を設ける
- 質問の間に適度な間を置き、候補者の回答をしっかりと傾聴する姿勢をみせる
- 候補者の回答に対して、適切なフォローアップや質問を用意しておく など
参加者の個性や新たな一面を見いだしにくい
構造化面接では、決められた質問に沿って進めるため、候補者の予想外の魅力や能力を発見しにくい課題があります。
優秀な人材を見逃さないよう、下記のような点を意識することをおすすめします。
- オープンエンドの質問を含める
- 候補者の回答に基づいて、柔軟に追加質問を行う
- 面接の最後に、候補者が自由に話せる時間を設ける など
準備に時間と手間がかかる
構造化面接の効果的な実施には、質問項目の設計や評価基準の策定など、入念な準備が必要です。
この際、下記の点を抑えておくと効率的に準備が進みます。
- 人事部門と現場部門が協力して質問項目を作成する
- 過去の採用データを分析し、効果的な質問を特定する
- 定期的に質問項目や評価基準を見直し、継続的に改善する など
面接で自社の魅力を伝えるのが難しい
構造化面接は候補者の評価に重点を置いているため、自社の魅力を十分に伝えられないことがあります。
しかし、面接は候補者を選ぶ場であると同時に、候補者から選ばれるための場でもあります。
構造化面接を行うなかで候補者に企業の魅力を伝えるためには、下記のような対策を盛り込むと良いでしょう。
- 面接の一部に会社説明の時間を設ける
- 質問項目に自社の強みや特徴を織り込む
- 候補者からの質問時間を十分に確保する など
過度に対策されることがある
構造化面接では同じ質問を繰り返し使用するため、候補者が事前に対策を立てやすくなります。
候補者の本来の姿を見極めるには、質問内容の工夫が必要です。例えば、下記のような点を盛り込むことをおすすめします。
- 定期的に質問内容を更新する
- 状況設定型(「もし◯◯という状況が起こったら、どう対処しますか?」)の質問を取り入れる
- 候補者の回答に対して、具体的な事例を求める追加質問を準備する など
まとめ
構造化面接は、採用プロセスの質を向上させる手法のひとつとされています。効果的な構造化面接の実施により、採用のミスマッチを減らし、優秀な人材の確保につながることが期待できます。自社の採用課題を明確にし、目的に合った手法を採用することも、より効果的な人材採用につながるでしょう。
しかし、導入には自社の状況や目的に合わせた適切な調整が必要です。メリットとデメリットを十分に理解し、自社に最適な採用方法を選択しましょう。
なお、優秀な人材の確保や候補者の見極めにお悩みの方は、ぜひ下記の資料をご覧ください。採用の質を高め、効率化させるポイントをわかりやすく解説しています。
解説資料|採用ミスマッチを防ぐ!採用の質を高め、効率化させるポイント
採用の質・効率アップにむけた、課題と打ち手とは
本資料では、企業が人材採用活動の質と効率を向上させるために、採用アセスメントを活用する効果的な方法について解説しています。
- 採用活動の現状と課題
- 採用の質・効率アップにむけた打ち手
- 採用アセスメントツールの活用方法
- アセスメントツールのご紹介

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















