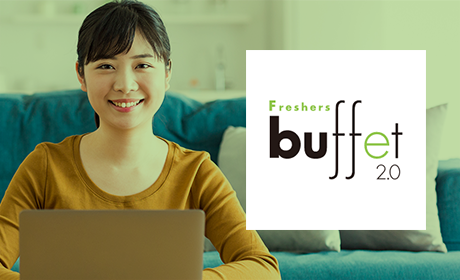- 対象: 人事・教育担当者
- テーマ: 研修/教育
- 更新日:
eラーニングとは?メリット・デメリットを徹底解説!
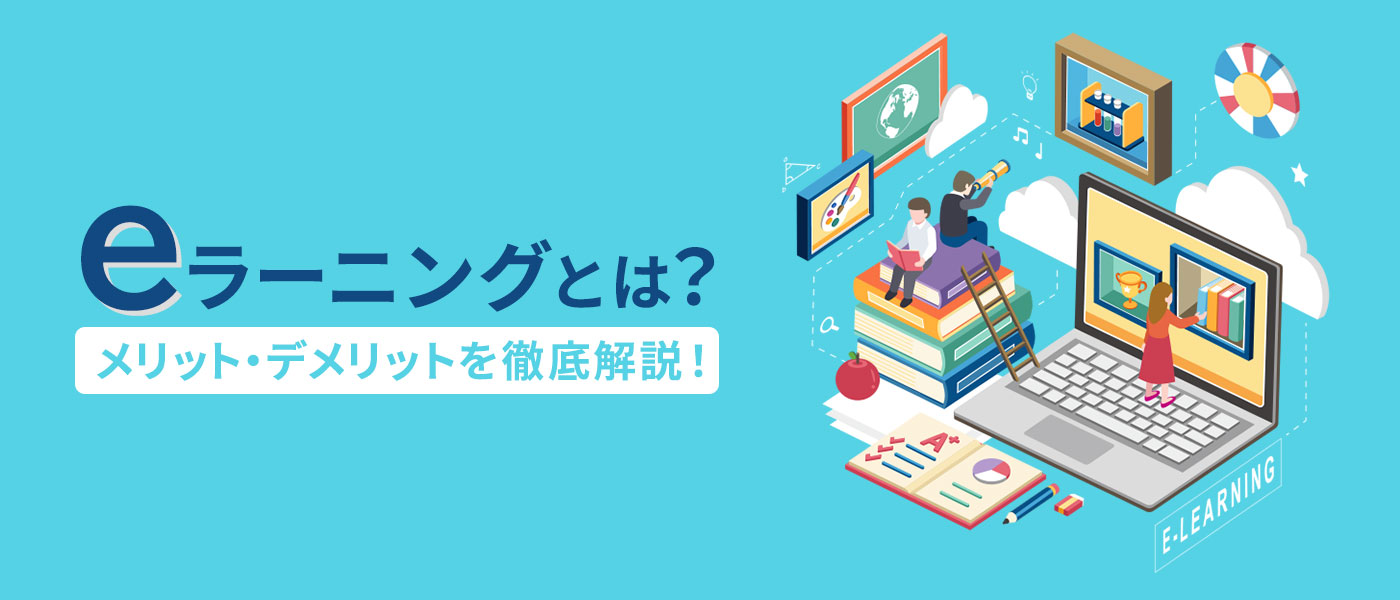
企業の人材育成でも、デジタルの利便性を活用して個人学習を支援したいという企業が増えています。自社の人材育成にも取り入れたいが、そもそも「研修とどう違うのか」「eラーニングならではのメリットや活用方法は?」などを調べている方もいるのではないでしょうか?
今回は、eラーニングとは何か、他の人材育成との違いやメリット・デメリットについて解説します。
関連サービス

関連サービス
ハラスメントやコンプライアンスなど、全社理解におすすめ
「守りの教育」をこれ1つで!eラーニングライブラリ®
eラーニングとは?
eラーニングは、あらかじめ用意されたコンテンツを視聴して学習する研修方法です。これは「オンライン学習」とも呼ばれています。学習管理システム(サーバー)に保存された動画教材を、パソコンやスマートフォンなどの端末によって受講します。
受講者は自分の好きな時間に学習することができます。eラーニングは柔軟性と自分のペースで学習できるのが特徴であり、社内教育の手法のひとつとして広く活用されています。
下記資料では法人向けeラーニングのコース一覧をまとめています。詳しい学習内容を知りたい方はぜひお問い合わせください。
eラーニングの歴史
《eラーニング登場の歴史》
| 1950年代 | CAI (Computer Aided InstructionまたはComputer Assisted Instruction)にもとづく研究・開発が各国で行われる |
|---|---|
| 1990年代 | パーソナルコンピューターの普及にともない「CBT(Computer-Based Training)」と「WBT(Web-Based Training)」が登場する |
| 2000年代 | eブームにより「eラーニング」という言葉が誕生 |
eラーニングの歴史は、1950年代にまで遡ります。1950年代に「CAI」(Computer Aided InstructionまたはComputer Assisted Instruction)という考えが登場しました。CAIとは、コンピュータを利用した教育支援のことです。
1995年にはWindows 95が発売され、写真や動画を組み合わせたマルチメディア教材が作られました。マルチメディア教材の中でも、CD-ROM教材を中心とする学習は「CBT(Computer Based Training)」、Web環境を利用した学習は「WBT(Web Based Training)」と言います。
2000年代に入るとeコマース(EC)やeスポーツなどのeブームが始まり、WBTのようなネット環境を利用する教育を総じて『eラーニング』と呼ぶようになりました。
2000年代後半からは、スマートフォンやタブレットが普及し、モバイル学習(m-learning)が登場しました。
このように、eラーニングは技術の発展と共に進化を遂げてきたのです。今後も新しいテクノロジーの出現により、教育のアクセシビリティや効率性がさらに向上することが見込まれます。
オンライン研修とは?eラーニングとの違い
オンライン研修は、Web会議ツールなどを使ってオンラインで行われる研修方法です。これには「Webセミナー」や「ウェビナー」も含まれます。研修日時が事前に決められ、リアルタイムで行われます。従来の集合研修がオンラインに移行した形態と考えるとイメージしやすいでしょう。
講師と受講者が同じ時間に参加するため、講師は受講者の理解度を確認しながら進行することができます。オンライン研修は効率的かつ柔軟な学習方法として社内教育に活用されています。
オンライン研修とeラーニングの違い
両者はどちらもオンライン学習ですが、一般的にオンライン研修は双方向型であり、eラーニングはオンデマンド型の学習です。
双方向型であるオンライン研修はリアルタイム配信を行い、講師と受講者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら進行します。
一方、オンデマンド型のeラーニングはあらかじめ用意された学習コンテンツを受講者が自分のペースで視聴します。目的に合わせて、適切な学習形式を選択することが必要です。
eラーニングのメリット
ここでは、eラーニングのメリットを6つ紹介します。
1 場所や時間を問わず受講できる
集合研修の場合は、研修場所を確保して受講者と教育者の双方のスケジュールを調整する必要があります。会場の費用や交通費などのコストもかかります。
一方、eラーニングは場所や時間を問わず受講できるため、コストや手間がかからない点がメリットです。
インターネット環境さえあれば自分のペースで学習を進められます。
2 社員数を問わず教育の質を均一化できる
集合研修やオンライン研修の場合、講師のスキルによって教育の質に差が生まれることがあります。指導者研修などを行うのは有効ですが、コストがかかります。
一方、eラーニングは全受講者が同じ教材で学習できます。居住地や勤務地を問わず、同じ学習環境を提供でき、教育の質を均一化できるのは大きなメリットです。
3 受講者に合わせたプログラム設計ができる
eラーニングの教材は、多くのコンテンツから自身に必要な内容を選んで学習することが可能です。
「新入社員向け」「営業職向け」といったように、習熟度や階層、職種などに合わせた学習プログラムを設計し、一人ひとりに合った学習を提供できます。
また受講者にとっても、自分に足りない知識・スキルから学べるため、効率的に成長できます。
4 手軽に教材を修正・アップデートできる
eラーニングであれば、プラットフォームの管理画面で手軽に教材内容を追加したり修正したりできます。
社員研修は、時代の変化やニーズに合わせて変更・アップデートしていくことが大切です。特にコンプライアンス研修は、法改正に合わせて教材を変える必要があります。とはいえ、すでに作成した教材を更新するのは時間も手間もかかるものです。
eラーニングを導入することで、技術や業界のトレンドが変化した場合も最新の内容を教材に組み込めます。
5 学習進捗・成績を一元管理できる
eラーニングでは個々の受講者の進捗状況をリアルタイムで把握し、管理できます。
社員数の多い企業において、受講者一人ひとりの学習状況をひと目で把握できるのは大きなメリットです。
受講者がコース内でどの程度進んでいるか、どのセクションで苦労しているかを簡単に確認でき、適切なフィードバックが可能です。
また、学習の進捗具合を確認して、受講者の特性やどういったテーマに関心があるのかを把握することもできます。
6 反転授業やブレンディッドラーニングが実施しやすい
反転授業とは、「授業で学習し、自宅で復習する」という一般的な学習スタイルではなく、「自宅で予習し、授業でさらに学習する」というスタイルを指します。
ブレンディッドラーニングとは、集合研修やeラーニング、動画コンテンツなど、複数の学習方法をブレンド(組み合わせた)した学習法のことです。
eラーニングは反転授業やブレンディッドラーニングと相性が良く、eラーニングをテストや対面研修などと組み合わせることで、教育の質を高められます。
eラーニングのデメリット
eラーニングの導入を考えている場合は、事前にデメリットも把握しておきましょう。
受講者のモチベーション維持が難しい
eラーニングは受講者の好きなタイミングで学習を進められるメリットがありますが、学習が継続できるかどうかは受講者のモチベーション次第です。
集団研修や学校の授業などと違って「学習しなければいけない環境」がないことから、受講者自身がスイッチを入れて取り組まなければいけません。
また、eラーニングはひとりで取り組む学習方法であり、集合研修に比べて受講者同士の交流がないこともモチベーションの維持が難しい要因のひとつです。
受講者のモチベーションを維持するには、学習をフォローできる機能を備えたeラーニングシステムを選ぶのがおすすめです。
たとえば、下記のような機能が挙げられます。
- 教育担当者側が設定したeラーニングの学習テーマをお知らせできる機能
- 学習の進捗状況に応じて学習を喚起するリマインドメールを自動送信する機能
質問にリアルタイムで対応できない
対面研修の場合、受講者の質問に対してその場で即時回答でき、受講者は一つひとつ理解を深めながら学習を進められます。
しかし、eラーニングで講師に質問するためにはメールやチャットなどで連絡を取らなければならず、回答を得るまでに時間がかかってしまいます。
複数の学習方法を用いるのもおすすめです。
知識のインプットはeラーニングで行い、集合研修ではそのテーマについてディスカッションをするなど組み合わせることで、受講者のモチベーションを維持し学習効果を高めることができます。
自社独自の教育内容を盛り込むのが難しい
基本的にeラーニングはあらかじめ搭載している学習教材を利用するため、自社独自の内容などは盛り込めません。
理念研修などでオリジナルの資料を使用したい場合は、学習教材を一から作成する必要があります。とはいえ社内でeラーニング用の学習教材を作成するのは手間もコストもかかってしまいます。
そのため既存の資料をアップロードして教材を作成できる機能を備えたeラーニングシステムを選ぶのがおすすめです。
社内で作成した資料とプラットフォームに用意されている教材とを組み合わせて、オリジナルの学習教材を作ることができます。
eラーニングを始めるために必要な準備
eラーニングのメリット・デメリットを知り、前向きに導入を検討したいと思った方も多いのではないでしょうか。
次に、eラーニングを自社に導入するための必要な準備を紹介します。
eラーニングシステム(学習管理システム:LMS)
eラーニングシステムとは、eラーニングの配信や受講者の学習管理などができるシステムのことです。学習管理システム (LMS:Learning Management System )とも呼びます。
eラーニングシステムに搭載されている基本的な機能は以下の通りです。
- コンテンツ管理:教材の登録・検索・管理をする機能
- 学習管理:受講者の学習進捗や学習結果を管理する機能
- 通知機能:受講者に必要な通知を送信する機能
- ユーザー管理機能:受講者のアカウントを管理する機能
ひとくちに「eラーニングシステム」といっても、提供している会社によって搭載されている機能は異なります。
自社のニーズに合ったシステムを選ぶことが重要です。
eラーニングシステムの選び方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
失敗しないeラーニングシステムの比較ポイントを解説!活用方法や注意点、メリット、デメリットまで
学習教材
基本的なeラーニングシステムには学習教材が標準搭載されています。
また既存の資料をアップロードして教材を作成できる機能があれば、社内にある資料を活用して教材を作成することも可能です。
そのほかに必要な学習教材を内製したい場合は、下記の方法があります。
- 1. 提供会社が用意している教材を購入する
- 2. 提供会社に制作を依頼する
- 3. 提供会社に内製化支援を受ける
教育担当者
受講者の学習を管理、支援する教育担当者も決めましょう。
教育担当者はeラーニングの運用に関して下記のような役割を担い、受講者の学習を支援します。
- 受講者から寄せられる質問に回答する
- 受講者の学習状況に応じて受講を喚起する
eラーニング活用のトレンド
eラーニングは時代とともに変化・発展してきました。
ここでは、eラーニングを活用した学びのトレンドを2つ紹介します。
1.マイクロラーニング
マイクロラーニングは、短時間での学習を目的としたeラーニングの一種です。
eラーニングの学習コンテンツは通常、30分~1時間程度であるのに対し、マイクロラーニングは1分~5分程度となっています。
マイクロラーニングは、忙しい受講者でも隙間時間を活用して学習を進められるのがメリットです。
2.動画教材
ITの技術が発展し、スムーズに動画のアップロードや再生ができるようになったことから、動画教材が主要なトレンドになっています。
例に挙げると、「講師の授業を録画した動画」「キャラクターが登場するアニメーション」などがあります。
動画教材のメリットは、視覚的なアプローチで受講者の学びを深められる点です。
【番外編】研修とeラーニングはどう使い分ける?
研修とeラーニングは同じオンライン上での学習ですが、メリット・デメリットが異なります。そのため、それぞれの教育方法の特性や強みを理解した上で使い分けることが重要です。
たとえば、グループディスカッションやワークショップのような対話によって学を深める場合は、双方向のコミュニケーションが可能な研修が向いています。知識のインプットであれば、隙間時間を活用して学べるeラーニングが効率的です。
また、オンライン研修とeラーニングを組み合わせるのも有効です。
eラーニングでインプットした知識について、オンライン研修を通して受講者同士で語り合い、考えを深めるなどの活用方法があります。
オンライン研修の内容を理解しているかどうかについて、確認テストをするのも良いでしょう。
まとめ
eラーニングは、インターネットを使った学習形態です。受講者は、パソコンやスマートフォンからeラーニングシステムにアクセスし、配信されている教材を選択して学習を進めます。eラーニングは、場所や時間に縛られず受講できる点がメリットです。
日本能率協会マネジメントセンターでは、約80年の企業向け人材育成を支援しています。受講者や目的に応じた各種eラーニングをご用意しておりますので、ぜひご相談ください。研修とeラーニングを組み合わせたご提案など、御社の課題に合わせてラーニングデザイナーがご提案いたします。
eラーニングライブラリ®
コンプライアンスなど「守りの教育」をこれ1つで!
変化が激しい中「守り」の教育は、 企業存続の前提条件。ハラスメント、コンプライアンス、情報セキュリティ等、今全社に必要な教育をこれ一つでまるっと解決!
- いま企業が必要としている教育をラインナップ
- 1年間定額で学び放題
- デジタルで、全社の受講管理もかんたん

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます