- 対象: 全社向け
- テーマ: 研修/教育
- 更新日:
企業のコンプライアンス違反事例集! 根本的な原因から考える解決策とは

社会的責任を負う企業のコンプライアンス違反は、経営に深刻な影響を与える問題です。昨今、この事例が増えており、コンプライアンスへの取り組みはさらに重要性を増しています。
具体的な対策としては、社内規定の整備や外部講師の招へい、外部の専門サービスなどを利用した研修による社内理解の徹底が考えられます。
経営幹部から管理職、新入社員に至るまで、包括的な理解を促す研修を定期的に実施し、コンプライアンスを遵守する意識を社内に浸透させることが重要です。
今回は、コンプライアンス研修の重要性と実施方法について詳しく解説します。
関連資料
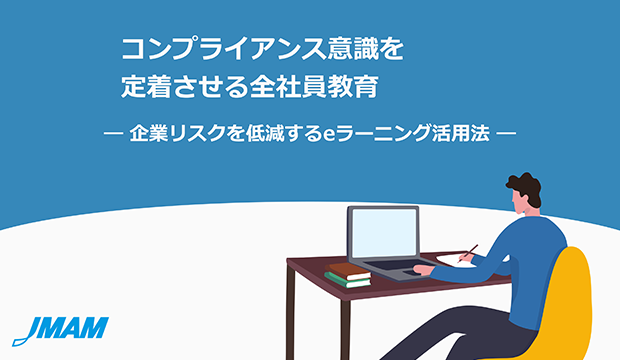
関連資料
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と課題解決に向けたポイントを紹介
コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
目次
- 2024年はコンプライアンス違反倒産が過去最多
- そもそもコンプライアンスとは?
- コンプライアンスが注目され始めた背景
- 企業によくあるコンプライアンス違反の事例
- 【2024年】最新のコンプライアンス違反事例
- 企業でコンプライアンス違反が起こる根本的な原因
- 企業におけるコンプライアンス違反の予防策
- コンプライアンス研修の重要性・メリット
- コンプライアンス研修で実施する主な内容
- コンプライアンス違反事例にもとづくケーススタディの設計方法
- コンプライアンス研修の対象者は?
- コンプライアンス研修の実施方法
- コンプライアンス研修の流れ
- コンプライアンス研修で結果を出すための4つのコツ
- よくある質問
- まとめ
2024年はコンプライアンス違反倒産が過去最多
2024年のコンプライアンス違反による倒産は倒産全体の約4%を占め、388件に達しました。3年連続で前年を上回り、2023年から連続で300件を超えています。
出典:「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年)」(帝国データバンク)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250124-compliance2024/
もっとも多かった違反類型は「粉飾」
2024年の違反類型別の内訳をみると、トップは「粉飾決算」で95件(構成比24.5%)に上り、過去最多となりました。
粉飾決算とは、企業が自社の財政状態を実際よりも良く見せるために、意図的に不正な会計処理を行い、事実とは異なる決算書を作成する行為を指します。
2024年に粉飾決算が増加した要因のひとつといわれるのが、「ゼロゼロ融資」です。
ゼロゼロ融資は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経営に影響を受けた中小企業や個人事業主向けに、実質無利子、無担保で実施された融資制度の総称です。
ゼロゼロ融資は資金繰りに一時的な好転をもたらしたものの、一部の企業にとっては、経営実態の悪化が表面化しにくい状況を生み出す素にもなっていました。その後、ゼロゼロ融資の返済の開始とともに、粉飾決算の表面化が相次いだと考えられています。
違反類型別のランキングでは、粉飾に次いで「業法違反(労働安全衛生法違反や指定取消など)」が72件で2位、3位は「資金使途不正」で70件となっています。
もっとも多かった業種は「サービス業」
コンプライアンス違反による倒産件数を業種別の大分類でみると、サービス業が122件と最多でした。
サービス業のうちもっとも多い業種は「広告・調査・情報サービス業(広告代理業者やソフトウェア業者など)」で50件を占めています。
サービス業に次いで、建設業が68件、小売業が54件となっています。
そもそもコンプライアンスとは?
コンプライアンスの具体的な意味について、関連性が高く、混同されやすいコーポレートガバナンスやCSRとの違いもあわせて解説します。
コンプライアンスの意味
コンプライアンスは、公正や倫理を守るための取り組みで、「法令遵守」の訳語です。
さらに企業コンプライアンスの場合は、法令だけでなく社会的規範や倫理も含めて守ることを指します。
コーポレートガバナンス・CSRとの違い
コーポレートガバナンスとは、健全な企業を実現させるために経営を監視・監督する仕組みを整え、不正や問題を未然に防ぐ取り組みです。
経営の透明性を確保すると、投資家に安心感を与え、新たな出資や融資を得やすくなります。
一方、CSR(企業の社会的責任)は、自社の事業活動が地域や環境、人権問題などに与える影響に対して責任ある行動を取り、説明責任を果たす考え方です。
企業は自社の利益追求のみならず、従業員や顧客をはじめとするステークホルダーの要望や期待を考慮し、社会に貢献することを通じて、CSRを適切に果たす必要があります。
コーポレートガバナンスは不祥事の防止や企業価値の向上を目指すのに対して、CSRは社会からの信頼を向上・維持させる目的があります。
コーポレートガバナンスとCSRの主な目的は異なりますが、コンプライアンスにおいて相互に関連している重要な概念です。
コンプライアンスが注目され始めた背景
下記のような不祥事や社会変化を背景に、コンプライアンスの重要性が認識されるようになりました。
- 1 企業の不正や不祥事
- 2 SNSの普及
- 3 人的資本経営の推進
各項目について、詳しく解説します。
企業の不正・不祥事
コンプライアンスが注目され始めた背景として、企業による不正や不祥事の増加があげられます。バブル崩壊後に多くの不正が相次ぎ、日本のガバナンスが疑問視されるようになりました。
《当時発生した不正・不祥事の例》
- 巨額損失補填問題
- リクルート事件
- 簿外債務問題
対策として、政府は商法や会社法の改正だけでなく、大企業に対するコーポレートガバナンスコードの取り決めなど、不正予防に向けての制度改定を行いました。
不祥事を防ぐ組織体制へと変革するためには、経営層が率先してコンプライアンスの重要性を理解し、社内に浸透させる動きが大切です。
企業の倫理観や行動規範の再構築、世間からの評価も考慮しながら内部統制に取り組む必要があります。
SNSの普及
スマートフォンの普及によってSNSの利用率が増加しているのも、コンプライアンスが注目されるようになった理由のひとつです。
SNSの危険性に対する意識が低いユーザーも存在しており、コンプライアンス違反につながる発言も多くみられます。
従業員が非常識な意見や倫理観に欠けた発言をすると、それが拡散されて多くの批判や誹謗中傷を受け、ビジネス活動に影響するおそれがあります。
不適切な発言だけでなく、内部告発や情報漏えいなどもSNSで批判の的になる可能性があるため、注意すべきです。
普段から常識やマナーに考慮し、企業の秘密情報や個人のプライバシーを尊重した姿勢が求められています。
従業員にこのような意識付けを行い、リスクを軽減するためにも、コンプライアンス教育が重要です。
人的資本経営の推進
多くの企業で人的資本経営が推進され、コンプライアンスが改めて注目されるきっかけになりました。
人的資本経営は、人材を企業の資本と捉えて持続的な成長を促す手法です。
人的資本経営を推進する上で重要とされているのが情報開示です。企業が開示すべき内容として次の7分野があります。
- コンプライアンス、倫理
- 育成
- エンゲージメント
- 流動性
- ダイバーシティ
- 健康、安全
- 労働慣行
経済産業省でも人的資本経営の重要性が強調されており、「人材版伊藤レポート」では従来の考えを変革する必要性が述べられています。人的資本経営に取り組むと、従業員の能力が可視化されるだけでなく、生産性の向上も期待できます。
企業が人材への投資を積極的に行い、持続的な成長を促すことが求められているのです。
参考:「『人材版伊藤レポート2.0』を取りまとめました」(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220513001/20220513001.html
企業によくあるコンプライアンス違反の事例
過去に企業で起きたコンプライアンス違反の事例を紹介します。
法令違反
コンプライアンスにおいて特に注意すべきなのが法令違反です。
企業が法律に違反して事業を行うと、損害賠償や罰金が発生するだけでなく、企業の信頼を大きく損なうおそれがあります。
企業が法令違反をした具体的な事例として、下記のような行為があげられます。
- 商標登録された商品名と類似する製品を販売した
- 著作物を無断で業務利用した
法令違反を防ぐためには、従業員が正しい知識を身につけられるよう育成プログラムを実施することが有効です。
また専門家やコンサルタントを雇い、継続的なサポートとガイダンスを行うのも効果的です。
企業全体で法令を遵守することで、信用やカスタマーロイヤリティの維持・向上が期待できます。
労働問題
長時間労働やハラスメントが原因で、従業員が心身の不調をきたすケースは多く、働く環境の整備が求められています。
労働問題の事例では、電通の安全配慮義務違反が有名です。
この事件では、ハラスメントに加えて勤怠管理や労務管理も問題を発生させた要因とされており、電通のマネジメントや組織体制が疑問視されました。
兵庫県警でも過去に嫌がらせ行為やアルコールハラスメント(アルハラ)が判明するなど、企業のみならず公的機関でも同様の問題が起きています。
労働量の制限や従業員のメンタルヘルス支援、ハラスメント対策の強化などを通じて、社会全体で意識改革を図り、予防や解決に取り組むことが必要です。
不正経理
コンプライアンス違反の事例において、不正経理も対策が求められている問題のひとつです。
不正経理とは、粉飾決算や横領隠蔽、脱税など、意図的に財務諸表を改ざんする行為を指します。
不正経理における最近の事例では、全国旅行支援キャンペーンに関する人件費の架空計上がありました。感染者や給料支払いの有無を伏せて嘘の申請を行い、不正に金銭を取得していた問題です。
不正経理も会社の信用を失うだけでなく、罰金や裁判、関連企業との取引停止など多くのリスクをともないます。内部監査や倫理研修を行い、社会規範を守るための具体的な対策が欠かせません。
情報漏えい
昨今多くの企業において情報漏えいが報告されており、業界・業種を問わず多くの被害をもたらしています。
情報漏えいは人為的なミスだけでなく、システムの脆弱性や内部不正行為によって引き起こされています。
情報漏えいが起きた例として、下記があげられます。
- USBメモリを紛失して顧客のデータや社外秘の情報が流出した
- メールを通じてマルウェア感染した
情報漏えいが起きる背景には、テレワークの普及でデバイスを持ち運ぶ頻度が増加したことも関係しています。
個人情報の漏えいは、取引先や顧客からの信頼も損なう危険があります。従業員へのセキュリティ教育や意識改革に加えて、導入するデバイスやサービスの見極めが重要です。事前の対策や対応方針の策定により、情報漏えいの被害を抑えられます。
【2024年】最新のコンプライアンス違反事例
次に、2024年に発覚した最新の違反事例を4件紹介します。
広告代理店|過少計上の疑い
ある広告代理店で、仕入れ計上に関する書類改ざんなどの不適切会計が判明した事例です。
計上年度のズレ、もしくは未計上により、子会社が累計で約6億6,000万円の過少計上を行った可能性があるとして、外部の専門家を含む特別調査委員会が立ち上がりました。
事実関係の精査や原因の究明を行った結果、リスク管理の甘さやコンプライアンス意識の欠如、内部統制の不備などが指摘されています。
水道局|SNSへの不適切な投稿
水道局の職員が自身のSNSアカウントで不適切な投稿を繰り返していた事例です。
市民からの信頼を著しく損なったとして、1か月の減給(10分の1)の懲戒処分が下っています。
男性職員がSNSで上司や市民を誹謗中傷しているとの情報提供を受け、同局が調査したところ、不適切行為が発覚しました。
投稿内容から所属が特定される可能性もあるため、たとえ匿名でも軽はずみな投稿は避け、立場をわきまえた適切な情報発信が求められます。
自動車メーカー|認証試験の不正
日本の大手自動車メーカー5社で、型式指定の取得に必要な認証試験での不正行為が相次いで発覚しました。
型式指定とは、新車の量産や販売にあたり、衝突時の安全性や排ガスなどの項目で、国が定める基準を満たしているか審査を受ける制度です。
今回、国土交通省の調査により、各社で不適切な試験方法の採用や虚偽データの提出などの不正が見つかりました。
自動車の安全性を揺るがす事案となり、一般ユーザーにも大きな衝撃を与えたことから、各メーカーには厳正な対応と再発防止が強く求められています。
食品メーカー|ボロ家ハラスメント
ある食品メーカーでは、新入社員寮の劣悪な住環境が原因で内定辞退を引き起こす問題が発生しました。
当初、社員が説明で聞いていた住環境とは異なり、建物の傾きや窓の隙間がある社員寮だったことが報道で暴露され、「ボロ家ハラスメント」として企業体質が批判を浴びました。
その後、新入社員に対する環境整備や配慮が不十分だったとして、居住空間の整備が行われています。
企業でコンプライアンス違反が起こる根本的な原因
続いて、こうしたコンプライアンス違反がなぜ起こるのかについて、その根本的な原因を解説します。
従業員の規範意識が低い
行動規範やマニュアルが不明確で、倫理を重んじる組織の風土が醸成されていない場合、従業員の規範意識やモラルが育ちにくい傾向にあります。
その結果、「見つからなければ良いだろう」といった安易な考えから不正が行われ、それが常態化すると、深刻な違反行為や不祥事に発展するリスクが高まります。
従業員の知識不足
法令や社内規則、ハラスメントといったコンプライアンスに関する知識が不足し、認識の甘さから違反行為や不適切な行動に至る従業員もいます。
また、法改正や社会常識の変化など、最新の動向が反映できていない企業環境も、コンプライアンス違反が発生する要因のひとつです。
社内体制が整っていない
不正を防止するための社内体制が整備されていない企業では、コンプライアンス違反が発生しやすくなります。
例えば、本来は部下を育成する立場にある管理職が自ら違反をしていれば、部下のコンプライアンス違反を助長する可能性があります。
また、管理体制が不透明で、現場への監視が行き届かない環境では、従業員のコンプライアンス違反を防止できません。
そのほか、報告や相談しにくい風土も従業員の意識低下につながりやすく、組織全体のコンプライアンスリスクを高める一因となります。
企業におけるコンプライアンス違反の予防策
コンプライアンスを強化するために企業が行うさまざまな取り組みを紹介します。
- 従業員へのヒアリングやアンケート
- 行動規範やマニュアルの整備
- コンプライアンス研修の実施
- 相談窓口の設置
従業員へのヒアリングやアンケート
従業員へのヒアリングやアンケートは、コンプライアンス違反を防止するための有効な取り組みです。
従業員への聞き取りで自社の課題や職場環境の問題点が明確になり、取り組む方向性が定まります。
業界特有のリスクも存在するため、専門家の意見も参考にするのがおすすめです。
行動規範やマニュアルの整備
コンプライアンスの取り組みにおいて、行動規範やマニュアルの整備も欠かせません。行動規範やマニュアルを通して正しい知識を吸収できることから、従業員による違反行為への抑止力につながります。
法令違反に関する取り組みは弁護士に監修してもらい、定期的な見直しも必要です。
作成後は全体に周知し、企業倫理を守ることの重要性を伝えるとともに組織に浸透するよう努めましょう。
コンプライアンス研修の実施
コンプライアンスに対する正しい知識を身につけるためには研修の実施が欠かせません。
法令関係や倫理観、モラルなど、コンプライアンスに関する網羅的な知識を学ぶのが目的です。
経営層や管理者も研修に参加して、コンプライアンスの重要性を従業員に示す必要があります。
なお下記の資料では、eラーニングを活用したコンプライアンス教育の効果的な導入方法を紹介しています。研修設計や従業員育成にお悩みの企業様は、ぜひご覧ください。
相談窓口の設置
相談窓口の設置も、コンプライアンス違反を未然に防ぐ有効な手立てになります。
従業員が安心して活用できるよう、相談内容の秘密保持や不利益を被らないようにする配慮が必要です。
相談窓口は対面や電話、メールなど、複数の方法を用意するのがおすすめです。
コンプライアンス研修の重要性・メリット
企業がコンプライアンス研修を実施する重要性と、具体的なメリットについて解説しましょう。
なお、コンプライアンス研修の重要性や実施方法については、こちらの記事もご覧ください。
コンプライアンス研修が重要な理由とは?実施方法から効果を出すためのコツ、過去の違反事例まで解説
当事者意識が身につく
質の高いコンプライアンス研修は、従業員の法令遵守に対する当事者意識を高めます。
特に従業員が自分事として捉えられる内容を選定することで興味関心が引き出され、自分事として考えられるようになります。
研修では、実際の業務で役立つ身近な事例を取り上げましょう。業務との関連性を理解することで組織の信頼を損なうような違反が予防され、結果として企業の信頼性や透明性の向上につながります。
社会人としてのビジネスマナーが身につく
組織に長く在籍すると、組織独自の常識に染まり一般常識が希薄になったりズレが生じたりすることがあります。そのため、研修を通じて適切なビジネスマナーを学び、社会人としての対応を身につけることが重要です。
これにより、社内外における信頼性や協調性が高まるでしょう。
実践的に正しい行動を学べる
研修を通じて具体的な事例から学ぶことで、法令や倫理規定への理解が深まり、実務でも適切な判断や行動ができる実践的な力が身につきます。
従業員育成を行うことはコンプライアンス違反を防止するとともに、早期に違反を特定する手段にもなります。同時に、企業側が違反行為を見逃さず報告できる環境を整えることも必要です。
企業や組織の価値が高まる
コンプライアンスの強化は、信頼性や信用を築き、企業の評判やブランド価値を向上させる意味でも重要です。
コンプライアンスの徹底によって企業の信頼度は高まり、競争力の強化や持続的な成長と発展にもつながります。
コンプライアンス研修で実施する主な内容
コンプライアンス研修で取り扱う主な内容について詳しく解説します。
情報やセキュリティ
情報漏えいは、会社の信頼を脅かす重大な問題に発展するため、取り返しのつかないことになる前に、研修を実施し従業員が重要性を理解する必要があります。無防備な情報管理は、企業価値を損なう危険性を孕んでいます。企業の生命線ともいえる情報を守る意識が必要です。
パスワード管理やメール誤送信予防、バックアップの実施、ウイルス対策、内部不正による情報漏えいの防止、Wi-Fiや公衆無線LANの利用など、多岐にわたる対策が必要です。
SNSの利用方法
SNSの投稿内容は、企業のイメージを大きく左右します。一度炎上すれば、そのダメージは計り知れません。
従業員の投稿内容には十分注意すること、また従業員自身が「どのような投稿が問題となるのか」を理解することが大切です。
ハラスメントへの対策
パワハラ、セクハラなどのハラスメント防止への対策も重視されます。価値観の違いにより、他人を傷つけたり、迷惑行為になったりすることを防ぎます。
研修では、多様な視点を理解するための手法が提供されます。ハラスメント行為を未然に防ぐ上で、一人ひとりの違いを尊重し、互いへの理解を深めることが求められます。
著作権などの侵害について
著作権侵害の予防にも焦点が当てられます。例えば、他社の写真やデータの無許可使用は、大きな問題を生む可能性がある問題です。
この種の違反は、悪気がなくても発生します。無意識のうちに他人の知的財産を侵害することは、ビジネス上の重大なミスとなるため、十分な注意が必要です。
コンプライアンス違反事例にもとづくケーススタディの設計方法
研修効果を高める方法としては、違反事例を用いたケーススタディが効果的です。
具体的な事例の分析や検討を通じて、従業員がコンプライアンス違反を自分事として捉えられるようになり、実践的な力を育成できます。ケーススタディの設計手順は下記の通りです。
ステップ1|取り上げる事例を決める
自社の状況や課題から研修の目的を定め、その目的や受講者に合った事例を選びましょう。受講者にとって身近な事例を選ぶことで、当事者意識を持ちやすくなります。
例えば、実際に社内で起こった違反事例や同業他社で発生したケース、ニュースやSNSで大きく取り上げられた最新事例などが考えられます。
ステップ2|気づきとなるポイントを決める
選定した事例に対して、「受講者にどのような気づきを得てほしいか」という学習のポイントを設定します。ケーススタディが単なる事例紹介に終わらず、深い学びとなるためには、違反の線引きや発生の原因、対処法などへの気づきが不可欠だからです。
報告義務の重要性、ハラスメントの定義、情報リテラシーといったコンプライアンスに関するテーマを設定し、事例をもとに受講者に伝えたい核となるポイントを整理しましょう。
ステップ3|良いケース・悪いケースの2パターンを作成する
事例をもとに、手本にしたい「良いケース」と、規範に沿わない「悪いケース」を作成します。ステップ2で定めた気づきのポイントが効果的に学べるケースを考えましょう。
特に重要なのは、悪いケースに関する考察です。コンプライアンス違反に該当する理由、問題が発生した背景、取るべきだった適切な対応などについて具体的に整理しておきます。
ステップ4|ケーススタディの進め方を決める
研修の目的やゴール、受講者の属性、時間数などを考慮して、ケーススタディをどのように進めるか決定します。一般的な進め方は下記の3つです。
- ストーリー型
特定のストーリーを通して課題を提示し、受講者に自由に考えさせる形式 - 選択式型
複数の選択肢からもっとも適切だと思う行動を選択させる形式 - シチュエーション型
実際に起こり得る状況を設定し、受講者にどのような考え方や行動を取るか考えさせる形式
ステップ5|回答項目を設定し、最終調整する
ステップ4で決定したケーススタディの進め方に合わせて、具体的な問いかけや選択肢、ロールプレイングの内容などを検討します。
従業員の思考パターンや日頃の行動を反映させた内容にすると、活発な議論や多様な気づきが生まれやすくなり、学びの質を高められます。選択肢を考える際は、特定の回答へ偏りすぎないように表現を工夫しましょう。
コンプライアンス研修の対象者は?
コンプライアンス研修の対象者は従業員だけでなく、経営者や管理者も含まれます。
企業の規定や法的要件を遵守し、適切な行動を取ることが、企業を構成するすべての人々に求められるからです。
経営陣や管理職の参加は、従業員への模範となるだけでなく、企業全体にコンプライアンスを浸透させる上でも重要です。
コンプライアンス研修の実施方法
実際に研修を実施する際には、どのような手段があるのでしょうか。コンプライアンス研修の実施方法について解説します。
講師による社内研修
専門講師を招いた社内研修を行います。経験豊富な専門家による研修では、コンプライアンスに関する知識を効果的に学べます。
専門家にその場で質問できるため、受講者は自身の業務においても具体的に考えを深められます。
公開講座の受講
異業種交流型の公開講座の受講も手段のひとつです。社外の方とともに受講することで、井の中の蛙にならず、広い視野を持つことができます。
自社の常識にとらわれることなく、他社からの意見も柔軟に取り入れることで、より良い職場づくりにもつながるでしょう。
オンラインによる研修
オンラインでの研修であれば、場所を選ばずに受講できます。また、eラーニングによる受講も次の理由からおすすめです。
- いつでも好きなときに受講できるため、会場コストや移動コストを削減できる
- 階層や対象者に合わせたカスタマイズが可能
- 人材育成担当者は、学習の進捗や習熟度を一元管理できる
- 何度でも繰り返し受講できて学習効果を高められる
下記の資料では、最新事例で企業倫理・コンプライアンスを学べるeラーニングライブラリ®のコース概要について紹介しています。気になる方はお問い合わせください。
コンプライアンス研修の流れ
コンプライアンス研修を実施する際に押さえるべき内容、流れを詳しく解説します。
従業員の認識レベルの確認
最初に、従業員のコンプライアンスに対する認識度や理解度を評価した上で、必要な研修項目を決定します。
また、上司のコンプライアンスへの理解も重要です。上司がしっかりとコンプライアンスを把握していることで、従業員への指導やサポートが円滑に行われます。
組織全体でのコンプライアンス意識の向上を図るために、認識レベルのチェックは重要なステップとなります。
研修内容の確認
対象者やコンプライアンスの内容に基づき、適切な研修プログラムを構築します。具体的な法的要件や企業ポリシーに焦点を当てたトレーニングや、ケーススタディの活用など、研修内容を調整します。
研修内容の確認を通じて、従業員が必要な知識やスキルを習得して、コンプライアンスに関する理解を深めることが目的です。
振り返りの調査を実施
研修内容を振り返り、従業員の理解度や習得した成果をチェックします。調査の結果をもとに、研修の効果や課題を把握し、今後の研修計画に反映させましょう。
コンプライアンス研修で結果を出すための4つのコツ
効果的なコンプライアンス研修を実現するための4つのコツを解説します。
実践を交えながら行う
コンプライアンス研修の効果を上げるためには、「実践的な学習」が重要です。まずは、現実のケースを取り入れてみましょう。
理論だけでなく現実の課題感を実感できます。
役職や立場によって目標を設定しておく
コンプライアンス研修を成功させるためには、「役職ごとの目標設定」が大切です。異なる役職、立場では、異なる視点、責任が生まれます。それゆえに、研修はその役職に応じてカスタマイズするべきです。
例えば、上層部は組織の倫理的価値を理解し、リーダーシップを発揮することが重要です。一方、従業員は日常業務のコンプライアンスを理解し、適切に行動することが求められます。これらの違いを理解し、適切な目標を設定することが、効果的な研修を成功させる鍵となります。
定期的に研修を行う
効果的なコンプライアンス研修の秘訣は、「定期的な実施」にあります。単発の研修で一時的な理解は得られるかもしれませんが、継続的な意識の向上へつながる保証はありません。
それに対して、定期的な研修は、法改正や社会の変化への対応を可能にするだけでなく、コンプライアンスの重要性をその都度確認する機会となります。毎月または四半期ごとに継続して研修を実施することで一貫して従業員の高い意識を保ち、コンプライアンスへの理解と実践を組織全体で維持・深化させられます。
良い「タイミング」で研修を行う
コンプライアンス研修に効果をもたらす要素のひとつは「タイミング」です。特に研修の対象となる問題が社内や同業者で起きた場合に重要となります。
例えば、自社でコンプライアンス違反が発生した際に、その原因と解決策を学ぶための研修を行うと、従業員は具体的な事例を通じて理解を深められます。また、同業者で問題が起きた場合も、同様の過ちを犯さないように、その事例から教訓を学ぶことが可能です。
このようなタイミングで研修を行うことで、単なる理論学習以上の効果を期待できます。具体的な事例を通じて学ぶことは、コンプライアンスをより身近なものとし、その重要性を深く認識させます。
よくある質問
コンプライアンス研修に関連する「よくある質問」について解説します。
どんな内容の研修がありますか?
コンプライアンス研修の内容は、一般常識や情報、セキュリティなどが一般的です。
受講者は研修を通じて、コンプライアンスの重要性をはじめ、ビジネス環境における法的要件や倫理的な規範、遵守のための具体的な実践方法などを学びます。
研修を受けてどんな効果が得られますか?
例えば、コンプライアンス違反がもたらす第三者への悪影響を学ぶことで、他者を傷つける行為を防ぎ、倫理的な行動を取る意識が高まります。
そのほかにも、組織内の信頼関係や社会的評価の向上、法的トラブルの回避など、ポジティブな効果が期待できます。
どんなコンプライアンス違反が起こりやすいですか?
発生頻度の高いコンプライアンス違反として、SNSの不適切な利用や労務管理の違反などがあります。
具体的には、SNS上での機密情報の漏えいや社内ルールの無視、労働法や労働条件の違反などが該当します。研修では、事例を通じて違反のリスクや重要性への理解を深め、適切な行動を促すことが必要です。
まとめ
コンプライアンス研修の重要性は否応なく高まっています。規範意識を高め、従業員の倫理的な行動を促したい企業にとって、コンプライアンス研修は有効な手段です。良好なコンプライアンス文化は、ビジネスの長期的成功に寄与し、企業の良い評判にもつながります。
JMAM(株式会社日本能率協会マネジメントセンター)は、1979年から研修を実施しており、人事・人材育成に関する多彩なプログラムを提供しています。特に、個々人の行動をコンプライアンスの視点で振り返り、互いに成長を促す職場づくりを目指す育成プログラムは、企業のコンプライアンス向上に効果的です。
これらはeラーニングで提供されており、時間や場所を選ばず学習できるのが魅力です。新たなコンプライアンス研修の導入を検討中の企業様は、ぜひ一度、このサービスの詳細をご覧ください。
解説資料|コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と従来の課題解決に向けたポイントを紹介
本資料ではeラーニングを活用したコンプライアンス教育の効果的な導入方法と、課題解決に向けたポイントをご紹介します。
- 企業に求められるコンプライアンス強化の背景
- 一般的なコンプライアンス研修の内容と課題
- eラーニングによる課題解決と期待される効果
- eラーニングと集合研修の違いと特徴
- サービス選定時の重要ポイント
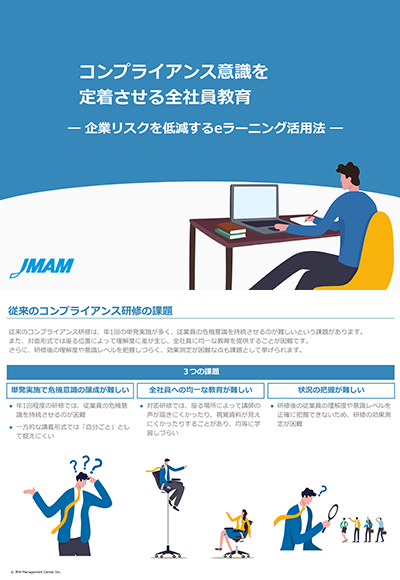
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















