
企業のコンプライアンス違反は、経営に深刻な影響を与えます。
昨今、これを目の当たりにする機会が増えておりコンプライアンス対策の重要性が増しています。
具体的な対策としては、外部講師の招へいや、外部の専門サービス等を利用した研修の実施が考えられます。
自社のビジネス環境に囚われず、包括的な視点でコンプライアンスの全体像を理解するための研修を経営幹部からマネジメント、新入社員まで、すべての社員に定期的に実施することが重要です。
今回は、なぜコンプライアンス研修が重要であるのか、そしてどのようにして実施するべきなのかについて詳しく解説します。
関連資料
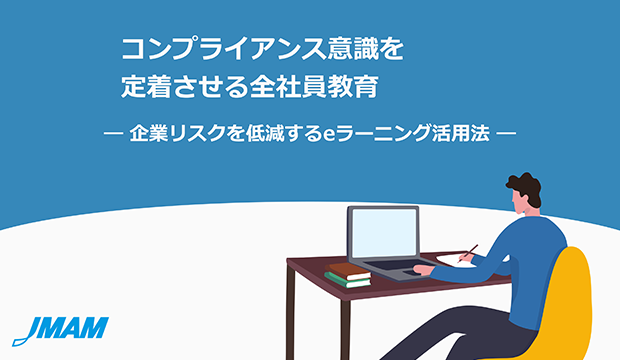
関連資料
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と課題解決に向けたポイントを紹介
コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
コンプライアンス研修とは?
はじめに、コンプライアンス研修の基礎知識について分かりやすく解説します。
コンプライアンスの意味
コンプライアンスは、公正や倫理を守るための取り組みで、「法令遵守」の訳語です。
さらに、企業コンプライアンスの場合には、法令だけでなく社会的規範や倫理も含めて守ることを指します。
コンプライアンス研修は、その重要性、違反のリスク、遵守すべき法令の理解が目的となります。
コンプライアンス研修の対象者とは?
コンプライアンス研修の対象者は一般社員だけでなく、経営者や管理者も含まれます。
すべての社員が企業の規定や法的要件を遵守し、適切な行動を取ることが求められます。
研修は役職や階層に関係なく、組織全体のコンプライアンス文化を確立するために必要です。
経営陣や管理職の参加は、全社員に対する模範となり、コンプライアンスの重要性を示す一環です。
コンプライアンス研修が重要な理由とは?
コンプライアンス研修の重要性はいくつかの理由によります。
まず、風通しの良い職場環境を作り上げるために必要です。研修を通じて、社員が法的要件や企業の倫理規定を理解し、適切な行動を取ることができます。さらに、研修は不祥事を未然に防ぐためにも重要です。
コンプライアンスについての知識がないままでは、違反のリスクが高まります。研修を通じて社員教育を行い、コンプライアンス違反を防止します。
また、研修は早期にコンプライアンス違反を特定する手段にもなります。社員が適切な知識を持ち、違反行為を見逃さず報告できる環境を整えることが重要です。
コンプライアンス研修は組織の信頼性向上やリスク軽減のために欠かせない要素といえます。
コンプライアンス研修の流れ
コンプライアンス研修を実施する際に抑えるべき内容、流れを詳しく解説します。
社員の認識レベルの確認
最初に、社員の認識レベルを確認します。コンプライアンスに対する認識度や理解度を評価した上で、必要な研修内容を決定します。
また、上司のコンプライアンスへの理解も重要です。上司がしっかりとコンプライアンスを把握していることで、メンバーへの指導やサポートが円滑に行われます。
組織全体でのコンプライアンス意識の向上を図るために、認識レベルの確認は重要なステップとなります。
研修内容の確認
次に、研修内容の確認を行います。対象者やコンプライアンスの内容に基づき、適切な研修プログラムを構築します。
具体的な法的要件や企業ポリシーに焦点を当てたトレーニングや、ケーススタディの活用など、研修内容を調整します。
研修内容の確認を通じて必要な知識やスキルを習得し、コンプライアンスに関する理解を深めることが目的です。
振り返りの調査を実施
研修終了後には、振り返りの調査を行うことも重要です。研修内容を振り返り、社員の理解度や習得した成果を確認します。
調査の結果をもとに、研修の効果や改善点を把握し、今後の研修計画に反映させましょう。振り返りの調査は、研修の質の向上や社員の能力向上を促進し、組織全体のコンプライアンス文化を強化するための貴重な手段です。
コンプライアンス研修の実施方法
実際に研修を実施する際には、どのような手段があるのでしょうか。コンプライアンス研修の実施方法について解説します。
講師による社内研修
専門講師を招いた社内研修を行います。経験豊富な専門家による研修では、具体的な知識を効果的に学ぶことができます。質問などもしやすく、参加者の理解を深めることができます。
公開講座の受講
異業種交流型の公開講座の受講も手段のひとつです。社外の人とともに受講することで、井の中の蛙にならず、広い視野を持つことができます。常識を覆される経験によって、職場環境の改善につながるでしょう。
オンラインによる研修
オンラインでの研修であれば、時間や場所を選ばずに受講できます。また、eラーニングによる受講も次の理由でオススメです。
まず、全社員を対象にできるため、場所や時間の調整やコスト削減が可能です。また、階層や対象者に合わせたカスタマイズが可能で、学習の進捗や習熟度を確認できます。さらに、何度でも受講することができます。
コンプライアンス研修の4つの目的とは?
コンプライアンス研修を行うべき、4つの目的について詳しく解説します。
- 1.企業や組織のルールを知るため
1つめは、企業や組織のルールを知ることです。社会人としての常識を持ち、組織人としての意識を持つことが重要です。これにより、企業や組織のイメージに関わる問題を予防し、信頼性や透明性を高めることができます。 - 2.社会人としてのビジネスマナーをつけるため
2つめは、社会人としてのビジネスマナーを身につけることです。組織に長く在籍すると、組織独自の常識に染まり一般常識が希薄になったりズレが生じたりすることがあります。研修を通じて適切なビジネスマナーを学び、社会人としての対応を身につけることが重要です。これにより、社内外における信頼性や協調性が高まるでしょう。 - 3.コンプライアンス違反によるリスクを抑えるため
3つめは、コンプライアンス違反によるリスクを抑えることです。コンプライアンス違反は個人の責任だけでなく、会社や組織の責任も重大になります。研修を通じてリスクの重大さを認識し、正しい行動を身につけることが重要です。これにより、コンプライアンス違反による法的、経済的なトラブルを回避し、企業・組織の信頼性を高めることが可能になります。 - 4.企業や組織の価値を高めるため
4つめは、企業や組織の価値を高めることです。コンプライアンスの遵守は信頼性や信用を築き、企業の評判やブランド価値を向上させます。また、コンプライアンスによる適切な行動は社会的貢献にもつながります。社会の期待に応え、法令や倫理を守ることで、企業や組織の信頼度が高まります。これによって競争力を強化し、持続的な成長と発展を達成することができます。
コンプライアンス研修で実施される主な内容
コンプライアンス研修で実施される主な内容について詳しく解説します。
情報やセキュリティ
情報漏えいは、会社の信頼を脅かします。
無防備な情報管理は、企業価値を損なう危険性を孕んでいます。企業の生命線とも言える情報を守る意識が必要です。
多くの人が想像以上に情報やセキュリティに対する関心が低い場合があるため、研修によってこの認識を深めることは重要です。
SNSの利用方法
SNS投稿は、企業のイメージを大きく左右します。一度炎上すれば、そのダメージは計り知れません。
「どのような投稿が問題となるのか」を理解することは大切です。コンプライアンス違反の投稿は企業に損害を与え、信頼を失います。社員の投稿内容には十分注意が必要です。
ハラスメントへの対策
ハラスメント防止への対策も重視されます。価値観の違いにより、他人を傷つけたり、迷惑行為になることを防ぎます。
研修では、多様な視点を理解するための手法が提供されます。ハラスメント行為を未然に防ぐため、お互いの違いを尊重し、互いに理解することが求められます。
著作権などの侵害について
著作権侵害の予防にも焦点が当てられます。他社の写真やデータの無許可使用は、大きな問題を生む可能性があります。
この種の違反は、悪気がなくても発生します。無意識のうちに他人の知的財産を侵害することは、ビジネス上の重大なミスです。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)について
下請法は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律です。元請事業者と下請事業者の間の取引において、優越的地位の濫用を防止し、公正な取引環境を確保するために制定されています。
下請法の遵守は、元請・下請双方の責任です。元請企業は法的義務を確実に履行し、下請企業は自社の権利を理解して適切に行使することで、健全な下請取引関係を構築することができます。
定期的な社内研修やコンプライアンス体制の整備を通じて、下請法の理解を深め、違反リスクを最小化することが重要です。
コンプライアンス研修で起こりがちな課題
コンプライアンス研修の実施においては、次のような課題が起こりがちです。研修を実施する際の参考にしてください。
内容がつまらなく感じられる
研修の中身が受講者にとって「知っていることばかり」と感じられると、興味を失いやすくなります。
定義の解説や法律の紹介など、形式的な内容に終始すると、自分事として捉えにくく、学習意欲の低下につながります。
特に、受講者の業務内容や知識レベルに合っていない場合、理解も定着もしづらくなります。
実践につながらない
知識偏重の研修では、受講者が実際の業務場面で適切に判断・行動できないことが多くなります。
特に「実施すること」自体が目的化した研修では、実践を促す仕組みが不十分になりがちで、本来達成すべき行動変容や人材育成などの目標が見失われてしまいます。
研修を受けた直後は理解していても、現場の慣習や雰囲気に流されて、行動に反映されないケースは少なくありません。
コストとのバランスが取りにくい
全社員、特にパートやアルバイトも対象とした研修は、費用面での負担が懸念されます。
一部の社員に限定して実施すると、非受講者の行動がリスク要因となり、組織全体への影響も否定できません。
コンプライアンス研修を「自分ごと化」させる5つのコツ
コンプライアンス研修の効果を高めるには、受講者の当事者意識がポイントです。そのための5つのコツを解説します。
- 1.実践を交えながら行う
コンプライアンス研修の効果を上げるためには、「実践的な学習」が重要です。まずは、現実のケースを取り入れてみましょう。これにより、理論だけでなく現実の課題感を実感できます。 - 2.役職や立場によって目標を設定しておく
コンプライアンス研修を成功させるためには、「役職ごとの目標設定」が大切です。異なる役職、立場では、異なる視点、責任が生まれます。よって、研修はその役職に応じてカスタマイズするべきです。
例えば、上層部は組織の倫理的価値を理解し、リーダーシップを発揮すべきです。一方、社員は日常業務のコンプライアンスを理解し、適切に行動する必要があります。これらの違いを理解し、適切な目標を設定することが、効果的な研修を成功させる鍵となります。 - 3.定期的に研修を行う
効果的なコンプライアンス研修を行う秘訣は、「定期性」です。単発の研修では、一時的な理解は得られるかもしれませんが、継続的な意識へとつながる保証はありません。
それに対して、毎月、または四半期ごとの定期的な研修はコンプライアンスの重要性を常に思い出させます。
また、時代の変化にあわせて研修内容を定期的に見直すことも大切です。「なぜ今このテーマが重要なのか」という背景や社会的な意義も伝えましょう。 - 4.良い「タイミング」で研修を行う
コンプライアンス研修に効果をもたらす要素のひとつは「タイミング」です。これは特に研修の対象となる問題が社内や同業者で起きた場合に重要です。
例えば、自社でコンプライアンス違反が発生した際、その問題の根源と解決策を学ぶための研修を行うと、社員は具体的な事例を通じて理解を深めます。また、同業者で問題が起きた場合も、それを教訓に研修を実施することで、同様の過ちを犯さないようにすることが可能です。
このようなタイミングで研修を行うことで、単なる理論学習以上の効果を期待することができます。具体的な事例を通じて学ぶことは、コンプライアンスをより身近なものとし、その重要性を深く認識させます。 - 5.管理職の主体的な姿勢をみせる
研修の場で管理職がどのように振る舞うかは、部下の意識や行動に大きな影響を与えます。管理職が受け身でいたり、形式的な参加にとどまっていたりすると、「これは本気でやらなくても良い」と受け取られがちです。
管理職自身が積極的に発言したり、自らの失敗談を共有したりするなど、主体的に研修に関わりましょう。
コンプライアンス研修の質を高める効果測定の方法
コンプライアンス研修の質を高めるためには、受講者の反応や理解度、行動変容、さらには投資対効果まで、多角的に研修効果を測定することが重要です。
ここでは、効果測定の主要な4つの方法を紹介します。
研修の効果測定の方法|測定結果を育成プログラムの改善につなげるには
満足度を測る場合|研修後アンケート
満足度の把握は、受講者の率直な感想を収集する上で有効です。研修直後に実施するアンケートには、テーマの選定、講義の分かりやすさ、講師の教え方、時間配分などの項目を含めましょう。
選択式の設問は結果を数値で分析しやすく、回答率の向上にもつながります。一方で、記述式の設問も設けておくことで、表面的な評価だけでなく受講者の本音を引き出すことができます。
また、ポジティブな意見を誘導しないように、設問の構成にも工夫が必要です。
理解度を測る場合|理解度テスト
理解度を把握するには、筆記試験やeラーニングでのテストが効果的です。研修のテーマや目的によっては、レポート提出による測定も検討できます。
テストの事前告知や、結果を可視化することで受講者の意識が高まり、学習定着率の向上も期待できます。重要なのは、内容をしっかり理解していなければ解けないような設問を設定することです。
研修後の行動量を測る場合|活用度テスト
実際に業務での行動変化が見られたかを確認するためには、アンケートだけでなく、上司・同僚・部下へのヒアリングも有効です。受講前後の行動の変化を、主観と客観の両面から比較・評価しましょう。
また、非受講者との比較も取り入れることで、研修による影響をより明確に分析できます。ただし、行動変化が一時的なもので終わる可能性もあるため、一定期間後に再度確認することで習慣化や定着の度合いも把握できます。
単に行動量を測るだけでなく、なぜ変化したのか、あるいは変化が見られなかった理由についても掘り下げることが、次の研修改善に直結します。
研修コストに対する効果を測る場合|ROI分析
ROI分析は、「数値化できる利益」に関する費用対効果を明らかにする手法です。
研修効果を測る場合は、研修によって得られた成果(売上向上、収益増、コスト削減など)と、そのためにかかったコストを比較し、費用対効果を算出します。下記の式で求められます。
ROI(%)=(研修による利益-研修コスト)÷研修コスト×100
人件費や資料代、運営コストなどを含めた上で分析を行うことで、経営層に対しても研修の価値を具体的に示すことが可能になります。
ただし、どこまでを研修コストとして算出するか、また成果が研修以外の要因による影響を受けていないかといった点には注意が必要です。6か月~1年程度の期間をかけて定期的に効果を測ることが望ましいでしょう。
コンプライアンス研修の効果が出ないときのチェックポイント
コンプライアンス研修で成果が得られない場合、いくつかの共通する原因が考えられます。以下のポイントを確認することで、改善につなげる手がかりを得られるはずです。
研修の目的(ゴール)を正しく伝えられているか
コンプライアンス研修は「リスク感度を高める」「未然に問題を防ぐ」ための手段であり、企業の信頼を守る土台です。
しかし、研修を実施すること自体が目的化してしまうと、本来の意義が薄れてしまいます。また、研修の目的(ゴール)が不明確であることも効果が出ない一因です。
研修担当者は、この目的を明確に理解した上で社員にも正しく共有することが不可欠です。
実施方法・研修内容と対象者がマッチしているか
実施方法や研修内容が対象者に合っていないと、対象者のレベル感に合わず、当事者意識が薄れやすくなります。その結果、研修内容の定着率が悪くなってしまうことがあります。
効果的な研修を実現するためには、まず受講者の理解度を測定することが重要です。
対象者の職位、経験年数、担当業務を踏まえて、必要な内容を適切な方法で伝えていく必要があります。一律の研修ではなく、階層別や部門別にカスタマイズした内容を検討しましょう。
好ましくない企業文化が根付いていないか
研修だけでは社員の行動が変わらない場合、企業文化そのものに課題がある可能性があります。「上司がやっているから問題ない」「指摘しづらい雰囲気がある」などの状態では、研修で得た知識が実践に活かされません。
こうした会社組織の根本に原因がありそうな場合は、企業文化そのものの見直しが必要になることもあります。研修の効果を高めるためには、経営陣のコミットメントと組織風土の改善が不可欠です。
人事担当者は研修実施前に、現場の声を聞き取り、組織内にコンプライアンス違反を助長するような文化がないかを調査することが重要です。
興味をもたせる工夫を取り入れているか
社員が知りたいのは法令の条文ではなく、「業務を行う上で何がどこまで許されて、何が問題となる可能性があるのか」ということです。
ケーススタディやロールプレイング、グループディスカッションなど、参加型の研修手法を取り入れることで、社員の関心を引き、実践的な学びを提供できます。
よくある質問
コンプライアンス研修に関連する「よくある質問」について解説します。
どんな内容の研修がありますか?
コンプライアンス研修では、一般常識や情報、セキュリティなどの内容があります。
参加者はこれらの研修を通じて、コンプライアンスの重要性や具体的な実践方法を学びます。
研修はビジネス環境における法的要件や倫理的な規範を理解し、遵守するための基礎を提供します。
研修を受けてどんな効果が得られますか?
例えば、コンプライアンス違反による影響や第三者への悪影響を学ぶことで、他者を傷つける行為を防ぎ、倫理的な行動を取る意識が高まります。
そのほかにも、組織内の信頼関係や社会的評価の向上、法的トラブルの回避など、ポジティブな効果が期待できます。
どんなコンプライアンス違反が起こりやすいですか?
SNSの不適切な利用や労務管理の違反などのコンプライアンス違反が起こりやすいです。
SNS上での機密情報の漏えいや社内ルールの無視、労働法や労働条件の違反などが該当します。
これらの事例を通じて、違反のリスクや重要性を理解し、適切な行動を促す研修が行われます。
まとめ
コンプライアンス研修の重要性は否応なく高まっています。企業は規範意識を高め、倫理的な行動を促すために、コンプライアンス研修導入が必要です。良好なコンプライアンス文化は、ビジネスの長期的成功に寄与し、企業の良い評判につながるでしょう。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)は、1979年から企業研修を実施しており、人材育成に関する多彩なプログラムを提供しています。特に、個々人の行動をコンプライアンスの視点で振り返り、互いに成長を促す組織づくりを目指す育成プログラムは、企業のコンプライアンス向上に効果的です。
これらはeラーニングで提供されており、時間や場所を選ばず学習できるのが魅力です。
新たなコンプライアンス研修の導入を検討中の企業様は、ぜひ一度、このサービスの詳細をご覧ください。
解説資料|コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と従来の課題解決に向けたポイントを紹介
本資料ではeラーニングを活用したコンプライアンス教育の効果的な導入方法と、課題解決に向けたポイントをご紹介します。
- 企業に求められるコンプライアンス強化の背景
- 一般的なコンプライアンス研修の内容と課題
- eラーニングによる課題解決と期待される効果
- eラーニングと集合研修の違いと特徴
- サービス選定時の重要ポイント
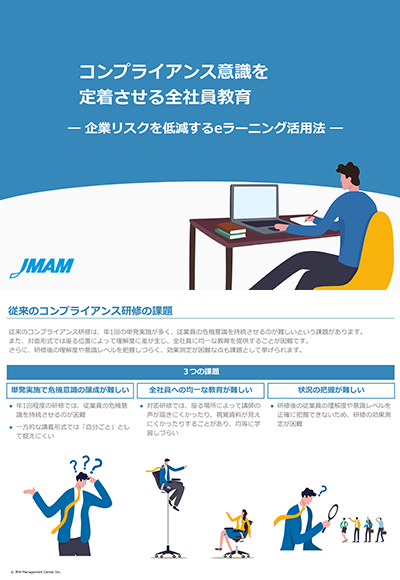
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















