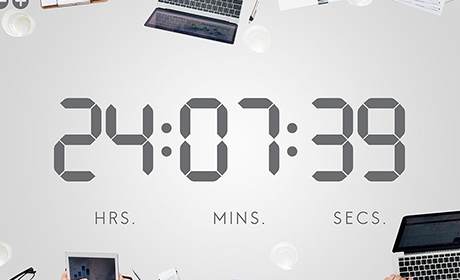- 対象: 管理職
- テーマ: 働き方
- 更新日:
管理職の残業が減らない理由は?残業削減に効果的な対策を紹介
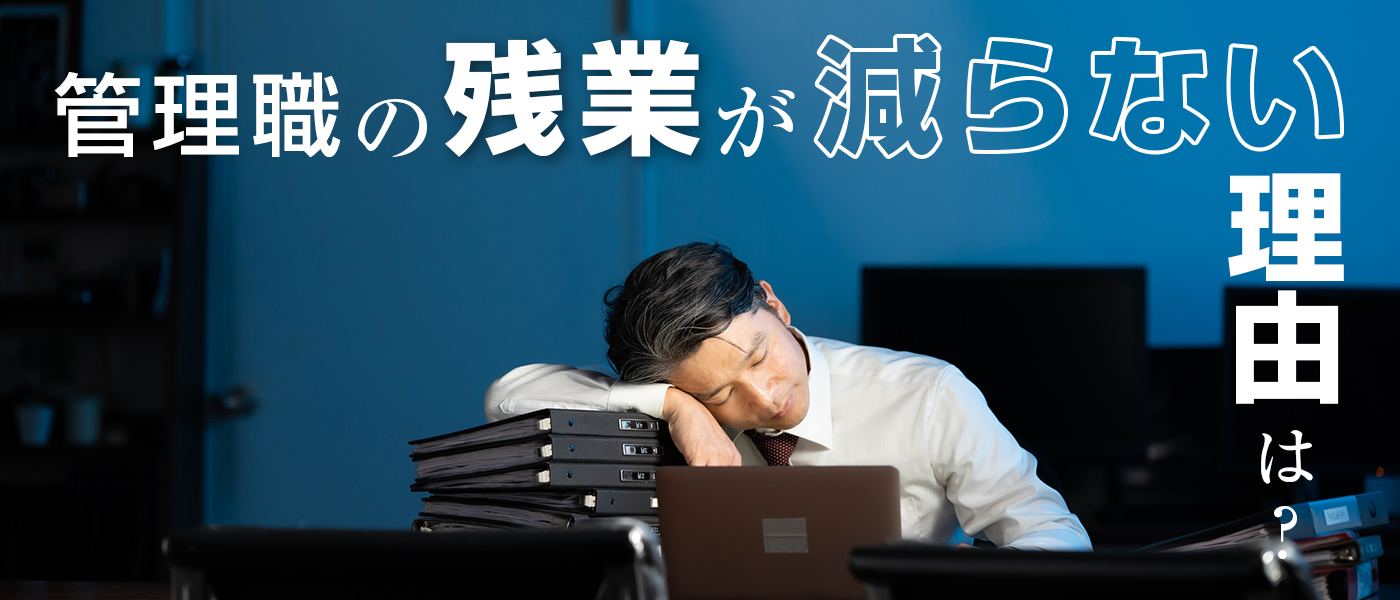
昨今、多くの企業で働き方改革が推進されていますが、残業で消耗する管理職は増加傾向にあります。理職の慢性的な残業を減らすには、具体的にどのような施策を行えば良いのでしょうか。
今回は、管理職の残業の現状を踏まえて、残業が減らない理由や残業時間を減らす対策と注意点・ポイントについて解説します。
関連サービス

関連サービス
管理職の学びに特化したeラーニング
マネジメント・ビュッフェ
管理職の残業の現状
総務省が2024年5月分に実施した調査を分析すると、全産業における管理職全体の1日当たりの就業時間は平均で8.5時間でした。(フルタイム以外を除く)そのうち、情報通信機械器具製造業、金融業、保険業、宿泊業に従事する管理職は1日当たりの就業時間が平均10時間以上となっています。
労働基準法における残業とは、労働基準法で定められた「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を上回る時間外労働を指します。労働基準法に照らし合わせると、管理職は毎日30分~2時間ほどの残業をしていることがわかりました。
ただし、原則として法定上で管理職と認められる管理監督者には労働時間の上限がなく、これは時間外労働も同様です。なお、深夜労働については管理監督者も規制の対象です。
管理的職業従事者がいる業界の中で最も長い時間働いているのは、電話機、交換装置、ファクシミリなどを製造する情報通信機械器具製造業で、週間就業時間は平均60時間との結果が出ています。そのほか、週平均で46時間以上働いている業種は下記の通りです。
- 飲食料品、食料品などの製造業
- 小売業
- 金融業・保険業
- 映像・音声・文字情報制作業(テレビ番組制作会社、出版社など)
- 通信業
出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)5月分結果」
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/
管理職の残業が減らない理由
管理職は業務量が多く、責任も大きいため、長時間労働のリスクが高くなります。そのほか、管理職の残業が減らない理由としては下記の点も指摘されています。
働き方改革によるしわ寄せ
残業規制や有給取得を柱とした「働き方改革関連法」が2019年に施行されたことを機に、労働時間を削減する動きは進んでいます。しかし、部下の労働時間が減ったしわ寄せで、中間管理職の負担は増加傾向にあるのが実情です。
パーソル総合研究所の調査によると、働き方改革が進んでいる企業では、62.1%の中間管理職が「管理職の業務量が増加した」と回答しました。進んでいない企業では48.2%、全企業の平均は52.5%であり、働き方改革が進んでいる企業のほうが業務量の増加を感じる中間管理職が多い傾向にあります。
管理職の負担が増加している主な理由として、業務量や仕事の仕方は従来のまま、働き方改革の推進により労働時間の削減のみ進んでいる点があげられます。勤務時間内に終わらなかった部下の仕事を引き継ぐ形で、中間管理職の業務量が増えてしまう構図です。
そのほか「名ばかり管理職」として不当に時間外労働を強いられている可能性も否めません。名ばかり管理職とは、権限のない名目上の管理職にもかかわらず、労働時間の規制の対象外である管理監督者と扱われることで、残業代が支払われない社員を指します。
名ばかり管理職は違法性が認められる場合もあり、コンプライアンスの観点からも是正されるべき課題です。
出典:パーソル総合研究所「パーソル総合研究所、中間管理職の負担の実態を調査で明らかに 働き方改革進む企業で負担増す中間管理職。62.1%が自らの業務量増加と回答」
https://rc.persol-group.co.jp/news/201910030001.html
残業削減に対する意識の低さ
経営層や上位の管理職そして管理職が、残業を前提とした働き方を是正しようとする意識が低いことも、残業が減らない原因のひとつです。主な理由としては、長時間労働の常態化で発生するリスクを理解していない点があげられます。
管理職に仕事が集中し、長時間労働や深夜残業が増えれば、否応なしに疲労やストレスが蓄積されていきます。その結果、集中力や判断力の低下を招いてミスやトラブルを誘発するほか、生産性の低下も起こりかねません。メンタル不調や過労死のリスクも高まります。
このような状況は、管理職のモチベーション低下の原因となり、離職リスクを高めるほか、管理職になりたがらない若手社員を生む弊害にもつながります。
残業が評価される社内風土
日本の企業では、勤勉さの表れとして長時間労働を美徳とする文化が続いてきました。業務効率化や生産性向上の必要性が叫ばれるようになった現在も、企業によっては長時間労働を良しとする風潮が残っているようです。
残業といっても、理由はさまざまです。例えば、季節的な業務量の増加が原因の残業もあれば、作業密度の低いだらだら残業、上位の管理職や部下が残業しているために帰りづらくなる付き合い残業などもあります。
必要性や理由が問われることなく、残業の多さを評価する環境では、管理職の残業を減らすことは難しいでしょう。
非効率な業務の多さ
計画的な業務進行や仕事の効率を重視しない企業では、無駄な業務が多くなり、結果として残業で帳尻合わせをする可能性が高くなります。
業務効率を下げる要因としては、下記が考えられます。
- 長時間もしくは回数の多い会議
- 目的や納期など、ゴールが曖昧な指示出し
- 承認プロセスが複雑な決裁
管理職の場合、経営層と関わる機会が多い分、調整の手間や待ち時間は長くなる傾向にあります。そのほか、属人化された業務や、導入したITツールが有効活用されていない状況も残業を増加させる要因です。
管理職の残業削減におけるポイント・注意点
次に、管理職の残業削減を考える上で押さえておきたいポイントと注意点を解説します。
個人の努力だけでは残業削減は実現しない
残業を前提としない働き方を実現するには、組織全体で取り組む必要があります。残業を生む組織の仕組みや風土は、個人の努力だけでは変えられません。
また、うわべだけの取り組みでは定着しないため、継続して実行できるための工夫も重要です。全社的な施策を立案する際は、下記のポイントを押さえておきましょう。
①制度・ルールの設計
ヒアリングで管理職や従業員の意見を取り入れながら、現場の状況に即した実効性のある制度・ルールを構築しましょう。ただし、制度・ルールは徹底させるほど、従業員に心理的な負担を与えかねません。実施後は効果測定を行い、必要があれば改善や変更をすることも大切です。
②生産性を高めるマネジメントの遂行
経営層や上位の管理職が、率先して残業削減の意識醸成や労働時間のマネジメントに努めることも重要です。
③システムの活用
残業を生む過重な業務負担の軽減を目的に、業務効率化を促進するITツールを有効活用する方法も効果的です。また、勤務状況を正確に把握する上で、労働時間を可視化できる勤怠管理システムやPCログの活用も役立ちます。
時短ハラスメント(ジタハラ)はNG
残業にまつわるハラスメントに「時短ハラスメント(ジタハラ)」があります。ジタハラとは、業務量が変わらず、具体的な方法も提示しないまま、残業削減や定時退社を強要することです。
ジタハラは、サービス残業や持ち帰り残業の増加を招く可能性があります。見かけ上の勤務時間を削減することで、こなせなくなった業務を終わらせようと、勤務記録に残らないサービス残業や持ち帰り残業をするようになるからです。
その結果、生じるデメリットとして、労働実態に合った適正な賃金が支払われないことに起因するモチベーションの低下や離職率の悪化などがあります。また、必要な時間を確保できないことから、業務の遅延や品質の低下を招くおそれもあります。
管理職の残業を減らす有効な対策3選
残業削減の取り組みは、管理職のモチベーション維持や離職率低下などに良い影響を及ぼすほか、会社全体の業務効率を見直す契機にもなります。
また、長時間労働の対策を講じている企業は、女性管理職比率が高いというデータもあります。残業削減は、女性活躍やダイバーシティ推進にもつながる施策といえるでしょう。
最後に、管理職の残業削減を促す具体的な施策を3つ紹介します。
勤務時間や業務状況の見える化
残業削減の施策として、管理職の労働時間を可視化してモニタリングや分析を行うことが効果的です。分析結果に応じて業務の優先順位の明確化やタイムマネジメントを実施しましょう。
タイムマネジメントとは、勤務時間内で効率的に業務を進めることにより、生産性の向上を目指す管理の手法です。その前提として業務を洗い出した上で工数を把握し、重要度を見極めて優先順位をつける作業が必要となります。
日次や月次などで計画を立て、実行後は作業効率や成果などを振り返り、必要に応じて改善します。業務を見える化する過程で、次のような工夫をすることも管理職の残業削減に有効です。
- 今までの労働時間を整理する
- 会社全体における労働時間の目標を設定する
- 各部署における労働時間の目標を設定する
システムによる業務の効率化
働き方改革のしわ寄せを受ける管理職の残業を減らすには、社内全体で業務量を減らす必要があります。その際に役立つのが、業務効率化を促すシステムやツールです。
例えば、チャットツールやWeb会議システムを活用すれば、打ち合わせや会議の効率化のほか、コミュニケーションの不足も補えるので、部下の業務状況を把握しやすくなります。下記も業務効率化に役立つツールです。
- 社内ポータルサイト
- タスク管理アプリ
- 業務を自動化できるRPAツール
- 申請・承認のワークフローシステム
残業に対する意識改革
長時間労働が当たり前の方も多い管理職世代の意識を変えるには、残業を前提とする働き方や、長時間労働が評価される組織風土を社内全体で変革していかなければなりません。
まずは、次のような説明を全社的に周知することで、残業削減に向けた取り組みへの理解を得ることから始めると良いでしょう。
- なぜ残業削減が必要なのか
- 残業削減のメリットは何か
そのほか、経営層による働き方改革に関するメッセージの発信、労働時間の現状や取り組み状況の全社的な共有も有効な施策です。
管理職の意識改革には、管理職研修も効果的です。JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、「リーダーシップ開発論」を基に、管理者の役割や取り組むべき課題について学ぶシミュレーション研修を提供しています。
実践演習やフィードバックを通して自分自身の強みや行動のくせなどを振り返ることにより、管理者として一段上を目指すための行動変容を促します。詳しくは、研修「気づいて成長する管理者コース」をご覧ください。
まとめ
働き方改革の影響で従業員の業務時間は抑えられている一方、責任のある管理職が業務を引き受ける形で、残業時間が増加傾向にあります。管理職の残業時間を減らすには、企業全体で残業を良しとする企業風土の変革や、残業を前提にしない働き方に取り組む必要があるでしょう。
今回紹介した中でも、特に重要な対策は「勤務時間や業務状況の見える化」と「残業に対する意識改革」です。人事部門が現場の状況を正しく理解し、管理職をサポートしながら業務を変えていく視点を持つことが大切です。「改善するのは現場」という、ある意味丸投げにする対応では現実的な改善にはなりません。本当に管理職の残業を減らすことを目指すならば、人事部がしっかりと現場を理解し、導くことが重要です。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、「ノー残業マネジメント術」など、管理職に必要な学びに特化したeラーニングを提供しています。マネジャーが悩む「働き方改革」の進め方のコツを実践的に習得するなど、御社でのマネジメント育成にぜひお役立てください。
マネジメント・ビュッフェで学べる「ノー残業マネジメント術」
マネジメント・ビュッフェは、管理職の継続的な学びを実現するために生まれたJMAM独自のeラーニングです。診断機能があり、管理職層の教育に特化した175のテーマから、それぞれのニーズに合わせて効率的に学習できます。
そのなかでも「ノー残業マネジメント術」は、チームでの生産性向上のコツや、時短ハラスメントをしないための労務知識のポイントを学習し、Q&A形式の実践的なテキストで、マネジャーが悩む「働き方改革」の進め方のコツを習得できます。コース受講後には、自身の課題に落とし込むレポート作成、また講師からの添削もついており、管理職に気づきを与える実践的な学習となっています。職場の生産性向上や働き方改革推進に課題を抱える管理職向けの研修を検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。
マネジメント・ビュッフェ
管理職の学びに特化したeラーニング
業務スキルとマネジメントスキルは別物。管理職に必要とされるブレないリーダーシップ、部下の育成など、様々なマネジメントスキルを体系的に習得できます。
- 管理職の学びに特化した充実の175テーマ
- 自律した学びが育つ、学習習慣をつける
- デジタルを活用し効率的に学習が進む

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます