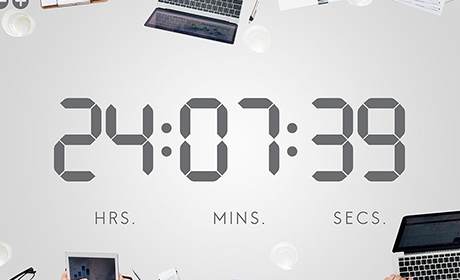- 対象: 全社向け
- テーマ: 働き方
- 更新日:
裁量労働制とは?メリット・デメリットや適切な運用のポイントを解説
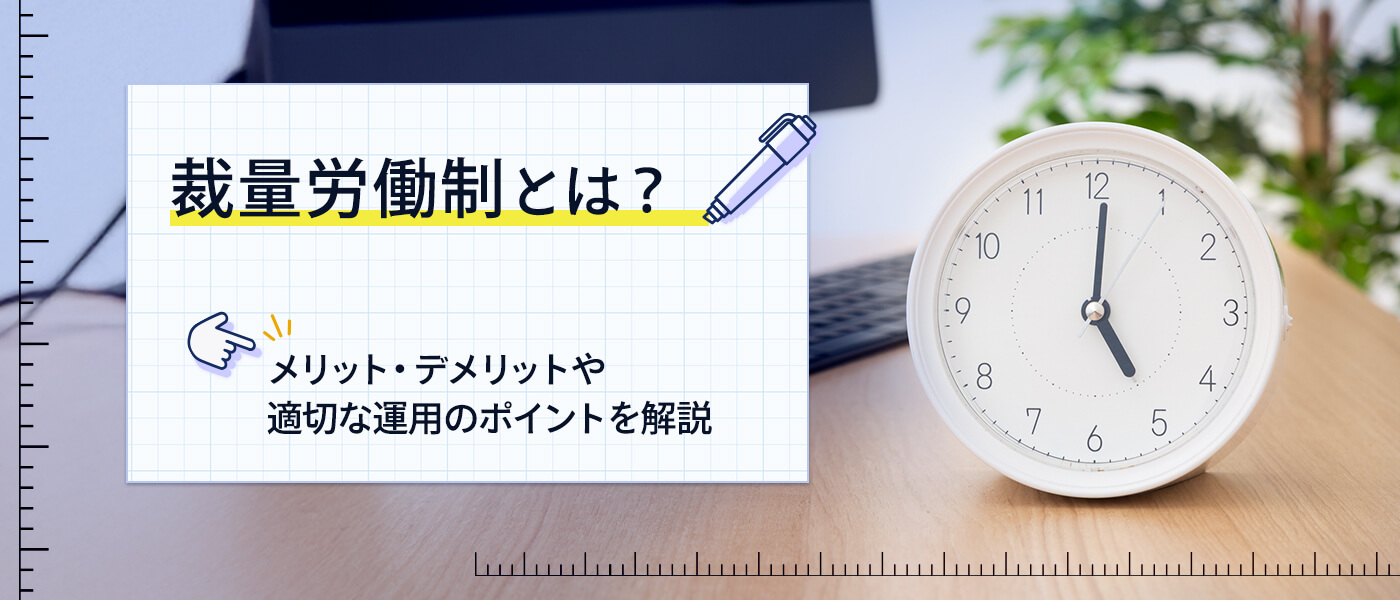
多様な働き方の推進や生産性向上を求められる企業にとって、裁量労働制は有効な選択肢のひとつです。
2024年には法改正により新たな要件が追加され、適用業務の拡大や健康・福祉確保措置の強化など、人事担当者が把握すべき内容が大幅に変わりました。
適切な導入と運用を行うためには、制度の基本的な仕組みから法的要件、メリット・デメリット、そして成功のポイントまで正確に理解することが不可欠です。
今回は、裁量労働制とは何かから最新の法改正内容まで、人事担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。
関連サービス

関連サービス
管理職の学びに特化したeラーニング
マネジメント・ビュッフェ
裁量労働制とは?
裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ企業と労働者で取り決めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金を支払う制度です。
例えば、みなし労働時間を8時間と定めた場合、実際の労働時間が6時間であっても10時間であっても、同じ8時間分の賃金が支払われます。
ただし、すべての業務に適用できるわけではなく、厚生労働省が定める特定の業務のみが対象となります。導入を検討する際は、適用要件や運用ルールを正確に理解することが重要です。
裁量労働制の基本ルール
裁量労働制は「業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」にのみ適用できる制度で、「専門業務型」と「企画業務型」の2つのタイプがあります。
①専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、特定の専門知識や技術を活かして業務を行う職種に適用されます。
業務のやり方や時間配分などの具体的な指示が困難とされる19の業務が厚生労働省令で定められており、研究開発、デザイン、クリエイティブ制作、ソフトウェア開発、弁護士・公認会計士などの士業が該当します。
②企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画・立案・調査および分析業務に適用されるもので、業務の方法を大幅に労働者に委ねる必要がある業務が対象です。
具体的には、事業戦略の策定、新商品・サービスの企画開発、市場調査・分析などの業務が含まれます。
これまでの裁量労働制の課題
裁量労働制には長時間労働の常態化という大きな課題がありました。制度の趣旨は労働者の裁量による効率的な働き方の実現ですが、実際には長時間労働が発生しても残業代が支払われないケースが問題となっていました。
さらに深刻な問題として、一部の企業では適用職種が厳密に定められているにも関わらず、営業職や一般事務職など、本来は対象外の従業員にも裁量労働制を適用し、残業代削減の手段として悪用するケースが報告されています。
これらの課題を受けて、厚生労働省は2021年に労働基準法施行規則を改正し、裁量労働制の適正な運用を図るため、健康・福祉確保措置の強化や労働時間の状況把握の義務化などの規制を強化しました。
【2024年4月~】裁量労働制に関する法改正
2024年4月1日から、裁量労働制に関する労働基準法施行規則等が改正され、専門業務型・企画業務型の両方において新たな手続きが追加されました。
制度導入には、これらの改正要件を満たした適切な設計が不可欠です。
【2024年版】労働基準法の改正点!人事部門が押さえておきたいポイント
改正ポイント1|業務の適用範囲の見直し
専門業務型裁量労働制の対象業務が19職種から20職種に変更され、新たに「銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)」が追加されました。
金融機関でM&A業務に従事する専門職についても、業務の性質上その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要があります。
参考:
・厚生労働省「専門業務型裁量労働制について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001164346.pdf
改正ポイント2|健康・福祉確保措置の強化
2024年4月1日から、専門業務型・企画業務型共通して健康・福祉措置を講じることが必要となり、従来の措置に加えて新たな項目が追加されました。
対象労働者全員への措置として、「勤務間インターバルの確保」「深夜労働の回数制限」「労働時間の上限措置」「連続した年次有給休暇の取得」が追加されています。
また、個々の労働者の状況に応じて講じる措置としては「一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導」などが新たに規定されました。
勤務間インターバルでは11時間以上、深夜業の回数制限では1か月あたり4回以内で設定するのが望ましいとされています。
改正ポイント3|労使協定と同意の取り決め
専門業務型裁量労働制を適用するにあたっては、2024年度以降対象者本人の同意が必要となり、労使協定で定めるべき事項も追加されました。
具体的には、「制度の適用にあたって労働者本人の同意を得ること」「制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと」「制度の適用に関する同意の撤回の手続き」を労使協定に明記する必要があります。
改正ポイント4|労使委員会における運営規程・決議事項の追加
企画業務型裁量制度においては労使委員会の運営規程に定める事項や労使委員会での決議事項が追加されました。
運営規程に追加された事項には、「対象労働者に適用する賃金や評価制度の内容について、事前に労使委員会に説明すること」「制度の実施状況の把握の頻度・方法など、制度を適正に運営するために必要な事項」「労使委員会を開催する頻度」があります。
特に重要なのは、労使委員会の開催頻度が「6か月以内ごとに1回」へと変更されたことです。
制度の信頼性・透明性を高めるため、定期的かつ継続的なチェック体制を強化するための具体的な義務が設けられたのです。
参考:
・厚生労働省「企画業務型裁量労働制について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001164442.pdf
裁量労働制のメリット
裁量労働制は、企業と労働者の双方にメリットをもたらす制度です。
企業におけるメリット
企業におけるメリットは次の点があげられます。
- 実労働時間の管理が不要となり、人事部門の業務負担が軽減される
- 従業員の創造性や専門性を活かした業務遂行が可能となり、より質の高い成果を期待できる
成果主義による生産性の向上と労務管理の効率化が可能です。
労働者におけるメリット
労働者にとってのメリットは、次のような点です。
- 自己の裁量で仕事の進め方や時間配分を決められる(自由度が高い)
- 実際の勤務時間に関係なく定められた時間分の給与が保証されるため、効率的な働き方を追求できる
働き方の多様化を求める現代の労働者にとって、プライベートと仕事のバランスを自分でコントロールできることは大きな魅力となります。
裁量労働制のデメリット
裁量労働制には多くのメリットがある一方で、企業と労働者の双方にデメリットも存在します。
制度導入を検討する際は、これらのデメリットへの適切な対策を講じることが重要です。
企業におけるデメリット
企業におけるデメリットは以下の点があげられます。
- 導入時の厳格な要件への対応が必要で、労使委員会の設置・運営や対象業務の明確な特定に時間とコストがかかる
- 成果の評価基準の設定が難しく、不公平感を生まないような制度設計が求められる
- 労働者の健康管理や長時間労働の防止のための新たな管理体制の構築が必要
特に2024年の法改正により健康・福祉確保措置が強化されており、従来とは異なる管理体制が求められます。
労働者におけるデメリット
労働者においては、次のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 実際の労働時間が長くなっても定められた時間分の給与しか支払われない
- 自己管理が不十分な場合は長時間労働につながるリスクがある
- 成果での評価により精神的なプレッシャーが大きくなる可能性がある
自由度の高い働き方ができる反面、労働者自身の自己管理能力と責任感が重要です。
裁量労働制の成功につながる“適切な運用”のポイント
制度の導入を成功させるためには、法的要件を満たすだけでなく、労働者の健康と生産性の両立を図る適切な運用体制の構築が重要です。
最後に、そのポイントを解説します。
法律上の手続きを正しく理解する
労使協定や労使委員会決議の内容、労働基準監督署への届出手続き、労働者本人の同意取得など、すべての法的要件を正確に理解して実行しましょう。
特に2024年の法改正により追加された要件については、既存の制度を見直し、適合させることが必要です。
また、定期的な法令遵守状況の確認と、必要に応じた制度の見直しを継続的に行うことで、制度の有効性を維持できます。
労働時間の厳格な管理
適切な運用がなされていないと長時間労働を助長し、健康被害が懸念されます。従業員の実労働時間を正確に把握し、適切に管理することが重要です。
具体的な管理方法として、勤怠管理システムの活用による出退勤時刻の正確な記録や、休日出勤や深夜労働の事前承認制度の導入が効果的です。
労働基準法により、深夜(22時~翌5時)に仕事をする場合や、法定休日に出勤をする場合は、通常の賃金に加えて「割増賃金」を支払わなければならないため、正確な労働時間の把握は賃金計算の観点からも不可欠です。
従業員の健康管理
裁量労働制を適用する労働者全員に対して、適切な健康管理と福祉措置の実施が法律で義務づけられています。
以下の内容を参考に、従業員一人ひとりが健康に働きつづけるための、適切な管理と体制の構築を行いましょう。
①労働時間管理に関する措置
・勤務間インターバルの確保
・深夜業の回数制限
・代償休日や特別休暇の付与
②健康管理に関する措置
・健康診断の実施
・年次有給休暇の取得促進
・健康問題についての相談窓口の設置
③専門的なケアとして
・健康状態に応じた配置転換
・産業医による保健指導
まとめ
裁量労働制は、労働者の裁量で業務の時間配分や進め方を決められる制度で、企業の生産性向上と労働者のワークライフバランス実現の両立を可能にします。2024年の法改正により健康・福祉確保措置が強化され、より適切な運用が求められています。
多様な働き方の推進と生産性向上を実現するため、まずは自社の業務内容と法的要件を照らし合わせ、適切な制度設計から始めてみましょう。
労務管理基本シリーズ 2.「労務管理と健康確保対応編」の概要
裁量労働制の導入においては、従業員への理解促進と正しい運用を実現するための育成が欠かせません。
そこで、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)では、裁量労働制を含む労務管理の基本を体系的に学べる研修を提供しています。裁量労働制の適正な運用に欠かせない、労務管理と従業員の健康確保に関する実務的な知識を学ぶことができます。
マネジメント・ビュッフェ
管理職の学びに特化したeラーニング
業務スキルとマネジメントスキルは別物。管理職に必要とされるブレないリーダーシップ、部下の育成など、様々なマネジメントスキルを体系的に習得できます。
- 管理職の学びに特化した充実の175テーマ
- 自律した学びが育つ、学習習慣をつける
- デジタルを活用し効率的に学習が進む

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます