- 対象: 全社向け
- テーマ: キャリア
- 更新日:
ガラスの天井とは?根本的な原因と有効な人事施策を紹介

「ガラスの天井」という言葉は、主に女性の社会的地位の向上や昇進の妨げとなる、見えない障壁を指す表現として広く知られています。女性の社会進出は進んでいるものの、いまだ多くの企業・業界にガラスの天井は存在するといわれています。
ガラスの天井を打破することは、企業のROE(自己資本利益率)を高めることや、人材不足を解消する上で重要です。今回は、ガラスの天井の基本的な概念や原因、解消するための有効な施策について紹介します。
関連資料
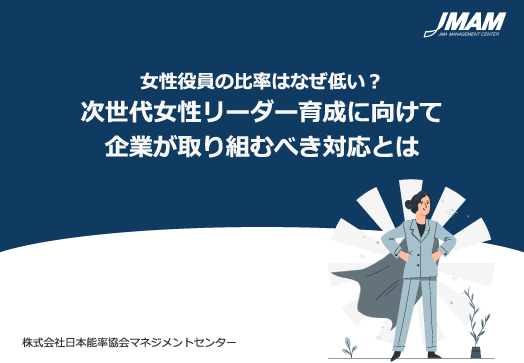
関連資料
なぜ女性リーダーの育成が必要なのか、そのメリットと課題を解説
次世代女性リーダー育成に向けて企業が取り組むべき対応とは
ガラスの天井とは
まずは、「ガラスの天井」について詳しく説明します。
基本概念
ガラスの天井とは、性別や人種などを理由に組織内で高位のポジションに昇進できない状況を指す比喩表現です。この言葉は、英語の「グラスシーリング(glass ceiling)」に由来し、ガラスのように透明な「見えない障害物」として例えられます。特に女性に対する組織内の不公平な待遇を象徴することが多く、努力や成果に関わらず昇進が阻まれる状況を示しています。
ガラスの天井が存在する組織では、昇進に値するスキルや経験をもっていても、性別など個人の属性が理由で高いポジションに到達できません。社内の男女比が等しいにもかかわらず、上層部のポジションに男性が圧倒的に多い場合は、ガラスの天井が存在する可能性があります。
「壊れたはしご」との違い
ガラスの天井のほかに、女性のキャリア進出を阻む比喩表現として「壊れたはしご」という言葉もあります。これはガラスの天井とは異なり、キャリアの初期段階から昇進が難しいことを意味するものです。
従業員が昇進していくプロセスを表す「はしご」が、女性にとっては最初から壊れており、男性と平等に昇進することが難しい状況を示しています。キャリアの初期段階から不利な立場に置かれていれば、最終的に経営陣や上級職に就く女性が少なくなるのは必然的といえるでしょう。
ガラスの天井と壊れたはしごは、どちらも女性が企業での昇進やキャリア構築において不平等な扱いを受けていることを示していますが、大きな違いは「タイミング」です。ガラスの天井はキャリアの途中段階で遭遇する障壁ですが、壊れたはしごはキャリアの初期段階で女性が不利な立場に置かれている状態を示しています。
ガラスの天井が存在する日本の現状
日本において、ガラスの天井は依然として存在するといわれています。その現状について、3つの観点から解説します。
管理職全体に占める女性の割合が少ない
日本では女性の社会進出が進んでいるものの、管理職や役員のポジションに就いている女性の割合は依然として低いままです。
内閣府男女共同参画局が公表している「令和6年版男女共同参画白書」によると、東証プライム市場上場企業における女性役員比率は、2022年の11.4%から2023年には13.4%と、2.0%増加しています。また、上場企業の役員に占める女性の割合は9.1%から10.6%へと増加しています。しかし、国際的な水準と比較した場合、依然として低い数値にとどまっているのが現状です。
同資料によると、管理職全体に占める女性の割合は12.9%であり、諸外国と比べて低い数値です。加えて、係長級で23.5%、課長級で13.2%、部長級では8.3%と、上位の役職に進むにつれて女性の割合が減少しています。
政府は、東証プライム市場上場企業の役員に占める女性の割合について、2025年までに19%(令和5年12月閣議決定)、2030 年までに30%以上(令和5年6月すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)を定めているものの、目標まではほど遠い状態です。
出典:内閣府男女共同参画局「令和6年版 男女共同参画白書」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/pdfban.html
内閣府男女共同参画局「女性版骨太の方針2024」
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html
衆議院議員に占める女性の割合が少ない
政治分野でも同様にガラスの天井が存在している可能性があります。内閣府男女共同参画局が公表している「政治分野における男女共同参画の状況」の資料によると、2024年2月時点の女性議員の割合は、衆議院で10.4%、参議院で26.7%であり、閣僚に占める女性の割合は全体の4分の1に過ぎません。
衆議院の公式サイトによれば、2024年8月28日時点で衆議院議員全体の数は465名、そのうち女性議員の数はわずか51名で、女性の占める割合は約11%です。
出典:内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画の状況」
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka34-8.pdf
衆議院「会派名及び会派別所属議員数」
https://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/giin_top.htm
女性の家事・育児負担が他国よりも大きい
女性のキャリア形成に影響を与える要因のひとつに、家事・育児負担が女性に偏っていることもあげられます。
内閣府男女共同参画局が公表しているデータによると、日本の女性の無償労働時間は男性に比べて5.5倍にもおよんでいます。OECDの諸外国と比べ、最も家事・育児負担に男女差があることが明らかになりました。
このことから、仕事と家庭の両立が難しいことが、女性のキャリアアップの妨げとなっていることが考えられます。
出典:男女共同参画局「コラム1 生活時間の国際比較」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/column/clm_01.html
ガラスの天井が生まれる根本的な原因
ガラスの天井が生まれる根本的な原因について、詳しく解説します。
出産後のキャリア継続に対するアンコンシャス・バイアス
ガラスの天井が存在する主な原因には、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が大きく関わっています。アンコンシャス・バイアスとは、個人が無意識のうちに持っている偏見や先入観のことです。意識的に差別をしているわけではなくても、昇進やキャリアの機会に不公平が生じる状況を生む原因となってしまいます。
これは、特に出産や育児に関連するキャリアの中断に深く影響を与えます。働く母親に対する理解やサポートの不足が、キャリア継続を難しくする要因となるのです。
例えば、「出産をした女性はキャリアアップを断念するべきだ」や「育児を優先すべき」といった無意識の偏見は、女性のキャリア継続に対するハードルを上げてしまいます。
また、このような無意識のバイアスが家庭内でも影響し、女性が育児の大部分を担うことで、キャリアアップを諦めざるを得ない状況が生まれることもあります。
長期雇用・長時間労働が根付いている
長期雇用を前提とする企業は、従業員を早期に昇進させることに対して心理的な抵抗感をもつことがあります。早い段階で立場の格差が明らかになると、昇進できない従業員のモチベーションが低下するおそれがあるため、企業は昇進のペースを抑える傾向があります。
さらに、能力や生産性ではなく、企業への忠誠心(長時間労働、長期雇用)で評価されることも少なくありません。
また、日本の企業では、管理職に昇進すると仕事量が増え、長時間働くことが当然とされる傾向にあります。そのような文化のなかで、ライフイベントによって時間的制約が生まれやすい女性が管理職に昇進するのは容易ではありません。
このような長時間労働が必要とされる環境では、家庭と仕事の両立を望む女性が昇進の機会を失うことになります。日本で古くから根付いている長時間労働の文化が、女性のキャリア進展における障壁となり、結果としてガラスの天井を形成しているといえます。
ガラスの天井を打破する重要性・メリット
ガラスの天井を打破することは、企業や社会にとって多くのメリットをもたらします。下記で、その具体的な利点を紹介します。
ROEを高められる
ガラスの天井を打破し、女性の役員や管理職を増やすことで、企業のROE(自己資本利益率)を高める効果が期待できます。ROEは、企業が自己資本をどれだけ効率的に活用しているかを示す指標であり、数値が高いほど経営効率が良いとされています。
内閣府男女共同参画局「令和3年度 女性の役員への登用に関する課題と取り組み事例」によれば、女性役員の割合が高い企業ほど、ROEが高い傾向にあります。多様な視点から意思決定を行うことが、企業のパフォーマンスを向上させ、経営効率の改善にもつながるといえるでしょう。
出典:内閣府男女共同参画局「令和3年度 女性の役員への登用に関する課題と取り組み事例」
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/yakuin_r03.pdf
人材不足を解消できる
ガラスの天井を打破することは、女性にとって長期的に働きやすい環境を整えることにつながります。結果として、優秀な女性従業員の流出を防ぎ、定着率を向上させる効果が期待できます。
女性に限らず、すべての従業員の定着率が向上すれば、長期的な人材不足を解消できる可能性が高まるでしょう。
また、職場環境の改善や昇進機会の均等化によって、優秀な人材が集まりやすくなり、人材確保が容易になる点も大きなメリットです。多様なバックグラウンドをもつ人材が集まることで、企業の競争力も強まります。
投資家から評価されやすくなる
投資家は企業を評価する際、財務的な成果だけでなく、企業の社会的責任や持続可能性に対する取り組みも重視しています。つまり、ガラスの天井をなくし、多様性を尊重した経営を実施している企業は、投資家からの評価が高くなると考えられます。
そして、多様性が高い企業は組織全体の柔軟性や革新力が高まり、長期的な成長が期待できるため、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の魅力的な銘柄になりえるでしょう。ガラスの天井問題の解決は、資金調達やブランド価値の向上につながる、有意義な取り組みだといえます。
ガラスの天井を打破するための施策
ガラスの天井を打破するためには、「社内の意識改革」と「従業員同士の対話」が重要なポイントです。具体的な施策を紹介しましょう。
働きやすい職場環境の整備
ガラスの天井を打破するための施策として、女性が働きやすい職場環境の整備が重要です。女性がライフステージに合わせて柔軟に働ける体制を整えましょう。具体的には、時短勤務やフレックスタイム制度などの導入が有効です。
柔軟な働き方が可能であれば、出産や育児などで一時的に働き方を変える必要がある女性もキャリアを継続しやすくなります。また、企業にとっても人材の流出を防げるメリットがあり、定着率の向上につながります。
さらに、労働時間ではなく「生産性」に基づく公正な評価制度の導入も不可欠です。これにより、長時間労働に頼らない職場環境が整い、男女問わず公平に評価することができます。
社内コミュニケーションの活性化
社内コミュニケーションを活性化させ、従業員が自由に意見を交わせるような職場環境を整備しましょう。具体的には1on1ミーティングやメンター制度、360度評価などの導入が効果的です。
1on1ミーティングは、女性がキャリアの中で直面する課題や不安を、上司に直接相談できる場でもあります。キャリアの進め方や職場環境に関する悩みを共有でき、上司から具体的な支援やアドバイスを受けることが可能です。
また、メンター制度によって経験豊富なメンターが女性従業員をサポートすることで、キャリアの指針をもちやすくなります。加えて、昇進やリーダーシップを取るための具体的な助言を行い、キャリアの壁を乗り越えるための支援をすることが重要です。
360度評価では、上司だけでなく同僚や部下、さらには顧客など複数の立場から評価が行われるため、評価が多面的で公正になります。性別に関係なく、個々のパフォーマンスやスキルが評価されるため、女性のリーダーシップや能力が正当に評価されやすくなります。
キャリアアップ体制の整備
ガラスの天井を打破する施策として、キャリアアップ体制の整備も欠かせません。特に、女性が安心してキャリアを積み重ねていけるよう、キャリアパスを明確に整えることが重要です。
多くの企業では、女性が出産や育児などをきっかけにキャリアの中断や変更を余儀なくされる場合があり、これがガラスの天井の一因であるといえます。そのため、企業は女性が長期的にキャリアを築ける体制を構築し、昇進を目指せる環境を提供することが大切です。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、女性のキャリアアップセミナーをはじめ、人材育成に関するさまざまなプログラムをご提供しております。女性が活躍できる職場づくりや、キャリアアップ支援に力を入れたい人材育成担当の方は、ぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
「ガラスの天井」とは、性別や人種などを理由に組織内で高位のポジションに昇進できない状況を指す比喩的な表現で、特に女性に対する組織内の不公平な待遇を象徴しています。日本では女性の社会進出が進んでいるものの、管理職や役員のポジションに女性が就いている割合は依然として低く、多くの企業にガラスの天井が存在していると考えられます。
ガラスの天井を打破することは、企業の経営効率を高め、優秀な人材を確保するために不可欠な要素です。企業がこれから取り組むべきは、女性が安心してキャリアを築ける職場環境の整備と、ジェンダー平等を促進するための施策の実施といえます。
次世代女性リーダー育成に向けて企業が取り組むべき対応とは
女性役員の比率はなぜ低い?
なぜ女性リーダーの育成が必要なのか、そのメリットと課題を整理したうえで課題解決の方向性を解説します。
- 女性リーダー、女性役員が求められる背景
- 女性リーダー育成において直面する課題
- 課題解決にむけた取り組み
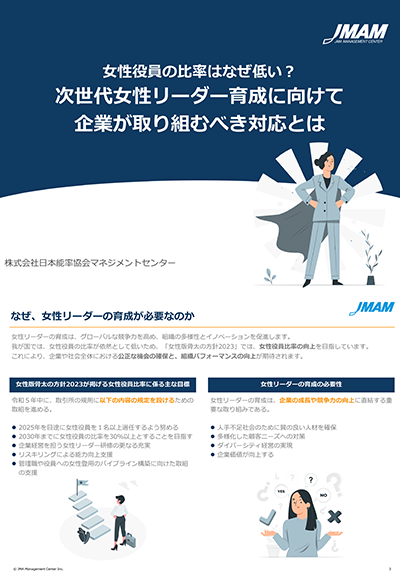
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















