- 対象: 全社向け
- テーマ: マネジメント
- 更新日:
優秀な女性管理職・役員を増やすために企業ができる施策とは

多くの企業が、女性管理職・役員の割合を思うように上げられないと悩んでいるのではないでしょうか。組織の多様性が社会的に求められていることは理解しながらも、「短期的な利益につながりづらい」「長年に渡って培われた企業の文化や風土に関わるので、どのように社員を巻き込み変えていったらいいのかわからない……」というお声をよく伺います。
今回は、女性管理職・役員を育成するメリットや有効な施策について紹介します。組織における女性活躍推進の取り組みの参考にしてみてください。
関連資料
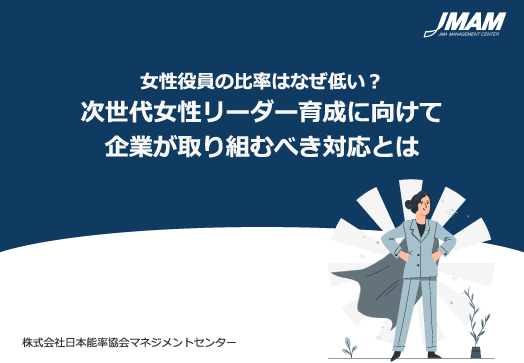
関連資料
なぜ女性リーダーの育成が必要なのか、そのメリットと課題を解説
次世代女性リーダー育成に向けて企業が取り組むべき対応とは
日本の女性管理職・役員への登用が進まない理由
日本の女性管理職・役員の割合は、依然として低水準にとどまっています。
「令和6年版 男女共同参画白書」によると、令和5年(2023年)の女性(15~64歳)の就業率は73.3%と高まっているものの、管理的職業従事者に占める女性の割合は12.9%にすぎず、諸外国と比べて低い状況です。
役職別に見ると、係長級23.5%、課長級13.2%、部長級8.3%と、上位の役職になるほど女性の割合が低くなっています。上場企業の役員に占める女性の割合も10.6%、東証プライム市場上場企業では13.4%と低迷しています。
政府は東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割合について、2025年までに19%、2030年までに30%以上という目標を掲げていますが、現状では目標達成までの道のりは遠いと言えるでしょう。
出典:
・内閣府男女共同参画局「令和6年版 男女共同参画白書」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/gaiyou/pdf/r06_gaiyou.pdf
・内閣府男女共同参画局「女性版骨太の方針2024」
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2024_honbun.pdf
下記より、日本の女性管理職・役員が少ない理由について、詳しく見ていきましょう。
アンコンシャス・バイアスの影響
社会には未だに男女の役割分担意識が根強く残っており、女性が管理職・役員に就くことに対して肯定的な企業風土が醸成されにくい状況があります。これはアンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)の一種です。
特に企業の中高年世代において、管理職や主要業務は男性が担うべきという先入観をもつ社員は少なくありません。家庭においても、共働き世帯でも女性の家事育児負担が大きい傾向が見られます。
妊娠・育児・介護などのライフイベントの負担が女性に偏っている
女性の管理職・役員登用が進まない背景には、妊娠・育児・介護などのライフイベントの影響も大きく関わっています。
育児介護休業法では、育児休業をしたことを理由に解雇、そのほかの不利益な取扱いをしてはならないとされています。しかし多くの企業では、同じ勤続年数の社員と比較して、育児休業取得者の評価は低くなりがちな傾向があり、育児休暇の取得が人事評価に影響を及ぼしています。
ライフステージの変化の影響が大きい女性であっても、昇進を見据えて働き続けられるような環境が整っていないのが現状です。
女性自身の昇進への意欲が低い
女性管理職・役員が少ない理由のひとつに、昇進に対して前向きでないことがあげられます。働く女性の多くは、「自分に管理職・役員は向いていない」「それほどコミットできない」と感じ、昇進することをネガティブに捉えているようです。
家庭と仕事の両立の困難さや将来の理想像とのギャップを感じ、昇進を躊躇する傾向もみられます。また、社内に女性管理職・役員がおらず、ロールモデルが不在であることも女性が管理職・役員として働くキャリアを描けない大きな要因です。
これらの要因が複合的に作用して、女性の管理職・役員登用を妨げているのです。
女性管理職・役員が増えるメリット
女性管理職・役員が増えることで、企業にとってさまざまなメリットがあります。
ダイバーシティ推進につながる
女性管理職・役員の育成は、企業のダイバーシティ推進に大きく貢献します。多様な視点や経験を持つ人材が意思決定に関わることで、新たなアイデアや革新的な解決策が生まれやすくなるでしょう。
また、女性ならではの視点を取り入れることで、多様な働き方にも対応しやすくなり、労働環境の改善へとつながります。従業員のエンゲージメントが高まり、組織全体の活性化が期待できます。
結果として、企業の競争力向上や持続的な成長にも寄与する可能性が高いのです。
社会的な評価が高まる
女性管理職・役員の比率が高い企業は、社会的な評価が高まる傾向にあります。
具体的には、ESG投資家からの注目を集め、投資対象としての魅力が増します。また、「女性の働きやすさを重視する企業」「ワークライフバランスに注力する企業」という好印象を与え、顧客や求職者からの支持を得やすくなるでしょう。
さらに、「えるぼし認定」や「くるみん認定」の取得により、採用時のアピールにもつながります。「えるぼし認定」は女性の活躍推進に関する取り組みを評価する認定制度で、「くるみん認定」は子育てサポート企業として評価基準を満たした企業に付与されます。いずれも厚生労働大臣が認定を行います。
人手不足の解消につながる
優秀な女性が長く働き続けられるようになると、人手不足の解消にもつながります。
女性管理職・役員を育成するには、女性が柔軟に働ける環境が不可欠です。優秀な女性がライフステージの変化によりフルタイムで働けなくなっても、在宅勤務や時短勤務が可能であればその時間で質の高い業務をこなせます。
また、育児や介護で一度職場を離れてしまっても、復帰しやすい環境があればほかの職場に転職してしまうことがありません。
企業の競争力向上や優秀な人材の獲得に寄与できるでしょう。
業務効率の改善につながる
育児や介護などとの両立のために決められた業務時間で働く女性が管理職・役員になることは、より業務効率を改善し効率的に働き、時間を意識して成果を出すことへの意識が高まります。そのため従業員は無駄を省き、優先順位を明確にして働く習慣が身につきやすくなります。
また、フレキシブルな勤務時間や在宅勤務の導入により、個々のライフスタイルに合わせた効率的な働き方ができるようになることで、女性だけでなくすべての働き方改革にもつながり、組織全体の生産性向上への貢献が期待できます。
女性管理職・役員を増やすための施策
女性管理職・役員の社内登用を増やすために、企業ができることは多岐にわたります。これから紹介する施策は、女性社員のキャリア開発を支援し、リーダーシップスキルを向上させるとともに、組織全体の意識改革を促進します。
特に効果的と考えられる具体的な取り組みについて、詳しくみていきましょう。
ロールモデルとなる女性リーダーを周知する
成功した女性リーダーの経験を積極的に表彰し、功績を広く認知することで、後進が目指したくなるロールモデルを増やすことができます。
また、女性リーダーによるセミナーやワークショップを開催することも重要です。若手女性社員が身近な成功例に触れる機会が増え、自身のキャリアアップへの意欲が高まります。
女性リーダーの積極的な意思決定への参画は、組織全体の多様性と創造性の向上にもつながるでしょう。
社内外のネットワークを形成する
女性管理職・役員の育成には、ネットワークの形成が重要な役割を果たします。活躍の場を広げるため、同業や異業種のリーダーとの交流の機会を積極的に設けましょう。
リーダーシップを鍛える機会を提供し、経営の視点から意思決定を行う疑似体験を通じて、取締役としての役割や使命感を体感させることも大切です。社内外のネットワークの形成を促進し、専門知識を持つ社外取締役候補との人脈を広げられるような異業種交流会や、異業種セミナーへの参加も有効でしょう。
また、同時にコミュニケーションスキルを高めることも重要です。立場や考えの異なる相手との意思疎通が円滑になり、周囲の理解を得やすくなります。
上司がキャリア開発を支援する
女性のキャリア志向を高めるには、女性社員に向き合う上司の存在も重要です。上司には、女性の多様なキャリア観や働き方を受容し、個々の状況に合わせた支援やフォローを行うことが求められます。
具体的には、役員が1対1で育成や昇進を後押しするスポンサーシップ・プログラムが有効です。日本経済新聞の調査(2015年)によると、女性社員が役員に昇進した主な理由として「引き立てたり機会を与えてくれる上司の存在(約7割)」があげられました。
身近な上司の支援により、女性社員は具体的なキャリアパスを描き、管理職や役員への道を自信を持って歩むことができるでしょう。
出典:男女共同参画局「平成28年度 女性リーダー育成に向けた諸外国の取組に関する調査研究(女性役員登用の閣議決定目標「2020年10%」達成に向けて)」
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/gaikoku02_research.html
人事評価制度を見直す
女性管理職・役員の育成には、女性が管理職・役員に昇進するための明確な基準と条件を設けることが重要です。キャリアパスの透明性が高まり、女性社員にとって管理職を目指すことがより現実的になります。
現状の評価制度では女性のライフスタイルに適応できない可能性があるため、男女で異なる基準を設定することも検討しましょう。さらに、女性管理職の増加に関する具体的な数値目標を掲げることで、組織全体のキャリア昇進への意識が高まります。
柔軟な働き方を実現できる制度を導入する
令和6年の男女共同参画白書によると、管理職として働く条件として重視している項目に男女差が顕著に現われています。特に「出産・子育てとの両立支援」「育休等によるキャリア中断への配慮」「育児等の配偶者との分担」については、女性が男性よりも10%前後高いスコアとなっていました。
これらの課題に対応するための具体的な施策として、柔軟な勤務体系や在宅勤務の導入、育児・介護休暇の拡充、そして復職後のキャリアサポートなどが効果的です。女性社員がライフイベントを経ても継続的にキャリアを築ける環境が整い、より多くの女性が管理職・役員を目指しやすくなるでしょう。
出典:内閣府「令和6年版 男女共同参画白書」
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/gaiyou/pdf/r06_gaiyou.pdf
社内の意識改革を行う
女性管理職・役員を増やすには、社内全体の意識改革も同時に行っていく必要があります。
特に重要なのは、アンコンシャス・バイアスの排除です。無意識のうちに、良かれと思って行っている配慮、または自身のバイアスが、活躍を妨げていることがあります。
アンコンシャス・バイアスは、無意識だからこそ自分から気づくことが難しいため、eラーニングなどで性別に対する固定観念や偏見について学び、自らの思考や行動を振り返る機会を設けることが重要です。また、多様性の重要性や女性リーダーシップの利点について理解を深めることで、全社的な意識変革を促すことができます。
女性の活躍を阻む見えない障壁を取り除き、より公平で活力ある職場環境の創出につなげましょう。
まとめ
政府では、東証プライム市場上場企業役員に占める女性の割合について、2030年までに30%以上という目標を掲げています。
とはいえ、企業の持続的成長と競争力強化のためには、30%以上という数値達成を目的とせず、有能な人材をしっかり登用していくことが重要です。そのほか、キャリア開発支援、柔軟な働き方の導入、人事評価制度の見直しなど、多角的なアプローチも必要です。
また、社員育成はスキルを習得し応用することだけではなく、マインド(個人の覚悟)の醸成にも有効です。
これらの施策を適切に実施することで、より多くの女性が活躍できる環境が整い、企業の発展につながるでしょう。
女性活躍推進についてさらに詳しく学びたい方は、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)主催のセミナーにぜひご参加ください。JMAMでは、スキル習得応用だけではなく、マインド醸成の支援プログラムもご用意しております。
JMAMへのお問い合わせは下記リンクをご覧ください。
次世代女性リーダー育成に向けて企業が取り組むべき対応とは
女性役員の比率はなぜ低い?
なぜ女性リーダーの育成が必要なのか、そのメリットと課題を整理したうえで課題解決の方向性を解説します。
- 女性リーダー、女性役員が求められる背景
- 女性リーダー育成において直面する課題
- 課題解決にむけた取り組み
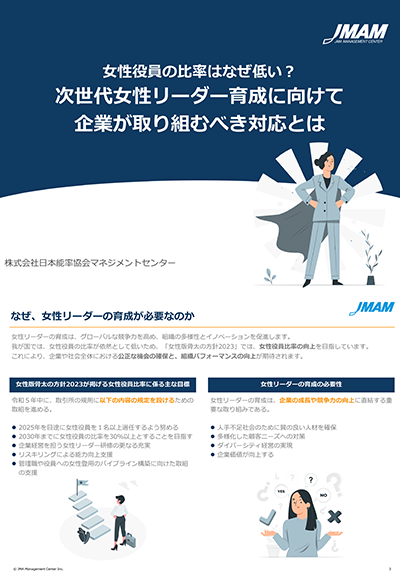
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















