- 対象: 全社向け
- テーマ: ビジネススキル
- 更新日:
ラポール形成とは?効果や企業で実践できるテクニックを解説

ラポールとは、人間関係において重要な「架け橋」を意味します。ビジネスにおいても、この信頼と共感の関係を築くことは、円滑なコミュニケーションや効果的なチームワークにつながります。今回は、ビジネスシーンでも注目されている「ラポール形成」の基本的な概念から、その効果、企業で実践できる具体的なテクニックまで詳しく解説します。
関連資料
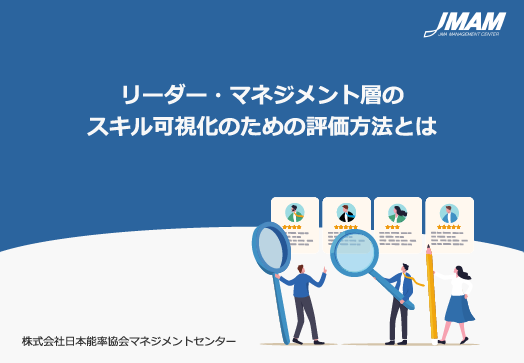
関連資料
マネジメント層のスキルを可視化し、育成や人材配置に活用するための評価方法について解説
リーダー・マネジメント層のスキル可視化のための評価方法とは
ラポール形成とは
ラポール形成の「ラポール(rapport)」はフランス語で「架け橋」を意味し、自分と相手の心に橋が架けられたように信頼や共感が生まれ、言葉や行動で表現せずとも気持ちが通じ合う状態を指します。
主にセラピーの分野で使われている言葉で、セラピストとお客様(クライエント)の間に信頼関係を築き、リラックスできる環境をつくるために役立つ考え方を指します。
ラポール形成は、ビジネスの現場においてもさまざまな効果をもたらします。具体的なメリットについては後述します。
企業におけるラポール形成の重要性
企業において同僚や上司とラポール形成を行うことには、次のメリットがあります。
心理的安全性を確保できる
ラポールが形成された職場環境では、従業員が心理的安全性を感じることができます。心理的安全性とは、組織内で自分の考えや意見を誰にでも安心して発信できる状態のことです。
ラポール形成により従業員同士の信頼関係が深まると、チームワークの向上にもつながります。その結果、プロジェクトがスムーズに進行するとともに、従業員それぞれの生産性が高まります。
心理的安全性が高い組織のメリットについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
円滑なコミュニケーションができる
ラポールが形成されることで、お互いに相手を理解した状態で会話ができ、言葉だけでは伝わりにくい感情やニュアンスも伝わりやすくなります。例えば、チームメンバーがプロジェクトの進捗について話し合う際、ラポール形成ができていると、お互いの意図や懸念を深く理解し合えるため、誤解を生みにくくなります。
また、お互いが自分のペースで話せるため、急かされることなく自分の考えをしっかりと伝えられ、気持ち良くコミュニケーションを取れます。
結果として、良い雰囲気の職場になり、従業員のモチベーション向上にもつながるでしょう。
生産性の向上につながる
ラポールが形成されている環境では、従業員同士のスムーズな情報交換や意思疎通が可能となり、組織全体のパフォーマンスが向上します。例えば、プロジェクトチームが新製品の開発に取り組む際、各メンバーが自由に意見を交換できることで課題が迅速に解決し、時間や労力を削減できます。
また、情報伝達のミスが減り、意思決定が迅速かつ正確に行えるようになります。
定着率の向上につながる
企業におけるラポール形成は、従業員の定着率の向上にも大きな影響を与えます。ラポールが形成された職場環境では、従業員が企業に対して居心地の良さを感じ、「この企業で働き続けたい」と思うようになるでしょう。
その結果、離職率が低下し、定着率の向上が期待できます。
ラポール形成の3原則
ラポールを形成するためには、3原則を満たす必要があります。細かなテクニックよりも重要度が高いため、確実に理解しておきましょう。
肯定と尊重
「肯定と尊重」は、相手の価値観や感情を肯定し、尊重する姿勢をもつことです。単にテクニックとして行うのではなく、心から相手を理解しようとする姿勢が求められます。
また、相手の考えに対しても、肯定することが重要です。プロジェクトの進行中にチームメンバーが新しいアイデアを提案した場合、そのアイデアが実現可能かどうかにかかわらず、まずは肯定的に受け入れましょう。「その考えは面白いね。もっと詳しく聞かせて」という姿勢を示すことで、メンバーは自分の意見が尊重されていると感じ、コミュニケーションが円滑に進みやすくなります。
類似性の法則
「類似性の法則」は、共通の事柄や行動の同調によって一体感が生まれ、相手に安心感や好感を抱くようになることを指します。これは、人間が自分と似た特性や興味をもつ相手に対して親近感をもちやすいという心理的傾向に基づいています。
例えば、営業担当者が取引先の担当者との初対面で、相手がスポーツ好きであることを知った場合、自身もスポーツに興味があることを伝えると共通の話題が生まれ、会話が弾みやすくなります。共通の話題があると、取引先の担当者は営業担当者に対して安心感や好感を抱きやすくなり、ビジネス関係がスムーズに進展するでしょう。
ペーシングとリーディング
ペーシングとは、相手の呼吸や話し方、視線などを合わせることです。これにより、相手は自分が理解され、共感されていると感じやすくなります。
例えば、営業担当者がクライアントとの打ち合わせで、相手の話す速度やトーンに合わせて話すと、クライアントは自然と安心感を抱き、打ち解けやすくなります。
一方、リーディングとは、ペーシングを通じて信頼関係を築いた後に、相手を目的に合わせてリードすることです。
例えば、チームリーダーがプロジェクト会議で、メンバー全員の意見をまずはペーシングによって丁寧に聞き取った後、自らのビジョンや次のアクションを提案することで、メンバーを自然にリードします。その結果、メンバーはリーダーに対する信頼感をもちつつ、目標に向かって動きやすくなります。
社内研修で取り入れたいラポール形成のテクニック
ラポール形成のテクニックは、過度に用いるとわざとらしくなったり違和感を与えたりするため、さりげなく行えるようになるまで練習しましょう。ラポールを形成するテクニックのうち、代表的な4つのテクニックを紹介します。
キャリブレーション
キャリブレーションは、相手の仕草や表情、雰囲気、姿勢などを細かく観察する技術です。相手の感情や意図を理解するために役立ちます。2人1組で行うトレーニングでキャリブレーションを習得しましょう。
まず、パートナーに好きな人のことを思い浮かべてもらい、そのときの仕草や表情、姿勢を観察します。次に、同じように嫌いな人を思い浮かべてもらい、その様子を観察します。好きな人と嫌いな人を思い浮かべたときの違いを理解しましょう。
次に、パートナーに黙って片方を思い浮かべてもらいます。その際の仕草や表情を観察し、どちらを思い浮かべているかを当てることを目指します。このトレーニングによって相手の微細な変化を読み取る能力が養われ、より深いコミュニケーションが可能になるでしょう。
バックトラッキング
バックトラッキングとは、相手が使った言葉をそのまま返す「オウム返し」のテクニックです。バックトラッキングには、「事実を繰り返す」「感情や気持ちを繰り返す」「要約する」の3種類があります。
「事実を繰り返す」手法は、相手が「自分の状況が理解された」と感じやすくなるため、信頼関係が深まります。
このように、相手から「そうそう」「そうなんです」といった肯定的な反応を得ることが目標です。
バックトラッキングは、すでに信頼関係がある親しい相手とのコミュニケーションで特に効果を発揮します。家族や親しい友人との会話で意識的に行いましょう。
ミラーリング
ミラーリングは、相手の仕草や姿勢、動きを鏡に映すように真似するテクニックです。体の状態が合うと、心の状態も自然と合ってくるという心理学的な原則に基づいています。
具体的なトレーニング方法として、3人1組で行うワークを紹介します。モデル、ミラーリングする人、観察者の3人が必要です。それぞれ、次のように行動します。
- モデル
自然な姿勢や動きをする - ミラーリングする人
モデルの動きを注意深く観察し、できるだけ正確に真似する - 観察者
モデルとミラーリングする人の両方を見て、2人の姿勢や動きが一致するように指示を出す
マッチング
マッチングは、相手の声の大きさや話すテンポ、声のトーンなどを合わせることで、相手との一体感や信頼感を築くテクニックです。相手は自分が理解されていると感じ、コミュニケーションが円滑になっていきます。
自然と相手の話し方に合わせていく感覚を養うために、一方が話し手、もう一方が聞き手となり、次のように練習しましょう。
- 話し手
自然に話す - 聞き手
話すペースやトーンに意識的に合わせる
まとめ
ラポール形成は、普段のコミュニケーションの中で意識することから始まります。社内でラポール形成を促進したい場合は、今回紹介したテクニックを理解し、実践することが重要です。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、ビジネス上の信頼関係を構築する「論理的コミュニケーション」を学ぶ研修を提供しています。この研修では、ラポール形成を含むさまざまなコミュニケーション技術を体系的に学ぶことが可能です。従業員のコミュニケーションスキルを向上させたい方は、ぜひご検討ください。
リーダー・マネジメント層のスキル可視化のための評価方法とは
組織の要である「管理職」のスキルレベルを把握する
優れたリーダーシップやマネジメントスキルを持つ人材の育成は企業の持続的な発展に欠かせません。保有スキルを可視化し、育成や人材配置に活用するための評価方法について解説しました。
- スキル可視化が必要とされる背景
- マネジメント層のリーダーシップ評価方法
- スキル評価ツールのご紹介

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















