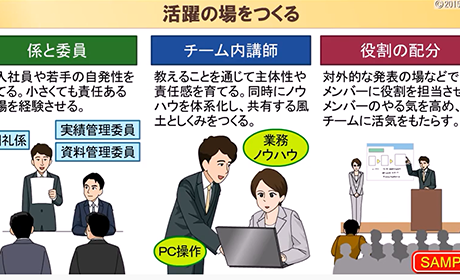- 対象: 人事・教育担当者
- テーマ: 研修/教育
- 更新日:
非認知能力は大人でも伸ばせる!重要性や社員教育の方法を解説

近年、社員教育において、非認知能力が注目されています。具体的にどのような能力を指すのか、どういった方法で向上させれば良いのか知りたい人事担当者もいるのではないでしょうか。
今回は、非認知能力が注目される理由や種類、社員の能力を育てる方法について解説します。
関連資料

関連資料
キャリアの変貌と、必要となる施策のポイントをまとめました
人生100年時代のキャリアデザイン ~自律的なキャリア形成のあり方とは~
非認知能力とは
まずは非認知能力についてくわしく解説します。
そもそも認知能力とは
非認知能力について説明する前に認知能力について改めて理解しておきましょう。
認知能力とは、一般的にIQテストや学力テストなどで数値化できる能力のことを指します。具体的には、計算力、記憶力、言語力、IQ(知能指数)などを指します。
数字で判断がしやすいことから、採用や人事評価において認知能力の高さを重視するケースは多くあります。
この際、認知能力を高めるには、非認知能力を鍛えることが重要だということを押さえておきましょう。
非認知能力は人生の成長を支える力
非認知能力は、客観的に数字で測ることができない能力のことです。具体的には、意欲や自信、自制、協調、共感といった心の部分の能力を指します。
非認知能力は、米国の経済学者であるジェームズ・J・ヘックマンの研究から注目されるようになりました。また、2015年にOECD(経済協力開発機構)によって提唱された「社会情緒的スキル」も、非認知能力と同様のスキルを指します。
社会情動的スキルは、「一貫した思考・感情・行動のパターンに発言し、学校教育またはインフォーマルな学習によって発達されることができ、個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与えるような個人の能力」と定義することができる。
※引用:「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成(ベネッセ教育総合研究所 訳)」(OECD)
https://www.oecd.org/education/ceri/FosteringSocialAndEmotionalSkillsJAPANESE.pdf
非認知能力が注目される背景
非認知能力がなぜ注目されるようになったのか、背景について詳しくみていきましょう。
ジェームズ・ヘックマン教授による研究
非認知能力が注目される背景に、ジェームズ・ヘックマン教授が1962年から行った幼児教育が低所得層の子どもたちに与える影響の検証の研究があります。
幼児教育を受けたグループは、そうでないグループと比較して、学歴・年収・犯罪率の低さといった社会的成功を表す要素で好ましい研究結果を残しました。
一方で、両方のグループのIQの差はほとんどなかったため、非認知能力が社会的成功に影響を与えていると結論づけられたのです。
人生100年時代の到来
非認知能力が注目される背景として、近い将来、人生100年時代が到来することもあげられます。
100歳まで生きるのが当たり前の時代で人生を幸せに生きるには、変わりゆく環境の中で生きがいをもって働くための自立心や思考力、周囲と良好な関係を築くコミュニケーション能力や協調性、新しい技術への適応力などが重要です。
このことから、数字では判断が難しい非認知能力は、長い人生を豊かに生きるための力だと考えられるようになりました。
AIの発達
以前より、AIが現在の職業の大半を担う存在になりうると考えられています。特に2022年11月に公開されたOpenAIのChatGPTは性能が高く、ビジネスでも活用される機会が増えています。
AIの得意領域であるルールに伴った作業や判断、データの記憶、データ処理などは将来的に人間の仕事ではなくなる可能性があります。
このような時代で自らのキャリアを築いていくには、AIがもたない独自性や創造性、社会性などのスキルを身につけなければなりません。
非認知能力は、まさにこれらの要素を含んでおり、AIとの差別化や共生という意味でも注目すべきスキルといえます。
非認知能力の種類
それでは、具体的にどのようなスキルが非認知能力と呼ばれるのかを詳しくみていきましょう。
非認知能力に含まれる力
非認知能力に含まれるスキルには下記があげられます。
| 非認知能力に含まれる能力 | 具体的なスキル |
|---|---|
| 自分と向き合う力 | ・自制心 ・ストレス管理能力 ・レジリエンス ・メタ認知能力 |
| 自分を信じる力 | ・自己肯定感 ・自己効力感 |
| 自分を高める力 | ・内発的動機付け ・GRIT(やり抜く力) ・意欲、向上心 |
| 他者と関わる力 | ・共感性 ・コミュニケーション力 ・リーダーシップ |
自分と向き合う力は、自分について理解して感情や行動をコントロールする能力です。該当するスキルを高めることで、困難な状況やイレギュラーな事態が発生したときも、本来の力を発揮することができます。
自分を信じる力は、目の前の課題や目標をやり遂げる力が自分に備わっていると信じる能力です。自己肯定感や自己効力感が土台にあると、物事が失敗しても自分を過度に否定することなく前向きに捉えることができます。
自分を高める力は、成長のために自分を変革させる能力を指します。新しい物事にも関心・意欲をもつスキルや、自らのモチベーションを引き出すスキル、最後まで諦めずにやり抜くスキルなどが当てはまります。
他者と関わる力は、集団生活を円滑に進めるための能力です。他人は自分とは違う価値観をもつことを理解し、相手の感情や思考を想像して行動できるスキルを指します。
非認知能力を育む土台となる要素
非認知能力を育むには、土台となるアタッチメント(愛着)が必要です。アタッチメントとは、人と人との感情的なつながりを指すものです。
幼児期に母親と日々の生活や遊びの中で、アタッチメントを形成できれば、その後の成長段階でも良い結果を得やすいといわれています。アタッチメントを正しく形成できると、その後の意欲や主体性、自制心の醸成につながっていきます。
非認知能力は大人になってからも鍛えられる
非認知能力にはアタッチメントが必要だと説明しましたが、これは「大人になった社会人では非認知能力を高められない」という話ではありません。
非認知能力には大きく3つの階層があり、「表面的なもの」「意識によって変えられるもの」「先天的に形成されるもの」に分けられます。
そのうち、意識によって変えられる価値観・自己認識・行動特性は、社会人に必要な非認知能力であり、社員教育によって高めることが可能です。
特に自制心や協調性、忍耐力、人間関係におけるスキルなどは大人になった後のほうが高めやすいともいわれています。
社員の非認知能力を育てる方法
社員が非認知能力を養うことにより、企業側には多くのメリットが発生します。
社員が自らの感情や思考を客観的に把握してコントロールできるようになれば、目の前の物事に対して常にポジティブな行動ができるようになります。
自己成長や自己実現を主体的に考えられるようにもなるため、具体的な行動を起こしやすくなるでしょう。
総じて、能力開発やキャリア自律につながるため、組織力の向上や生産性の向上を実現できます。
会社が非認知能力を育てるには、下記のポイントが重要ですので、押さえておきましょう。
- 意識改革:自分がこうなりたい、こう在るべきという意識のベースをつくること
- 課題の発見:自分に足りないもの、必要なものは何かを考えること
- 行動特性:どんな状況でもスキルを発揮できるようにすること
具体的な方法を紹介します。
理想の在り方について意識させる
まずは、自分がこうなりたい、こう在るべきという意識のベースをつくることが重要です。
経営破綻を経験したある企業では、再建する際にフィロソフィ(理念)の策定から始めたそうです。パーパスを実現するために、企業の考えや社員の行動はどうあるべきかを共有することで、意識改革が進んだのです。
会社側から自社の社員がもつべき意識や価値観などを伝え、理想の在り方についての意識付けを促しましょう。共通の認識が生まれ、向かうべき方向を捉えることができます。
自分にとって何が必要かの気づきを与える
理想のあり方についての意識付けができたら、会社側が伝えた理想の状態を踏まえて、社員自身に何が足りないのか、何があれば達成できるのかを考えてもらいましょう。
自身の性格や気質を客観的に知ることで、必要な非認知能力は何かが見えてきます。
1on1ミーティングなどの対話の機会に上司からの客観的な評価を伝え、自己認識を促すことも有効です。
具体的な行動の習慣化を促す
足りない能力や伸ばしたい能力を鍛えるための方法を実践してもらいましょう。
例えばレジリエンスを鍛えるために、感情のくせや思い込みに気づき対処したり、自己効力感を高めたりする方法があります。これらを学び、記憶して、身に付けるという流れを繰り返し行います。
学ぶだけでは、実際の行動変化に結びつくことはありません。日々の意識と実践を通じて、スキルを本質的に身につけることが大切です。
まとめ
非認知能力は、変化の激しい現代に適応し、成長し続けるための重要な要素です。これからの人材教育においては、可視化できる能力だけでなく、社員の内面的な能力に着目することが大切です。
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では逆境やトラブル、ストレスに直面した際にしなやかに適応し、速やかに立ち直る力(レジリエンス)を養うためのノウハウを蓄積しています。
下記の資料では、社員のレジリエンスを育む方法についてまとめています。
社員の心の成長や能力開発に課題を感じている人事担当者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。
レジリエンスが高い「個人」と「組織」のつくり方
ストレス状態を把握し、速やかに立ち直る!
「ストレスにしなやかに適応し、素早く立ち直る力」であるレジリエンスを高めるポイントをまとめました。
- レジリエンスが注目されている背景
- 「個人」のレジリエンスを高める3つのステップ
- 「組織」のレジリエンスを高めるポイント
- おわりに
この機会に下記より資料をご請求ください。
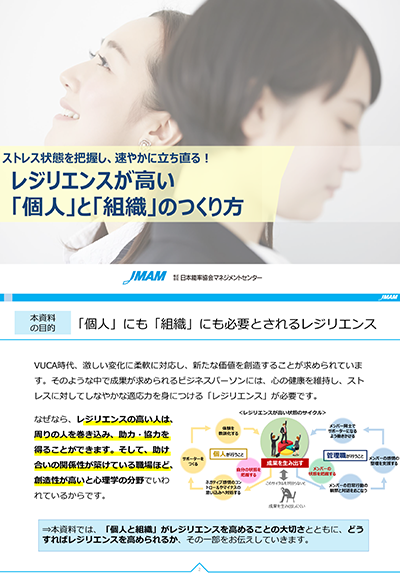
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます