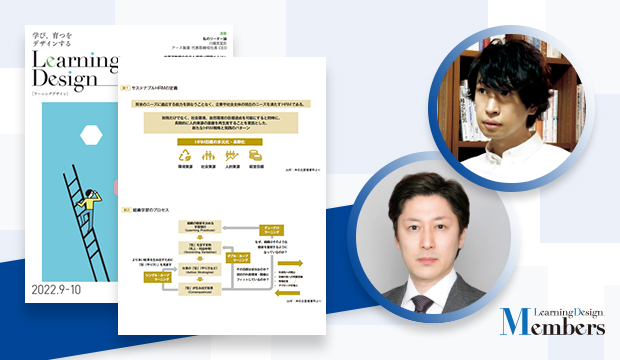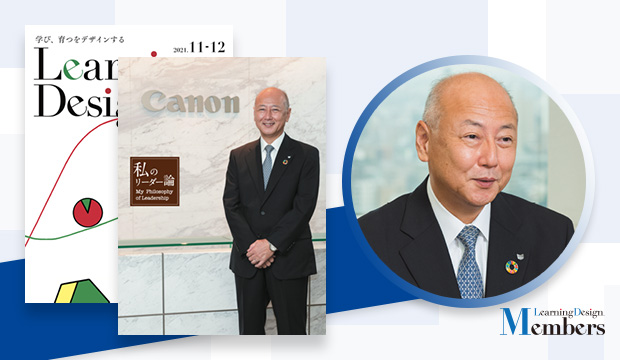企業のESGの重要性の高まりや、SDGsの推進等によって、国際社会におけるサステナビリティへの取り組みが必須となっています。サステナビリティは、企業の持続的な価値創造に影響を及ぼし、企業経営の根幹をなす要素となっていくでしょう。
そこで注目を集めているのが、「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」という新しい概念です。SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくことと、そのための変革を指します。この記事では、SXの詳細情報や求められている背景、具体的な事例などをわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
関連資料
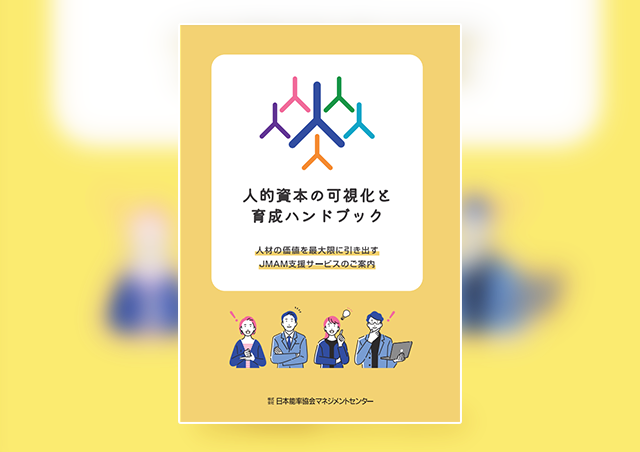
関連資料
人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内
人的資本の可視化と育成ハンドブック
SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは ?
SXとは、不確実性の高まる環境下において、社会および企業のサステナビリティ(持続可能性)をより重視した経営を行う、という考え方です。正式名称は、「サステナビリティ・トランスフォーメーション(sustainability transformation)」です。経営方針や投資家との関係性を見直し、中長期的に企業価値を向上させていくことを目指します。
2020年8月に発行された、経済産業省の「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」中間取りまとめによれば、SXは下記のように定義されています。
「企業のサステナビリティ」(企業の稼ぐ力の持続性)と「社会のサステナビリティ」(将来的な社会の姿や持続可能性)を同期化させる経営や対話、エンゲージメントを行っていくことが重要であるとし、こうした経営の在り方や対話の在り方を「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」と呼ぶ
出典:「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」中間取りまとめ
(https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828011/20200828011.html)
企業の持続可能性(サステナビリティ)
持続可能性(サステナビリティ)には、大きく2つの観点があります。
1つめは、「企業の持続可能性(サステナビリティ)」です。上述した経済産業省の資料によれば、「企業の稼ぐ力の持続性」と言い換えられています。
ビジネスにおいて、企業本来の「稼ぐ力」が重要なのは言うまでもありませんが、SX時代では、その「稼ぐ力」を長期的に維持・向上していかなければなりません。現時点での事業活動の成功具合だけに注目するのではなく、将来の市場においても、現在以上の競争優位性を保っていく必要があります。
ゆえに、以下のような取り組みが重要になってくるでしょう。
- 将来性を見据えながら、事業のポートフォリオを見直していく
- 自社ならではの強みを明確にし、イノベーションの創出に力を入れる
- 中長期的な視点で、企業価値を高める経営をしていく
また、SXに取り組み、自社の持続可能性を明示することは、「信用の獲得」にもつながります。自社のステークホルダー(利害関係者)に良い印象を与えるため、「資金調達や利益確保しやすくなる」というメリットが生まれるでしょう。
社会の持続可能性(サステナビリティ)
2つめは、「社会の持続可能性(サステナビリティ)」です。同じく経済産業省の資料によれば、「将来的な社会の姿や持続可能性」と言い換えられています。
昨今、コロナ禍やロシア・ウクライナ戦争など、ビジネス環境を激変させるような予測不可能な出来事が次々と起こっています。
このような不確実性が高い社会において、企業が持続的に成長していくためには、将来の社会の姿を具体的に描き、そこから逆算してビジネスを進めていくことが大切です。
また、詳しくは後述しますが、SDGs(持続的な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)に目を向けてみることも重要です。
SXとDX(デジタル・トランスフォーメーション)の違いとは?
SXと似ているワードで「DX」があります。両者は確かに似たようなワードではありますが、その意味はまったく異なります。そこでこの章では、「SXとDXの違い」について簡単に解説します。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)とは、デジタル技術を用いながら業務改革を起こすことです。デジタルテクノロジーを用いて業務の効率化・競争優位性の確保などを目指します。
一方、SXは、事業活動の持続可能性(サステナビリティ)を重視した取り組みのことです。中長期的な視点で事業変革を行い、企業価値の持続的な向上を目指します。
SXとDXは相反するものではなく、どちらか片方だけに取り組めばよいわけではありません。たとえば、サステナビリティを目的とした事業を行う際に、その効果を高めるためにデジタルツールを活用するといったことが考えられるでしょう。
両者を統合し、様々な視点から事業戦略を考えていくことが大切です。
なお、DXに取り組む際には、以下の記事を参考にしてみてください。
SXが注目される背景とは?
世の中の不確実性が高まってきたこと、社会全体でサステナビリティへの要請が高まってきたことを受け、企業は中長期的に企業価値を向上させなければ生き残れない時代となりました。そこで注目を集め出したのが「SX」です。
また、政府(経済産業省)が、「価値協創ガイダンス2.0」をアップデートしたこと、および「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめたことも背景の一つだと言えるでしょう。「価値協創ガイダンス2.0」とは、SXの意義や重要性について明示した報告書であり、SXを経営改革に落とし込むための実践的なフレームワークでもあります。
また、「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」とは、SX研究会(サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会)の報告書として、SXの実践の重要性を述べるとともに、SXの実現に向けた具体的な取組を整理したものです。
出典:価値協創ガイダンス2.0/伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)|経済産業省
(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220831004/20220831004-a.pdf)
さらに、SXを語る上では、以下の3つの観点が重要になります。
SDGs(持続可能な開発目標)の観点
SDGsとは、2015年9月に国連総会で採択された開発目標・行動計画のことで、「Sustainable Development Goals」の略語です。持続可能な世界を実現するため、多様性に富んだ社会を実現するために、「17の目標」と「169のターゲット(具体指標)」が示されています。
企業がSXを推進することは、SDGsを達成することにつながり、ひいては投資家・消費者からの信頼獲得にもつながります。
ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点
ESGは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の頭文字を組み合わせた言葉です。
2006年、国連は、投資に関する行動指針として「PRI(責任投資原則)」を発表しました。その中で、投資判断の新しい基準として「ESG(環境・社会・ガバナンス)」が紹介されています。
ESGに配慮した経営ができていれば、「将来性のある企業」「持続性のある企業」と判断され、株主や投資家からの評価も高まります。逆に、ESGへの配慮なくして、SXの実現は不可能だと言えるでしょう。
人的資本経営の観点
投資家は、企業への投資判断を行う際、財務状況だけでなく人的資本情報もチェックしています。当たり前ですが、企業を支えているのは人(人的資本)です。ゆえに、人的資本を重要視していない企業は、残念ながら持続的な成長は見込めません。
既に、欧米の上場企業などは、人的資本(Human Capital)に関する情報の開示が義務付けられています。
日本でも、人的資本情報の開示義務化に向けて、政府が様々な動きを見せています。2023年3月期より、大手企業4000社を対象として、有価証券報告書(有報)に人的資本情報(人材投資額や社員満足度など)の記載が求められるようになりました。
なお、人的資本経営について詳しく理解したい方は、以下の記事をご参照ください。
SXを推進するために必要なダイナミック・ケイパビリティ
この章では、SXを推進するために必要な「ダイナミック・ケイパビリティ」について解説します。
ダイナミック・ケイパビリティとは?
ダイナミック・ケイパビリティとは、簡単に言うと、「企業変革力・企業対応力」です。カリフォルニア大学バークレー校のデイヴィッド・J・ティース教授が、戦略経営論の中で提唱した言葉です。
政府が発表した「製造基盤白書(ものづくり白書)2020年版」では、以下のように定義されています。
ダイナミック・ケイパビリティとは、環境や状況が激しく変化する中で、企業が、その変化に対応して自己を変革する能力のことである。
出典:製造基盤白書(ものづくり白書)2020年版|経済産業省
(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_html/honbun/101021_2.html)
具体的には、以下の3つの能力を指します。
- 変化を感知する【感知力(Sensing)】
まず、感知力(Sensing)です。これは、自社にとっての脅威やトラブルなどを感知・推測する能力のことを指します。
企業が生き残っていくためには、自社の状況や外部環境などを客観的に分析し、「変革が必要なくらい危機的な状況なのかどうか」を素早く感知しなければなりません。 - 機会を捉える【捕捉力(Seizing)】
続いて、捕捉力(Seizing)です。これは、適切なタイミングで現状の資産や技術を再編成して、競争力を獲得するような能力です。
まずは、変革すべきタイミングを捉えることが大切です。その後、具体的にどのような変革を行うべきなのかを考えます。自社が保有している資産・知識・技術を見直し、再構成しながら、競争力を高めていきましょう。
また、現状のデータやテクノロジーだけに依存するのではなく、将来を見通した情報収集・技術変革が求められます。 - 変化する【変容力(Transforming)】
最後に、変容力(Transforming)です。これは、生み出した競争力を持続的に有効活用するため、組織全体を刷新していく能力です。
たとえば、「現状の組織構造を組み替える」「人事制度を大きく見直す」といったイメージです。また、組織変革は一度で完結するものではありません。継続的に社内を刷新し、活性化させながら、理想的な状態へと変容していきましょう。
ダイナミック・ケイパビリティを強化するには?
企業が持続的に成長していくためには、ダイナミック・ケイパビリティを身につけるだけでなく、強化していく必要があります。そのために大切なのは、積極的に新しいデジタル技術を取り入れ、社内に浸透させることです。
たとえば、デジタル技術を導入し、迅速なデータ収集や正確なデータ分析が可能になれば、「感知力(Sensing)」や「捕捉力(Seizing)」は大きく向上するでしょう。また、「変容力(Transforming)」を高めるためには、DXへの取り組みが必要不可欠です。
デジタルデータを取り扱う技術がなければ、外部環境の変化を素早く察知することも、柔軟に変容していくことも難しくなるでしょう。
SXを実践している企業事例
日本社会においては、まだSXへの取り組みは進んでいないのが現状です。一方、SXを実践し、既に成果を出している企業も存在します。この章では、「SXの企業事例」を3件紹介します。
ユニリーバ
ユニリーバは、イギリスのロンドンに本社を構える、世界的な一般消費財メーカーです。
2010年、同社は「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン(USLP)」を導入しました。USLPとは、簡単に言うと、ビジネスとサステナビリティの両立を目指すプランです。「すこやかな暮らし」、「環境負荷の削減」、「経済発展」の3つの分野において、50個以上の数値目標を設定しました。
たとえば、USLPの実践を通して、工場からのCO2排出量を65%削減することに成功しています。また、水使用量を47%、廃棄物量を96%も削減しています。
さらに2021年、同社は「ユニリーバ・コンパス」という成長戦略を策定しました。「地球の健康を改善する」、「人々の健康、自信、 ウェルビーイングを向上させる」、「より公正で、より社会的に インクルーシブな世界に貢献する」という3つの分野で、具体的な数値目標を掲げ、SXの実現を目指し続けています。
出典:ユニリーバ「地球と社会」
(https://www.unilever.co.jp/planet-and-society/)
富士通
富士通は、日本を代表する大手電子機器メーカー・ITベンダーです。
グループ全体でSXに取り組んでおり、2020年には、企業パーパスを「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」に刷新しました。
さらに、パーパスの実現を目指すため、2021年には「Fujitsu Uvance」という新事業ブランドを策定しました。サステナブルな社会をつくるため、以下の7つの分野に注力しながら、様々な取り組みを始めています。
- Sustainable Manufacturing
- Consumer Experience
- Healthy Living
- Trusted Society
- Digital Shifts
- Business Applications
- Hybrid IT
また、同社は、SXを社内に浸透させるために、「サステナビリティ貢献賞」という社内評価制度を用意しています。2022年度は、富士通グループ各社から166件の応募があり、大賞2件、優秀賞7件が選ばれました。
出典:富士通「Our story」
(https://www.fujitsu.com/jp/about/purpose/)
みずほファイナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループは、みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券などを傘下に置く、日本の大手金融グループです。
富士通と同様に、グループ全体でSXの推進に取り組んでいます。脱炭素化や資源循環、生物多様性の保護、人的資本など、様々な角度からアプローチしているのが特徴的です。
また、同社には約1,000名の「サステナビリティ経営エキスパート(みずほ所属のCSR検定2級合格者が対外的に名乗ることができる名称)」が在籍しており、自社だけでなく、お客様企業のSX推進も支援しています。
出典:<みずほ>のサステナビリティ
(mizuho-fg.co.jp/csr/mizuhocsr/index.html)
まとめ
今回は、SXの詳細情報や求められている背景、具体的な事例などを紹介しました。
不確実性の高まる環境下において、企業が生き残り続けるためには、SXの実現が欠かせません。ぜひ当記事を参考にしながら、SXに関する理解を深め、中長期的な企業価値の向上を目指してください。
なお、企業の持続的な成長のためには、人材の価値を最大限引き出すような「人的資本経営」の実践が必要不可欠です。
「人的資本経営」のポイントをまとめた資料を用意しましたので、こちらよりぜひダウンロードください。
人的資本の可視化と育成ハンドブック
人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内
人的資本経営を推進する際のポイントについて解説しながら、「人的資本の可視化」と「人材育成施策の改善」を支援するJMAMのサービスについてご案内しています。
- 人的資本経営が注目される背景
- 情報開示をする際のポイント
- 具体的にどう測るのか
この機会に下記より資料をご請求ください。
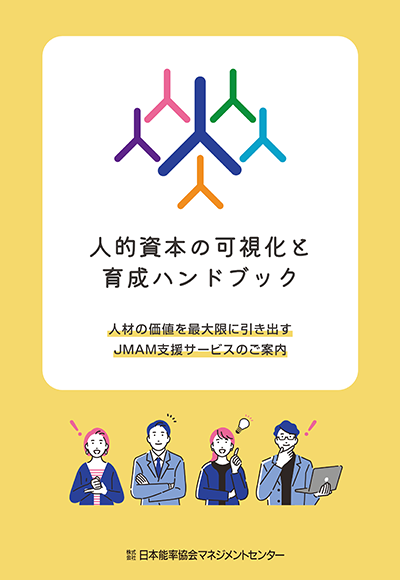
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
-
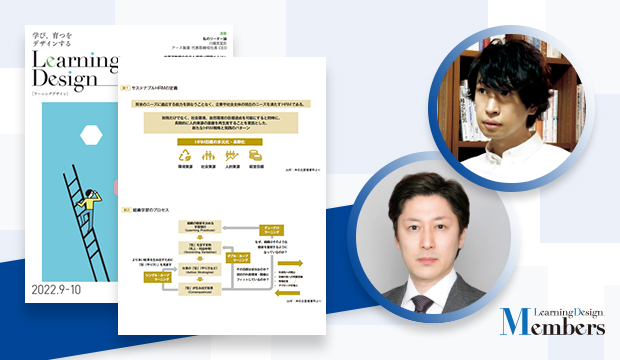 「サステナブル人事」入門~持続可能性を実現するための人事とは~
「サステナブル人事」入門~持続可能性を実現するための人事とは~ -
 石坂産業|‟地域に愛される会社“を目指した取り組みが 社員の挑戦を後押しする
石坂産業|‟地域に愛される会社“を目指した取り組みが 社員の挑戦を後押しする -
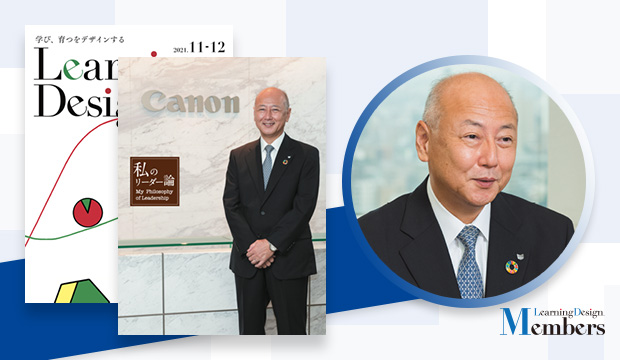 キヤノンマーケティングジャパン|社会課題の解決には技術だけでなく人間力も必要感性を持ったDX人材を育成
キヤノンマーケティングジャパン|社会課題の解決には技術だけでなく人間力も必要感性を持ったDX人材を育成
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます