- 対象: 管理職
- テーマ: マネジメント
- 更新日:
部下育成の悩みを抱える人へ|失敗する原因と成功するポイントを解説

上司による部下育成は業績を上げるため、ひいては企業が発展するにあたり欠かせない課題です。しかし、実際に部下育成を試みても結果につながらず、困っている人もいることでしょう。
そこでこの記事では、部下育成に失敗する原因や成功させるポイント、具体的な育成方法について解説します。部下育成に悩んでおり効果的な育成方法を検討しているマネジャーや、マネジャーに部下育成能力を高めてほしいと考えている人材育成担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
部下育成に失敗する原因とは
部下が思うように育たないことには様々な原因がありますが、ここでは一般的に多い5つのケースについて解説します。
感情的・高圧的になっている
部下が自分の思うように動いてくれないと苛立つこともあるでしょう。しかし、感情的・高圧的な態度を取ると部下が心を閉ざし、萎縮してしまう可能性もあります。
部下が自ら考え、質問し、行動しやすい環境づくりが大切です。
自分の価値観を押し付けている
ときには部下にアドバイスすることも大切ですが、そのアドバイスが自分の考えや方法の押し付けとなっている場合、部下は自分の考えを言わなくなり、最終的には考えなくなります。無理な意思の抑圧は反発につながる恐れもあるため、部下にも行動や意思決定の選択権を与え、自律的な行動をうながすようにしましょう。
部下の仕事に手を出してしまう
部下に仕事を任せていると、ミスへの心配や作業の遅さから、自分がやった方がいいと判断してしまう場合もあるでしょう。しかしそこで部下の仕事を奪ってしまうと、部下が経験を積む機会を奪ってしまいます。また、自分に任せてもらえないことに対し、部下が自信を失くす可能性もあります。
考えてもらう時間を与えていない
部下の成長を望むなら、部下が自ら考え行動する経験を積ませることが大切です。
行動の選択や決定を部下に任せることは上司にとってリスクがあり、やるべきことを細かく指示したほうが仕事はスムーズですが、部下の成長の機会を奪いかねません。
細かい作業を指示する場合でも、この作業は何のために行っているのかなど、目的を意識させるといった工夫が必要です。部下が自分の仕事の意味や進め方を考えられるようにしましょう。
信頼関係ができていない
信頼関係が構築されていないために部下に対する評価を適正にできず、間違った育成方法を取り失敗しているケースもあります。信頼関係を構築するためには、普段からの部下との頻繁なコミュニケーションが必要です。
部下育成を成功させるためのポイント
ここまでに解説した原因を把握したうえで、次に紹介する7つのポイントを押さえながら、部下育成に取り組むとよいでしょう。
対等な関係を意識する
普段から部下の話に耳を傾けるように心がけ、上司が相手でも、部下が自分の意見を気軽に言える関係を築いておくことが大切です。発言や意見交換をする機会もなく指示を受けるだけの仕事は、やりがいがないためモチベーションの低下につながります。部下の業務をサポートする際、部下の意見を尊重しながら行うことで対等な関係を築きやすくなるでしょう。
関連コラム 心理的安全性の高い職場の作り方 生産性を上げるGoogle流マネジメント手法も解説
自分の考えを押し付けないように注意する
部下を一人前に育てたいなら口を出したい気持ちは抑えて、部下にも考える時間を与えなければなりません。上司がやるべきことは自分の考えを部下に認めさせることではなく、部下の考えを理解しそのサポートをすることです。経験不足や知識不足で部下が誤った判断をしそうなときなどに、適宜上司として手本を見せてあげるとよいでしょう。
できるだけ部下に任せる
部下の指示待ちを習慣化させないためには、仕事を積極的に任せることも大切です。部下が主体的に行動した結果、失敗する可能性もありますが、すべての経験が部下にとっては成長の糧となります。
仕事を任せる際には、自信につながる成功体験を部下が少しでも多く重ねられるように、上司が目標設定からサポートしてあげるのもよいでしょう。
プロセスも評価する
部下を評価する際には、成果だけではなくそこに至るプロセスや考え方にも目を向けることが大切です。仕事では成果を出すことが重要ですが、成果が出なかった取り組みでも、フィードバックして将来的に成果へつなげられれば、結果として有意義となります。
なお、フィードバックとは、言動からみられる改善点や評価ポイントを本人に伝え、改善や成長を促すことです。
関連コラム ビジネスにおけるフィードバックの意味とは?具体的な手法やすぐに使える例文を解説
定期的に進捗報告をしてもらう
突然のトラブル時でも何をすべきか迅速に判断できるように、部下が進捗状況を細かく定期的に報告する体制を整えておきましょう。また、報告を受けて終わるのではなく、報告内容に対して適切なフィードバックを行うことも大切です。
キャリア・アンカーを活用する
キャリア・アンカーとは、キャリアを選択する際に変えられない価値観や欲求などがあるという概念で、アメリカの組織心理学者が提唱したものです。
指導で変えられない部下の根幹にある考えや価値観を、上司がしっかり理解しておけば、適切な指導やアドバイスができ、信頼関係を築きやすくなります。適性にあった人材配置や個々に応じた育成もできるようになるため、学んでおくとよいでしょう。
コミュニケーションで理解を深める
部下の性格や価値観を理解できる機会として、日頃から部下とコミュニケーションを取るように心がけましょう。部下それぞれの性格や価値観を理解し、個々にあった育成方法を取り入れることが部下を成長させるためには有効です。
また、自分への理解が深い上司の前では安心してのびのびと仕事ができるため、部下も成長しやすくなります。
効果的な部下育成の方法とは
ここでは、部下育成に効果が期待できる方法を具体的に5つ紹介します。実践するときの参考にしてください。
コーチング
コーチングとはコミュニケーションを取るなかで、上司が部下の自主性を引き出すフォローを行うことにより、部下の成長を促す方法です。
知識などを一方的に与えて育てるティーチングと比べると、成果が出るまでに時間がかかり、結果は上司の腕次第となる方法ですが、部下の主体性を大切にしながら無理をさせずに育成できます。
1on1ミーティング
1on1(ワンオンワン)ミーティングとは、部下の仕事に対する意欲を高めるために、上司と部下が1対1で行うミーティングです。
対話を通して問題提起を行い、解決に向けた対策や実行に向けたプランを立てます。定期的に実施することで人材育成のベースとなる部下の現状把握ができるほか、対策やプラン立てを部下本人に考えさせるため自主性を高められます。
関連コラム 1on1ミーティングの効果とは?注目される背景や実施のポイントを解説
OJT
OJTとは、職場で実際の仕事を行いながら先輩社員が若手社員に指導する育成方法で、正式名称は「On the Job Training」といいます。実践的な教育ができるため部下を即戦力として育てやすく、状況や各人に応じた指導もできる点が魅力です。
マネジャー自身が指導者となる場合もありますが、年長の部下がOJT担当者となり若手を教え、マネジャーはその進捗をフォローするという形が望ましいでしょう。
教える側のメンバーにとってもよい成長機会となります。
関連コラム OJT担当の役割とは?担当者育成のポイントや上司の心構えまで解説
OFF-JT
OFF-JTは「Off The Job Training」の略称です。仕事の現場で指導を行うOJTに対して、研修など、職場とは別の場所で行う育成方法を指します。知識などは座学学習をし、実践的なスキルは専門のトレーナーやスタッフが教えることが一般的です。
OFF-JTを導入すると、専門性の高い知識を集中して学べる環境を部下に与えられます。
MBO
MBO(Management by Objectives)とは、目標達成に至るまでの過程を可視化して管理し、その結果を人事評価に反映させるシステムです。目標は個人が目指すものと企業が目指すものがリンクするように、上司と部下との話し合いのなかで設定します。
個人の目標の達成が企業の成果にもつながるため、部下の仕事に対するモチベーションを上げやすい点が特徴です。
部下の状況別でとるべき行動
部下育成にあたり上司がとるべき行動は、部下の仕事に対する成熟状況に応じて決めます。ここでは、成熟レベルを4つに分類したうえでレベルごとに取るべき行動を解説します。
●レベル1:入社したばかりの人や未経験者のように、自分で何をすべきか判断できない相手には、詳細な指示を与えてこまめな確認も行うことが必要です。
●レベル2:入社2~3年目など、業務を1人でできるレベルの部下には一定の指示やサポートは行うものの、提案は部下自身に行わせて自主的な行動を促します。
この段階で、レベル1の新人のOJT担当などに任命すると、指導するために自分の業務への理解を深めるようになり、成長が見込めます。ただし、まだ自らの業務にも一定のサポートが必要な段階なので、抱え込みすぎないよう上司がこまめにフォローを入れることも必要です。
●レベル3:すでに高い能力を持っている部下なら、業務を遂行する能力は十分にあるため、サポートはしつつ、意思決定の責任は共有する方法が有効です。
●レベル4:専門家レベルに達している人の場合には業務に熟達しているため、部下とはいえ責任も含めてすべてを任せます。部門としての方向性を伝え、目的を果たすためにはどうしたらいいか、マネジャーと共に考えてもらえるような立場になると心強いです。他のメンバーの指導者になってもらうことを任せてみることも有効でしょう。
まとめ
部下育成を成功させるためには、まず部下を理解し、部下それぞれが持つ価値観や考え方、成熟度などにあった方法を上手に選び活用することが大切です。部下を理解するためには日頃からコミュニケーションを取り、対話を行うことが重要となります。
株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、新入社員から経営幹部まで、さまざまな立場や役割に応じた教育プログラムを展開しています。コーチングやOJTなどのほか、「対話」に関わる教育プログラムや情報提供なども行っていて、多様化する部下に対応した学習も可能です。その時々に注目されているテーマにも幅広く対応した内容となっているため、ニューノーマル時代に即した育成方法も習得できます。
ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方
書籍「チームワーキング」ポイント解説
チームの機能不全状態を解消し、成果を創出する
本資料は立教大学の中原淳教授・田中聡助教著『チームワーキング ケースとデータで学ぶ「最強チームのつくり方」』をベースに、チームの機能不全に悩む職場の立て直しに資する内容となっています。
- 「チームの病」を克服するために必要なチームワーキング
- チームが機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」
この機会に下記より資料をご請求ください。
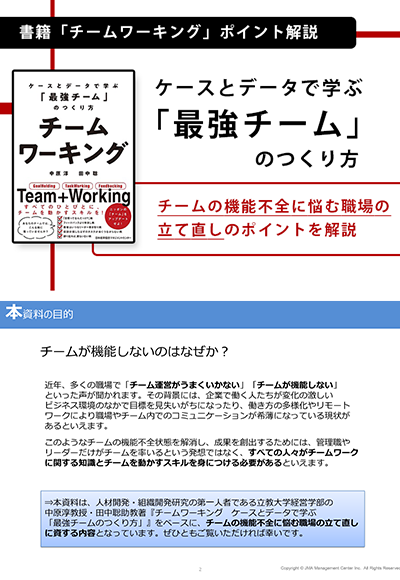
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
-
 沢渡 あまね氏|イマドキ職場の問題を整理 チーム“で”マネジメントし 抱え込まないしくみをつくる
沢渡 あまね氏|イマドキ職場の問題を整理 チーム“で”マネジメントし 抱え込まないしくみをつくる -
 イオン|ワークライフバランスの悩みを解決! 学びを通して 行動がともなう“イクボス”へ
イオン|ワークライフバランスの悩みを解決! 学びを通して 行動がともなう“イクボス”へ -
 博報堂|ツールを活用して マネジメントの暗黙知を形式知化
博報堂|ツールを活用して マネジメントの暗黙知を形式知化
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















