- 対象: 全社向け
- テーマ: マネジメント
- 更新日:
チームのレジリエンスを強化するためのマネジメント術を解説

現代の企業環境は、コロナ禍やDX推進、働き方の多様化などによって急速に変化し続けています。本記事では、チームのレジリエンスとは何かを解説し、管理職やチームリーダーが実践できる具体的なマネジメント術をご紹介します。これらの手法を身につけることで、どんな変化や困難にも柔軟に対応できる強いチームを構築できるでしょう。
関連資料

関連資料
「ストレスにしなやかに適応し、素早く立ち直る力」であるレジリエンスを高めるポイントを解説
レジリエンスが高い「個人」と「組織」のつくり方
レジリエンスとは何か?チームレジリエンスの基本概念
レジリエンスは、元々物理学で「外力を受けても元の形に戻る性質」を意味する用語です。組織やチーム運営においては、困難な状況に遭遇した際に、それ乗り越えてもとの状態に戻るだけでなく、経験を糧にして以前よりも強くなる力を指します。
個人のレジリエンスとチームレジリエンスの違い
個人のレジリエンスは、一人ひとりが持つストレス耐性やメンタル回復力を中心とした概念です。一方、チームレジリエンスは個人の能力だけでは限界があり、メンバー同士が協力し合い、組織全体として困難を乗り越える仕組みづくりが不可欠になります。つまり、チーム全体で支え合う文化や仕組みが重要な要素となるのです。
現代の企業環境におけるレジリエンスの重要性
VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる現代のビジネス環境では、従来の計画通りに物事が進むことは稀になりました。新型コロナウイルスの感染拡大、急速な技術革新、顧客ニーズの多様化など、予期せぬ変化が日常的に発生しています。
困難な状況を経験することで、チーム内のコミュニケーション強化や新たなスキルの獲得、より効率的な業務プロセスの構築など、様々な改善につなげられるのです。
「心の回復力」などと訳されるレジリエンスを促進していくために、組織は一人ひとりが持つ価値観を尊重することが大切だと語っている。フラットな立場で語り合い、互いの内面に向き合い、刺激し合い、支え合う相互作用のなかでこそ、自分らしいレジリエンスが芽生える―― 。そのような組織であれば、スムーズに失敗から立ち直り、失敗経験から学ぶ姿勢に転じていけるということだ。
引用元:失敗から学ぶ組織に必要な「自発性」と「関わり合い」
https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=22257
レジリエントなチームの4つのタイプ
研究によると、レジリエントなチームには大きく分けて4つのタイプが存在します。それぞれの特徴を理解することで、自分のチームがどのタイプに当てはまるかを把握し、適切なマネジメント手法を選択できます。
| タイプ | 特徴 | 対処法 |
|---|---|---|
| バネ型 | 困難から素早く回復し、元の状態に戻る | 迅速な問題解決と効率重視の仕組みづくり |
| 風船型 | 柔軟性が高く、様々な状況に適応できる | 多様性促進と創造性を活かす環境整備 |
| 起き上がりこぼし型 | 困難や大きな変化を受け流し、素早く対処する | 優先順位の明確化とリスク評価の徹底 |
| 柳型 | しなやかに曲がりながら折れない | 長期視点での戦略立案と継続的改善 |
チームレジリエンスを構成する3つの基礎能力
強いレジリエンスを持つチームには、共通して備わっている3つの基礎能力があります。これらの能力を意識的に育成することで、どのような困難な状況にも対応できるチームを構築できます。
コミュニケーション力の向上
レジリエントなチームの最も重要な要素は、オープンで率直なコミュニケーションです。メンバー全員が自分の意見を安心して発言でき、建設的な議論を通じて最良の解決策を見つけられる環境が必要です。心理的安全性が確保されたチームでは、失敗や困難な状況についても隠すことなく共有され、早期の問題解決につながります。
具体的には、定期的な1on1ミーティングの実施、匿名での意見収集システムの導入、などが効果的です。また、リーダー自身が率先して自分の失敗や課題について話すことで、メンバーも安心して本音を語れるようになります。
多様性受容と相互支援体制の構築
異なる背景や専門性を持つメンバーが集まるチームほど、多角的な視点から問題を分析し、創造的な解決策を生み出せます。年齢、性別、職歴、価値観などの多様性を受け入れ、それぞれの強みを活かせる環境づくりが重要です。
相互支援体制では、メンバー同士がお互いの業務を理解し、困った時には自然に助け合える関係性を築くことが大切です。具体的には、スキルマップの作成による能力の可視化、ローテーション制度の導入、メンター制度の活用などが挙げられます。これにより、特定の人に業務が集中するリスクを分散し、チーム全体の適応力強化につながります。
学習継続と改善文化の醸成
レジリエントなチームは、困難な経験を単なる試練として終わらせるのではなく、必ず学習の機会として活用します。失敗を許容する文化を育て、挑戦を奨励する企業文化の構築が不可欠です。
定期的な振り返りの機会を設け、何がうまくいったのか、何が改善できるのかを客観的に分析します。その結果をドキュメント化し、チーム内で共有することで、同じ失敗を繰り返すことなく、組織全体の成長につなげられます。また、外部研修への参加や他部署との交流を通じて、新たな知識やスキルを継続的に取り入れることも重要です。
困難発生時の段階別マネジメント手法
チームが実際に困難な状況に直面した際には、段階に応じた適切な対応が必要です。事前準備から回復・成長まで、それぞれのフェーズで効果的なマネジメント手法を実践することで、チーム全体のレジリエンスを最大限に発揮できます。
事前準備段階でのリスク評価とシナリオプランニング
困難が発生する前の準備段階では、想定されるリスクを洗い出し、それぞれに対する対処法を事前に検討しておくことが重要です。シナリオプランニングを活用して、最悪の事態から最善の結果まで複数のパターンを想定し、それぞれに対応するアクションプランを策定することで、実際の困難に冷静に対処できます。
具体的には、月次でのリスク評価会議の実施、業界動向や競合他社の動きの継続的な監視、緊急事態対応マニュアルの作成と定期的な見直しなどが効果的です。また、メンバー全員がリスク意識を共有できるよう、定期的な情報共有の場を設けることも大切です。
危機発生時の迅速な意思決定と役割明確化
実際に困難な状況が発生した際には、迅速かつ的確な意思決定が求められます。平時から意思決定プロセスを明確にし、緊急時には誰がどのような権限を持って判断するかを全員が理解していることが不可欠です。
危機管理においては、情報収集、現状分析、対策立案、実行、効果測定という一連の流れを素早く回すことが必要です。この際、役割明確化により各メンバーが自分の責任範囲を正確に把握し、重複や漏れのない対応を実現できます。また、定期的な進捗共有により、状況の変化に応じて柔軟に戦略を修正することも大切です。
回復段階でのフィードバック文化の活用
困難な状況を乗り越えた後の回復段階では、経験から得られた学びを確実に組織の財産として蓄積することが重要です。フィードバック文化を通じて、成功要因と改善点を客観的に分析し、次回以降に活かせる形で知識として蓄積します。
振り返りの際には、個人の責任追及ではなく、プロセスや仕組みの改善にフォーカスすることが大切です。また、困難を乗り越えた経験は、チームの一体感を高め、自信と達成感を共有する貴重な機会でもあります。成功体験を積極的に評価し、メンバーのモチベーション向上につなげることで、さらに強いチームを構築できます。
心理的安全性を高めるマネジメント実践法
心理的安全性は、チームレジリエンスの土台となる最も重要な要素です。メンバー全員が安心して本音を語り、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えることで、チーム全体の適応力と回復力を大幅に向上させられます。
失敗を学びの機会に変える仕組みづくり
レジリエントなチームでは、失敗を責めるのではなく、貴重な学習機会として捉える文化が根付いています。失敗事例を積極的に共有し、そこから得られた教訓を全員で共有することで、同じミスの再発防止と新たな気づきの獲得を同時に実現できます。
具体的な取り組みとしては、失敗事例データベースの構築、改善提案制度の導入などがあります。重要なのは、失敗を個人の問題ではなく、チーム全体で解決すべき課題として捉えることです。
オープンなコミュニケーション環境の整備
心理的安全性の高いチームでは、階層や立場に関係なく、誰もが自由に意見を述べられる環境が整っています。定期的な対話の場を設け、様々な視点からの意見交換を促進することが大切です。
効果的な手法として、順番に全員が発言するラウンドロビン方式での意見収集、匿名での提案システム、逆さピラミッド型の会議運営などがあります。重要なのは、形式的な場だけでなく、自然な対話が生まれる環境を意識的に作り出すことです。
多様な価値観を受け入れる組織風土の醸成
チームメンバーの多様性を真に活かすためには、異なる価値観や働き方を受け入れる柔軟な組織風土が必要です。年齢、性別、国籍、職歴などの違いを強みとして活用し、創造性と問題解決能力を向上させられます。
多様性促進の具体策として、インクルーシブリーダーシップの研修実施、メンタリング制度の充実、フレキシブルな働き方制度の導入などがあります。また、チームビルディング活動を通じてメンバー同士の理解を深め、お互いの強みを認識できる機会を定期的に設けることも重要です。多様性を受け入れるチームは、様々な角度から問題を分析し、より革新的な解決策を生み出すことができます。
目標設定と自主性促進によるチーム強化
レジリエントなチームを構築するためには、明確な目標設定と各メンバーの自主性を促進する仕組みづくりが欠かせません。共通のビジョンを持ちながら、個人の主体性を最大限に発揮できる環境を整えることで、困難な状況でも一致団結して立ち向かえるチームが形成されます。
共有ビジョンに基づく目標設定の重要性
チーム全体で共有するビジョンと目標があることで、困難な状況に直面してもメンバー全員が同じ方向を向いて行動できます。明確で具体的な目標設定により、各メンバーが自分の役割と責任を正確に理解し、主体的に行動する基盤を作ることができます。
効果的な目標設定のためには、SMART原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・時間的制約)を活用し、短期目標と長期目標のバランスを取ることが不可欠です。また、目標達成のプロセスにおいて、定期的な進捗確認と必要に応じた軌道修正を行うことで、変化する環境に柔軟に対応できます。メンバー全員が目標設定のプロセスに参加することで、オーナーシップ意識も高まります。
権限委譲と意思決定の分散化
自主性の促進には、適切な権限委譲と意思決定プロセスの分散化が不可欠です。マイクロマネジメントではなく、各メンバーが判断できる範囲を明確にし、その範囲内での自由な行動を奨励することが大切です。
委譲した権限の範囲と責任を明文化し、定期的な振り返りを通じて適切な調整を行うことも重要です。これにより、緊急時にも各メンバーが迅速に判断・行動できる体制を構築できます。
成果評価と継続的な成長支援
自主性を促進するためには、成果に基づいた公正な評価システムと、継続的な成長をサポートする仕組みが必要です。個人の努力と成果を適切に評価し、さらなる挑戦を後押しする文化を醸成することが大切です。
効果的な評価システムには、定量的な指標だけでなく、チームへの貢献度や困難な状況での対応力なども含めることが重要です。また、評価の結果を次の成長目標設定につなげ、個人のキャリア開発とチームの目標達成を両立させる取り組みが求められます。メンター制度や内部研修制度を充実させることで、メンバー全員が継続的にスキルアップできる環境を整えることも大切です。
実践事例から学ぶレジリエンス向上のポイント
理論だけでなく、実際の企業や組織での取り組み事例を参考にすることで、より具体的で実践可能なレジリエンス向上策を学ぶことができます。成功事例から共通するポイントを抽出し、自組織の状況に応じてカスタマイズして活用することが重要です。
危機を成長機会に変えた組織の特徴
レジリエンスの高い組織には、危機的状況を単なる困難として捉えるのではなく、組織を進化させる貴重な機会として活用する特徴があります。危機発生時に既存の枠組みを見直し、より効率的で柔軟性の高い業務プロセスや組織構造を構築することで、以前よりも強い組織へと変貌を遂げています。
危機対応を全社的に取り組む体制を整え、その過程で得た知見を平時の業務にも応用することで、組織全体の能力向上を図っています。
継続的な改善を実現する仕組みづくり
レジリエントな組織では、一度構築した仕組みに満足することなく、継続的な改善を通じてさらなる強化を図っています。定期的な見直しサイクルを設け、変化する環境に応じて仕組みをアップデートし続けることが大切です。
効果的な改善サイクルの例として、四半期ごとのレジリエンス評価、年次での危機対応訓練、他社との事例共有会などがあります。これらの活動を通じて、現状の課題を客観的に把握し、具体的な改善策を立案・実行します。
メンバー全員が参加できる文化づくり
真にレジリエントなチームでは、リーダーだけでなく、すべてのメンバーが主体的にレジリエンス向上に貢献できる文化が根付いています。階層に関係なく、誰もが改善提案や課題の指摘を行える環境を整えることが重要です。
全員参加の文化を醸成するためには、小さな改善提案でも積極的に評価し、実現可能なものは迅速に実行に移すことが大切です。また、改善活動への参加を評価制度に組み込み、貢献度に応じた適切な認識を与えることも効果的です。
まとめ
本記事では、現代の不確実性の高いビジネス環境において重要となるチームレジリエンスの概念から、具体的なマネジメント手法まで幅広く解説しました。レジリエントなチームを構築するためには、単発の取り組みではなく、継続的で体系的なアプローチが不可欠です。
- レジリエンスは困難から立ち直るだけでなく、さらに強くなる力である
- コミュニケーション力、多様性受容、学習継続の3つの基礎能力が重要
- 事前準備から回復まで段階別のマネジメント手法を実践する
- 心理的安全性の確保がレジリエンス向上の土台となる
- 明確な目標設定と自主性促進により主体的なチームを構築する
- 実践事例から学び、継続的改善により組織を進化させる
自分のチームに最適なレジリエンス向上策を見つけ出し、どんな困難にも負けない強いチームづくりに取り組んでみてください。
社員の心の健康を守り、組織を強くする レジリエンス向上
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する「レジリエンス向上」プログラムは、社員一人ひとりの心の健康を支え、変化に強いしなやかな組織づくりを目指す、人事・人材育成や新人・採用ご担当者様向けのソリューションです。ストレスへの対処法を学び、逆境から立ち直る力を養うことで、社員のパフォーマンス向上と組織の活性化を支援します。
解説資料|レジリエンスが高い「個人」と「組織」のつくり方
ストレス状態を把握し、速やかに立ち直る!
「ストレスにしなやかに適応し、素早く立ち直る力」であるレジリエンスを高めるポイントをまとめました。
- レジリエンスが注目されている背景
- 「個人」のレジリエンスを高める3つのステップ
- 「組織」のレジリエンスを高めるポイント
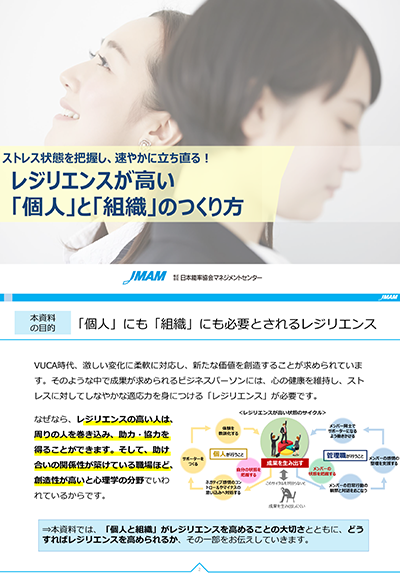
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















