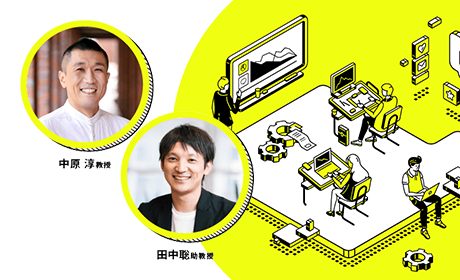- 対象: 全社向け
- テーマ: ビジネススキル
- 更新日:
チーミングとは?意味と成果を生むチームの作り方の基本

変化の激しい昨今のビジネス環境において、従来型の固定チームでは対応が困難な課題が増えています。そこで注目されているのが「チーミング」という概念です。チーミングとは、状況に応じて柔軟にメンバーを組み合わせ、多様な専門性を活かしながら成果を創出する動的なチーム運営手法です。チーミングによって、従来の枠組みに縛られないダイナミズムを生み出すことが期待されます。本記事では、チーミングの意味から具体的な実践方法まで、成果を生むチームの作り方の基本を詳しく解説します。
関連資料

関連資料
「チームワーク」を高めたい方へおススメの資料はこちら
ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方
書籍「チームワーキング」ポイント解説
チーミングとは何か 基本概念と特徴
チーミングとは、固定的なチーム構成にとらわれず、プロジェクトや課題に応じて最適なメンバーを組み合わせ、協働を通じて成果を創出するアプローチを指す言葉です。
チーミングの意味と語源
チーミング(Teaming)は、ハーバード・ビジネススクールの組織行動学者であるエイミー・エドモンドソン教授によって提唱された概念です。エドモンドソン教授は、チームを「形成されるもの」から「継続的に形づくられるもの」へと捉え直しました。従来の「チーム」は文法上、名詞であることから、固定的な集団を指すのに対し、「チーミング」は動詞とすることで、メンバーが協働する行為そのものを表現しています。チーミングによって、状況の変化に応じて柔軟に連携体制を構築できる組織運営を可能にすることを目指します。
チーミングの特徴
チーミングには、従来のチーム運営とは明確に異なる特徴があります。重要な特徴の一つは、メンバーの流動性です。固定メンバーにこだわらず、プロジェクトごとやフェーズごとに最適なメンバーを選定することで、各段階で最も適切な専門性とスキルを活用できる体制を構築します。
また、学習する組織としての側面も重要な特徴の一つです。チーミングでは、メンバー同士が互いの知識や経験を共有し、プロジェクトを進めながら継続的に学習を重ねていきます。この学習プロセスにより、個人のスキル向上だけでなく、組織全体の知識ベースも拡充されていきます。
さらに、心理的安全性の確保も重要な特徴です。多様なバックグラウンドを持つメンバーが短期間で効果的に協働するためには、オープンなコミュニケーションが不可欠であり、失敗を恐れずに意見を交わせる環境づくりが求められます。
現代ビジネスにおけるチーミングの重要性
デジタル化やグローバル化が進む現代において、チーミングの重要性はますます高まっています。新規事業の立ち上げ、技術革新への対応、市場変化への迅速な適応など、不確実性の高い環境下では、柔軟な連携によって多様な知見を素早く統合できる組織が競争優位を築くことができます。
従来型チームとチーミングの違い
チーミングと従来型チームの違いを理解することで、なぜ現代の組織にチーミングが必要なのかの理解につなげましょう。
組織構造とメンバー構成の違い
従来型チームは、固定メンバーによる長期的な関係性を基盤とした組織構造です。一方、チーミングでは、プロジェクト型組織として状況に応じてメンバーが流動的に参加します。この違いにより、チーミングでは常に最適な専門性を持つメンバーで課題に取り組むことが可能になります。
時間軸と成果創出プロセスの比較
時間軸の違いも重要なポイントです。従来型チームは中長期的な視点で業務を継続し、段階的に成果を積み上げていくプロセスを採用していました。チームの設計や安定性に重点を置き、安定した成果の創出を目指します。
チーミングでは、短期集中型のアプローチが基本となります。特定の課題や目標に対して、限られた期間内で最大限の成果を創出することを目指します。スピードと柔軟性を両立させながら、学習サイクルを高速化して価値創造を加速するのが特徴です。
成果創出のプロセスにおいても、従来型が計画→実行→評価の直線的なプロセスを辿るのに対し、チーミングでは学習→実験→調整のスパイラル型プロセスを採用します。
チーミングがもたらすものと従来型のチームの欠点
従来型チームは安定性と継続性に優れていますが、環境変化への適応に時間がかかる傾向があります。チーミングでは、多様性とスピード感を重視することで、イノベーション創出に必要な新しい視点や発想を生み出しやすくなります。
チーミングが注目される背景
なぜ今、多くの組織でチーミングが求められているのでしょうか。その背景には、現代社会の構造変化と、テクノロジーの進歩があります。
ビジネス環境の変化と課題
現代のビジネス環境は、VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)と呼ばれる不確実性の高い状況が常態化しています。このような環境では、予測困難な変化に対して迅速かつ柔軟に対応できる組織体制が競争力の源泉となることから、チーミングによる柔軟な組織運営が期待されます。
テクノロジー進化への対応
AI、IoT、ブロックチェーンなどの新技術が次々と登場する中、単一の専門領域だけでは解決できない複合的な課題が増加しています。チーミングにより、技術者、マーケター、デザイナーなど異なる専門性を持つメンバーが協働することで、テクノロジーの革新を事業価値へと変換できる体制を構築できます。
特にデータ分析のような高度な専門領域では、他部門との連携と、それを支える人材の橋渡し的なスキルが必要です。
人事部門のDXといっても、すべてを個人や単独の部門で行う必要はありません。データ分析は専門家に任せるといったチーミングをうまく機能させる必要があります。データ分析部隊が、必ずしも人事の専門知識を持っているとは限らないので、両者をブリッジできる素養を身につけておくことが重要になってくると思います。
引用元:エンゲージメントサーベイで実現するカルチャー改革
https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=18313
働き方の多様化への適応
リモートワーク、副業、フリーランス活用など、働き方の多様化が進む中で、従来の固定チーム運営では優秀な人材の活用機会を逃してしまうリスクがあります。チーミングを行うことで、多様な働き方をする人材を効果的に活用し、組織の創造性と生産性を向上させることが期待できます。
イノベーション創出の必要性
市場の成熟化により、既存概念の延長線上では、競争相手や市場との差別化が困難になっています。チーミングによって異なる視点や経験を持つメンバーが協働することで、従来の発想を超えた革新的なアイデアや解決策を生み出す可能性が高まります。
成果を生むチーミングの要素
効果的なチーミングを実現するためには、いくつかの重要な要素を理解し、それらを実践する必要があります。まずは、それらの要素について理解を深めましょう。
目的とビジョンの共有
チーミングの成功には、メンバー全員が共通の目的意識を持つことが不可欠です。短期間で協働関係を構築するためには、プロジェクトの目標、期待される成果、各メンバーの役割を明確に定義し、共有する必要があります。明確なビジョン共有により、メンバーは自律的な判断と行動を取ることができ、効率的な協働が実現されます。
心理的安全性の確保
エドモンドソン教授が重視する心理的安全性は、チーミングの基盤となる概念です。メンバーが失敗を恐れずに意見を述べ、リスクを取って挑戦できる環境を作ることで、創造的な協働が生まれます。リーダーは、多様な意見を歓迎し、建設的な議論を促進する役割を果たします。
相互理解と信頼関係の構築
異なる専門性や背景を持つメンバーが効果的に協働するためには、相互理解が重要です。各メンバーの専門分野、経験、価値観を理解し合うことで、多様性を強みとして活用できる相互信頼関係が構築されます。
継続的学習とフィードバック文化
チーミングでは、短期間で最大の成果を上げるために、継続的な学習と改善が必要です。定期的な振り返りとフィードバックを通じて、協働プロセスを最適化し、学習する組織としての能力を向上させます。
チーミングの具体的な実践方法
ここからは、具体的なチーミングの実施方法と各プロセスを解説します。
プロジェクト設計と人材選定
効果的なチーミングの第一歩は、プロジェクトの特性を分析し、必要な専門性とスキルを明確にすることです。課題の複雑さ、期間、求められる成果を基に、最適なメンバー構成を設計します。単に優秀な人材を集めるのではなく、相互に補完し合える多様な専門性を組み合わせることが重要です。
効果的なキックオフとチーム立ち上げ
チーミングでは、短期間で効果的な協働関係を構築する必要があります。キックオフミーティングでは、以下の要素を含む包括的な立ち上げを行います。
- プロジェクトの背景と目標の詳細な説明
- 各メンバーの専門性と期待役割の明確化
- コミュニケーションルールと作業プロセスの確立
- 成功指標と評価基準の共有
コミュニケーション活性化の仕組み
多様なメンバーが効果的に協働するためには、コミュニケーションの質と頻度を高める仕組みが必要です。定期的なスタンドアップミーティング、専門知識の共有セッション、非公式な交流機会を設けることで、メンバー間の理解を深め、創造的なアイデア交換を促進します。例えば、「自己紹介×スキルマッピング」や「ペアインタビュー」などといったワークを通じてメンバー相互の背景理解を深めることで、短期間でも心理的安全性と信頼の土台を築くことが期待されます。
成果測定と改善プロセス
チーミングの効果を最大化するためには、定期的な成果測定と改善が欠かせません。プロジェクトの進捗だけでなく、チーム内の協働プロセス、メンバーの満足度、学習成果も評価指標に含めます。これにより、次回のチーミングでより効果的な協働を実現できます。
チーミング導入時の課題と解決策
チーミングを組織に導入する際には、様々な課題が発生する可能性があります。こうした課題に対処するためには、事前に発生しうる課題を予測・理解し、対策を準備することが成功の鍵となります。
組織文化との調整
従来の階層的な組織文化や部門縦割りの慣習は、チーミングの障壁となる場合があります。段階的な導入を行い、小規模なパイロットプロジェクトから始めることで、組織全体の文化変革を促進しながらチーミングの価値を実証することができます。
リーダーシップスタイルの変化
チーミングでは、従来の指示命令型リーダーシップではなく、サーバント・リーダーシップやファシリテーション型のリーダーシップが求められます。リーダーは、メンバーの自律性を尊重し、協働を支援する役割にシフトする必要があります。
評価制度と人事戦略の見直し
個人評価中心の従来の人事制度では、チーミングの成果を適切に評価できない場合があります。協働貢献度、知識共有、他メンバーの成長支援なども評価項目に含める包括的な評価制度の構築が必要です。
技術的基盤の整備
効果的なチーミングには、コラボレーションツール、プロジェクト管理システム、ナレッジ共有プラットフォームなどの技術的支援が重要です。適切なデジタルツールを活用することで、時間と場所の制約を超えた協働が可能になります。
チーミングで学習する組織を作るには
チーミングを活用して学習する組織を構築することで、組織全体の適応性と創造性を継続的に向上させることができます。ここでは、具体的な実践方法について詳しく解説します。
学習する組織とは
学習する組織とは、組織のメンバーが継続的に学習能力を高め、組織全体が環境の変化に適応し、成長し続ける組織のことです。ピーター・センゲによって提唱されたこの概念は、現代の変化の激しいビジネス環境において、組織の持続的な成長を実現するために不可欠とされています。
学習する組織では、個人の学習が組織の学習につながり、組織の学習が再び個人の成長を促進する好循環が生まれます。このような組織では、失敗を学習機会として捉え、新しい知識やスキルを積極的に取り入れる文化が根付いています。
チーミングは、この学習する組織の実現において重要な役割を果たします。異なるバックグラウンドを持つメンバーが協働することで、組織内の知識の多様性が高まり、学習機会が増加するからです。
イノベーション創出方法
チーミングを通じたイノベーション創出には、体系的なアプローチが必要です。まず、組織内の多様な知識と経験を効果的に組み合わせるためのプラットフォームを構築します。これには、社内の専門性データベースや過去のプロジェクト事例の蓄積が含まれます。
次に、異業種連携や外部パートナーとの協働を積極的に推進し、組織外の知識やリソースを活用します。このような外部との連携により、組織内では生まれにくい革新的なアイデアや解決策を創出できます。
さらに、失敗を恐れずに新しいアイデアを試行錯誤できる環境を整備します。イノベーション創出には実験的な取り組みが不可欠であり、短期的な失敗を許容する文化が必要です。
多様性を活かした組織運営
チーミングにおける多様性の活用は、組織の競争力向上に直結します。年齢、性別、専門分野、文化的背景などの多様性を持つメンバーが協働することで、従来にない視点や解決策を生み出すことにつながると期待されます。
多様性を効果的に活かすためには、以下のような取り組みが重要です。まず、多様な意見を受け入れる包容力を持つリーダーシップの育成が必要です。また、異なる価値観や働き方を尊重し、全てのメンバーが貢献できる環境を整備します。
さらに、多様性が生み出す創造性を最大化するために、適切なファシリテーションスキルを持つメンバーを育成します。これらの取り組みにより、組織は多様性を競争優位の源泉に変えることができます。
チーミングを支援するツールと環境整備
効果的なチーミングを実現させるためには、チーミングの仕組み作りだけではなく、適切なツールと環境の整備が不可欠です。
デジタルコラボレーションツールの活用
現代のチーミングでは、クラウドベースのコラボレーションツールが重要な役割を果たします。リアルタイムでの情報共有、ビデオ会議、共同編集機能などを活用することで、物理的な距離に関係なく効率的な協働が可能になります。
ナレッジマネジメントシステム
チーミングで得られた知見や経験を組織全体で活用するためには、体系的なナレッジマネジメントが必要です。プロジェクトの成果、失敗からの学び、メンバーの専門知識を蓄積し、次回のチーミングで活用できる仕組みを構築します。
まとめ
チーミングは、変化の激しい現代のビジネス環境において、組織の競争力を高める重要なアプローチです。従来型の固定チームから脱却し、柔軟で多様性に富んだ協働体制を構築することで、イノベーション創出と課題解決力の向上を実現が期待できます。
- チーミングは状況に応じて最適なメンバーを組み合わせる動的なチーム運営手法
- 心理的安全性、目的共有、相互理解が成功の基盤となる重要要素
- 新規事業開発や技術革新などの変革局面で特に高い効果を発揮
- 組織文化の変革とデジタルツールの活用が導入の鍵
- 継続的な学習と改善により組織全体の協働能力を向上
まずは小規模なプロジェクトやチームからチーミングを試行し、実際の現場での成功体験を一つひとつ積み重ねていくことが重要です。こうした成功事例は、チーミングの有効性を組織内で証明し、他部門や全社への展開を後押しする強力な基盤となります。また、導入に際しては、十分な準備と関係者への理解促進、適切なリーダーシップの育成が不可欠です。取り組みのなかで生じる課題には柔軟に対応し、継続的なフィードバックと改善を重ねることで、チーミングの成熟度を高めていくことができます。
このような段階的かつ計画的な取り組みにより、変化に強く、学習し続ける組織文化が醸成され、やがて組織全体においても持続的に成果を生み出す強固なチーミング体制を築くことができるでしょう。チーミングを通じて、一人ひとりの力が組織全体の成長エンジンとなる未来を目指しましょう。
成果を創出し続ける「最強チーム」のつくり方
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する「チームワーキング」関連プログラムは、チームの機能不全を解消し、成果を出すチームづくりを目指す、企業のリーダーや管理職、および人事ご担当者様向けの研修です。データとケースに基づいた実践的な理論を学び、メンバーの協働を促進し、パフォーマンスを最大化するチームマネジメントを学んでいただけます。
解説資料|ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方
書籍「チームワーキング」ポイント解説
チームの機能不全状態を解消し、成果を創出する
本資料は立教大学の中原淳教授・田中聡助教著『チームワーキング ケースとデータで学ぶ「最強チームのつくり方」』をベースに、チームの機能不全に悩む職場の立て直しに資する内容となっています。
- 「チームの病」を克服するために必要なチームワーキング
- チームが機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」
- チームが効果的に機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」
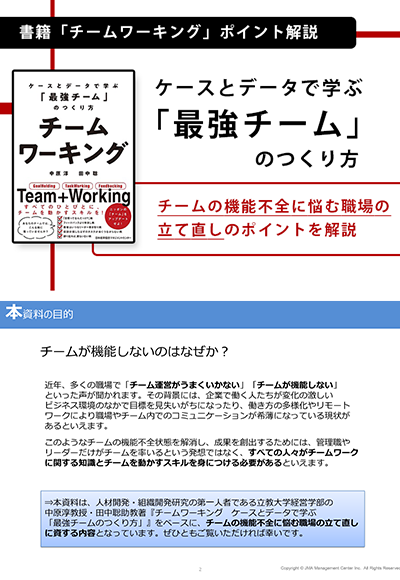
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます