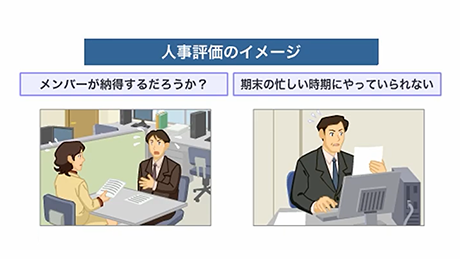- 対象: 全社向け
- テーマ: ビジネススキル
- 更新日:
コンピテンシーとは?メリットや活用例、導入方法を徹底解説

コンピテンシーとは、業務で成果を上げる行動や思考パターンのことです。企業の人材戦略に取り入れることで、採用や人材育成の効率化が期待できます。
今回は、コンピテンシーの定義やそのメリット、活用例、さらには評価を導入する具体的なプロセスについて解説します。
関連資料

関連資料
アセスメントを活用した、納得感と成長を促進する評価制度の設計方法を解説
昇進・昇格審査設計のポイントと留意点
コンピテンシーとは
まずは、コンピテンシーの定義や似ている言葉との違いについて説明します。
コンピテンシーの定義
コンピテンシー(competency)という言葉は、英語の「コンピテンス(competence)」から派生しています。
この言葉自体は「環境に適応する能力」や「技術」など、仕事に必要な適切な能力を意味しています。
ビジネスにおけるコンピテンシーとは、業務において成果を上げるために必要とされる行動や思考のパターンを指します。
ある職種で成功している人がどのような行動を取っているか、どのような方法で成果を上げているのかを観察して、コンピテンシーを明確化するのが一般的です。
これは、主に採用活動や人材育成の戦略設計において活用されます。
似ている言葉との違い
コンピテンシーと混同されがちな言葉には、「スキル」「アビリティ」「コア・コンピタンス」「ケイパビリティ」などがあげられます。
それぞれの違いを簡単にまとめました。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| コンピテンシー | 成果に結びつく行動特性を指す。業務における成功を達成するために必要な能力や行動パターン。 |
| スキル | 特定の作業を実行するために必要な技術や知識。 |
| アビリティ | 特定の行動を実行できる能力、潜在的な可能性を含む。 |
| コア・コンピタンス | 企業が持つ、他社には真似できない独自の競争優位性となる技術や知識。 |
| ケイパビリティ | 組織や個人が持つ総合的な能力、特に変化に適応する力を指す。 |
コンピテンシーの活用例
コンピテンシーは、採用や人材育成の場面で広く活用されています。
企業の人材戦略に取り入れることで、より効率的で成果を出す人材を育成できると同時に、業務のパフォーマンス向上を実現することができます。
具体的な活用例をいくつか挙げてみましょう。
人事評価
コンピテンシーは、人事評価の基準を明確化するために活用されることがあります。
コンピテンシーにもとづいて、業務で求められる具体的な行動や思考パターンを評価基準に含める方法です。例えば、「問題解決力」や「コミュニケーション能力」など、業務で重要なスキルを項目化し、それぞれに評価の基準を設けます。
能力開発・キャリア開発
コンピテンシーは、能力開発やキャリア開発にも役立ちます。
従業員がどのようなスキルや行動特性を身に付けるべきかを、コンピテンシーを活用して明確にする方法です。
具体的には、従業員の職務に必要なコンピテンシーをリスト化し、そのスキルや行動がどの程度備わっているかを自己評価や上司の評価を通じて把握します。その上で、今後の成長に必要なスキルを明確化し、従業員とともに具体的な開発プランを作成します。
採用・面接
採用活動においてもコンピテンシーは活用されています。
面接や選考基準にコンピテンシーを組み込むことで、候補者が職務に求められる具体的な行動特性を持っているかどうかを評価することが可能です。
例えば、「チームワーク能力」や「柔軟性」といった職務に関連するコンピテンシーを選考基準として設定します。
面接時では、候補者に過去の職務経験や具体的な状況における行動を問う質問を行い、どのようにその能力を発揮したかを確認します。
コンピテンシーを活用するメリット
コンピテンシーを活用することで、企業の採用活動や人材育成に多くのメリットがあります。
特に、自社に適した人材を見極める力が高まり、効率的な育成が可能になるため、組織全体の生産性向上にもつながります。
ここでは、コンピテンシー活用の主なメリットを紹介します。
人材評価や人材育成の質が高まる
コンピテンシーを評価基準として取り入れることで、人事評価の透明性が高まり、従業員の成長につながる点もメリットです。
人事評価が明確になることで、従業員は、自分がどのような行動を期待されているのかを理解しやすくなります。
評価に対する納得感が高まるほか、今後どのようなスキルや行動を身に付けるべきかが明確になり、キャリア開発に向けた具体的なステップを踏みやすくなります。
その結果、組織全体で能力向上や人材開発に取り組む基盤が整いやすくなり、人材育成の質を向上させるのにも役立ちます。
生産性の向上を見込める
ハイパフォーマー(優秀な従業員)の行動や思考が評価基準に反映されることで、従業員がそれを意識して行動するようになるため、組織全体の業務パフォーマンス向上につながります。
その結果、業務の効率化が進み、業績の向上も期待できます。
組織全体の生産性向上は、企業にとって重要な競争力の源泉となるため、コンピテンシーを導入する価値は大きいといえます。
自社に合う人材を採用しやすくなる
面接の質問内容をコンピテンシーにもとづいて設計することで、自社で活躍できる人物像が明確になります。
そのため、候補者の適性をより正確に評価でき、入社後の活躍が期待できる人材を早い段階で見つけることが可能です。
採用基準が具体的であれば、採用のミスマッチや早期離職のリスクを軽減することにもつながるでしょう。
コンピテンシー評価の3つのモデル
コンピテンシー評価を導入する際には、評価のためのモデルを選定することが重要です。
代表的なコンピテンシーモデルには、実在型モデル、理想型モデル、そしてハイブリッド型モデルの3種類があります。
作成方法や特徴が異なるため、企業のニーズや状況に応じて使い分けることが大切です。
下記は、それぞれの作成方法と特徴をまとめた表です。
| 型 | 作成方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 実在型モデル | 実際に存在する優秀な従業員をもとにモデルを作成 | ・コンピテンシーをイメージしやすく、他の従業員の納得感を得やすい |
| 理想型モデル | 企業にとっての理想の人物像をもとにモデルを作成 | ・社内にモデルとなるべきハイパフォーマーがいないときに有効 |
| ハイブリッド型 | 実在型と理想型を合わせてモデルを作成 | ・2つのモデルの良い部分をうまく取り入れられる |
ここでは、各モデルについてより詳しく解説します。
成果主義モデル
成果主義モデルでは、従業員が達成すべき成果や目標に対する行動特性を重視します。
具体的な業績や成果にもとづいた評価が行われるため、組織全体の目標達成を促進するのに役立ちます。
従業員がどのような行動を取れば成果を上げられるのかを洗い出し、それに必要なコンピテンシーを明確にします。業績評価に直結するため、明確で測定可能な成果が求められます。
行動主義モデル
行動主義モデルは、従業員の行動や態度に着目し、その行動がどのように成果に繋がるかを評価します。
具体的な行動のパターンを定義し、成功した人材の行動を再現できるようにすることが重視されます。
成果を上げている従業員がどのような行動を取っているか、どんなスキルや態度が成功につながっているのかをモデル化します。
能力主義モデル
能力主義モデルは、従業員が持つ基本的な能力や潜在能力を重視する評価方法です。
従業員が現時点で持っているスキルや知識、経験をもとに評価され、今後の成長のポテンシャルにフォーカスされます。
従業員がどの程度の能力を持っているか、またその能力がどのように組織に貢献するかを見極めることができます。
コンピテンシー評価を導入する流れ
コンピテンシー評価を導入するためには、企業のニーズに合った明確なプロセスを踏むことが重要です。
下記は、コンピテンシー評価を効果的に実施するための基本的な流れです。
なお、JMAMでは管理者およびその候補者向けに、コンピテンシー・行動ベース評価の実践的な研修を提供しています。
これからコンピテンシー評価を取り入れたい人事担当の方は、ぜひご確認ください。
ステップ1|ハイパフォーマーへのヒアリング
まずは、生産性の高いハイパフォーマーへのインタビューを行います。
どのような行動が成果につながっているのかを把握するために、実際の行動特性を明確にする必要があります。
ヒアリングは、職種や役割ごとに行うと効果的です。
重要なのは、成果だけに焦点を当てるのではなく、その成果を上げるためにどのような行動を取ったのか、その理由にも注目することです。
また、成功するために共通している思考や行動パターンも分析し、モデル化しましょう。
ステップ2|コンピテンシーの洗い出し
次に、インタビューで得られた行動特性をもとにコンピテンシーを洗い出します。
ここでは、スペンサー&スペンサーのコンピテンシー・ディクショナリーと呼ばれるモデルが活用されるケースが多くあります。
▼コンピテンシー・ディクショナリーの項目
| 領域 | コンピテンシー | コンピテンシーの定義 |
|---|---|---|
| 達成・行動 | 達成思考 | 成果を追求する思考のスタイル |
| 秩序・品質・正確性への関心 | 作業の正確性と品質に対する高い関心 | |
| イニシアチブ | 自ら積極的に行動を起こす姿勢 | |
| 情報収集 | 必要な情報を適切に収集する能力 | |
| 援助・対人支援 | 対人理解 | 他者の感情や立場を理解する力 |
| 顧客支援志向 | 顧客満足を重視した行動や思考 | |
| インパクト・対人影響力 | インパクト・影響力 | 他者に対する影響を与える力 |
| 組織感覚 | 組織の価値や目標を理解し行動に反映 | |
| 関係構築 | 良好な対人関係を築く能力 | |
| 管理領域 | 他者育成 | 他者の成長を支援する能力 |
| 指導 | 他者に知識やスキルを伝える能力 | |
| チームワークと協力 | チーム内で協力し、ともに成果を上げる姿勢 | |
| チームリーダーシップ | チームを率いて成果を出す力 | |
| 知的領域 | 分析的志向 | 複雑な問題を分析し解決する能力 |
| 概念的志向 | 広い視野で考え、概念的な理解を深める | |
| 技術的・専門職的・管理的専門性 | 特定の技術や知識を深める能力 | |
| 個人の効果性 | 自己管理 | 自分の感情や行動を適切に管理する能力 |
| 自信 | 自分の能力に対する確信 | |
| 柔軟性 | 環境や状況に応じて柔軟に対応する力 | |
| 組織コミットメント | 組織の目標や価値に対するコミットメント |
出典:Spencer & Spencer(1993)
コンピテンシー・ディクショナリーは、一般的な評価基準を示すものです。従業員の行動や思考を細かく分類し、企業の文化や目標に合ったものを選びましょう。
もし、このディクショナリーにない特定の行動特性が見つかった場合は、それを自社特有のものとして残すかどうかを検討してください。
ステップ3|企業の理念やビジョンとのすり合わせ
洗い出したコンピテンシーを、企業の理念やビジョンと照らし合わせましょう。
理想的なコンピテンシーが企業の目標と一致しているか確認し、一致しない場合は排除するか、修正を加えます。
この段階で、企業の価値観やビジョンに最も合ったコンピテンシーを選定することで、従業員の行動が企業文化に沿ったものとなり、長期的な組織の成長につながります。
ステップ4|評価に取り込むべきコンピテンシーの選択
最後に、評価に取り入れるべきコンピテンシーを選定します。
すべてのコンピテンシーを評価基準に組み込むことは運用面で負担が大きくなるため、特に成果に影響を与えるものや、育成において重要な要素を選びます。
評価基準として採用するコンピテンシーは、実際の業務や業績向上に直結するものを優先しましょう。
評価者の負担を軽減しながらも、効果的な人材評価ができるように設定することが大切です。
なお、管理者を対象とするコンピテンシー評価には、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する多面診断「RoundReview®」をご検討ください。各社のハイパフォーマーの管理者にみられる行動から質問項目を作成しているため、対象者と他社一般平均との比較や育成課題の把握に役立ちます。詳細は下記からご確認いただけます。
まとめ
コンピテンシー評価は、企業の人材戦略のひとつとして長年活用されており、今でも十分に有効な評価方法です。企業の目標に合ったコンピテンシー評価を導入することで、採用や人材育成の質が向上し、組織全体の生産性向上につながる可能性があります。
ただし、コンピテンシー評価の導入においては、パフォーマンスの高い人をモデルにすることが、必ずしも将来的にイノベーションを生む人材のモデルとなるとは限りません。
特にVUCAの時代では環境変化に迅速に対応できる自律性を養う必要があります。コンピテンシー一辺倒ではなく、イノベーションを生む人材をどう考えるかを軸に評価を進めることが重要です。
また今後は、反面教師としてその評価を活用することも重要になってきます。こうした点を踏まえ、コンピテンシー評価を柔軟に活用することが求められます。
目標管理・人事評価調査 ~目標管理制度の運用実態編~
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、多様な働き方が推進される現代で、どのように目標管理や人事評価が運用されているのかを実態としてまとめています。
人事評価制度の構築や運用に課題を感じている人事担当の方は、ぜひ下記の資料もご覧ください。
解説資料|昇進・昇格審査設計のポイントと留意点
アセスメントを活用した、納得感と成長を促進する評価制度の設計方法を解説
本資料では、昇進・昇格審査における課題と解決策を紹介し、アセスメントを活用した、納得感と成長を促進する評価制度の設計方法を解説します。
- 昇進昇格審査評価と基準の変遷
- 昇進昇格審査に関する問題意識(4年前との比較)
- 育成しながら選抜する昇進昇格審査フロー例
- アセスメントセンターとV-CATを組み合わせた評価

関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます