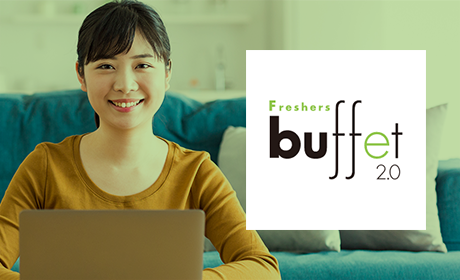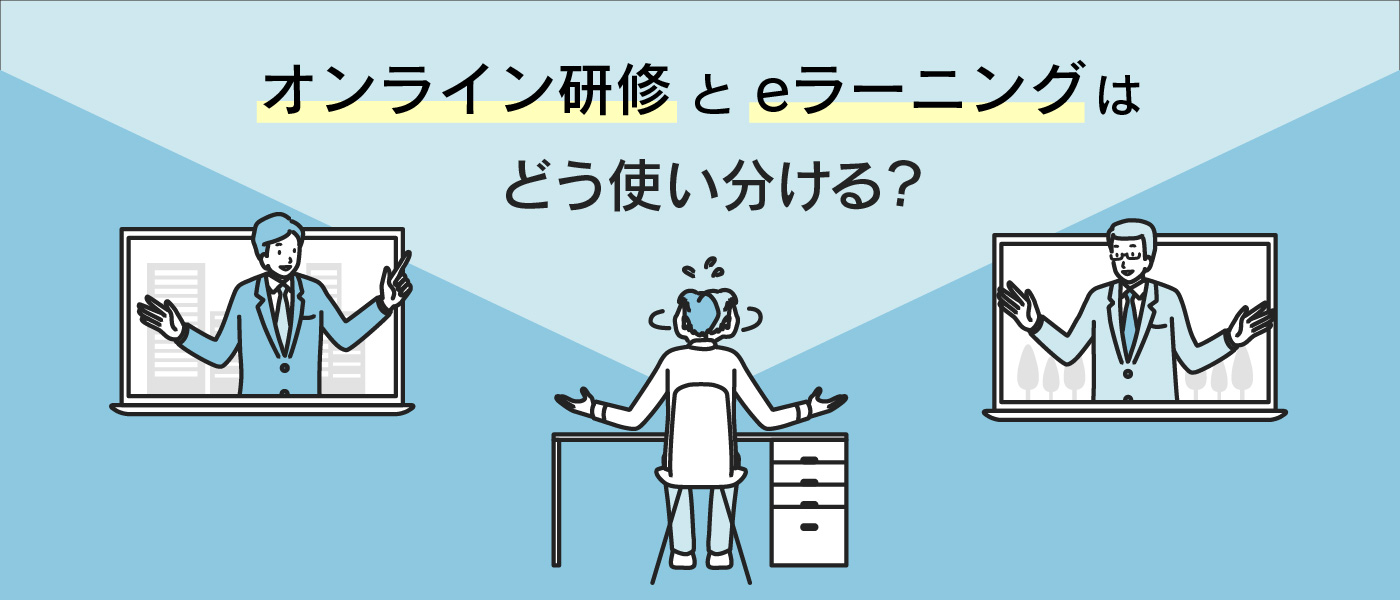
オンライン学習方法には、主にオンライン研修とeラーニングの2つがあります。これらの違いや、どのように使い分けるべきかについて、迷う人事・人材育成担当者も多いのではないでしょうか。オンライン研修は「双方向型」と呼ばれ、参加者と講師がリアルタイムにコミュニケーションを取りながら学ぶ形式です。一方、eラーニングは「オンデマンド型」と呼ばれ、参加者が自分の都合に合わせて学習コンテンツを利用する形式です。
企業が目的に応じて適した手法を選べるように、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説します。
関連サービス

関連サービス
変化への対応が必須の時代に。社員教育をこれ1つで。
法人向け定額制 eラーニング「eLearning Library」
オンライン研修とeラーニングの違いとは?
はじめに、オンライン研修とeラーニングの違いについて解説します。
オンライン研修とは
オンライン研修は、Web会議ツールなどを使ってオンラインで行われる研修方法です。これには「Webセミナー」や「ウェビナー」も含まれます。研修日時が事前に決められ、リアルタイムで行われます。従来の集合研修がオンラインに移行した形態と考えるとイメージしやすいでしょう。
講師と受講者が同じ時間に参加するため、講師は受講者の理解度を確認しながら進行することができます。オンライン研修は効率的かつ柔軟な学習方法として社内教育に活用されています。
eラーニングとは
eラーニングは、あらかじめ用意されたコンテンツを視聴して学習する研修方法です。これは「オンライン学習」とも呼ばれています。学習管理システム(サーバー)に保存された動画教材を、パソコンやタブレットなどの端末によって受講します。
教材は事前に用意されているため、日時を合わせる必要がありません。受講者は自分の好きな時間に学習することができます。eラーニングは柔軟性と自分のペースで学習できるのが特徴であり、社内教育の手法の一つとして広く活用されています。
オンライン研修とeラーニングの違い
両者はどちらもオンライン学習ですが、一般的にオンライン研修は双方向型であり、eラーニングはオンデマンド型の学習です。双方向型であるオンライン研修はリアルタイム配信を行い、講師と受講者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら進行します。一方、オンデマンド型である、eラーニングは予め用意された学習コンテンツを受講者が自分のペースで視聴します。目的に合わせて、適切な学習形式を選択することが必要です。
オンライン研修のメリット・デメリット
オンライン研修のメリット・デメリットについて解説します。
オンライン研修のメリット
オンライン研修では、受講者の反応や理解度がリアルタイムで確認できます。研修の建付けによっては、受講者同士で交流し学びを深めることも可能です。また、ネット環境と端末さえあればどこでも実施・受講できます。会場費や移動費のコストを削減することもできますし、全国どこからでも研修に参加できます。オンライン研修は効率的で柔軟な学習手段です。
オンライン研修のデメリット
オンライン研修では、Webカメラやマイクなどの機材の準備が必要です。また、研修日時に合わせて予定を組む必要があります。さらに、機材によっては通信トラブルが発生する場合があります。これらの要素は、スムーズな学習や参加に支障をきたすことがあります。ただし、適切な準備と対策をしておくことでデメリットは最小限に抑えることができます。
eラーニングのメリット・デメリット
続いて、eラーニングのメリット・デメリットについて解説します。
eラーニングのメリット
eラーニングは、リアルタイム配信ではないため、教材の修正やアップデートが容易で、最新の情報を学習者に提供しやすいことが特長です。また、全学習者に均等に教材を配信することができ、研修品質の均一化も図ることができます。
さらに、学習の進捗状況をリアルタイムに把握することができ、学習データを蓄積することも可能です。これにより、受講者に合わせた提案やサポートが行えます。また、受講者に最適な教材やコースを提供することもできます。
また、従来の集合研修と違い会場費や移動費などが不要となるため、eラーニングの導入により、コストを削減することができます。さらに、採点の自動化により、テスト結果を即座に把握・フィードバックすることが可能です。
eラーニングのデメリット
eラーニングでは学習管理システムなどの導入が必要です。これには一定のコストや導入作業が伴うことがあります。
また、受講者の疑問や質問に対する即時の解決が難しいというデメリットもあります。リアルタイムの研修や現場教育と比較して、受講者が講師や他の受講者との対話が制限されるため、疑問点を解消するまでの時間がかかります。
さらに、eラーニングでは受講者の学習意欲を向上・維持させることが難しいというデメリットもあります。自宅やオフィスなどの環境で学習を行うため、他の仕事や日常生活との両立や集中力の維持が課題となります。
最後にeラーニングでは受講者同士の交流が制限され、コミュニケーションが難しいというデメリットも挙げられます。リアルタイムの研修や現場教育では受講者同士が交流し合い、学びの共有やネットワーキングが行われますが、eラーニングではそれができません。
これらのデメリットはeラーニングに特有のものであり、適切な対策や工夫を行うことで、デメリットを最小限に抑えることができます。
オンライン研修とeラーニングを効果的に使う方法
それぞれの特性を理解した上で、効果的に活用する方法を解説します。
自社のニーズに合う教育方法を選ぶ
自社のニーズ=なんのために教育を行うのか定めましょう。
オンライン研修とeラーニングは、同じオンライン上での学習ですが、メリット・デメリットが異なります。自社の状況に応じて適切な選択を行うためには、以下の点に注目する必要があります。
まず、自社にすでにオンライン教材があるか、予算やノウハウを持っているかなどのリソースの有無を調査します。また、双方向のコミュニケーションが必要かどうかや、アウトプットを期待するかなどの要件も重要です。
それぞれの教育方法の特性や強みを理解した上で、使い分けることが重要です。また、単独ではなく組み合わせて利用することで相乗効果を発揮することも可能です。たとえば、eラーニングでインプットした知識について、オンライン研修を通して受講者同士で語り合い考えを深めるなどの活用方法もあります。また、オンライン研修の内容を理解しているかどうかについて、eラーニングを使って確認テストを行うといった方法もあるでしょう。
自社のニーズに合った研修方法を選ぶためには、目的や予算、学習スタイルなどを考慮し、綿密な計画を立てることが重要です。適切な研修方法の選択は、効果的な学習とスキルの向上につながります。
事前に研修の説明会を開く
自社の教育の目的に合わせ、実施形態や教育方法が決まったら、実施する前に事前説明会を開きましょう。説明会では研修の目的を明確にし、システムやツールの操作方法をレクチャーします。また、マイクやカメラの切り替え方法など、研修に必要な基本的な使い方も事前に説明しておくと参加者は安心です。
さらに、事前説明会では研修マニュアルを配布することもおすすめです。受講者が事前にマニュアルを確認することで、研修がスムーズに行えます。
事前準備により、オンライン研修やeラーニングを効果的に活用することができます。参加者の理解度や安心感を高め、円滑な学習の進行を実現します。
受講者の進捗管理をする
次に受講者の進捗管理が重要です。連続した研修カリキュラムを組む場合、受講者の参加履歴や学習状況を管理することが必要となります。これにより受講者の進捗を把握し、適切なフォローアップやサポートを行うことができます。
出欠確認はもちろんのこと、研修後にテストやレポートの提出を求めるケースもあります。それによって、受講者の理解度や成果を評価し、研修の効果を測ることができます。
受講者の進捗管理は、オンラインツールや学習管理システムを活用して効率的に行うことができます。進捗状況の把握と適切なフィードバックを通じて、受講者の学習成果を向上させることが可能です。
まとめ
オンライン研修はWeb会議ツールなどを使ってオンラインで行われる研修であり、双方向のコミュニケーションやリアルタイムの参加が特徴です。一方、eラーニングは予め用意されたコンテンツを視聴して学習する形式であり、自分のペースで学習できる点が特徴です。それぞれの違いを理解した上でうまく使い分けていきましょう。
まずは社内でeラーニングから展開したいと考えている企業様には、1979年より企業向け研修を実施している歴史ある会社「株式会社日本能率協会マネジメントセンター」が提供しているeラーニングサービスがおすすめです。360以上の多彩なテーマの講座が、1年間定額で受講し放題のサービスとなっています。
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます