- 対象: 中堅社員
- テーマ: 研修/教育
- 更新日:
メンター制度とは?成功事例・失敗例から学ぶ導入のポイントとは

新入社員や若手社員の早期離職に頭を悩ませている人事担当者の方は多いのではないでしょうか。厚生労働省の調査によると、大卒新入社員の約3割が3年以内に離職しているという現実があります。この課題を解決する有効な手段として注目されているのがメンター制度です。
本記事では、メンター制度の基本的な仕組みから実際の成功事例・失敗例まで詳しく解説し、自社での効果的な導入方法をご紹介します。人材定着率の向上と組織力強化を実現するための具体的なノウハウを身につけることができるでしょう。
関連資料
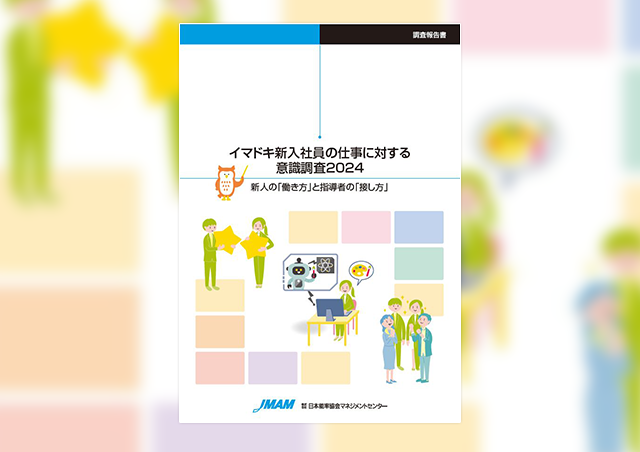
関連資料
最新版!新人の「働き方」と指導者の「接し方」の実態に加え、Z世代の「学び」や「リーダーシップ」などにも焦点を当てています
今すぐ無料で見る|イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024
メンター制度とは何か?基本的な仕組みと目的
メンター制度とは、経験豊富な先輩社員(メンター)が新入社員や若手社員(メンティー)に対して継続的な指導とサポートを提供する人材育成制度です。単なる業務指導にとどまらず、キャリア形成や人間関係の構築まで幅広くサポートする点が特徴的です。
メンター制度の基本構造
メンター制度では、通常1対1または1対複数の関係でペアリングが行われます。メンターは業務上の直属の上司ではない先輩社員が選ばれることが多く、これにより心理的安全性の高い相談環境を作り出すことができます。定期的な面談を通じて、メンティーの成長を多角的にサポートしていきます。
従来のOJTとの違い
メンター制度とOJTの最大の違いは、その目的と範囲にあります。OJTが主に業務スキルの習得に焦点を当てるのに対し、メンター制度はより包括的なサポートを提供します。メンティーの個人的な悩みや将来のキャリアプランについても相談できる環境を整えることで、職場への適応と長期的な成長を促進します。
メンター制度導入の主な目的
多くの企業がメンター制度を導入する目的は、新入社員や若手社員の離職率改善、職場での孤立感の解消、キャリア支援の充実、社内コミュニケーションの活性化などが挙げられます。特に近年は、テレワークの普及により対面でのコミュニケーション機会が減少していることから、意図的な関係構築の場としてメンター制度の重要性が高まっています。
メンター制度導入のメリット
メンター制度の導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを正しく理解することが重要です。制度設計時にこれらの要素を考慮することで、より効果的な運用が可能になります。
企業が得られる主なメリット
最も注目すべきメリットは定着率向上による離職率改善です。メンティーが職場に馴染みやすくなることで、早期離職のリスクを大幅に軽減できます。また、メンター自身のリーダーシップスキル向上や組織全体のコミュニケーション活性化といった副次的効果も期待できます。
メンティー側のメリット
メンティーにとって最大のメリットは、安心して相談できる環境の確保です。業務上の疑問から人間関係の悩みまで、幅広い内容を気軽に相談できることで、ストレスの軽減と早期の問題解決が可能になります。キャリア支援の観点からも、先輩社員の経験談を直接聞けることで、自身の将来像を具体的に描きやすくなります。
効果的なメンター制度導入の手順とポイント
成功事例と失敗例を踏まえて、実際にメンター制度を導入する際の具体的な手順と押さえるべきポイントを解説します。段階的なアプローチにより、自社に最適な制度を構築することができます。
導入準備段階での目的設定と体制構築
メンター制度導入の第一歩は、明確な目的設定です。離職率改善、人材育成の効率化、組織コミュニケーションの活性化など、自社が解決したい課題を具体的に特定します。目的に応じて制度の設計方針が大きく変わるため、経営層と人事部門、現場管理職が一体となった検討体制を構築することが重要です。また、制度運用に必要な予算と人的リソースの確保も事前に行います。
メンター選定基準と研修プログラムの策定
効果的なメンター制度の運用には、適切なメンター選定が不可欠です。業務スキルの高さだけでなく、コミュニケーション能力や指導への意欲、時間的余裕などを総合的に評価します。選定後は、メンタリングスキルを向上させる研修プログラムを実施します。傾聴技法、フィードバック方法、目標設定支援など、実践的なスキルを身につけることで、メンター自身の不安解消と指導品質の向上を図ります。
ペアリング方法と面談運用のガイドライン
メンターとメンティーのペアリングはメンター制度の成功の鍵を握る重要な要素です。単純な部署配属や年次だけでなく、性格特性や専門分野、キャリア志向などを考慮したマッチングを行います。面談頻度は月1-2回程度が目安ですが、導入初期は週1回程度の高頻度で実施し、関係性の構築を促進します。面談内容のガイドラインも整備し、一定の品質を保ちながらも柔軟性を確保します。
導入時の工夫や運用のポイントが分かる、企業の実践事例も参考になります。
メンターには3カ月間のメンター期間の前に、2カ月ほどかけて事前学習を行います。その事前学習では、アドバイスではなくまずは話をじっくり聞くことを徹底し、できるだけ寄り添い、メンティーのWell-beingに重きを置くことを強調しています。もともと面倒見のよさが社風として培われているせいか、エントリー数は毎回メンティーよりメンターの方が多い。メンターへの応募者は自身が若手のころに他組織の先輩や管理職にお世話になった経験から、今度は自分が後輩の力になりたいと考えるのかもしれません
引用元:個々の自律を通じたキャリア開発と能力開発を実現する教育施策
https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=22597https://jhclub.jmam.co.jp/seminar/seminarreport_20231204.html
運用体制と継続的改善のためのPDCAサイクル
メンター制度の効果を最大化するためには、導入後の継続的な改善が欠かせません。PDCAサイクルを活用した運用体制の構築により、制度の質を向上させ続けることができます。
効果測定と評価指標の設定
メンター制度の効果を客観的に評価するため、定量的・定性的な指標を設定します。定量指標としては離職率、定着率、昇進率、満足度スコアなどが挙げられます。定性指標では、面談記録の分析やインタビュー調査を通じて、制度の実質的な効果を測定します。これらの指標を定期的にモニタリングし、データに基づいた改善策を立案することで、制度の持続的な発展が可能になります。
メンター支援とフォローアップ体制
メンター制度の継続性を確保するためには、メンター自身への支援体制が重要です。定期的なメンター研修の実施、メンター同士の情報交換会の開催、人事部門による個別面談など、多層的なサポートを提供します。また、メンタリング活動を人事評価に反映する仕組みを構築することで、メンターのモチベーション維持にもつながります。
制度改善のためのフィードバック収集
制度の改善には、現場からのフィードバックが不可欠です。メンター・メンティー双方からの定期的なアンケート調査や面談を通じて、制度運用上の課題や改善要望を収集します。収集したフィードバックは速やかに分析し、必要に応じて制度の修正や追加施策の検討を行います。この継続的な改善プロセスにより、自社の文化や特性に最適化された独自のメンター制度を構築することができます。
ツール活用による効率的なメンター制度運営
デジタル化が進む現代において、適切なツールの活用はメンター制度運営の効率化と効果向上に大きく貢献します。特にリモートワークが普及した環境では、オンラインツールの活用が必須となっています。
面談記録と進捗管理システムの導入
面談内容の記録と進捗管理を効率化するため、専用システムの導入が有効です。面談の日程調整から内容記録、目標設定と達成状況の追跡まで、一元的に管理できるシステムを構築します。これにより人事部門は制度全体の運用状況を把握しやすくなり、個別のフォローアップや全体的な改善策の立案が容易になります。クラウドベースのシステムを活用することで、場所を選ばずアクセス可能な環境も整備できます。
コミュニケーションツールの効果的活用
定期面談以外の日常的なコミュニケーションを促進するため、チャットツールやビデオ会議システムを積極的に活用します。気軽に質問や相談ができる環境を整えることで、メンティーの不安解消と学習機会の増加につながります。また、グループチャットを設置することで、複数のメンター・メンティー間での情報共有や相互学習も促進できます。
学習リソースとナレッジベースの構築
メンタリング活動を支援するため、オンライン学習リソースやナレッジベースを構築します。過去の成功事例や よくある質問、推奨する学習コンテンツなどを整理し、メンター・メンティー双方が参照できる環境を整備します。これにより、メンタリングの質の標準化と効率化を同時に実現することができます。
成功事例から学ぶ効果的なメンター制度運用法
実際にメンター制度で成果を上げている企業の事例を分析することで、効果的な運用のポイントが見えてきます。ここでは具体的な成功事例とその要因を詳しく解説します。
資生堂の事例
資生堂は「PEOPLE FIRST」の考えのもと、2017年からリバースメンタリング制度を導入しています。若手社員がリーダー層のメンターとなり、ジェンダーや国籍、年代、キャリアなど多様なバックグラウンドを持つ人材の交流・学びの場を提供しています。
さらに2022年からは「キャリアメンタリングプログラム」を開始し、社員が上司以外の管理職と対話して中長期的なキャリアプランを構築する支援を行っています。女性活躍推進では、2020年にエグゼクティブオフィサーと女性社員によるメンタリングプログラムを開始し、ロールモデルとのタッチポイント創出とキャリア支援を実現しています。
これらの取り組みにより、2030年までに国内の男女比率50:50を目指し、現在の女性管理職比率は国内41.1%、グローバル全体59.5%(2025年1月時点)という成果を上げています。
出典:資生堂、ジェンダー平等を推進するイベントを開催|株式会社資生堂公式サイト
https://corp.shiseido.com/jp/newsimg/3978_v8f99_jp.pdf
フコク生命の事例
フコク生命では2006年度から総合職新入職員を対象としたメンター制度を導入し、完全公募制による「チーム・メンター」構造が特徴です。メンターは立候補制で選ばれるため「やらされ感」がなく、2007年度からは管理職の「シニアメンター」がメンターをサポートする二層体制を確立しています。
重要なのは、新入職員の所属以外の先輩がメンターとなることで、業務上の利害関係を排除し率直な相談環境を提供している点です。活動は主に電話で行われ、全国支社に配属される新入職員の孤独感軽減に効果を発揮しています。
この制度により新入職員とメンター双方の成長、若手層のネットワーク構築、企業文化継承が実現し、2010年度「メンター・アワード」組織部門優秀賞を受賞しています。
出典:「メンター・アワード2010」優秀賞の受賞について|富国生命保険相互会社公式サイト
https://www.fukoku-life.co.jp/about/news/upload/20100226.pdf
ネスレ日本の事例
ネスレでは複数のメンタープログラムを展開し、グローバル企業ならではの規模と多様性を活かした制度を構築しています。最も注目すべきは「コーポレート・メンタリング・プログラム」で、100人を超える上級経営幹部がトップ経営陣と2人1組になり、18ヵ月間の専門性向上プログラムを実施しています。
各市場でも独自のプログラムを展開し、ネスレスペインの「メンター・ネス」プログラム、ネスレオセアニアの「メンタリング@ネスレ」など、地域特性に応じたメンタリング制度を運営しています。ネスレニュートリションも2008年から独自のメンタリングプログラムを開始し、事業部門レベルでの人材育成を強化しています。
これらの制度により、多様性(ダイバーシティ)とジェンダーバランスの推進、安心して業務に取り組める環境の構築を実現し、グローバル企業における体系的なメンター制度の成功例となっています。
出典:ネスレ共通価値の創造報告書|ネスレ日本株式会社公式サイト
https://www.nestle.co.jp/sites/g/files/pydnoa331/files/asset-library/documents/csv/csv_synopsis_2009.pdf
失敗例から学ぶ導入時の注意点と対策
メンター制度の導入が必ずしも成功するとは限りません。失敗事例を分析することで、同様の問題を回避し、より効果的な制度運用につなげることができます。
制度の形骸化
よく見られる失敗パターンは制度の形骸化です。メンター制度を導入したものの、目的の明確化や運用ガイドラインの整備が不十分だったため、メンターとメンティーの面談が雑談に終始するなど、具体的な成長支援につながらないケースがあります。この問題を解決するためには、制度導入前に明確な目標設定と評価指標の策定、定期的な効果測定の仕組み作りが不可欠です。
メンターの負担過多による問題
メンター1人に対して複数のメンティー(指導対象者)を割り当てすぎたため、メンターの負担が過重になり、メンター自身のモチベーション低下と業務品質の悪化を招くこともあります。この事例から学べる対策は、適切な人数配分の設定とメンターへのサポート体制の構築です。メンター同士の情報交換会や人事部門による定期的なフォローアップが効果的です。
ミスマッチへの対応
メンターとメンティーの性格や価値観の不一致により、関係性が悪化し、双方のストレス増加を招く結果となりました。この問題の対策として、ペアリング前の面談機会の設定や相性を考慮した配置、途中でのペア変更を可能とする柔軟な制度設計が重要です。
まとめ
メンター制度は、適切に設計・運用されれば企業の人材定着と育成に大きな効果をもたらす制度です。成功事例と失敗例の分析から、制度の成否は導入準備と継続的な改善にかかっていることが明らかになりました。
- メンター制度は離職率改善と人材育成の効率化に有効な手段である
- 明確な目的設定と適切なメンターの選定・研修が成功の鍵となる
- 形骸化や負担過多などの失敗要因を事前に対策することが重要
- PDCAサイクルによる継続的改善で制度の質を向上させる
- デジタルツールの活用により運営効率と効果の向上が期待できる
自社の課題と目標を明確にした上で、段階的なアプローチによるメンター制度の導入を検討してみてください。従業員の成長と組織の発展を両立する効果的な制度構築により、持続可能な人材育成体制の確立を目指しましょう。
Z世代の早期戦力化を実現する 新入社員・若手育成
JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する「新入社員・若手育成」プログラムは、Z世代の価値観やキャリア観を深く理解し、彼らが自律的に成長するための土台づくりを目指す、人事・教育企画ご担当者様や指導者向けの研修です。データに基づいた最新の傾向を捉え、効果的な関わり方や指導法を学び、若手人材の早期活躍と定着を支援します。
イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2024
新人の「働き方」と指導者の「接し方」やZ世代の「学び」や「リーダーシップ」
2016年から毎年行っている「新人の働き方と指導者の接し方」に関する内容に加え、Z世代の「学び」や「リーダーシップ」、仕事や職場への満足度が高い特徴にも焦点を当て、さまざまな切り口からその実態を明らかにしています。
- 新入社員(Z世代)の実態と特徴
- ビジネスパーソンの学習姿勢別にみる「学び」への意識
- イマドキ新入社員(Z世代)への指導育成
- [考察・提案]これからの新人・若手社員の成長支援
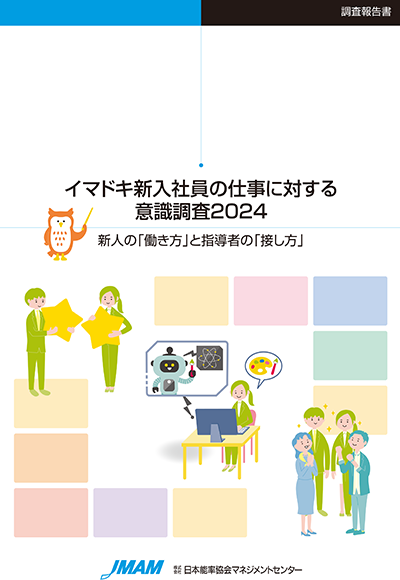
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















