
近年、企業経営において「ガバナンス」がますます重要視されています。ガバナンスは、企業が持続可能な成長を遂げるための基本的な管理体制を指し、内部統制やリスクマネジメントの強化などが求められます。特に上場企業は、株主やステークホルダーからの信頼を獲得するために、コーポレートガバナンスコードを遵守することが必要です。
今回は、ガバナンスの定義や重要性を解説するとともに、企業がガバナンスを強化するための具体的な施策について詳しく紹介します。
関連資料
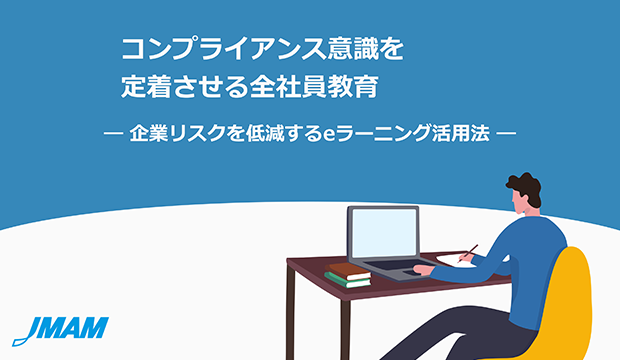
関連資料
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と課題解決に向けたポイントを紹介
コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
ガバナンスとは?
ガバナンスの定義や似ている言葉との違いについて詳しくみていきましょう。
ガバナンスの定義
ガバナンス(governance)は、企業や組織が持続可能な成長を実現し、社会的責任を果たすための「統治・支配・管理」を指す言葉です。企業におけるガバナンスは、「健全な企業経営を目指す仕組み」や「企業自身による管理体制」などを意味します。
管理体制を整えることで、企業は外部環境の変化に迅速に対応でき、利害関係者(ステークホルダー)からの信頼を得やすくなります。
また、役割と指示系統を明確にするための仕組みづくりもガバナンスの一環です。具体的には、企業が新しいプロジェクトを立ち上げる際のプロジェクトリーダーの選定や報告経路の明確化などがあげられます。
ガバナンスと似ている言葉との違い
ガバナンスと似た意味をもつ言葉として、「コンプライアンス」「内部統制」「リスクマネジメント」があります。それぞれの言葉とガバナンスの違いについて、詳しくみていきましょう。
①コンプライアンス
コンプライアンスは法令や規則の遵守を意味し、ガバナンスの一部として企業が守るべき基準を定めるものです。ガバナンスを構築するためには、コンプライアンスを強化し、リスクマネジメントする必要があります。
ガバナンスとコンプライアンスとの違いについては、下記のコラムでも紹介しています。
コンプライアンスとガバナンスの違いとは?強化するメリット、方法についても解説
②内部統制
内部統制は、企業内部の業務プロセスが適切に運用されているかを確認する仕組みのことです。ガバナンスの枠組みのひとつであり、不正防止や業務の効率化を目的としています。
③リスクマネジメント
リスクマネジメントは、企業が直面する可能性のあるリスクを特定し、その影響を最小限に抑えるための対策を講じるプロセスです。コンプライアンスの遵守もリスクマネジメントのひとつです。
上場企業が遵守すべき「コーポレートガバナンスコード」とは?
「コーポレートガバナンスコード」は、企業が健全な経営体制を構築するために守るべき原則や指針を示したガイドラインです。2015年に金融庁と東京証券取引所が主導で作成し、2021年に改訂を加えています。
コーポレートガバナンスコードでは、企業が経営を行う上で守るべき5つの基本原則が定められています。
| 原則 | 説明 |
|---|---|
| 株主の権利・平等性の確保 | 株主の権利を尊重し、平等に扱う。特に少数株主や外国人株主への配慮が必要。 |
| 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 | 従業員や取引先など、株主以外の利害関係者の権利を守り、適切に協働する。 |
| 適切な情報開示と透明性の確保 | 経営に関する重要な情報を正確に開示し、透明性を確保する。 |
| 取締役会等の責務 | 取締役会が企業の戦略やリスク管理を指導し、経営陣を監督する責任を負う。 |
| 株主との対話 | 株主総会以外の場でも株主と対話を行い、株主の意見を理解し、適切に対応する。 |
出典:日本取引所グループ「コーポ―レート・ガバナンス」
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html
上場企業は定期的に「コーポレートガバナンス報告書」を提出し、ガバナンス体制の現状を公開しなければなりません。
5つの原則が守られているかどうかが評価され、守られていない場合には、その理由と改善計画を明示する必要があります。
ガバナンスが注目されるようになった背景
ガバナンスが注目されるようになった背景には、社会問題化した事件の発生や企業の経営環境の変化があります。
企業による不正・不祥事の増加
1990年代のバブル経済崩壊後、日本では企業による不正や不祥事が相次いで発覚しました。一例として、大手企業による粉飾決算や贈収賄事件などがあげられます。
このような背景から、企業に対する社会的信頼が大きく損なわれたため、企業の経営を監視するためのガバナンス体制の整備が急務とされたのです。
国際的な競争力強化の必要性
経済のグローバル化が進展するなかで、外国人投資家の持ち株比率が増加し、企業に対して国際的な競争力の強化が求められるようになりました。特に、日本企業が海外市場での存在感を高めるためには、透明性の高い経営と信頼性の確保が不可欠です。
そのため、企業はステークホルダーとの信頼関係を築くことを目的として、ガバナンスに注力するようになりました。
ガバナンスを強化する具体的なメリット
ガバナンスを強化することは、結果として企業の持続可能な成長につながります。ガバナンスを強化するメリットについて、詳しくみていきましょう。
メリット1|株主からの信頼性が向上する
ガバナンスの強化に取り組むことで、株主からの信頼性が向上し、株価が安定しやすくなります。内部監視体制が整備されている企業は、組織内の自浄作用が働き、不祥事や不正が発生しにくい環境になるためです。
また、経営陣が不正を行うリスクを大幅に減少させることが可能なため、経営状態が健全であると評価されやすくなります。
メリット2|企業価値が高まる
ガバナンスの強化を通じて、法令や規則、倫理を厳守する姿勢を対外的に示すことが可能です。そのため、社会的信用が向上し、外部からの企業評価が高まります。
その結果、資金や優秀な人材が集まりやすくなるメリットも期待できます。
メリット3|資金調達がしやすくなる
金融機関は、融資や出資の審査で企業のガバナンス体制を重要な評価基準としています。コーポレートガバナンスに則った透明性の高い情報開示を行う企業は、信頼性が高いと見なされ、審査が有利になります。
資金調達が円滑になれば、財務状況の安定化を実現できるでしょう。さらに、新規事業立ち上げの際の資金調達も円滑になり、企業の成長が加速することも期待できます。
メリット4|社内の不正を防止する
ガバナンスを強化することで、企業内の監視体制が充実し、組織内部の腐敗や不正を未然に防ぐことができます。例えば、内部通報制度を設け、不正行為が発覚した際には即座に通報・相談を行う体制を整備することで、不正行為の早期発見と防止につなげられます。
なお、内部通報制度は従業員数(非正規労働者も含む)が300人を超える企業に導入が義務付けられています。
メリット5|企業の競争力・継続性が高まる
ガバナンスの強化には、企業の競争力と継続性を高める効果もあります。健全な経営体制が整っている企業は利益が安定しやすく、中長期的な成長が期待できます。
企業のガバナンスを強化する5つの施策
次に、ガバナンス強化に必要な5つの施策を紹介します。
施策1|社内外へ方針を共有する
ガバナンス強化の第一歩は、ガバナンスの重要性を経営者から全従業員へ伝えることです。新しいガバナンス方針の策定後は、その内容を全従業員に向けて共有しましょう。口頭だけでなく、社内ポータルサイトやメールを通じて周知することが重要です。
また、Webサイトや広報誌を活用して社外のステークホルダーにも方針を発信し、企業の透明性を示しましょう。
▼担当部門
経営陣:ガバナンスの重要性を従業員に伝える
総務部門または経営企画部門:全従業員へガバナンス方針を伝達する
広報部門:テークホルダーへ方針を共有する
施策2|行動規範や判断基準におけるルール策定
ガバナンス強化に向けて具体的な行動規範や判断基準を策定し、それを明文化することが重要です。ルールが明確であればあるほど、従業員は日常業務で適切な行動を取ることができ、内部統制の強化につながります。
コーポレートガバナンスコードに基づいてルールの策定を行うことで、法的にも倫理的にも優れたガバナンスを実現できるでしょう。
▼担当部門
法務部門、人事部門:コーポレートガバナンスコードに基づく具体的な行動規範や判断基準を策定する
施策3|内部監査の実施
独立した内部監査部門を設置し、定期的に監査を行うことも有効です。客観的に評価する組織を社内に設けることで、ガバナンスの強化につながるほか、株主に対して経営の透明性を示すことができます。
内部監査部門は監査結果に基づき、必要であれば経営陣に助言を行いましょう。
▼担当部門
内部監査部門:独立した監査を実施し、社内の状況を評価する
経営陣:内部監査部門からの助言の受け入れと改善提案の実施
施策4|社外取締役・社外監査役など第三者機関の導入
ガバナンス強化の一環として、社外取締役や社外監査役などの第三者機関を導入することもひとつの方法です。例えば、企業が社外取締役を複数導入することで、経営判断において外部の視点を取り入れ、より客観的かつ中立的な意見を反映させることができます。
企業が不正行為を行わない環境をつくるだけでなく、社会的信頼を高める効果もあります。また、社外の監査役が企業の業務フローを定期的に監査すれば、内部の腐敗を未然に防ぎ、透明性をさらに強化することが可能です。
▼担当部門
取締役会:社外取締役や社外監査役の選任および導入に関する決定をする
総務部門:社外取締役や社外監査役のサポートと連携を行う
監査役室:社外取締役や社外監査役が業務フローを監査できる体制を構築する
施策5|従業員教育の強化
ガバナンスを強化するためには、従業員教育の徹底が不可欠です。従業員にガバナンスの基本原則から、適切な行動までを深く理解させる必要があります。
具体的には、定期的なコンプライアンス研修を通じて、従業員がガバナンスコードの内容やその重要性を再確認する機会を設けることが有効です。単なる知識の習得にとどまらず、日常業務においてどのように行動すべきかを明確に示し、実践的な理解を促しましょう。
新入社員に対しては、入社時にガバナンスに関する基本教育を行うことが重要です。企業の一員としての意識を早い段階から形成できれば、ガバナンスが企業文化の一部として根付きやすくなります。
さらに、内部監査役を育成するために、外部の専門機関が提供する研修プログラムを利用することも有効です。例えば、JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供するコンプライアンスの基本を学べる学習コースを活用することで、内部監査役が最新の知識とスキルを習得し、企業の監視機能を強化することができます。社内教育の際は、ぜひお役立てください。
このように、定期的な社内教育と外部研修を組み合わせることで、企業全体のガバナンスレベルを向上させることが可能です。
▼担当部門
人事部門:従業員向けのコンプライアンス研修や新入社員のガバナンス教育を企画・運営する
法務部門:ガバナンスコードの内容や重要性に関する専門知識を提供する
まとめ
ガバナンスは、企業の持続可能な成長と社会的信頼を支えるために欠かせません。ガバナンスを強化することで、企業は内部統制や透明性を向上させ、株主やステークホルダーからの信頼を獲得できます。ガバナンス強化に向けた施策としては、社内外への方針共有や行動規範の明確化、内部監査の実施、社外取締役の導入、従業員教育の徹底などがあげられます。今回、解説した内容を参考に、ガバナンスの強化に取り組みましょう。
解説資料|コンプライアンス意識を定着させる全社員教育
コンプライアンス教育の効果的な導入方法と従来の課題解決に向けたポイントを紹介
本資料ではeラーニングを活用したコンプライアンス教育の効果的な導入方法と、課題解決に向けたポイントをご紹介します。
- 企業に求められるコンプライアンス強化の背景
- 一般的なコンプライアンス研修の内容と課題
- eラーニングによる課題解決と期待される効果
- eラーニングと集合研修の違いと特徴
- サービス選定時の重要ポイント
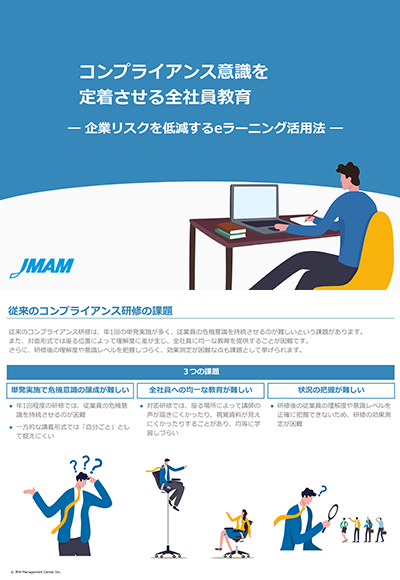
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます















