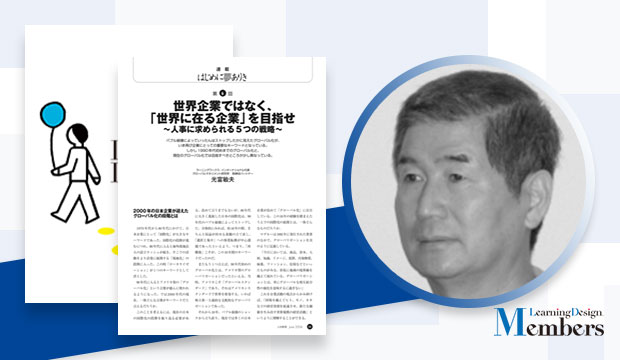- 対象: 全社向け
- テーマ: 働き方
- 更新日:
マトリックス組織とは?メリット・デメリット・事例をわかりやすく解説

急速に変化するビジネス環境において、従来の縦割り組織では対応しきれない課題が増えています。そこで注目されているのが「マトリックス組織」という新しい組織形態です。この組織構造は、複数の上司から指示を受ける特殊な指揮命令系統を持ち、プロジェクト型の業務と機能別の専門性を両立させることができます。
本記事では、マトリックス組織の基本概念から導入時のメリット・デメリット、実際の企業事例まで、人事担当者や経営層の方々が組織改革を検討する際に必要な情報を体系的に解説していきます。
関連資料
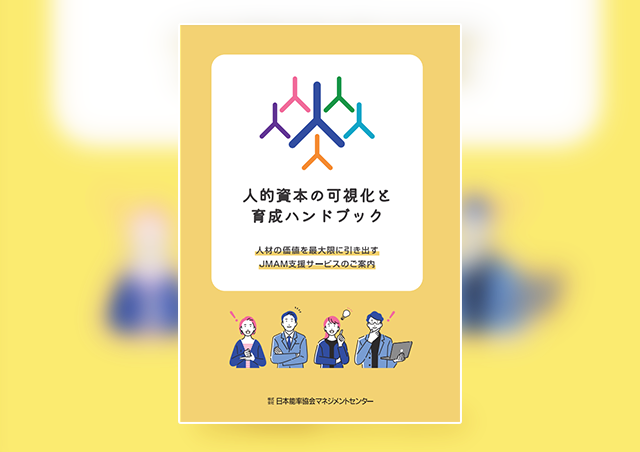
関連資料
人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内
人的資本の可視化と育成ハンドブック
マトリックス組織とは何か?を基本から
マトリックス組織とは、従業員が複数の上司から指示を受ける組織構造のことです。縦軸と横軸が交差する格子状の構造になっており、一人の従業員が機能別の部門とプロジェクトチームの両方に所属するのが特徴です。
マトリックス組織の基本的な仕組み
この組織では、従業員は通常二つの上司を持ちます。一つは職能別の部門長で、もう一つはプロジェクトマネージャーです。従業員は専門分野での業務とプロジェクト業務の両方を担当し、それぞれの上司から異なる指示を受けることになります。例えば、マーケティング部所属の社員が新商品開発プロジェクトにも参加し、マーケティング部長とプロジェクトリーダーの両方から指示を受ける形です。
このような複雑な指揮命令系統を採用する理由は、専門性を維持しながら部門横断型チームでの協働を実現するためです。変化の激しい市場環境では、単一部門だけでは解決できない課題が多く、複数の専門分野を組み合わせた対応が求められています。
従来の組織形態との違い
機能別組織では、各部門が専門性を深める一方で、部門間の連携が取りにくいという課題があります。一方、事業部制との違いは、マトリックス組織では専門機能を維持しながら横断的なプロジェクトにも対応できる点です。事業部制が縦割りの独立性を重視するのに対し、マトリックス組織はリソース共有と柔軟な人材配置を可能にします。
従来の階層型組織では、情報の流れが上下方向に限定されがちでした。しかし、マトリックス組織では横方向の情報共有も活発になり、より迅速な意思決定と問題解決が期待できます。
マトリックス組織導入のメリット
マトリックス組織の導入により、企業は従来の組織形態では実現困難だったさまざまな効果を得ることができます。ここでは、実際の導入効果として多くの企業が実感している主要なメリットを詳しく見ていきましょう。
リソース共有による効率性の向上
マトリックス組織では、優秀な人材を複数のプロジェクトで同時に活用できます。例えば、データアナリストが通常業務を行いながら、新商品開発プロジェクトにも参加することで、専門スキルを最大限に活用できます。限られた専門人材を効率的に配置することで、人件費を抑えながら複数のプロジェクトを並行して進められます。
従来の組織では、各部門が独自に専門家を抱える必要がありましたが、マトリックス組織では部門を超えて専門性を共有できるため、重複投資を避けることができます。これにより、全体的なコストパフォーマンスが向上します。
多角的な視点による意思決定の質向上
複数の部門から人材が集まるプロジェクトチームでは、さまざまな専門知識と経験が組み合わされます。マーケティング、技術、財務、営業など異なる視点からの意見が集約されることで、より質の高い意思決定が可能になります。
とくに新商品開発や市場参入などの重要な戦略的判断においては、単一部門の視点だけでは見落としがちなリスクや機会を発見できます。多様な専門性を持つメンバーが協働することで、市場のニーズにより適合した解決策を生み出すことができます。
人材育成と柔軟性の促進
マトリックス組織では、従業員が複数のプロジェクトに関わることで、幅広い経験を積むことができます。自分の専門分野以外の業務にも触れることで、ゼネラリストとしてのスキルも同時に身につけられます。
また、人材配置の柔軟性も大きなメリットです。市場の変化や事業の優先順位に応じて、人材を機動的に再配置できます。プロジェクトの終了と同時に新しいプロジェクトに移行することで、常に重要度の高い業務に適切な人材を配置できます。
イノベーション創出の促進
異なる部門の専門家が協働することで、従来の枠組みを超えた新しいアイデアが生まれやすくなります。部門間のコミュニケーションが活発になることで、思わぬ発見や改善提案が出てくることも多くあります。
とくに研究開発部門と営業部門、あるいは技術部門とマーケティング部門が密接に連携することで、市場のニーズに直結した技術開発や、技術の優位性を活かしたマーケティング戦略の立案が可能になります。
マトリックス組織のデメリットと課題
マトリックス組織には多くのメリットがある一方で、運用上の課題やデメリットも存在します。導入を検討する際は、これらの課題を十分に理解し、対策を準備することが重要です。
指揮命令系統の複雑化と対立
最も大きな課題は、複数の上司から異なる指示を受けることによる混乱です。プロジェクトマネージャーと部門長の優先順位が異なる場合、従業員はどちらの指示に従うべきか迷うことになります。明確な権限分担と意思決定プロセスを事前に定めておかなければ、従業員のストレスが増大し、業務効率が低下する可能性があります。
また、上司同士の意見対立が発生した際の調整メカニズムが不十分だと、問題解決に時間がかかり、プロジェクトの進行に支障をきたします。このような状況を避けるためには、組織設計の段階から慎重な検討が必要です。
責任と権限の散逸
複数の上司を持つ従業員にとって、自分の責任範囲が不明確になりがちです。問題が発生した際に、誰が最終的な責任を負うのかが曖昧になると、問題解決が遅れる原因となります。
とくに重要な意思決定において、各マネージャーが責任を回避する傾向が生まれると、組織全体の意思決定スピードが低下します。役割と責任分担を明文化し、定期的に見直すことで、このような問題を予防する必要があります。
コミュニケーションコストの増大
マトリックス組織では、調整すべき関係者が増えることで、コミュニケーションコストが大幅に増加します。会議の回数が増え、情報共有に要する時間も長くなりがちです。
また、異なる部門出身のメンバーが協働する際は、専門用語や業務プロセスの違いから誤解が生じやすくなります。効果的なコミュニケーションツールの導入と、定期的な情報共有の仕組み作りが不可欠です。
意思決定の複雑化と意思決定プロセスの長大化
多くの関係者が意思決定に関わることで、合意形成に時間がかかる場合があります。とくに緊急性の高い案件において、迅速な判断が求められる際に、調整プロセスがボトルネックになる可能性があります。
複数の視点からの検討は質の向上につながる一方で、決定までのプロセスが長期化するリスクもあります。重要度や緊急度に応じた意思決定プロセスの使い分けが重要になります。
マトリックス組織の成功事例と失敗事例
実際の企業におけるマトリックス組織の導入事例を通じて、成功要因と失敗要因を具体的に見ていきましょう。これらの事例から、自社での導入時の参考となるポイントを抽出できます。
花王の事例
花王は2012年から2013年にかけて組織全体を事業×機能のマトリックス型に再編成しました。ビューティケア・ヒューマンヘルスケア・ファブリック&ホームケアやケミカルの事業を縦軸に、サプライチェーンや会計、ITなどの機能を横軸としました。
全社をあげて、社内の生産、品質保証、生活者コミュニケーションセンターなど複数ある関連部門との緊密な連携が取りやすくなる環境作りを徹底しました。イノベーターを生む組織作りは、まさに「花王らしさ」が表れているといえます。
トヨタ自動車の事例
日本を代表するグローバル企業のトヨタは2016年に7つのカンパニーと地域別のビジネスユニットを組み合わせたマトリックス体制を整えました。第1トヨタ・第2トヨタなど4つのビジネスユニットを縦軸として設置し、技術開発本部や生産管理本部・経理本部を横軸としています。
この組織構造によって、よりローカルな市場の動向が把握しやすくなり、地域に応じた販売戦略の立案に専念できるようになりました。
失敗事例から学ぶ教訓
マトリックス組織では指示系統が複数になるため、対立が起きやすくなるのが大きな課題です。とくに高業績企業では部門の個性が強く、統合や連携が難しくなります。
こうした対立を防ぐには、マネジメント層が情報共有を徹底し、役割を明確にする必要があります。さらに、限られたリソースを複数のプロジェクトにどう配分するかも複雑になりがちです。
その結果、一部の従業員に業務が集中したり、部門間で利害の衝突が起きることもあります。機能型とプロジェクト型の特性を活かした最適な運用ができなければ、マトリックス組織はかえってコスト増と混乱を招く恐れがあります。
マトリックス導入時の運用上の注意点
マトリックス組織を成功させるためには、導入前の準備と導入後の継続的な改善が不可欠です。ここでは、実際の運用においてとくに注意すべきポイントを詳しく解説します。
効果的なコミュニケーション体制の構築
マトリックス組織では、情報共有の重要性が従来以上に高まります。定期的な調整会議の設定、共有すべき情報の明確化、適切なコミュニケーションツールの選定が必要です。
とくに、プロジェクトの進捗状況や重要な決定事項については、関係者全員が同じ情報を共有できる仕組みを作ることが重要になります。デジタルツールを活用したダッシュボードの作成や、定期的なステータス報告の標準化が有効です。
適切な評価制度の設計
複数の上司を持つ従業員の評価は、従来の制度では対応が困難です。各上司からの評価を適切に統合し、公平で納得感のある評価を行う仕組みが必要となります。
そのため、360度評価や複数評価者による評価制度を導入し、従業員の多面的な貢献を適切に評価できる体制を整えることが重要です。また、プロジェクトでの貢献と機能部門での貢献を適切にバランスさせた評価基準の設定も必要です。
こうした評価制度が求められる背景には、組織構造そのものの複雑さも関係しています。
“さらに、マトリックス組織であることも大きいでしょう。私の組織のCFO(最高財務責任者)は、私に報告するだけでなく、我々の上部組織のCFOにも報告しているため、その人の評価は、私と上部組織のCFOが話し合って決めるのです。このように、複数の目で多くの時間をかけて評価する仕組みがあるため、極端な評価にはならず、制度が正しく運用できるのです。”
引用元:巻頭インタビュー 私の人材教育論 万国共通に貢献度を高めるのは「エンゲージメント」
https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=4001
段階的な導入と継続的な改善
マトリックス組織の導入は、一度に全社で行うのではなく、特定の部門やプロジェクトから始めて段階的に拡大することが推奨されます。小規模での試行により、問題点を洗い出し、改善策を検討してから本格導入を行うことで、リスクを最小化できます。
また、導入後も定期的な振り返りと改善を継続することが重要です。従業員からのフィードバックを積極的に収集し、運用上の課題を早期に発見・解決する仕組みを作りましょう。
| 成功要因 | 具体的な取り組み | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 明確な役割定義 | RACIチャートの作成と共有 | 従業員の混乱防止 |
| 効果的なコミュニケーション | 定期調整会議とデジタルツール活用 | 情報共有の効率化 |
| 適切な評価制度 | 360度評価の導入 | 公平で納得感のある評価 |
| 段階的導入 | パイロットプロジェクトから開始 | リスクの最小化 |
まとめ
マトリックス組織は、複雑化するビジネス環境に対応するための有効な組織形態として注目されています。専門性を維持しながら部門横断的な協働を実現できる点が最大の特徴です。
- リソース共有による効率性向上と多角的視点での意思決定が可能
- 人材育成と柔軟な人材配置でイノベーション創出を促進
- 指揮命令系統の複雑化とコミュニケーション課題への対策が必要
- 明確な役割分担と適切な評価制度の設計が成功の鍵
- 段階的導入と継続的改善により運用リスクを最小化
マトリックス組織の導入を検討されている企業は、まず自社の課題と目標を明確にし、小規模なパイロットプロジェクトから始めることをおすすめします。成功事例と失敗事例から学び、自社に最適な形でのマトリックス組織構築を進めていきましょう。
「情報開示」から「企業価値向上」へ 攻めの人的資本経営 実践ハンドブック
本格化する「人的資本経営」の潮流にどう対応すべきかお悩みの、人事・人材育成ご担当者様へ。本ハンドブックは、開示義務への対応に留まらず、人的資本データを企業価値向上につなげるための要点を解説。貴社の「人」を最大の資本とするための、具体的な打ち手を提案します。
人的資本の可視化と育成ハンドブック
人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内
日本においても推進する取り組みが本格化している「人的資本経営」。株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、「人的資本の可視化」と「人材育成施策の改善」を支援するサービスを提供しています。以下から「人的資本の可視化と育成ハンドブック」を無料でご覧いただくことが可能です。
- 人的資本経営が注目される背景
- 情報開示をする際のポイント
- 具体的にどう測るのか
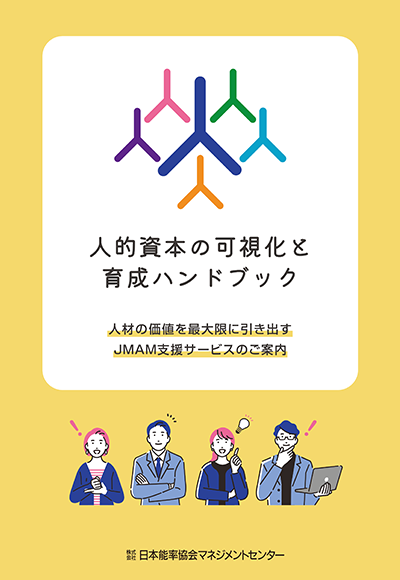
関連商品・サービス
あわせて読みたい
Learning Design Members
会員限定コンテンツ
-
 目的意識と哲学から真の課題を 捉え解決する技術経営者を育成
目的意識と哲学から真の課題を 捉え解決する技術経営者を育成 -
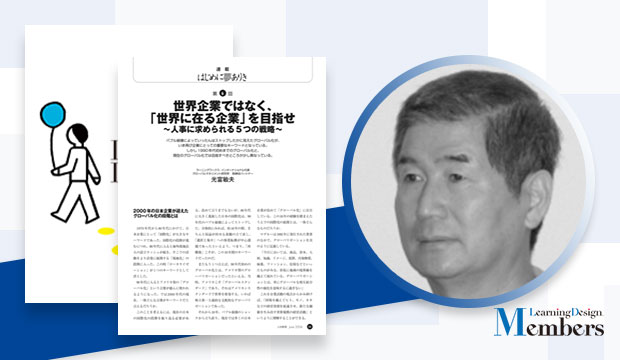 世界企業ではなく、 「世界に在る企業」を目指せ ~人事に求められる5 つの戦略~
世界企業ではなく、 「世界に在る企業」を目指せ ~人事に求められる5 つの戦略~ -
 顧客志向とチャレンジ精神変化をいとわないDNAが次の100年へ道筋をつける
顧客志向とチャレンジ精神変化をいとわないDNAが次の100年へ道筋をつける
人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。
情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。
専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。
- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!
- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!
- 調査報告書のダウンロード
- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます