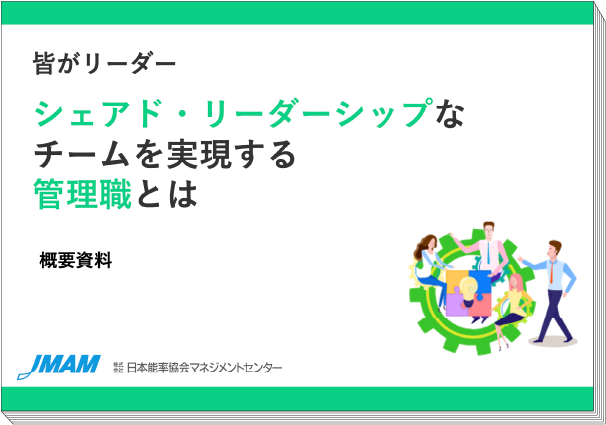書籍のご案内
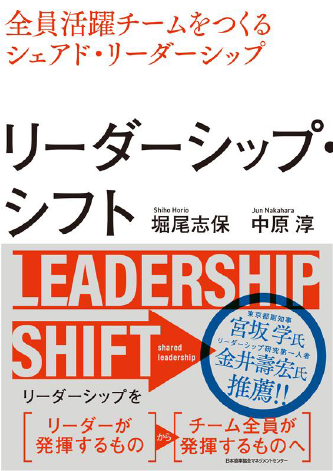
リーダーシップ・シフト全員活躍チームをつくるシェアド・リーダーシップ
本ページ掲載の内容は、「調査1」部分のインタにビュー結果のごくごく一部です。
管理職の方々からヒアリングさせていただいた内容全体から見えてきたポイントを含め、シェアド・リーダーシップな全員活躍チームをつくる管理職の行動をまとめた内容を中原教授・堀尾助教の共著で書籍化しました!
詳細をみる→

塩野義製薬株式会社 工藤 昌子氏
経営戦略本部 経営企画部
サステイナビリティ推進室 室長
インタビュイーの所属・役職名および以下概要は、インタビュー当時のものです。
(本調査のインタビュー実施期間:2020年12月~2021年2月)
内容は掲載をご許可いただいた範囲で、記事の形式とするため、見出しを追加し、⼀部順序や表現が再構成されています。
企業を評価する際の新指標として今、ESGへの関心が高まっている。ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字をとった用語である。塩野義製薬では、環境課題を含む諸課題への責任ある対応を強化し、「持続可能な社会への貢献」と「シオノギの成長」を実現するために、ESG関連の統括部門として経営戦略本部の経営企画部傘下にサステイナビリティ推進室を新設した。
会社として本格的にESG活動を推し進めるにあたり、ESGの専門家として加わったのが、工藤昌子さんである。工藤さんは、ESG投資のコンサルティング等を行う会社を経て、塩野義製薬に入社。広報部IRグループで投資家との折衝を中心とした仕事を担当した後、サステイナビリティ推進室の新設に伴い、同室長に就任した。経営層をはじめ、決して一筋縄ではいかない社内の多様な部門と連携・調整を図りながら、社外への発信を強化。自身の専門知識をメンバーに惜しみなく提供しつつ、学び合いの風土を築き、同社のESG活動をけん引している。
前職のコンサルティング会社時代、第三者の専門家の立場として、お客様に様々な提案をしてきました。提案を行うと、クライアントの方たちは専門家からの意見ということで、「じゃあそれでいきましょう」と、割とそのまま受け入れられるケースが多かったのですが、現場に展開すると、自分ごととして動いてもらえず、活動が頓挫してしまうこともありました。ですので、自分が率いるチームでは、皆で考え、合意形成をして推進する形で進めていきたいと考えていました。
私の場合は、転職してまもなくの管理職就任だったので、まずは会社のことをよく知らなければということと、人間関係をうまく構築していけるだろうかと不安を感じながらのスタートでした。前職と比べて会社の文化も業務フローもまったく違うので、最初は少し戸惑いもありました。ファーストステップとしては、新しく関わる方たちといかにして信頼関係を構築するかが重要だと思っていました。
前職ではプロジェクトを動かすリーダーの立場は経験していたものの、管理職という立場は今回が初めてです。管理職になってプラス面として感じているのは、メンバーがいることによって、できることの幅がすごく広がったことです。これまでは自分だけで進めてきた仕事も、管理職として室を任されたことで、チームとして取り組むことができ、推進力がとても上がりました。
サステイナビリティ推進室が新設され、私が室長に就任した時期は、コロナ禍でばたばたとテレワークに切り替わった時期です。そのため、組織の立ち上げにはかなり苦労しました。メンバーと十分なコミュニケーションをとることができず、相互理解をどのように深めていったらいいか頭を悩ませました。メンバーのESGに関する知識量も、専門家レベルの方もいれば、初めてESGに接する方もいて、様々な状態でした。
いろいろと思案し、まずはチーム全体で15回の勉強会を行うことにしました。知識量の多いメンバーを講師にし、2カ月の短期間で集中的に実施したのです。これにより、基本的な情報共有、知識の底上げができ、メンバー間の相互理解も深めることができました。
次に直面した課題は、チーム活動の意義を皆に理解してもらうことでした。ESGの業務は淡々と進んでいくものもあるため、今している仕事がどこにどのように役に立つかを実感しにくいところがあります。しかし、活動の意義を理解しないままでは、仕事の仕方にも差が出ると感じました。そこで、ESGの社会的な意義、会社にとっての貢献など、今の活動がどこにどのようにつながっているのかを私から丁寧に説明しました。私から伝えるばかりでは自分ごとになっていかないため、その後、各メンバーに、自分の担当業務が価値をもたらすまでのストーリーを、自分の言葉で語ってもらう取り組みへと変化させていきました。
一番苦労したのは、現場の方たちとのコミュニケーションです。社内の各部署にESGの取り組みを依頼しても、最初は本業「プラスα」程度にしか捉えてもらえないことも多く、なかなか理解を得られませんでした。ESGは、各部署でまさに行っている業務を改善していく活動ですが、現場の方には、自分たちの日々の活動とまったく関係のない仕事が増えたと見えることもあります。そのため、こちら側からの論理でなく、各現場からの見え方への理解を深めるよう努めました。
ESGの取り組みは、推進室のメンバー、現場の方々、経営層が三位一体となって推進していくことが不可欠です。そのため、各立場の方々としっかりとコミュニケーションをとり、活動の意義、情報の共有をしながら、相互に研鑽し合っていくことが重要だと感じています。
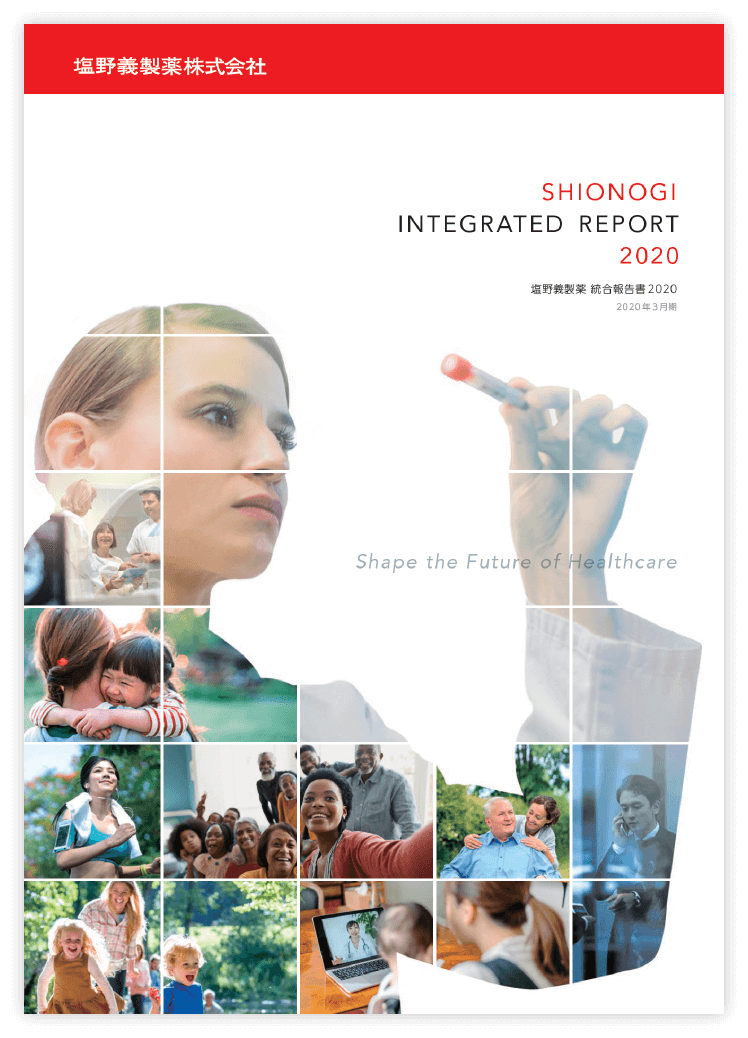
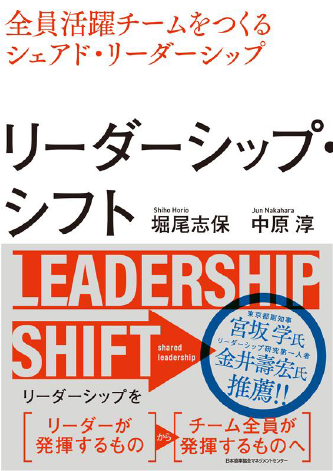
本ページ掲載の内容は、「調査1」部分のインタにビュー結果のごくごく一部です。
管理職の方々からヒアリングさせていただいた内容全体から見えてきたポイントを含め、シェアド・リーダーシップな全員活躍チームをつくる管理職の行動をまとめた内容を中原教授・堀尾助教の共著で書籍化しました!
詳細をみる→
シェアド・リーダーシップの考え方、これから求められるリーダーシップについてまとめた資料を
PDFでダウンロードできます。本サイト掲載情報をわかりやすくまとめた資料ですので、
ぜひお手元に置いてご覧くださいませ。