シェアド・リーダーシップを組織全体で
推進する先進企業
チームの力を生かした方がいいじゃない?
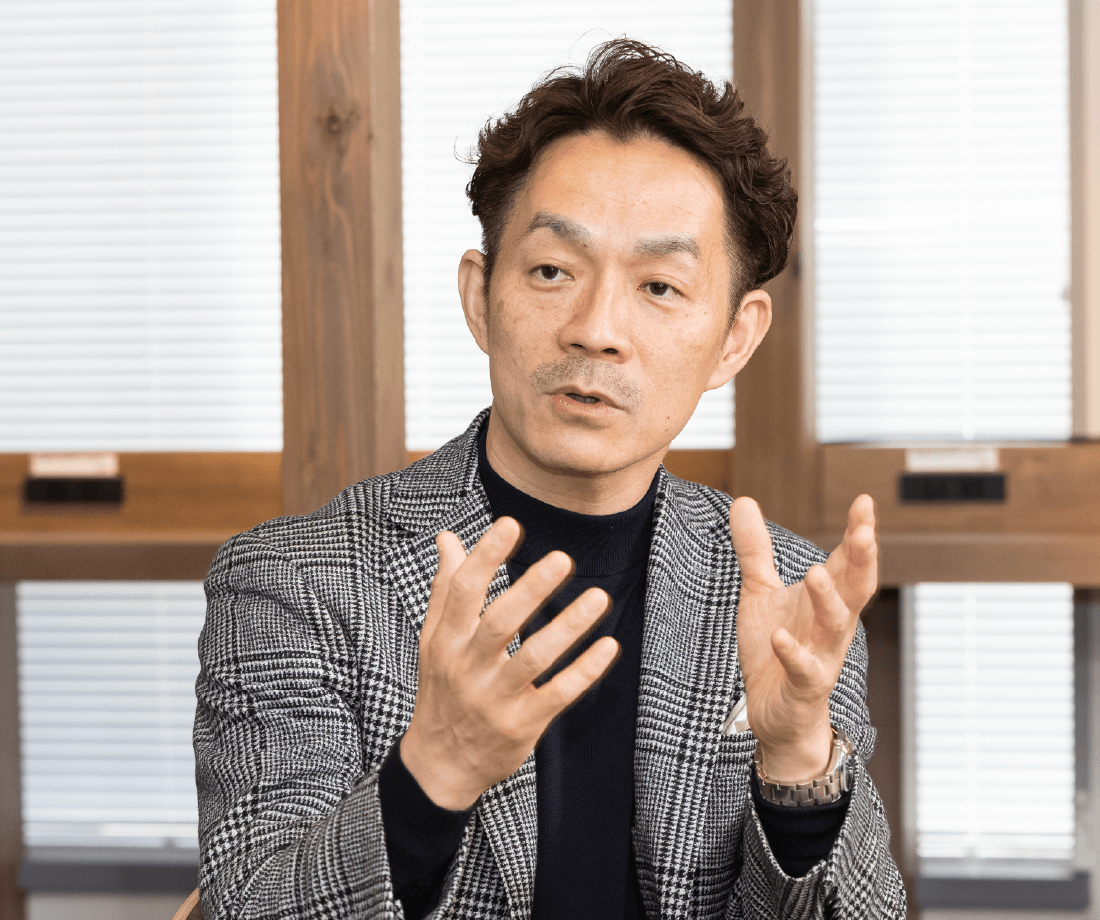
堀尾我々は、管理職を対象とした調査研究を続けるなかで、プレイヤーから管理職へのトランジション(転換)ができる人とできない人が生み出せる成果の大きな差を目の当たりにしてきました。業界を問わず、管理職になっても、プレイヤーとしてのマインドや行動を変えることができず、自分だけがスタープレイヤーでいたいと思う人は少なくありません。
しかしながら、チーム力、組織力を高めていくほうにマインドと行動をシフト(変化)できないと、組織としての可能性は小さくなっていくように感じます。瀬戸口さんご自身はそうしたトランジションにおける心の葛藤やそれを乗り越える過程で工夫されたことなどはありましたか?
瀬戸口自分自身が初めてプレイヤーから企画を決定する側の管理職に転じた時は、極力皆にフラットに公平に関わろうと気をつけました。
なぜかというと、決定した企画について「その企画は瀬戸口さんと○○さんの仲がいいから決まったんでしょ」とか「瀬戸口さんが関わっていた企画だから通ったんでしょ」と思われることがあれば、皆にとって不幸なことになるからです。
ですが、当時はそれをメンバー全員に言語化して伝えられていませんでした。それから「一人一人の力を発揮した方がいい」と考えながらも、今となってはおこがましいなと思うのですが、どこかで「アシスタントとして自分がもう1人いたら楽なのに…」などと思っていた節がありました。
今思えば、自分と同じ人がもう1人いても、ざるの目が合っているのでヌケは防げないんですよね。チーム力としては上がっていかない。それに色々なアプローチの可能性があるなかで自分のやり方だけを正解だと思ってしまうと次の世代の可能性も制限してしまうという点で持続可能性の面でも課題があったと思います。
まだあのときは、そうしたこともしっかりと理解ができていなかった。そういう意味では、当時は「それぞれの強みを生かして活躍してほしい」と本心からは思いきれていなかった部分もあったのだと思います。
堀尾「ざるの目が合ってしまう」とは、いい表現ですね。リーダーにも得意、不得意があり、不得意なところに関しては、それを得意とするメンバーにリーダーシップを発揮してもらえれば、リーダー、メンバー、チームのすべてにもたらされるものが大きいですよね。
私自身がシェアド・リーダーシップに興味を持ったのは、自分自身が管理職を担っていくなかで、女性ということもあり、自分が「グイグイ型のリーダーシップ」を発揮していくイメージがもてなかったということがありました。さらに、30代に出産、育児と管理職を両立していくなかで、管理職とプレイヤーを行ったり来たりする時期があり、役職の有無によって、あまりにもリーダーシップの発揮機会に差があることに違和感をもった、ということもありました。
多くの職場では管理職にリーダーシップ発揮の期待が集中しますが、それは管理職にとってもメンバーにとっても、あまりワクワクすることではないのではないか、と。
そうしたことをモヤモヤ考えていたときに、ハーバード大学のリンダ・ヒル先生やCCLというアメリカの研究機関の研究者から「欧米ではチームや組織全体でリーダーシップを発揮している企業では、業績やイノベーション創出にもよい影響がでている」と聞いて、これは自分の問題としても、研究者としてもしっかり研究して、その知見を日本の多くの職場にお届けしたい、と考えるようになりました。
瀬戸口そうでしたか。管理職やリーダーが一番経験豊富で、何でも知っていて、その人の指示を聞いておけば間違いがない、という時代も過去には確かにありましたが、今これだけ世の中が不確実になっていて新しいことも増えていると、管理職やリーダーが必ずしも全て網羅できるわけはないですからね。
苦手なことは自己開示して、助けてほしいと言える方がいいですよね。今はスーパーリーダーではなく、スーパーチームを目指した方がいいと思っています。
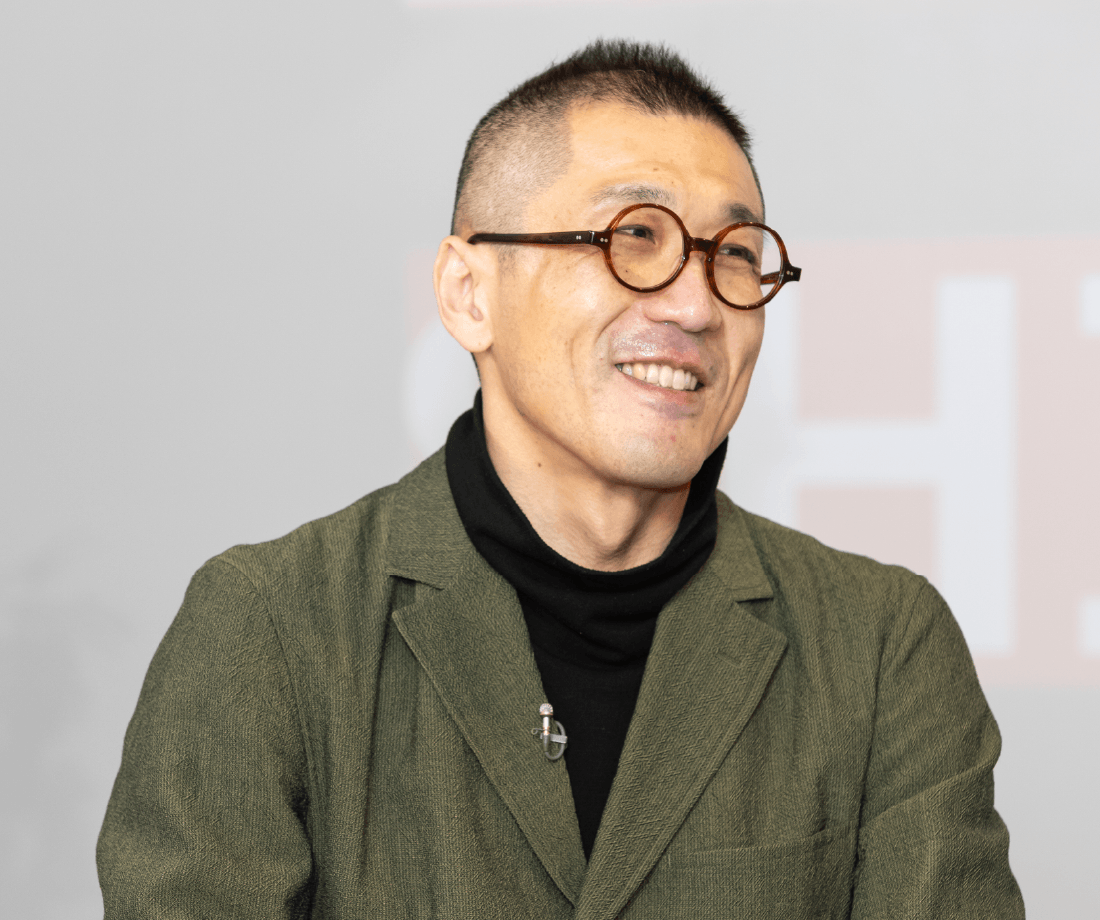
中原「スーパーリーダーを目指さない」というのは大切なことですね。WBCで野球世界一に導いた栗山監督やサッカーの森保監督も、かつての監督像やリーダー像とは、真逆ですよね。スポーツの世界でもかつては監督というのはカリスマ的な存在で、おっかなくて、監督がとにかく全て決めるというのが一般的でした。
ですが、栗山監督や森保監督のスタイルはそれとは真逆です。むしろ、彼らは選手をひとりひとりに話しかけ、ひとりひとりに寄り添い、選手たちの力を引き出しています。全員参加型のチームをつくっているのです。
瀬戸口「引っ張る力」ではなく「ひとりひとりを活かす力」なのですね。若い頃、プロデューサーになりたてのときに出会ったある名ディレクターのことを思い出しました。
当時のディレクターというのは、まさに全てを決める存在でした。女優さんの衣装や小道具から、カメラ割り、音楽、編集、全てをディレクションするのがディレクターだと思われていました。ですから、周囲は全てディレクターにお伺いを立てていたのです。
ところが、その名ディレクターは「自分は女優さんの衣装はわからない。とにかくこの女優さんをかっこいい刑事にしたいから、年代も近いあなたに任せます。あなたがOKしたものなら全部OKです」といった具合に助監督やスタッフに任せていたのです。
すごいな、と思いつつ、ややもすると責任放棄しているように見えなくもない行動なので、なぜそうしているのか聞いてみたのです。すると「わからないものをわかるって言うのは間違った方向に進むんだよ。そんな恐ろしいことはない。それよりも一番得意そうな人に任せて、その人が真剣に考えていいと言うものを信じてやるほうがいい。自分のOKが最後のOKになると分かっていたら、絶対頑張っていいものにしようと思うけど、最後はディレクターが決める、というのではそれぞれの仕事が甘くなってしまうでしょ。全てのスタッフがベストパフォーマンスをしてくれて、それを僕がOKって言っていい作品ができたら『面白かったですね!ディレクター!』って僕が評価される(笑)。だったら、 チームの力を生かした方がいいじゃない?」と言うのです。
衝撃でした。あのディレクターがやっていたのは、シェアド・リーダーシップだったのだ、と今は理解できます。
中原素晴らしいディレクターさんですね。
リーダーシップを共有する“心の葛藤”とは
堀尾リーダーシップをより多くの人が発揮できるようにシフトしていくということは、誰にとっても大きな変化だと思うのですが、中原先生も教育者として、学生に対してシェアド・リーダーシップ的な教育をなさっています。全て先生が決める、教える、というところから変えていこうと思われたきっかけなどがあったのでしょうか?
中原私のゼミは「自分の学びは自分でデザインせよ」というスローガンを掲げていて、何をどう学びたいかを、学生たち全員でひたすら対話して決め、皆が決めたことに私は最大限サポートをする、というやり方を取っています。
ですが、着任した当初からそれが貫徹できていたわけではありません。僕は何をどう学ぶのかを全て自分が決めていました。しかし、それは学生が学びたいものではなかった。
そうしたら、授業時間が始まっても、なかなかゼミが始まらないみたいな状態になりました。要するに、ゼミが崩壊してしまったのです。このやり方では、学生たちは動かないし、パフォーマンスも発揮できないし、学ぼうともしない。
それがわかったときに、先生としての僕が持っている権力みたいなものを全部リリースして、現在のスタイルに変えてみたのです。そうしたら次第にうまくいくようになりました。もちろん、組織なので、日々、順調に、今なお、課題はありますが。
瀬戸口その時に葛藤はなかったですか?
中原正直怖かったです。先生なのに、学生にゼミ運営をリードさせてしまっていいんだろうか?という心の葛藤がありました。
先生というのは「教壇に立ちたい病」「スポットライト浴びたい病」みたいなものに罹っているので(笑)、存在意義が揺らぐのだと思います。だから「学生に任せる」となったときに、すごく心がモヤモヤする。というより、怖いんです。自分のコントロールを外れると、学生がどこにいくかが、わからないので。
恐らくマネジメントスタイルを、シェアド・リーダーシップを推進していく方向へと変えていく管理職の方も、最初はこの辺がモヤモヤなさるのではないかと思います。ですが乗り越えると、すごく活性化します。
堀尾瀬戸口さんは経営層として組織全体でシェアド・リーダーシップを推進していこうとなさっているわけですが、現場の管理職の方々に対しては、どのように伝えていらっしゃるのでしょうか。
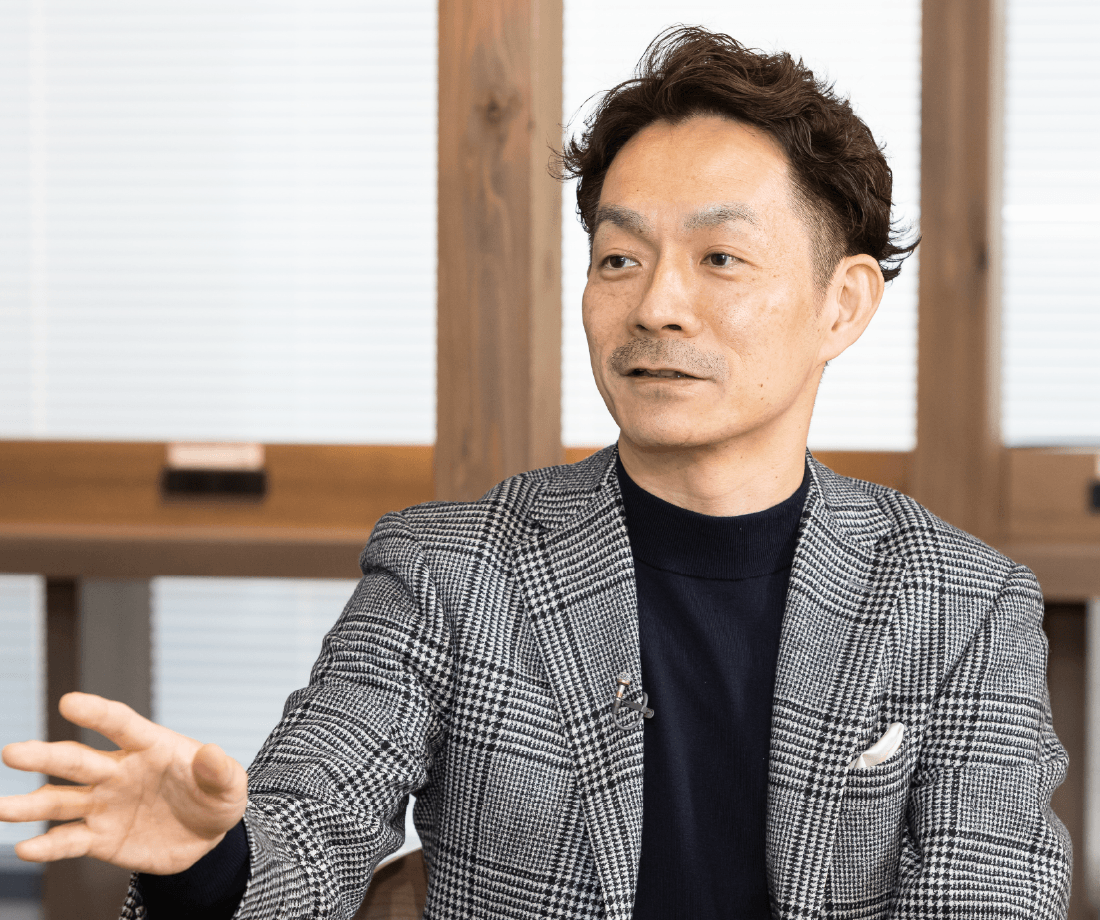
瀬戸口「自分自身がこういうチームや組織のつくり方をもっと早く知りたかった」という思いを率直に伝えていますね。
当時、自分としては一生懸命やっていたけれども、あのやり方が正しかったとは思っていません。失敗もしたし、正直うまくいかなかったと思うこともあります。
けれど、誰も「こういうやり方があるよ」と教えてくれなかった。もっと早く、シェアド・リーダーシップでスーパーチームを目指すというやり方がある、ということを知っていたら、あのときの自分はもっと良いチームを作れたかもしれない…と思うのです。
だからこそ、ライン長には研修を通して、考え方や方法のなかで「取り入れたらよさそう」と思えるものを1つでも2つでも手に入れて、自分のチームで実践してもらえたらいい、そう伝えています。
堀尾TBSでは全ライン長の皆さんにシェアド・リーダーシップの研修を実施され、そこで、瀬戸口さんがこうした背景や想いを最初に毎回、直接メッセージ発信なさっていたのがとても印象に残っています。